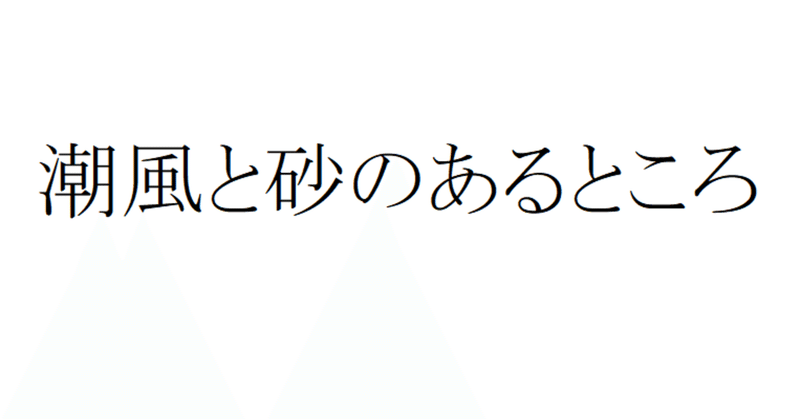
潮風と砂のあるところ 1・空の灯台守
砂漠と海、そして岩山。空の青、薄くちぎれちぎれに空を流れる雲。目に見えるのはそれだけだった。アンリはゆっくりと滑走路を端から端まで歩いた。固く平らに砂を押し固めただけの滑走路に異常は無い。これで一日の仕事の半分は終わったようなものだ。もう一度空を見上げる。海と砂漠、西にそびえる岩山、空。目に入るものはそれだけだ。
コーヒーとパンふた切れ、そしてオレンジがひとつ。本を読みながらでも、朝食の仕度から食事を終えるまで、三十分とはかからない。アンリは本をつかんで別の部屋に移る。「無線室」と書かれた扉をくぐると、いきなり水平線が目に飛び込んでくる。壁に開けられた大きな窓にはガラスも木の板もはめられてはいない。北に向かってどこまでも続く海と空が見える。一方の壁に向かう机の上には無線機、部屋の逆側には固い木製の長椅子。アンリは長椅子の上に横になると、本のページをめくった。部屋を吹き抜けて行く風には、塩と砂が含まれている。アンリの肌を伝い落ちる汗が、その砂を絡め取る。アンリはじっと時が過ぎるのを待っている。
午前十時、静かな雑音が機械から流れ出る。
「やあアンリ、いるかい?」
突然、陽気な声がスピーカーからこぼれ出る。この声はフェルナンドだろう。
「ああ、いるよ」
「定時連絡、エンジンはすこぶる快調。天候はなんら問題無し。風は静かだし、雨雲はかけらも見えない。このぶんなら予定より早くそちらを通過できそうだ」
「了解」
一時間後、アンリは無線機から離れ、窓枠に腰を下ろした。どこまでも続く青空、どこまでも続く碧海、明るい青と様々に色を変える濃いブルー。目に見える物はそれだけだ。砂漠の陽射しは本を読むには少し強すぎるようだ。アンリは目を細めて北の空を眺めた。毎日郵便飛行機を見守ってきた目は、爆音が耳に届くよりもはるかに早く飛行機を捕らえた。やがてフェルナンドの飛行機は二枚の翼が見分けられるほど高度を落とすと、滑走路の端でなびいている吹流しの真上で翼を振った。アンリも機上のフェルナンドから見えるかどうかなどお構いなしに、手を振って挨拶する。飛行機がこの小さな建物の上を飛び去ってしまうと、アンリは再び長椅子の上に横になり、本のページを繰る。一時間後、フェルナンドから最後の定時連絡を受ければ、彼の仕事は終わりだ。遠いアラニア・ノヴァ市の郵便航空機会社の事務所へ電話をかけ、報告する。「本日も異常なし、定期便は無事通過した」あとは心ゆくまで本を読み、西日がかすかに色づく頃、自転車で村へ出かけ夕食を摂る。時にはちょっとした買物をして飛行場へ帰る。それがアンリの生活のすべてだ。
無論、毎日がこのように平穏に過ぎていくわけではない。時にはアンリと滑走路がその存在意義を最大限に発揮する事もある。
一度、突然の嵐に定期便の飛行機が緊急着陸せねばならなくなったことがあった。あれはいつ頃だったろうか。そう、パイロットがレオンだったから、二年以上前ということになる。朝には晴れていた空が昼前に一変し、突然の風雨に見舞われた。飛行場の西側からこちらを見下ろす岩山の上に黒雲を認めたアンリは、 既に定時連絡を終えこちらまで十キロを切る距離まで近づいていたレオンに無線で呼びかけた。
「どうやら雨雲が近づいてきているようだ。大きく東に迂回した方がいい」
「了解。左に針路変更して、クラダ岬からサン・フェルナンデス方面へ向かう」
レオンは事務的な口調で返答した。外が暗くなったのに気付きアンリが窓際へ歩み寄ると、ちょうど激しい雨が落ち出した。木製の窓扉を閉め、卓上のランプに火を点けると、無線機が騒ぎ立てた。
「ダメだ、嵐に追いつかれた。もう一度進路を変えてそちらに向かう。雨宿りさせてくれ」
アンリは再び窓を開けた。たちまち腕にも顔にも雨が叩きつけられる。滑走路の端に立つ吹流しは、引きちぎれんばかりにはためいている。
「横風が激しい。着陸は無理だ!そのままの進路を維持しろ」
「こっちだって無理だ!このままじゃ現在位置もわからなくなる。へたすりゃ操縦不能だ」
「くそっ!しょうがない」
アンリは外へ飛び出すと、岩山を見上げた。雨のカーテンに遮られ、その頂上がはっきりとは見えない。空全体を見渡しても、雲の切れ間など見つかりもしない。
「視界も最悪だ」
そう叫んで室内に駆け戻った。
激しい雨にもかまわず、窓を大きく開け放して北の方角を見据える。風の唸り声は刻一刻と激しさを増している。双眼鏡を手に持ち、せわしなく視線を移動させるうちに、雨の帳を通してついに小さな影を認めた。双眼鏡で見ると、確かに飛行機だ。ただちに無線で呼びかける。
「こっちからは、そちらの機体を視認した。そちらからは滑走路が見えるか?」
「いや、だめだ。陸地はわかるんだが、滑走路の境界がはっきりしない」
「こちらの建物はわかるか?」
「いや、まだ見えない」
アンリは雨の中必死に目を凝らし、飛行機の進路を見極めようとした。
「よし、高度を落としながら十度右に旋回しろ。風に流されている事を忘れるな」
飛行機は命ぜられたとおり、高度を落としながら右旋回した。
「さらに右に五度旋回、高度も落とせ。今、高度約五百メートルだ」
アンリは必死に飛行機と滑走路を交互に確かめ、タイミングを計った。
「よし!左旋回六十度だ。今、滑走路への進入路上にいる。そのまま高度を落とせ。建物はまだ見えないか?」
「まだだ」
無視界に近い状態のまま、着陸前の微妙な誘導をしなくてはならないのは、アンリにとっても始めての事だった。知らず知らず声も激しく荒々しくなる。
「流されてる!修正しろ!右に二十メートル移動して今の進路に戻せ!」
誘導する側も勘が頼りなら、操縦する側も勘が頼りである。それでもレオンはぴったりと滑走路の先へと機体を戻した。
「見えた。飛行場の建物を確認した!」
「よし!建物の向かって右、十メートルの線が滑走路の中心だ。建物の手前三十メートルから、滑走路は始まっている。わかるな?」
「了解」
アンリは交信を終えると、窓も開け放したまま、外へと駆け出した。滑走路の脇に立って両手を大きく振り、滑走路を示す。
進入してくる機は、本来のアプローチより若干高度が低い様だ。アンリは不安に顔を歪めた。横風はやもうとはしない。着陸の為に速度を落とせば、きっと横転してしまうだろう。
機体はややオーバースピードで滑走路に接触した。着陸の角度が悪いのは、操縦者が地面の位置を把握しきれていなかったことを示している。それでも機体が滑走路の上に跳ね返される事も、脚を折って擱座することもなく滑走路の端で無事止まった。アンリが長い滑走路の端から端まで夢中で駆け寄るのと、必死の着陸を成功させたレオンが地に降り立つのとが、ほぼ同時だった。
「喜ぶのはまだだ!早く飛行機を格納庫に!」
アンリはそう叫んで、上翼と下翼の間の支柱を掴むと、機体を引っ張った。レオンもそれに倣い、二人がかりで飛行機を格納庫に引いていく。幾度も横風にひっ くり返されそうになりながらも、風を防げる場所に機体を収め扉を閉めた。アンリとレオンはずぶ濡れになった衣服を脱ぐ力もなく、そのまま床にへたり込ん だ。
嵐が過ぎ去ったのはその日の夕方だった。アンリは町に電話して、滑走路の補修に人を手配するのに忙しかった。飛行服から乾いた服へと着替えたレオンは、滑走路を端から端まで歩くと、晴れた空を見上げた。もはや雲一つ残ってはいない。
「今からでも飛べそうだな。滑走路もそれほど痛んでないし」
大声で部屋の中のアンリに呼びかけた。
「やめとけよ。今からじゃ夜間着陸になるぞ。それに見た目、ほんのちょっと土が流れただけに見えても、飛行機をひっくり返してしまうことだってよくある」
レオンは返事を返さなかった。
「町まで飯を食いに行こう。何もかも、明日の話だよ」
アンリは言いながら、上着を羽織った。
町の行き付けの食堂で肉と野菜を煮込んだ料理をつつきながら思う。そのレオンもそれから間もなく、いなくなってしまった。定期便の運行中に海の上で消息を断ったのだ。食事から帰ってくるなり、長椅子の上で正体なく眠りこけてしまったレオンの姿が今でもはっきりと思い出される。レオンの遭難と前後して相次いだ事故の多くが、酷使されすぎたパイロットの過労によるものだと噂された。幾度もパイロット達のストライキが発生したが、航空郵便会社は一度たりとも譲歩していない。ストのたびに契約しているパイロット達が入れ換えられて、それでおしまいだ。金を払ってでも空を飛びたいという連中はいくらでもいる。そして使い潰されて、自ら会社を去るか飛行機と運命をともにするか。アンリはテーブルの上に金を置いて立ちあがった。レオンのことなど思い出したせいで、今夜は飯がまずかった。早く帰って眠ることにしよう。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
