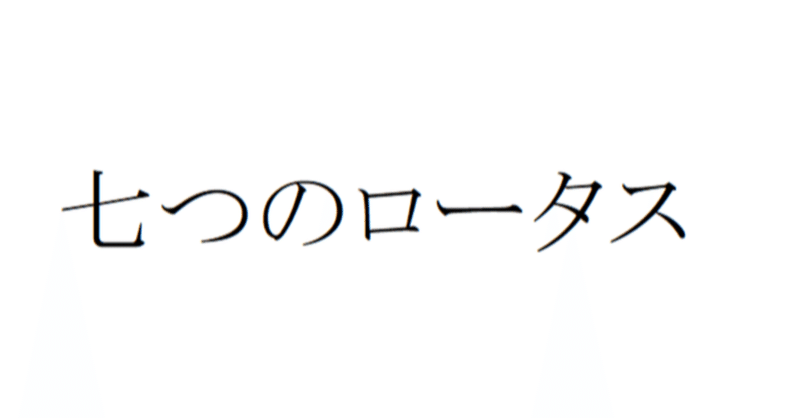
七つのロータス 第44章 レンII
どこまでも茫漠として広がる大地。戦士たちは平坦で特徴のない草原にも、記憶にある地形を見つけて馬の脚を早めた。ハラートの男たちとて、荒野の只中に残してきた女たちが気がかりなのである。徒歩で後に続く服属民の兵士たちなど忘れて、思い思いの速さで馬を駆けさせはじめる。たちまち隊列が乱れ、縦隊から水鳥の群れのような楔形に変わった。そのまま幾つかの丘を越え、遂に目指すオアシスを見つけると、戦士たちは馬を励まして疾走に移る。レンもまた、ただ一人の頼りであるヴァリィから取り残されぬよう、必死で馬を急かした。
両側に飛び去って行く風景の中心にオアシスを据える。風が耳元で唸り、肌を撫でてゆく。馬体とともに上下に躍る自らの体。長い緊張から解放された喜びが、ようやくにして沸き上がってくる。しばし体から力を抜いて手綱を持つ手を下に垂らせば、馬体と自らを繋ぎとめる両腿に波打つような筋肉の動きが伝わってくる。跳ねるように駆ける馬の力を楽しみ、周囲に轟く蹄の音を楽しむ。幾人かの戦士たちは族長を追い越して、先へ先へと馬を走らせてゆく。
何気なく後を見れば、男装した娘が周りの男たちとは違う真剣な表情で馬を走らせている。馬の行き脚を少しばかり緩めると、レンは巧く勢いを落せずに、驚いた顔をヴァリィに向けたまま追い抜いてしまった。笑いながら馬に合図して併走させるようにする。戸惑いながら前方と自分とを交互に見るレンの顔に、ヴァリィは視線を据えてオアシスに着くまで目を逸らさなかった。
オアシスのほとりには、寄り添うように並ぶ天幕。その周囲を大きく囲いこんだ柵の内外に、多くの人影と家畜の姿がある。戦士たちが近づくと、まずは天幕の周囲やオアシスで遊んでいた幼い子どもたち、次いで天幕を守っていた女たちが続々と柵の外へと迎えに出てきた。速度を落した馬の足許に、子どもたちがまとわりつく。急いで下馬した男たちは子どもを蹴散らすようにして馬を引いて行くが、満面の笑顔を浮かべていない者はいない。
ヴァリィは馬から飛び降りると、レンの馬の手綱も取って二頭まとめて引き始めた。レンは馬から降りることもできず、混乱した表情のまま運ばれてゆく。
泉のほとりでは戦士たちが馬に水を与えている。馬を休ませてはじめて、幸せな顔で従ってきた女たちと向合い、笑いあったり、抱き合ったり、優しい言葉をかけあったりするのだ。
ヴァリィも馬を水際に導くと、レンを両腕で抱きかかえるようにして馬から下ろした。新しい水を汲んだ革袋を女に渡し、自分は両手ですくった水を飲む。腹から胸へと水が染み渡っていく感覚。汗と土埃に覆われた顔を洗い首筋を拭うと、体にこもった熱が洗い流されていく。身を清めてからまた女と向かい合う。レンは革袋を手にしたまま、居心地悪そうにぼんやり立っている。
「来い」
ヴァリィがそう言って歩き出すと、レンは黙ったまま少し距離を置いて後に続いた。
ヴァリィが危害を加えるようすはないし、相手の言いなりになるほかできることがないこともわかっている。それでも何もわからないままに引きまわされるのは辛い。レンは息苦しいほどの不安を押し殺して、集落の中央にあるひときわ大きな天幕をくぐった。白い布越しに満たされる乳色の光に目が馴れるのに、暫く時間がかかる。
「よく帰られた」
「お帰り」
「お帰りなさいませ」
次々とヴァリィにかけられる声は、若い声も老いた声もみんな女の声のようだ。
やがてただの影としか見えなかったものが、人の姿を取り始める。天幕の一番奥に座を占めるのはかなり高齢の老婆。立ちあがってヴァリィを出迎えたのは初老の女性。他にも同じくらいの年齢やもう少し若い者、そしてずっと若いレンと変わらない歳に見える者など、天幕の中には女ばかり六人がただ座っていたり、 糸を紡いだりしていた。
「この娘の世話を頼む。無口だが、言葉に不自由はない筈だ」
帰還の報告を終えたヴァリィが、言いながらレンの体を押し出した。背中を押されて、よろめく様に天幕の中央に進み出る。
「娘さんだったかね。どうして男のなりをさせている?」
老婆がしわがれてはいるがはっきりとした言葉で問う。
「まあ、想像はつくだろう」
「珍しいな。お前がそんな気の遣い方をするのは」
老婆が笑うと、他の女たちにも含み笑いがうつる。ひとりひとりの笑い声は慎ましやかでも、いっとき天幕の中は笑い声でさざめいた。
「とにかく、頼んだぞ」
そう言ってヴァリィが出て行き、レンは知らない女の中に一人でとり残された。華やいだ笑い声が、もう一度破裂する。年少の女たちが、ヴァリィが照れていると言って面白がっているのだ。天幕の入口がふさがると、女たちの視線がただレンだけに向けられている。敵意ではなくただの好奇だろうが、落ちつかないことに変わりはない。
老婆に身振りで促されるまま、敷物の上に座る。
「固くなるなと言うても無理だろうが、楽にするがええ」
「はい、ありがとうございます」
老婆の言葉は優しいが、逆らいがたい力があった。
「まあ、まずは身なりだね」
老婆に命じられた娘が、寛いだ長衣を用意する。着替えると今度は水浴をするように言われ、その娘と一番歳若く見える娘とに付き添われて天幕を出る。泉まで歩く間、二人はまるで新しい女友達ででもあるかのように、気安く話しかけてきた。捕らわれの身である自分の立場と、今の境遇との格差が、苛立ちにも似た不安感をかきたてる。丁重に扱われてはいても、虜囚であることには違いない。けれどもそもそも命ぜられた以外のことなど、不安でできはしないのだけれども。
女が寛衣を着たまま水を浴びる習慣は、レンの部族と同じだ。腰が水につかるまで泉の中に歩み入り、二人の女に見守られながら水に浸した手で髪を梳くが、砂まみれの髪の半ばまでも通らないうちに、指に水気がなくなってもつれた髪に絡め取られてしまう。レンは泉の底に膝をつき身をかがめて、髪を直に泉水に落した。良く澄んだ水が砂埃で濁る。レンが髪を洗い、顔、首、肩、衣に包まれた体から、砂埃を擦りとっている間、付き添いの二人は、泉のほとりに座りこんでいた。素足で水を玩び、水面を波立たせながらおしゃべりに興じている。
体を洗い終え、肩までを水に沈めたまま周囲を見渡す。対岸の人影が大人か子どもかもわからないほど大きな泉。水を与えられていた馬たちは、既に水辺を離れて一箇所に集められていた。遠くでは帰還したばかりの戦士たちが、腰布だけの姿で水を浴びている。集落を囲む柵の外では、山羊を一頭まぜた羊の群れを、 まだ幼く見える子どもたちが見張っていた。まだ戦いに出る歳に満たない男の子も、それよりは多少年長の女の子も、みな馬に跨っている。ここでの暮らし振りは、滅ぼされるまでのキュイ族が送ってきた暮らしと、ほとんど変わりがないようだ。
思考が自分の血族のことに及ぶと、突然に涙が溢れた。部族の男たちは老人まで、みんな討ち死にした。女たちもほとんどが、逃げるより自ら命を絶つことを選んだ。レンたち馬に跨って逃げた者も、敵に追われてちりぢりになった。自分の他にまだ生きている者がいるとは思われない。もし生き延びていたとしても、 どれほど苦しい境遇にいるか…。
「ねえ、ヴァリィ様はこの人をお嫁さんにする気かな」
若い方の娘の言葉が耳に届く。まったく無邪気で楽しげな声。もう一人の女も、賑やかな笑い声をあげる。
「そうかもね。そうだったらいいな」
レンは沸き上がってくる様々の嫌な思いを噛み殺して、二人の声を意識から締め出した。両手ですくった水で涙を拭い、熱を帯びてきた顔を冷やす。二人の娘に心配や同情をされたくはなかった。
* * * *
ヴァリィは水辺に横になると、両腕を枕にして目を閉じた。ようやく追いついて来た服属民の兵たちに野営地を指定し、食糧を配給しといった仕事を監督していたらすっかり夕方になってしまった。戦いの高揚も素晴らしいが、緊張から解放された後のこの心地よい弛緩も良いものだ。夕暮れの日差しが暖かく体を包む。太陽からの熱い光に照らされる昼と、大地も空気も凍える夜とが繰り返す草原で、ほんの僅かな心地よい時間。目を刺す光も瞼を閉じれば気にはならない。
少しまどろんでから目を開けると、レンが立ったまま顔を覗きこむように見下ろしていた。
「どうした」
「この泉は知っているわ。キュイ族が羊を追って巡る放牧地の一つだった」
黙っていると、レンはまた口を開いた。
「あなたをどう思えばいいのか、わからないの」
ヴァリィは僅かに首を傾げて、先を促す。
「命の恩人なのは確か。だけどそもそもあたしの部族を滅ぼしたのもあなた。あたしはあなたを憎めばいいの?それとも感謝すべきなのかしら」
ヴァリィは上体を起こし、泉に向かって座った。
「座ったらどうだ」
レンはほんの少し間をおいて、ヴァリィと並んで座る。
「草原でふたつの部族が出会えば、道はふたつしかない。友情か戦争か。俺たちは最初、農耕民を滅ぼす戦いに手を貸すよう頼んだ。これをお前たちキュイ族は断ったのだ。後は戦いしかない」
「ずいぶん勝手な言い分ね」
「そうかな?大昔から草原の民はこうやって生きてきたんだ。そうでないなら農耕民の流儀に毒されている」
ヴァリィの目に炎上する荷馬車の円陣が甦ってくる。炎の帳の向こうには、折り重なって倒れる女たちの姿。
「キュイ族からの戦利品はなにもなかった。食糧も家畜も、女も…、手に入れる筈のもの全てが灰になってしまった。お前ひとりだけが、あの戦いでの戦果だ」
「あたしはただ仲間に戦勝を誇るための戦利品?」
自ら命を絶った女たちの服に火が燃え移り、やがて体も黒く焦げてゆく。熱気を顔に浴びながら、人の燃える匂いを吸いこみながら、ただ為す術もなく見ていることしかできなかった。ヴァリィには目を逸らすことすらできなかった。
「男が戦で死ぬのは当然のことだ。だけれど女まで死ぬことはない」
「罪滅ぼしだとでも言うの」
「部族の伝統に従っているだけのことだ。敵の部族の女を丁重に迎え入れるのが、俺たちのやり方だ」
部族の戦士を産み増やすため、敵の女も受け入れる。戦に出る戦士に代わって子どもを育てるのがその女たちである以上、女たちが部族に対して憎悪や怨念を抱くことがないようにしなくてはならない。それはムラト支族が長年続けてきた伝統だった。
「女の子たち、あなたがあたしと結婚する気じゃないかって噂してたわ」
「嫌か」
「え?」
レンは言葉を止め、瞬きもせずヴァリィを見つめた。その表情からは驚き以外の感情は読み取れない。ヴァリィは自分の目から、更にその奥を覗き込まれているような気がして、視線を泉に移した。茜色に沈んだ水面が、ときおり鋭い光を反射している。
「嫌なら嫌でかまわない。無理にお前の意に反することをさせる気もないし、嫌がられたからといって扱いを悪くすることもない。部族の女たちと一緒に暮してくれ。そのうち生まれた時から、俺たちと暮らしていたように思える時がくるだろう」
横目でレンを伺う。レンはもうヴァリィの方を向いてはいなかった。少しばかりうつむいて、静かに水面を眺めているばかりである。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
