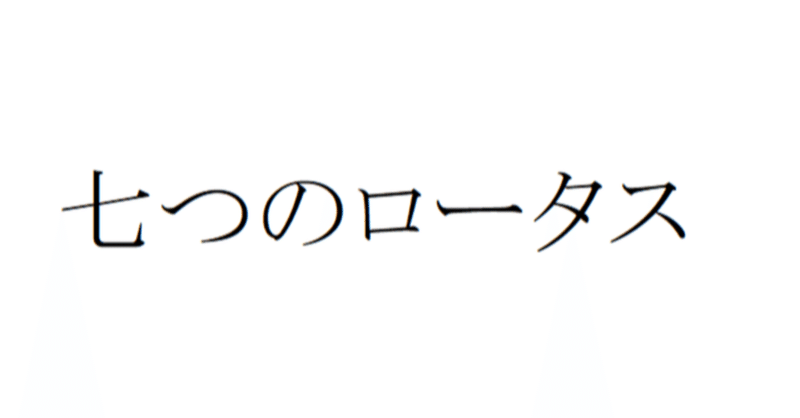
七つのロータス 第43章 パーラIV
侍女の真珠が、紗の帳を掻き分けるようにして入ってきた。今となってはこの奴隷身分の少女と乳母だけが、心の許せる存在である。パーラはゆっくりと顔を上げた。会議が始まるので呼びにきたのだろう。よくもこう毎日毎日会議ばかり…。
真珠が何も言わぬうちに静かに立ちあがり、目を伏せたまま部屋を出ようとして、帳を押しのける手が止まる。隣の部屋で待っていたのはジャイヌではなかった。
「先生」
オランエがそう呼ぶので、パーラにとってもティビュブロスは「先生」だ。
「陛下、勅令は果たされました」
ティビュブロスはそう言って、深々と頭を下げる。
「勅令……」
暫くティビュブロスの頭の上をさまよった視線が、不意に焦点を結んだ。右手が首飾りの玉璽を握り締める。
「兄さま!」
ティビュブロスはパーラの小さな叫び声は聞かなかったふりをした。
「大逆の罪を犯したジャイヌは、討たれました。陛下におかれましては、新たな摂政をご指名あそばされますよう奏上いたします」
「それは兄さまでもいいの?」
パーラは躊躇いながら問い返す。
「陛下にご要望が無ければ、わたくしめがオランエ様を推薦いたすつもりでした」
不意に涙がこみ上げてきた。両目に熱い滴が溜まる。
「兄さま」
もういちど呟いて、パーラは指で目を押さえた。
* * * *
騙された。そう悟った時には、既に皇帝の前に跪いた後だった。玉璽を手に入れるため、パーラを説得するだけの筈が、まるで話が違う。摂政になれという言葉の前では、捕らえるだけと聞いていたジャイヌが殺されたことさえかすんでしまった。
「そのような大役は、私にはとても荷が重うございます」
謁見の間に設けられた壇は、会議の間とは違って高い。跪くと視線は帝の足許よりも低くなる。壁際に控える書記や侍従の視線を意識しながら、オランエは深々と頭を下げた。
「大役なればこそ、あなた以外に任せられる者はないと思っています」
パーラが壇上から落ちついた声をかける。顔に疲れは見えるけれども、いざ改まった場に出れば、幼い頃から厳しく躾られた皇族としての挙措を見失いはしない。オランエは少しばかり妹を見直したが、思考はすぐに自分のことに戻る。なんとかして断らなくてはとは思うものの、皇宮に呼びつけられていきなり摂政への就任を要請されたオランエには考えをまとめる余裕が無い。
「私のような若輩よりも、ティビュブロス様はいかがでしょう」
「ティビュブロス殿は要職を歴任した優秀な廷臣ではありますが、軍事の経験が全くありません。特に今の時期には、文武に通じている必要のある摂政職には不適です」
あらかじめ入れ知恵されていたか。もう他の名前を出すわけにはいかない。野心家のラジや、しょせんはジャイヌの同類でしかないネ・ピアだのハジャルゴだのは論外だ。追詰められたオランエの頭から胸へと憤りが駆け抜けてゆく。
長い沈黙の後、オランエは自分の負けを認めた。
「拝受いたします」
「では、明朝の会議で正式に帝より任命されます。殿下はこのまま皇宮にお移り下さい」
改めて深く頭を下げたオランエに、若い書記の声が告げた。
不敬の罪で斬首される危険を冒してでも、全てぶち壊してやろうか、と思わなかったわけではない。しかしようやく救いを得た思いでいる妹を思うと、それはできなかった。腹の中で蝮が動き回っているような不快感。背に冷たい汗がにじむ。体が奇妙に強張り、平伏したまま頭を上げることさえできない気がした。
オランエはその日のうちに、与えられた内宮の一画に移った。女官の案内に従って、部屋に入りゆっくりと見渡す。全く壁の無い一面から、回廊を通して庭園を眺めることのできる大きな部屋。それに続く小さくて落ちついた寝室。かつて暮らしていた部屋とは違うが、よく似てはいる。何か必要な物があればティビュブロスの屋敷まで取りに人を遣るという女官に、いらないと答える。托鉢の鉢以外には、何も物など持っていないのだからと。
女官が立ち去ると、床の敷物ではなく南方の風習である椅子に座り、ぼんやりと宙を眺める。すぐにでも帰るつもりでいた瞑想者の森が、もはや手の届かない場所に遠ざかってしまった。いつしか少しばかり前かがみになり、視線は床に落ちていた。逃げられない場所に追い込まれ、一度は逃れ去った宮廷という怪物にもう一度立ち向かわねばならないという思い。自前の権力も強い後ろ盾もなしに、その宮廷で生きてきたティビュブロスの力を思い知らされたという思い。そればかりが頭の中を駆け巡って、他には何も考えることができない。
明日には皇宮での会議に出なくてはならない。その場で居並ぶ有力な廷臣たちから注がれる視線。それを思うと気が狂いそうだ。
出口の無い思考に捕らわれてのたうちまわるのに疲れ果てると、オランエは叫び声をひとつあげて立ちあがり寝室へと移った。横になっても不安はいっこうに晴れない。次第に投げ遣りな気分が増してくる。
「どうにでもなれと言うんだ」
瞑想者の森に戻りたいという激しい感情とともに、オランエは眠りに落ちた。
混乱した夢から覚めると、もう日が暮れていた。しばらくは身動きもせず、闇を見つめる。気分はいくらか落ち着いていた。
「摂政か」
無理やりとは言え、一度引き受けたものを放り出すことはできなかった。自分ならば摂政の務めを果たすことができる、という自負もあった。摂政の座に就くことを喜ぶ気持ちは全く無いが、貴族に生まれ皇族として育った間に教え込まれた使命感が少しずつ甦ってくる。
ダガ、イマノオマエハ、オドラサレテイルダケデハナイノカ。うるさい!心の中に突然響いた声に応える。避けられぬ状況を受け入れる決心がついたばかりのオランエを、声は再び揺り動かした。オマエニ、セッショウガツトマルノカ。務まるとも!やってみせる。オマエガセッショウヲリッパニコナスコトナド、ダレモノゾンデイナイカモナ。コウテイヲテナズケル。ソレイジョウノコトハ、モトメラレテハイナイ。それでは誰かが、政を思いのままにしようとしていることになる。ばかばかしい。筋書きを書いたのが、ラジでなく先生だということくらいはわかっている。先生はそんな野心家ではない。全ては帝国のため。皇帝を殺害した逆臣を除き、皇宮を正しい姿に戻すために行ったことだ。そのために自分の力が必要なら、協力を惜しんだりするものか。ガンバリスギルト、なーぷらノヨウ ニコロサレルコトニナルカモナ。
「失せろ!」
声は消えた。オランエは仰向けのまま、闇を睨んでいた。
* * * *
騙された。ジャイヌの死という大事件にもかかわらず淡々と進んで行く会議の中で、ラジだけが静かに怒りの炎を燃やしていた。息子である自分も知らぬうちに、ティビュブロスは有力者たちへの根回しを終えていたのだ。事件の前は計画が露見しないことを最優先していたのだから、前日の会議が中止されてから、わずか一日の早業だったはずである。
会議ではまず死んだジャイヌに代わって、オランエが摂政に任命された。皇帝の強い意向を受けてのものだ、という様子を列席者に見せつけながら。
「何者かに」殺された近衛将軍の後任は、近衛軍の兵士たちに人望のあついゴウイイが指名される。
「陛下には摂政を捕らえるように命ぜられましたのに、抵抗されたとは言え不首尾に終わりました。臣にはこのような大役を任ぜられる資格はありません」
ゴウイイは白々しい弁を述べて二度辞退した後で、近衛将軍の職を受けた。
当のティビュブロスは皇帝の私的な相談役として内宮に出入りする資格を与えられ、公的には参議に復帰した。更に皇帝自身の推薦によって、ネ・ピアとハジャルゴの縁故がそれぞれ一人ずつ参議の資格を得る。一方ジャイヌ派に与していた有力者たちには、懲罰的な人事は一切なかった。人事についての話はそれで終わり。会議は未だ解決の報せの入らぬプハラの戦況や、草原のオアシス国家との交易が途絶した影響などの議題に移ってゆく。ラジは今までと全く変わらず、ただそれを聞いているだけの立場だ。そもそも全て俺が考えたんだ。ラジはそう思いながら、奥歯を噛み締めた。会議が終わるまでの長い時間を、拳を握り締めてはまた開いたり、落ちつかない視線を人々の上にさまよわせたりして、ただ堪えるしかなかった。
* * * *
床に叩きつけられた杯が、音をたてて砕け散った。ラジの怒りをたたえる双眸が、ティビュブロスを見下ろしている。疲れきった体で息子と一戦交えるのは気が進まなかったが、避けることはできそうになかった。部屋に入ってくるなり、人の酒を取り上げて投げ捨てるなど尋常ではない。
「まあ、座れ」
奪われた杯とは別の杯を取って酒を注ぐ。可能な限りの余裕を演出する必要がある。
「ふざけるな!人の計画を横取りして俺には何も無しとはどういうことだ!」
ラジは立ったまま、まくしたてる。
「お前の計画、か。あのままやっていたら、お前の首は地面に転がっていた筈だ。なんと言っても杜撰だったからな」
ティビュブロスは笑い飛ばした。
「最初に考えたのは俺だ。その俺が…」
「出世できなかったのが、不満か?」
ラジに最後まで文句を言わせる気もない。
「憶えておけ。お前に実入りのいい役職をあてがってやるような余裕はない。有力貴族を懐柔するのに使える役職すら足りないんだ。それに露骨に自派を優遇する人事ができるような権力も、儂らにはまだない」
一口酒をあおる。
「将来の勉強のためと言うなら、書記か五百人隊長あたりの仕事を用意してやろう」
「オランエは摂政で、俺はただの書記か!」
「五年待て。五年このまま行ければ、もっと足許が固まるだろう。もっともお前が無能なら、どんな仕事も任せる訳にはいかんがな」
「話にならん!」
ラジは怒りを露わにして立ち去った。ティビュブロスはそちらには目も向けずに、杯の酒を流しこんだ。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
