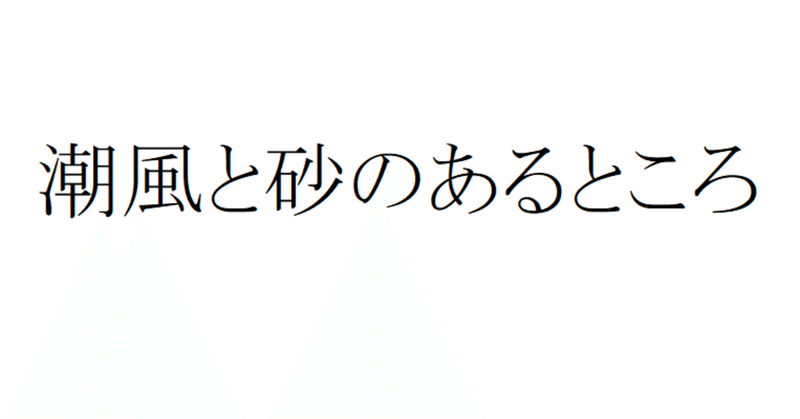
潮風と砂のあるところ 3・空へ
馬の蹄音がアンリの夢想を破った。医者がやって来たのだ。医者を室内に導くと、屋外に出て壊れた飛行機に歩み寄った。女に遠慮しただけではない。アンリにはやるべきこと、いや、やるべきだと思える事が残っていたのだ。発動機が完全に止まっているのは、女を引っ張り出しながら確認している。見たところ燃料が漏れ出している様子も無い。荷室の鍵は操縦席のボックスに入っていた。
準備が終わる頃には、陽射しは午後のものになっていた。痛いような感覚こそ和らいだものの、気温はいまだ上がり続けているのだろう。流れる汗は収まる気配を見せない。
屋内に戻ると、医者は帰り支度をしていた。
「打撲傷や圧迫による内出血は酷いし外傷もあるが、大怪我はしとらんよ。歩き回ったって、特に問題はないくらいだ」
医者は笑った。アンリは礼を言って、医者を送り出した。
航空郵便会社への電話でカタリナ=ヤハーという名だとわかった女は、長椅子に座ったまま虚ろな目を宙に向けていた。近づいても、アンリには注意をむけようともしない。何種類もの塗り薬の強力な臭いが鼻をついた。
「出かけてくるから、ゆっくりしていてくれ。無線機以外には盗られて困るようなものはないし、ここらへんは戸締りせずに寝ても大丈夫なような土地だから、特に気にしてもらうようなことはない」
女性パイロットはようやく顔を上げ、アンリの顔を見た。
「明日の昼までには戻る。台所には食べ物も飲み物も充分にある。自由に飲み食いしてくれ」
アンリは言いながら、箪笥の扉を開けた。
「どこへ行くの?」
「せめて荷物の賠償金だけでも払わないで済む様にしに行くのさ」
取り出した飛行服、ゴーグル、ブーツ、何年も使ってない品物だが手入れに怠りはない。
「飛ぶの?あなたが?」
「意外かい?」
アンリは女に笑いかけたが、答えはなかった。女はただ不思議そうな目をアンリに向けるだけだった。
格納庫の奥から引き出された大戦中の偵察機は、滑走路の端で静かに陽光をはね返していた。戦争が終わった後で武装を外され、帝国空軍の紋章を始めとする 全ての標章を塗り潰された飛行機。アンリが買い上げたものの、この飛行場にやって来る時に乗って以来、格納庫の奥でまったく省みられることのなかった機械は、静かに再び空を飛ぶ時を待っていた。汗だくになりながらクランクを回しエンジンを始動させると、上着をしっかりと着込み操縦席に登る。吹流しで風向きを確認してから時計に目を移す。日が暮れるまでにアラニア・ノヴァの空港に辿り着けるだろう。ゴーグルを目に当て顔を上げると、窓越しにカタリナがこちらを見守っていた。手を振ってみたが、やはり答えはない。あるいは微笑んだり、何か言ったりしたのかもしれないが、この距離ではわからなかった。動力軸を繋ぐと、軽い衝撃があってプロペラが回り始めた。出力を上げる。機体が滑走路を滑るように進みはじめる。轟音とともに加速。タイミング良く操縦桿を引くと、 飛行機は静かに浮かび上がった。何年振りかの感覚に、胸の中が何か液体のような物で満たされていく。
高度を上げる。いつも見上げている岩山を一息に飛び越す。岩山の頂上に大戦中の高射砲陣地が見えた。何丁もの機銃が朽ち果てるままに打ち捨てられている。
ところどころ真っ白な雲の塊が浮かび、空はひたすらに青い。
針路をほぼ南南東、まっすぐアラニア・ノヴァへ向かう方向に取る。海のように砂の広がる地形はやがて岩山の台地に遮られる。断崖の縁、こぼれ落ちそうなぎりぎりの所に、家々が身を寄せ合う様に立つ集落があった。白い石材が照りつける陽光をはね返し、砂漠の中で死んだ動物の骨のようだ。熱帯の午後、動いている人影は目に入らない。
前方に目を向けると、いくつもの真っ白な雲の塊が身を浮かべていた。アンリは雲の端から"クジラ"が姿を現すのではないかと、目を凝らしていた。"クジラ"がこんなところを飛んでいるわけはない。そう思っても、一度身についた習慣は、容易には拭い去る事はできない。アンリは他に何者も飛んでいる筈の無い空の真中で油断無く周囲に目を配り、自分を狙う猛禽を、獲物となるべき"クジラ"を探しているのだった。馬鹿らしい。そう思っても、アンリは周囲に目を配る事は止めなかった。"クジラ"はいつだってこんなふうによく晴れた日に、あんな真っ白な雲から突然現れたのだから。
アンリは必死に上昇を続けていた。なんとしても"クジラ"の上へ出なくてはいけないのだ。薄い空気の中で酷使された発動機があえいでいる。ここでエンジンが止まったら、すべてはお終いだ。それでもアンリはスロットルを緩める事はなかった。後にはマーカス・イェール曹長とエラ・ゼフィル上等兵の機が続く。 充分な高度を確保すると、アンリは"クジラ"の群への緩降下へと入った。長く引き伸ばされた砲弾の形をした船体が、幾つも宙に浮かんでいる。アンリはそのうちのひとつに狙いを定めた。充分近づいたところで、機銃を叩きこむ。続いて敵の船体上の銃座からも、ガトリング砲が応射された。アンリは航路を一定させぬようにして、敵の射線を避けてゆく。敵の頭上を飛び越しざま、機体の下に吊り下げた焼夷弾を切り離した。焼夷弾と言っても、壊れやすい陶の容器に可燃性の液体を入れただけのものだ。タイミング良く投下された焼夷弾は、次々と巨大な船体に吸いこまれていく。
「くそっ!発火しなかったか!」
アンリは振り向いて、狙った敵が悠々と飛行を続けているのを確認すると毒づいた。まあいい、自分の仕事は終わりだ。あの飛行船は機銃の一掃射、一発の曳光弾で燃えあがることになる。それは"飛蝗"の仕事だ。アンリは翼を振って僚機に合図すると、基地へと機首を向けた。
アンリの背後で、強い光が閃いた。振り返ると"クジラ"の船首が火の玉に包まれていた。誰かの放った焼夷弾が、敵の銃座に命中して弾薬が誘爆したのだ。
「やった!」
アンリは腕を振り上げたが、次の瞬間には興奮は消え去っていた。せっかくの大爆発はうまく燃え広がらなかった。船首の上部を吹き飛ばされた"クジラ"は、 細かい気室に仕切られた内部の構造を露わにしながらも、まったく浮力を衰えさせた様子はなかった。大破した飛行船はさすがにゆっくりと旋回して、帝都への 爆撃行からは脱落していく。しかし逃げ返ろうとするその姿には、なおも見るものを圧倒するような力が備わっていたのだ。
「化物め」
アンリは敵の爆撃隊がわずか一機を欠いただけで、なおも進撃を続けているのを見届けると、もう二度と振り返らなかった。
帝都マクシミリアンポリスの上空に無数の"クジラ"が舞ったのは、大戦が始まって半年が過ぎた頃だった。アンリの属す第三飛行団の制空戦闘隊は、念願の新型機への装備転換のため、ちょうどマクシミリアンポリス近郊の基地で、慣熟訓練中だった。
「新型機を飛行船の迎撃に使うなんて、馬鹿げている!」
飛行隊にそのまま首都に留まるよう命令が出たとき、アンリは戦闘隊長に食って掛かった。新型機はそのような任務にはおよそ不向きな代物であり、まして前線にはこの対戦闘機戦闘に特化した機体を必要としている戦場があった。
「プロペラ同調式の機銃を装備した機体は我々の悲願でした。だが"クジラ狩り"のために、新型機が必要だったんじゃない!やっと、敵の戦闘機とまともに勝負ができるというのに!」
戦闘隊長は下手をすれば軍法会議ということにもなりかねない発言を、じっと聞きつづけた。
「貴様の気持ちはよくわかる。私だっておなじ気持ちだ」
男爵家の次男に生まれ、機体にも自分の紋章を描き入れている隊長は、常に「現代の騎士」という自らの出自を意識している様に思われる。もはや演出とすら言えないほど染みついてしまった「貴族的」な立ち居振舞い、言葉遣いは周囲にも無言のうちに強い影響を与える。彼の周りでは空気さえもが、襟を正さざるを得 ないようだ。
「空軍上層部の意向なんだ。開戦の直前に発足したばかりの空軍の名誉にかけて、これ以上帝都が空襲されるのを黙って見ているわけにはいかない、ということさ」
「最新鋭機があれば、北部戦線で制空権を奪取できるかもしれないんですよ」
「そして陸軍に手柄を立てさせてやっても、空軍は帝都をむざむざ爆撃されたことで肩身の狭い思いをすることになるんだ。北部戦線で陸軍が総崩れになれば、空軍の失態は目立たなくなるさ」
飛行隊長が本心から言っているのではない、ということはよくわかっていた。隊長自身も怒りで胸のうちが煮えたぎっていることは、いつもと変わらず冷静な言葉のうちにも表れていた。
「まあ、暫くのしんぼうだ。帝都を直接空襲だなんて、実効のあがらない作戦が長く続く筈が無い。心理面、それと外交面での成果を狙った短期的な作戦だよ。本来の任務に戻れる日も遠くはないさ」
しかし戦闘隊長の観測は楽観的すぎた。その後半年以上たっても、散発的な帝都空襲は続いていた。水素ではなくヘリウムガスを使った飛行船を量産する工業力、そして神聖不可侵である皇宮カステル・マクスミリアノが直撃弾をすら受けているという驚愕から立ち直った帝国側も、有効な反撃手段は無いままだった。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
