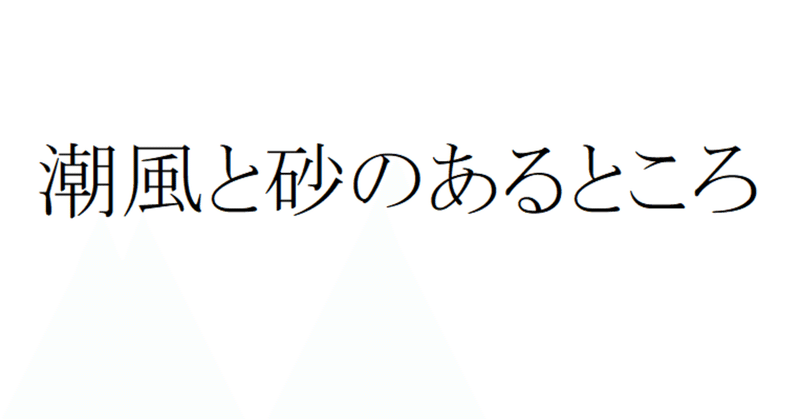
潮風と砂のあるところ 2・女パイロット
砂漠と海、そして岩山。空の青、薄くちぎれちぎれに空を流れる雲。目に見えるのはそれだけだ。アンリは無線室の大窓の前に腰掛け、定期便がやってくるのを待っていた。膝の上に読みかけの本を置き、指をしおり代わりに挟んで、北の空に目を凝らす。今日のパイ ロットは聞きなれない声だった。また誰かなじみの操縦士が夢破れて会社を去ったか、それとも命を落としたとみえる。やがて空を貫く航路上に、一点の影が現れた。今日も無事、定期便は上空を通過。万事異常なし。そう思いかけた時、無線機がわめき出した。
「エンジン不調。エンジン不調。そちらに着陸する」
アンリは首を振って、無線機の前に座りなおした。
「ここまでもつか?」
「たぶん。いや、今、発動機が完全に止まった」
アンリは横目で窓の外を見た。飛行機はまだかなりの距離がある。
「よし、できるだけ陸に近づけて着水しろ。すぐに舟を出して拾ってやる」
「飛行機は?荷物は?」
馬鹿げた質問だった。
「諦めろ。しかたない」
「なんとか飛行場まで辿り着ける様、やってみる」
「やめろ!無理をするな!」
返事はなかった。窓の方に向き直ると、機体は必死で水平を維持しようともがいていた。
「おい!やめるんだ!機体と命とどっちが大事だ?」
返事はない。アンリは思わず滑走路へと駆け出していた。飛行機はじわじわと高度を落としながらも、まだ安定を保っていた。しかし高度を維持しようという無意識の操作なのだろうか。じわじわと機首が持ちあがっていく。
「失速するぞ」
それでも操縦士はきわどい角度を保ちながら、滑走路と砂浜を隔てる砂丘を越えた。高度を落としていた飛行機はここで遂に失速した。バランスを崩しながらも、操縦士は必死に方向舵を操作して滑走路に滑り込もうとしている。アンリが成す術もなく見守っているうちに、飛行機、戦争中のMF‐3型連絡機をベースにした郵便機は、滑走路へと進入してきた。プロペラは既に向かい風を受けて緩慢に回っているだけで、推力を生み出してはいない。機体の水平は不安定で右に傾いたり、左に傾いたりを繰り返している。アンリは祈るような気持ちで、工具箱と救急箱を取りに格納庫の中へと駆けこんだ。郵便飛行機の左翼端が車輪より先に接地し破壊され、同時に機体が滑走路上で左に急旋回するのが格納庫の開け放たれた扉から見えた。
重い箱を二つも提げながら、外へ走り出る。郵便飛行機は滑走路脇の駐機場で、うずくまって止まっていた。かつてこの飛行場が賑やかだった頃なら、翼を連 ねる何機もの飛行機を巻き込まずにはいられなかっただろう。郵便飛行機は何もない空き地の真中で、先の吹き飛んで無くなってしまった左両翼を地につけて、斜めに傾いている。アンリは飛行機に駆け寄ると、操縦席を覗きこんだ。操縦士は体をシートに固定されたまま、首だけ前に垂らしている。死んでいるのか、気を失っているだけなのか判然としない。呼吸を確かめるために、頭を持ち上げる。
「女か」
アンリは一瞬動きを止めたが、すぐに仕事に戻った。今は他事を考えているひまはない。確かに呼吸をしていることを確認すると、ナイフで操縦士を座席に固定しているベルトを切断し、機体から引き摺り下ろす。額の左上、髪の生え際に大きな切り傷があって、かなり出血はしているが、深刻な外傷でははない。アンリは小柄な操縦士を抱え上げると、強い陽射しを避けられる室内へと運びこんだ。
操縦士が気を取り戻したのは、アンリが二件目の電話を終えようとしているところだった。
「怪我人が目を覚ましたようだ。また後でな」
電話を切って操縦士に目を向けると、女は寝かされていた木製の固い長椅子の上で上体を起こし、ぼんやりと宙を見ていた。アンリが飛行帽を外した時にあふれるようにこぼれおちた長い髪が、今は背中に垂れている。
「飛行機は?」
女はアンリの姿に気づくと、尋ねた。アンリは女の額から膝の上に落ちた濡れハンカチを拾って、未だに血のにじみ出ている傷口に当てた。
「もうしばらく押さえていろ。今、包帯を巻いてやる。」
「ねえ!飛行機は?荷物は?答えて!」
アンリはまっすぐ窓の外を指差した。郵便飛行機は半ばまで砕け散った左主翼と胴体で身を支え、平行する二枚の右主翼を斜めに空へと突き出している。
女は一、二度かすかに口を動かしたが、言葉にはならなかった。やがて奥歯を噛み締めると、その間から嗚咽をもらした。
「まあ、そう嘆くな。命があっただけよかったじゃないか。後で見てくるけど、荷物だって無事な物も多そうだ」
「うるさいっ!」
女はアンリが肩に置いた手を、はじくように払いのけた。アンリは操縦士の目に浮かんだ涙を見て、安易に慰めの言葉をかけた自分の迂闊さを呪った。
「もうおしまいだ。畜生」
震える唇でそういうなり黙り込んでしまった女を前に、アンリは町から医者が来るまでの時間を思っていた。早くてもあと半時間はかかるだろう。アンリは暫く女を放っておいてやることにした。
ささやかなキッチンで、ミルクを温めて持っていってやる頃には、女はいくぶん落ち着いていた。
「飲むか?牛乳じゃなくて、山羊のミルクだが…」
女は黙ってカップを受け取ると、長椅子の上で座り直そうとした。
「あまり動くなよ。あばらが折れてるかもしれないんだから。どこかに突き刺さったら、おおごとだ」
「ありがとう」
女は小さな声で礼を言うと、両手でカップを持ったまま視線を窓の外へ、壊れた飛行機へと移した。飛行機は幾度見なおしても、壊れ果てたままだ。また顔が歪み、言葉にならない声が漏れる。
「やっと…、やっと手に入れた飛行機なのに!ようやく仕事が順調になってきたところだったのに!」
飛行機から顔を背けてうなだれ、吐き捨てるように言う。
「お前さん、フリーランスかね」
相手は小さく頷いた。
「操縦は空軍で?」
「いいえ、空軍では女性パイロットは募集していなかった。女のパイロットは戦争中だけの特例だと言われたわ」
アンリの胸に痛む物があった。小さな小さな棘が、心臓を一刺ししたように。
「民間の飛行学校で習ったのか?高くついたろう?」
「父の遺してくれたお金に借金もして、仕事を始めたの。でもそれももうお終い。何もかも…、お終い」
女の声は徐々に小さくなり、消えていく様に言葉は終わった。
アンリは言葉無く、首を垂れたまま身動きもしなくなった女を見下ろし、窓の外に目を移した。砂漠の日は、砂やその他目に入るもの全てに照りつけ、反射してもなお目を刺すほどに鋭い。その光の中、飛行機の残骸はまるで遠い過去からそこにあったかのようだ。
地に繋がれた飛行機。アンリは再び女に視線を移す。その嘆きの意味をアンリははっきりと知っている。女の嘆きが我が事のようで、腹の中を刃物で掻き回される感覚に顔をしかめる。機体の購入に当てた資金も回収していないに違いない。その上期日までに荷物を運べなかった違約金は莫大なものになる。それに比べれば微々たる物とは言え、破損した積荷の賠償金だってばかにはならない。女がもう一度フリーのパイロットとしてやりなおせる可能性は全く無い。残されたのは借金を返すためだけに働く人生。それだけだ。
「結局、俺たちは利用されてるだけなんだ」
突然マーカスの声が耳元で響いた。
「軍隊は俺たちが、空を飛びたい!空を飛びたい!たとえどんな危険を伴おうと、空を飛ばずにはいられないって気持ちを利用して、飛行機を餌に、戦場に追い立てているのさ」
懐かしい声。この声の主もまた、飛行機と運命を共にした。飛行機という魔物、空という禁忌に魅入られた者の末路はいつだって悲惨だった。アンリは幾年にもわたって、幾十人ものパイロットを見てきた。空に別れを告げ、立ち去っていく者、それも五体満足なままで立ち去っていくものは僅かだった。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
