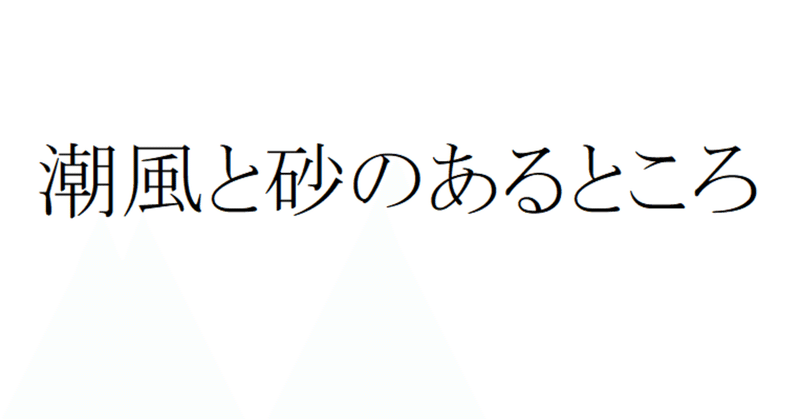
潮風と砂のあるところ 6・追憶
走っている。エラの名を呼びながら走っている。地面は乾いているが起伏が激しく、ひとつ間違えば捻挫してしまいそうだ。大地は見渡すばかりの緑である。アンリの腰の高さに揃った秋小麦。その穂を掻き分け踏みつけながら急ぐ。雲一つ無い明るい青空が、地平線で緑の大地と接している。コントラストすらない、たった二色に染め分けられた世界の中で、ただ一つだけ小さな染みのような色彩。アンリはそれが、墜落した飛行機だと知っている。主翼に張られた帆布のベージュ色。翼に描かれた帝国空軍の紋章。アンリはエラの名を叫びながら走っている。戦闘機は大きく傾いで、 上下の右主翼を空へ突き上げたままの姿勢で動こうともしない。
アンリはエラの名を呼びながら、飛行機にたどり着く。左の主翼は上下とも無残に壊れ果て、地面にも深い傷跡を残している。コクピットに回る途中も、エラの名を呼びつづけるが返事は無い。ベルトで座席に固定された体は、力なく重力の引き寄せるに任せて、上体を地に向けて垂れ下がらせている。必死で操縦席からエラの体を引きずり出す。その間にも、生命を感じさせる兆候は何一つ無い。両腕に抱きかかえると、女の首が大きくのけぞった。はずみで地に落ちていく飛行帽から滑り出す長い髪。熟れた小麦の穂の色をした髪。切れた額から流れ落ちる血が、赤黒く髪の根本にこびりついている。
「カタリナ!」
自分の叫び声で目が覚めた。しばらくそのまま、天井を見つめる。心臓が鼓動を数える事もできないほど早く打っている。アンリは深い呼吸を続け、気分が落ちつくのを待った。まだ日は昇っていなかったが東の空は明るく、かすかな光が窓から差しこんでいた。
何故、エラがカテリナと入れ替わっていたのだろう。エラの遺体など見ていない。あの風景もどこのものだとも知れない。助け出したのがカテリナだったのは、別に不思議ではない。昨日、実際に同じ事をしているのだから。とは言え、飛行機に駆け寄りながら叫んでいたのはエラの名だったのだ。心臓は落ち着いてきたが、まだ苦しいほど早く打ちつづけている。エラのことを忘れかけているのだろうか?あの痛みが過去の物になろうとしているのだろうか?
クジラ約三十、前線を通過、の報を受け第三飛行団戦闘隊はただちに出撃した。いつもどおり敵のやや上空から緩降下しながら、アンリは無数の飛行船が密集した方陣を形作っている、その威容を確認した。巨大な船体に描かれた鹿の枝角の紋章がはっきりと見て取れる。
「新型だ」
アンリは呟いた。敵の中には今まで戦ってきた飛行船もあったが、あきらかに銃座を増やし武装を強化した飛行船が半数以上を占めている。
「やばいな」
今までクジラを攻撃する時に利用できた機銃の死角が無くなっていた。今までの攻撃法が危険になってしまったことをはっきり意識しながら、なおも決然と飛行船に接近してゆく。機銃が船体の真上だけでなく、船体左右に設けられた張り出しの上にも据えられている。いつもと違って、敵はこちらよりも先に発砲してきた。アンリはランダムな回避運動をしながら、一番外側の飛行船の横腹に同高度から近づく。こちらにも新兵器があるのだ。機銃とガトリング砲の嵐の中、アンリも機銃を発射する。飛行船の銃手への威嚇以上の効果は期待できないが、それでもやらないよりはましだ。振り返って、味方が全機ついてきていることを確認すると、アンリは機体を急上昇させた。敵の船体を飛び越しざま、焼夷弾を投下する。今までの可燃性の液体を入れただけで、発火するかどうかは運任せの焼夷弾ではない。弾の中が二つに仕切られ、混合すると発火する性質のある二種類の薬品がそれぞれに収められている。容器が壊れれば、確実に発火するしくみだ。
突然、激しい衝撃に体を揺さぶられた。敵の機銃弾が、アンリの機体を貫いたのだ。慌てて振り返ると、アンリの目は燃えあがる飛行船の姿に吸い寄せられ た。被弾による損傷の確認も忘れるほど壮大なページェント。クジラはいかなる攻撃にもたじろがず、悠々と空を飛びつづけているように見える。しかし、その船体は炎をあげて燃えている。アンリだけでなく後続機も焼夷弾を命中させ、いまやその炎は船体の上部全体を覆っている。攻撃は完全に成功し、あの飛行船がもはや墜落するしかない事は明らかだ。それでも飛行船は浮力を失わない。攻撃される前とまったく同じように飛びつづけている。アンリの目に飛行船の炎は、 それ自体の内から噴き出す怒りの炎のように見えた。神話の時代の荒ぶる神。末期にあって、なおその力を誇示する巨鯨。アンリはいつまでも目を離すことができなかった。
本来の基地ではなく、手近な基地に着陸した途端、操縦士たちは戦闘隊長に呼び集められた。基地の整備員に飛行機を任せ、駆け出す。馴染みのない整備員に機体を預ける事に、かすかな不安と不快感を覚えた。
自ら第一中隊を率いて出撃した戦闘隊長の日焼けした顔は、汗と砂埃にまみれている。パイロットを前に整列させた隊長は、滑走路の端で再度の出撃命令を伝えた。
「我々はこれより、敵飛行船隊に対し反復攻撃を加える。各員、機体の損害状況を把握し報告せよ。出撃可能か否かの判断は、各自に任せる」
アンリは再び自分の戦闘機のもとへ駆けもどる。
「被弾の状況はどうだ?」
「機体胴部に二発。大穴が開いてたんで、塞いでおきました。応急処置ですが強度に問題はない筈です」
整備員の指差す所を見ると、木製の胴体に内側から板が当ててある。ただ釘打ちしてあるだけだが、構造的に負担のかかっている部分ではない。整備員の言う通り問題はないだろう。この整備員は優秀だ。アンリは整備員の適切な処置と、明確な返答に満足した。
「よし、第二中隊・一番機、出撃可能!」
朝の約三分の二に兵力を減らした部隊は、もう一度焼夷弾を積んで飛び立った。会敵地点はマクシミリアンポリスの上空になるだろう。兵力が減っていても、 熟練のパイロット達はスムーズに編隊を組み終えた。アンリは後方にマーカスとエラがついて来ているのを確認した。彼等と一緒なら死なずにすむような気が する。
離陸して間もなく、攻撃を終えて帰投する飛蝗部隊とすれ違った。対飛行船用の戦闘機は、敵と並んで飛びながら後席の機銃で敵を攻撃する昔ながらの戦法を追及した機体だ。射角を広く取るため胴体は長く、後席は主翼よりかなり後ろに位置している。しかし水素ではなくヘリウムを使い、重武装しているエラントの飛行船に対しては、飛行船には最適と思われていたこの戦法の優越性は失われてしまった。そして鈍重なこの機体では、アンリ達のような焼夷弾攻撃も不可能である。彼ら旧式機を与えられた部隊は、ひたすら古い戦法を続けていくしかない。アンリは遠くを過ぎ去っていく飛蝗部隊を見送った。編隊の組み方は雑で、編隊の周辺や後方に位置する機体は、まっすぐに飛ぶ事さえもままならぬようだ。彼等のほとんどは被弾しているだろう。中には銃手が死亡していたり、操縦士が負傷しているものもあるかもしれない。彼等のうちには、基地に辿り着くまでに力尽きる者もあるだろう。
アンリたちの部隊は、マクシミリアンポリスの爆撃を終えた飛行船に追撃をかけるかたちになった。いつもの攻撃パターン通り、緩降下で敵を捕らえられる位置に上昇し、そこから速度を上げながら敵に向かう。飛行船の一つが視界の中で、その姿を膨らませてゆく。 船体の横に設けられた張り出しの機銃座と、船体上部にあるガトリング砲塔、更に船体下に吊られたゴンドラの機銃や砲が次々に炎を放った。アンリたちはランダムな回避運動を繰り返しながら、飛行船に肉迫する。アンリは正面に見える機銃座に銃撃を加えた。機銃を発射する振動が全身に伝わってくる。エンジンが絶えず機体に与え続けている振動や、大気が機体を揺さぶる感覚とはまた異質な感覚だ。エンジンの爆音と機銃の発射音だけが聴覚を支配している。いつもどおり敵の船体を飛び越しざま、焼夷弾を切り離した。既に隣の飛行船が前方の視野いっぱいに立ちふさがっている。二隻の飛行船からの銃撃を受けながら、機体を旋 させ戦場からの離脱をはかった。アンリが攻撃した飛行船は、何事もなかったかのように浮かんだままだ。どうやら焼夷弾は命中しなかったらしい。まあいい、また死なずにすんだ。
自分が奇妙に無感動なのは、一日に二度も出撃した疲労のせいだろうか。攻撃を終えた飛行機を集め、編隊を組みなおす間、アンリはそんな事を考えていた。 脳髄に薄紙がかかったように思考がまとまらない。おそらく注意力も相当に落ちているだろう。アンリは後方を振り返った。直属のエラとマーカスはアンリのすぐ後をついてきている。彼らを死なせずに済んでよかった。アンリは固い座席に身を押しつけた。
あと十分も飛べば、力のみなぎるような熱いスープにありつける。後方の編隊の様子を確認しようとした時、アンリが考えていたのは、兵員食堂のチキンスー プのことだった。飯を食ったら、冷たい水で汗と体に残る熱気を洗い流し、横になって寝てしまおう。西の空は既にうっすら赤く染まりはじめている。
振り返った途端、違和感があった。その理由はすぐにわかった。エラが、いない。一瞬のうちに心臓が激しく打ち出し、息が詰まった。どこだ?激しく頭をめぐらし、エラの飛行機を探す。いた!エラは先頭に立つアンリのすぐ後ろから、編隊の最後尾に位置を移していた。何があった?アンリは翼を振って、編隊の先導をマーカスに委ねると、大きく旋回して機をエラと併行させた。
エラの機は編隊の巡航速度を保つ事ができず、じわじわと脱落しつつあった。アンリは危険を承知でエラの右、ぎりぎりのところまで機体を寄せた。エラの機体に被弾した様子は見られない。発動機の不調だろうか。操縦席のエラが、アンリを見てゆっくりと首を振った。
「あきらめるんじゃない!」
叫んでも相手に届かないのはわかっている。それでも叫ばずにはいられなかった。同行して飛ぶうちに、エラの機体は目に見えて速度を落としていった。それで もかろうじて揚力を保っている。このままだましだましでも、なんとか近くの飛行場まで辿りつけないだろうか?アンリは必死で、最短距離にある着陸可能な基地はどこか考え、もう一度エラを見た。彼女の視線はじっと前方に注がれ、瀕死の飛行機のコントロールに全神経を集中している様子だ。アンリは自分の機をエラの視線の先へ、エラの機の前方へと滑りこませた。基地まで帰る事は、もう考えてはいなかった。アンリは翼を振ってエラの注意を促し、ゆっくりと高度を下げ始めた。下は岩の多い山地で、とても不時着できそうにはない。だが、ここを過ぎてしまえば…。後を振り返り振り返りエラがいることを確認し、また前方に視線を戻す。すぐ先には、地平線まで広がる緑の農地が、平らな大地がある。なんとか、あそこまで…。
幾度目か後を振り向いた時、アンリは瀕死の飛行機が遂に推力を失っていくのを見た。発動機は完全に止まり、プロペラはただ向かい風と惰性で回っているに 過ぎなかった。一瞬、飛行機はそれでも、何事もなかったかのように飛び続けるように思えた。だが次の瞬間、力を失った飛行機はそれ自体息絶えるかのよう に、機首を沈みこませた。もはやエラの傍でアンリにできる事は何もない。アンリはスロットルレバーを引き絞ると、一気に加速して基地への航路に戻った。巡航速度に達しても、レバーを緩めることはない。ひたすら機体に最大速力を強いた。エンジンが焼けつく怖れも、燃料がとぼしいことも気にならない。万が一にも彼女が命を取りとめた時の為に、一刻も早く墜落地点に人を遣ること。それ以外は何も考えてはいなかった。何度も何度も、声に出してエラの名を呼びながら。仲間たちから遅れること数分で、基地の滑走路に滑りこむ。ひょっとしたらエラもこうやって、神業のような不時着をきめて、怪我一つせずに戻ってくるかもしれない。アンリはそんな考えにすがりついていた。
だけど、そんな奇跡はおこらなかった。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
