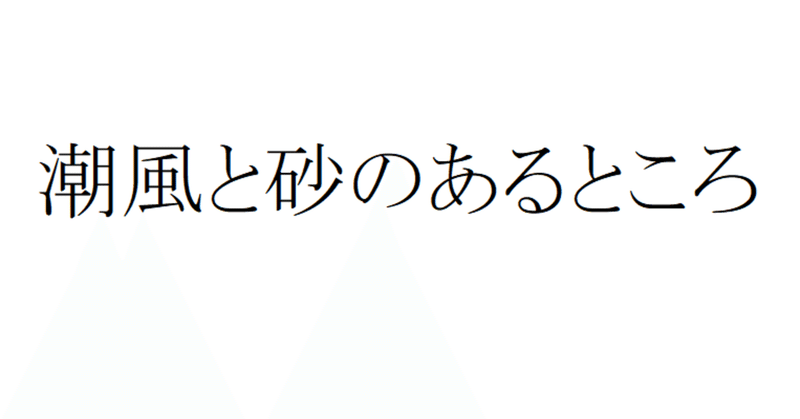
潮風と砂のあるところ 5・支社長
いつしか日は西に傾き、周囲の雲に赤みを帯びた光を投げかけ始めていた。航空郵便を積んだ複葉機は、赤い光の中を一線に飛びつづける。アンリはゴーグルごしに周囲を見まわし、美しいと思った。前後左右、そして上も下も、赤い光に包まれて飛ぶ。夕焼けを満たした球体の中を泳いでいるような気分。何かが自らの中に染みこんでいく。それでもアンリは飛行に酔いしれる事はなかった。果てしのない空にただ一人。ここはかつて望んだ平和な空だ。それを思うと苦い思いがこみ上げてくる。
空から赤い光が抜けていき藍色が忍びこむ頃、アンリは飛行機の高度を下げていった。宵闇の中に白く浮かび上がる、アラニア・ノヴァのいくつもの建物。天に向けて鋭く尖った鐘楼を持つ中央教会。列柱に飾られた重厚な正面を、日の出から日没まで人々で埋め尽くされる広場に向ける駅舎。同じ広場に面して、大きなドーム屋根を誇るのは市会議事堂。それらの建物を左手に見ながら、小麦の畑の上で更に高度を落とす。ただ広い空き地が広がっている、としか見えない飛行場は上空から見つけ易い施設ではない。それでもやがて、畑と滑走路の境が見分けられる様になる。無線も無電も積んでいないアンリの飛行機は、一度滑走路の上を飛び越し、その上で二回旋回して見せた。滑走路の傍らには幾つかの低い建物、そして真新しい高翼単葉式の旅客機が並んでいる。やがて滑走路の端で、着陸許可を伝える旗が振られた。軽い衝撃が、長いブランクで操縦の勘が鈍っている事を物語る。久しぶりの大地に降り立ち、飛行帽と飛行服を脱ぎ捨てると操縦席に叩きこんだ。風が、汗のこもった頭髪を軽やかに撫でいく。日は既に落ち、残光の中を何人もの作業員が言葉少なに立ち働いている。
郵便飛行機会社の事務所には、まだ数人の社員が残っていた。並べられた机の数からすると、日中はその数倍の人間がいるのだろう。
「中継飛行場のアンリ・ルアーブルだ。事情はさっき連絡したとおりだ」
一番手近にいた若い男に書類を手渡す。男は顔もあげずに、幾つか書きこみをすると控えを返してよこした。これで責任は果たした。あとは空港の事務所に行き、そこでも幾つかの手続きをすれば休むことができる。会社の事務所を出ようとすると、呼びとめる者があった。振り返ると事務所の奥の「支社長室」と記さ れた扉が開かれ、戸口にオリビエが立っていた。
「ルアーブル大尉!黙って行こうとするなんて、水臭いじゃないですか」
満面の笑みを浮かべながら近寄ってくるオリビエから反射的に目をそらしてしまったことを、アンリは恥じた。杖は突いているけれど、二本の足でしっかりと床を踏みしめてやってくるその姿には、右足が義足であることを示すものはなかった。それでもオリビエは、飛行機乗りの一つの末路、その典型的な姿であるの だ。
「大尉はやめろよ。退役して何年経つと思ってるんだ」
「戦争が終わってすぐ。ですからもう五年ですか」
アンリがようやくひとつの言葉を搾り出したのも一向に意に介さないように、相手は笑顔を崩さなかった。
「さあ、仕事は終わりでしょう?食事でもしましょうよ。後の手続きは、ウチの事務員にやらせておきますから」
七時になろうかというのに、夕暮れの光が残るアラニア・ノヴァの街。湿り気の多い熱い空気が、ずっしりと体にのしかかってくるようだ。石畳の狭い街路の両側は様々な商店が道にまで品物を並べ、食料品や香料の臭気があたりを満たしている。頭の上に大きな荷物をのせ、歌うような売り口上を途切れなく風にのせて歩く物売りの女達。素足でゆったりとした民族衣装姿の女達とは対照的な、背広姿の男たち。無論、男でも民族衣装を着ている者は少なくない。彼等は勤め人 ではなく、商店主や行商人だ。物乞いする子供たちが彼等の足元を駆け回る。中には大人達に蹴飛ばされるものもある。水売りがロバを引く横を、騎馬警官が威圧的に通り過ぎる。それらの雑踏を蹴散らす様に、アンリたちの自動車が進んでいく。
「暑いですけど、もうすぐですから」
オリビエは赤い顔に幾筋も汗をしたたらせていた。アンリは車のドアの上に肘をかけた姿勢で、微かな風を顔に受けようとしていた。
白い巨石を組み上げた建物の中は涼しかった。
「また組合はストライキをやってるのかい?」
白いクロスをかけたテーブルにつくと、アンリは尋ねた。
「ええ、パイロットと整備員を増員しろと言ってます」
「正当な要求だな」
アンリがそっけなく言うと、オリビエは気色ばんだ。
「そうでしょうか?会社にはこれ以上人を増やす余裕はないですよ」
「過労が原因の事故が減れば、お釣が来るさ」
「組合の連中と同じようなことを言いますね。言っておきますが、全飛行機に無線を、無電でなく無線ですよ!装備させている飛行機会社が他にありますか?その上、非常用の飛行場まで用意しているんですよ」
アンリは苦笑した。「お前こそいつから会社の広報担当になったんだよ」その言葉をかろうじて飲みこんだ。
「人里離れた所にいるからって、新聞も読んでないと思ってるのかい?ウチの会社の事故率は、他の会社と比べても酷いものじゃないか」
お仕着せを着たボーイが、スープと羊肉の料理、雉肉の料理を運んできた。
「無線にしたところで、パイロットを三人、整備員を五人増やす事に比べれば、決して高くはないだろう。事故が多いからってうるさい役人に対するポーズでやってる気がするがね」
「そんなこと…」
オリビエは吐き捨てる様に言って、料理を口に運んだ。視線は皿に向けられている。
「ストライキでフリーランスに荷物を運んでもらう羽目になっちゃ、かえって高くつくだろうに」
「その上、事故られちゃあ、ね。俺が本社の人間だったら、女のパイロットなんか使わなかったのに」
テーブルの向うまで駆けて行って殴りつけたい衝動を押さえつけ、雉肉を一切れ口の中で噛み下す。味がまるで感じられない。
「着水すれば安全だったのに、命がけで荷物を守ったんだ。英雄だぞ」
オリビエは鋭い口調に、たじろいだようだった。もう充分だ。この男だって会社に雇われているだけのこと。会社そのものじゃない。アンリは表情を緩めた。
「やめよう。なにもここで喧嘩を始める事はない。もうちょっと愉快な話題を探そうじゃないか」
ボーイがシナモンの香りのするパイ菓子と、熱いコーヒーを持ってきた。ふたりともしばし無言で、パイを引き裂き口に運んだ。やがて大戦中の武勇伝について、互いに語り始めた。アンリはにこやかな顔を作り、時には大声で笑ってみせさえした。しかし胸の奥に重く居座る何者かを忘れる事はなかった。
「ところで、マクシミリアンポリスの航空学校で教官を探しているんですが、どうです?やってみませんか?知った顔が何人もいますよ」
オリビエが話題を変えたのは、散々話して話題が尽きかけた頃だった。
「素人の飛行機に同乗するのか?ごめんだね!」
アンリは首を振った。
「ルアーブルさん。あなた、まだ四十にもなってないんでしょ。あの飛行場でこのまま埋もれているつもりですか?」
「給料と軍人恩給で、充分暮らしていけるからね」
そっけない言葉に、オリビエは身を乗り出してきた。
「何故?もう飛行機に乗る気はないんですか?」
「ああ」
アンリは椅子の背もたれに体を押し付けるようにして、両手は力なく脚の上に置いていた。視線は空になった皿の上を遊んでいる。
「もう一度、自由に大空を飛ぼうとは思わないんですか?」
「今、空のどこに自由があると言うんだ?」
精一杯皮肉な口調を作って応える。本当はその言葉を、金切り声で叫びたいくらいだったが。
オリビエは無言でコーヒーを口に運んだ。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
