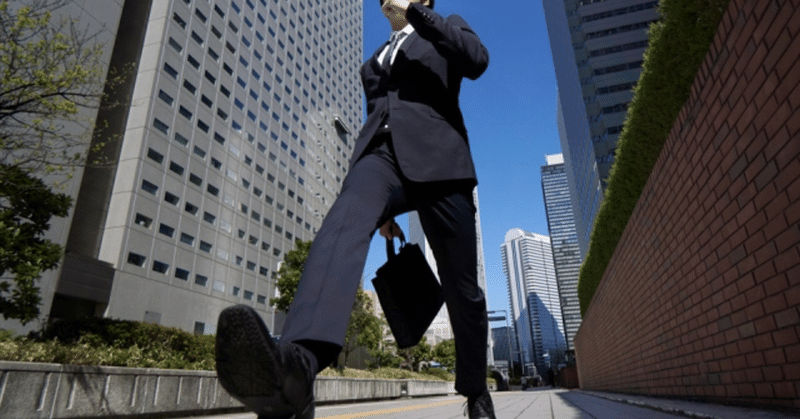
読み過ぎは危険。
「空白の才」が手に入るとしたら、候補の一つに「雑草を根っこから引っこ抜ける才」がいいなと最近考えている、政治家を目指していますおおきな木です。
「空白の才」とは「うえきの法則」という漫画で出てくるもので、どんな才能も手に入れられるやつです。「うえきの法則」大好きなんで是非読んでみてください。
さて今日は、空気を読む文化について少し話をしていきたいと思います。
みんなは思っている事をきちんと言葉にして伝えていますか?
心の中にあるその思いは、その人の心の中にあるだけで、伝えなかったらどんなに相手のことを思っていたって、なかったことになってしまうんです。
僕たちは超能力者ではない。だから相手に自分の気持ちを伝えることを怠っているのにもかかわらず、「なんでわかってくれないの?」「こんなの言わなくてもわかるでしょ?」は自分勝手が過ぎます。
日本人の特徴として「空気を読む文化」が出来上がっているのも関係しているよね。そもそもなんで空気を読む文化が出来上がってしまったのだろう。そこでルーツを調べてみました。
いろいろ調べて自分なりにまとめます。
歴史面から見ると、縄文時代と第二次世界大戦が大きく関係しているようです。
縄文時代では、稲作が普及していて、これを一人で行うことは難しく、他者と協力して行うことが必須だった。また、第二次世界対戦においては、「お国のために命を捧げる」ということが美徳とされていました。この考えがマジョリティー、多数という中で、異を唱えると猛反発をくらう。身の危険も出てくる。
どうもこの頃から「自分の本音を発信することができずに、回りに合わせる」という風潮ができてきたらしい。これが「空気を読む」という文化のルーツだと思う。
もう少し深堀りをすると、日本人はもともとストレスに弱い遺伝子らしいので、他人と意見が違ったり、反発されることに耐性がない。このように遺伝子的にも「空気を読む文化」をさらに発達させたと言えますね。
「空気を読む」ってことは、回りに合わせるってこと。
そこに自分の意見は大して必要ないから、きっと楽だと思う。考えるカロリーも必要としないし、他人から批判される恐れも心配も少ない。ではみんながみんな、そうであるとするならば、誰の意見が空気を作っているのか。
お気づきかもしれませんが、それは立場が上の「上司」や「先輩」ですよね。
その人達は、下の人よりも経験や知識があったりするわけで、発言する機会、量もあれば、発言をしやすい環境にいるということ。反対されることは滅多にないですよね。反対されても立場が上というだけで、ほぼ勝ち戦です。
魚と組織は頭から腐ると言います。
上司が腐っていても、その意見に乗ってしまう人がほとんどではないでしょうか。
疑問に思っていても、深く考えず、思考停止で従う。
「いや、おかしい!」と思った人がいても、大半が同調圧力に負ける。
そして、私には変えられないと諦める。
誰かが一緒に戦ってくれないと、戦えないと腰を抜かす。いつだって「誰か」を待っている。
きっとそういう人は、
回りに困っている人がいたって、「誰かが」
なにか問題が起きても「誰かが」
総理大臣が暴走していても「誰かが」
「誰かがなんとかしてくれる」そんな人生、僕は歩きたくないです。かっこ悪いから。
自分がおかしいと思ったから、意見をするし、変えたいものがあったから変えていく。
自分が全て決めている。自分の人生を歩いている感覚がたまらなく愛おしいです。
まとめます。
つまりは、
好きな人には好きって伝えて、
ありがとうもちゃんと伝えて、
ごめんねもちゃんと伝える。
反対意見だって、意見だから伝える。
「基本的には」なにを言ってもいいと思う。
ただ、その伝え方、言葉はしっかりと選ばないといけないよね。
思いを伝えるツール、道具として。使い方は間違っちゃダメです。
またね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
