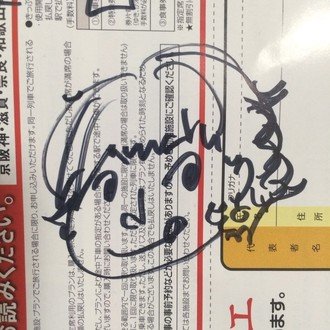干乾びた胎児(短編)
夜になると、彼らは夕食をとり、それから浜辺に出てパイプをふかすのだった。煙草の香りが魚たちにくしゃみを催させた。ロビンソン・クルーソーにとって、無人島の暮らしは楽しくはなかった。「ちょっとさびしすぎるな」と彼は言う。
エリック・サティ
一陣の風が吹き、砂が舞い上がった。砂は乾いた音を立てて人々を叩き、纏わりつく。即座に払いのける無数の手はなにも言わない、なにも語らない、あるものは湿って、あるものは乾いて、一様にしなやかな動きで砂を払いのけ、風が街を通り過ぎた頃、人々の肌に、手に、そして記憶にもはや砂の感触は残っていない。草臥れた肉体は飽きもせずに水を噴出し乾きの反復を繰り返してはもろくざらついた輪郭を得、深呼吸とともに時間は左から右へ澱みなく流れる。
男は眼に入った砂粒のせいにして落涙した、一度零れた涙はとめどなく溢れた、痩せた頬に幾筋かの轍をつくった。むせび泣く男は嗚咽を噛み殺している。ポケットのなかを硬く黒ずんだ指でさぐり取り出して火をつけた煙草をろくに吸うこともできずに、たった一口ふかしただけであとは指の間で煙をのばし、地に灰をはらはらと降らすばかりだ。男は向かいのベンチに腰かけている若い女を見つめる。顔を、肌を、髪の毛の一本一本まで舐めまわすようにいやらしく視線を這わせることで安易な恍惚を生み出そうとした。女は男の悪意ある視線にまったく気がつかないまま、黄金色に染まった空を見上げ、半分口をあけ、アスファルトで覆われた地殻を爪先で叩いているがあまりにもかすかなその音は喧騒に埋没してしまって男の耳に届かない。しかし視神経を刺激する爪先の緩慢な動きによって、男の硬い頭蓋骨で覆われた脳のなかで、こつ、こつ、こつ、という音が何度も浮き上がっては冷たく響き、街の風景は溶け、女の姿は曖昧になって網膜に焼け付いた別れた女の残像とだぶる。いや、それは捏造だ、偽物だ、反射的に現れた自己否定の声に捕えられて、自ら生み出した安直な恍惚は逃れられない恥辱へと姿を変える。やむこと無い街の喧騒は男を笑う声となり、たまらず耳を塞いだ。そして目は濡れては乾きを断続的に繰り返し、気づいた頃には女の姿はもうどこにもない。夏の終わりの夕暮れの公園、ぬるい空気のなかに香り立つ草木の匂いに男は思う。明日は雨が降るだろう。
――海なんて久しぶり
歩行に促されて流れる街の風景。頬に残る涙の筋がかすかに風を感じる。風に靡かれて女の声が喚起された、立ち止まった、握りしめた拳は緩められた、手からこぼれ落ちた砂は地面を叩き小さく音を立てた。平面的な海、顔のない群衆、脳裏を過った断片的な記憶が折り重なって、女の姿が男の瞳の奥で立ち上がる。男の視界は揺曳する。
海へ行こう、海へ行こうとせがむ女に負けた、出不精だったが電車に揺られて二時間ほどかけて海まででた。小学生のとき以来かなぁ、サンダルが鬱陶しくて弟と裸足で砂浜を走りまわったんだー、懐かしい、隣で女の嬉々とした声を聞いていた、機械的な動き、一見ごく自然な動きである不自然な動き、うん、うん、うん、と反射的に打った相槌で二人の間の余白を埋めた。回転する車輪、きしむ車体、霞んでゆく街の遠景。女はしゃべる。足の裏のあの感触、最初は痛いんだけど、気がついたら心地良くなってる、なってるの、日が暮れるころにはその感触も忘れてしまって、またサンダルを履いた頃にはもう砂の感触なんて思い出せない、あのとき本当に海に行ったのかも思い出せないの。遡行。女がしゃべるにつれて時計の針は揺らいでは逆向きに回り、女は少女の顔になった。違和感はなかった。違和感なく少女になったのが逆に違和感だらけで男は凝視する。女は女のままだった。少女ではなく女だった。しかしやはり違和感はなくて、違和感だらけなのは変わらない。電車を降りると、男は湿った空気に絡む潮と、直線的に肌に降り注ぐ強い陽射しに一瞬だけ、呼吸の仕方を忘れた。歩きたい、砂浜を、歩きたいの。女に手を引かれて息が零れた。駅構内に同様の動きを見せる男が、女が、幾人かいた、呼吸を忘れるほどでなくとも慣れない海沿いの土地に目が眩んだ男が、女が――
男は再び歩き出す。赤く燃える雲の平板が頭上を這う。
街の喧騒は途切れた。隔絶された室内は沈黙の音で満ちている、流れのない川の水底のような空間のどこかから、なにかが、卑しく笑う声を必死に押し殺しているような沈黙の音が満ちている。そのなにかの生暖かい息が男の肌を撫でるような感覚にとらわれ、あの恥辱がよみがえってきた。男は喉の奥から、腹の底からこみ上げてきた嗚咽を床に向かってぶちまけた。蹲って、鼻を啜って、泣いた、沈黙の音に、あの卑しい声に抵抗するように泣いた、必要以上に声を出して泣いた。靴を脱ぐと、かすかな音を立て砂粒が落ちた。靴下を脱ぐ。すると一握りほどの砂が、重い音を立てて落ちた。男は玄関にできた白い小さな砂の山に手を伸ばし、人差し指と親指でつまむ、つまみ上げる動作の途中でほとんどが零れ落ち、一粒だけ残った。白い粒だった。それを掌に乗せたところで少しむせ、弾みで粒は砂山に落ちた。砂の小山を見る。落ちるとどの粒を掌に乗せていたのかもはやわからない。その砂粒の落ちる音は男に聞こえなかった。軽く鼻を啜って、ズボンを脱ぎ、トランクスとTシャツだけになると、ベッドに座ってビールを一口舐めた。そこでようやくまともな声が出せそうな気がして、あ、と呟く。発音を確認すると、疲れた、と自分の声を再度確認した。自分の声を聞くと少し胸が晴れた気分になったが、声が消え、また暗澹とした沈黙の音に包まれると胸がつかえ、声がだせなくなった。缶ビールを見ると水滴とともに砂粒がついていた。散らかったテーブルの上の僅かなスペースに缶を置くと、自分の手形に砂が付着していた。自分の手を見ると砂がべっとりとついていた。太腿で手をはたいてからもう一度、掌をじっと見つめると砂粒が僅かに、しかし一様な密度で付着していた。立ち上がってベッドを見ると、尻の形をした窪みに砂粒が一握りほどあった。足元にはその二倍ほどの砂が落ちていた。男は何が起こっているのかを考える。耳に神経を集中すると、かすかに、ぱらぱらと音がしている。音に気がつくとそれは次第に大きくなる、男の静かな部屋のなかでそれははっきりと聞き取れる程度に輪郭を帯びる。どこからか砂が落ちている、上の階から砂が落ちてきているのではないか。そう思ってじっと天井を睨みつけた。上から落ちていると思えば思うほど砂が降っているように見えた。砂の音は次第に大きくなっていった。その加速度は緩慢だったが、男が音に気がついてから五分もすれば耳を手で塞いでも否応なく聞こえる程度になっていた。音こそするのに、落下しているはずの砂粒が体に当たらないことを、男は不思議に思った。するとその瞬間、トランクスがずれ落ちた。砂は男の肩幅ほどの長さを長軸にした楕円状にフローリングの床に薄く積もっており、トランクスは陸にあげられた海月のようにその上に張り付いている。男の萎んだ陰茎は一様な密度で砂に塗れ、陰毛に砂粒がまばらに絡まっていた。そして男の先端から砂粒がぱらぱらと剥落しているのをはっきりとその眼で見た。男はTシャツを脱ぎ捨てた。首まわり、脇の下、へそ、全身に隈なく砂が纏わりついている。床に落ちた砂は蛍光灯の光を弾いて男の眼を指すほどに白く光っているが、体に付着している砂は男の汗をすっているのかやや黒ずんでいた。男は自分の頬に手で触れてみた。ざらついた感触を手に、頬に感じたが、それは果たして手に付着した砂の感触なのか、それとも頬に付着している砂の感触なのか、それとも両方なのか、まったくわからなかった。手で頬をどれだけこすっても、砂の感触と砂のきしる音、そして剥がれ落ちて床の上に落ちる音が消えなかった。次から次へと、全身から砂が吹き出してくるようだった。気がつけば、男の肌は完全に砂に覆い隠されていた。男は洗面所に飛び込み、鏡の前に立つ。肌は砂で完全に覆われて見えない。唇も黒っぽい砂に覆われて、口と眼を避けて砂粒が肌を完全に埋め尽くし、男はそれを己の姿だと信じることができなかった、鏡のなかに住む薄黒い砂粒の間から真っ黒な瞳を覗かせている怪物にしか思えなかった。怪物の見開いた眼を見ながら下唇を噛むと、口のなかにまで砂のざらついた感触が侵入してきた。男は咄嗟に唾を顔の真下にある洗面台に吐き出した。唾は勢いのよい音とともに男の口から放たれたが、下唇に付着して、無色の粘く長い糸を引きながら砂粒を絡ませてゆっくりと落ちた。しぶとく唇にしがみつく唾の不快感と、まだ口のなかに砂粒が残っている不快感を拭うべく、ぶっ、ぶっ、ぶっ、とできるだけ大きな音を立てながら洗面台に向かって唾を出すも、出せば出すほど口のなかは乾き、砂の感覚を拭うことはできない、正確には砂はもう口のなかに残っていなかったが、乾きが男に砂が残っているという錯覚をもたらしていた。唾を吐くのをやめ、肩で息をしながら洗面台に顔を突っ伏しているとからからと音がする。砂粒が洗面台を叩く音だった。自分の頬を引っ叩くと、勢い良く砂が落ち、洗面台でわめきたてた。じっと掌を見る。砂は蠢いていた。砂の下の方から、皮膚から、新たな砂粒が男の汗を吸いながら湧き出していた。まるで砂粒一つ一つが生き物であるように思えた。それぞれの小さな砂粒は、自分の細胞だ、蛆虫のようにうねりながら皮膚から這いでては直ちにその生命は尽きて固く丸くなっている――男にはそう思えた。尚も砂粒は男の体から剥がれ落ちることをやめなかった。砂が洗面台の上を弾む音は砂が砂の上を弾む音へ変わる、質量感を増しながらやむことなく響く。
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。