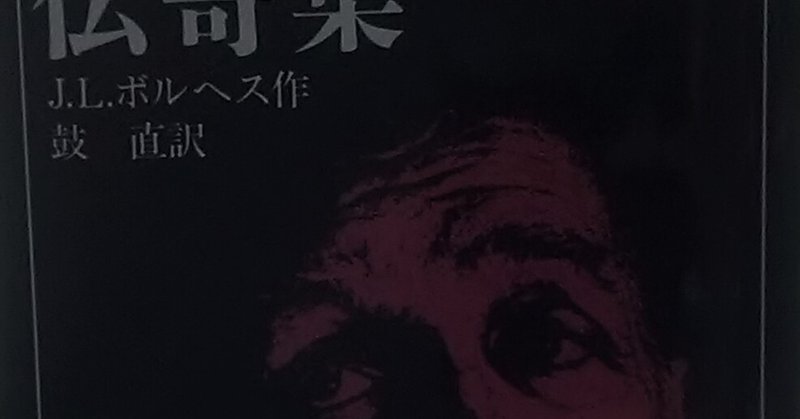
ボルヘス『伝奇集』より「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」 あるいは終末SF/侵略SFの話
ホルヘ・ルイス・ボルヘスの初期作集『伝奇集』(鼓直・訳、岩波文庫)をひさびさに読んだ。ボルヘス作品では、しくみや細部ばかりが書かれるので、人間同士の情念の物語を摂取すると脳がもたれそうなときもスルスルいける。
本日は収録作から一篇「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」を紹介する。以下の紹介はネタバレをふくむので、ネタバレを目にしたくない方はくれぐれもご覧にならぬように。
内容の紹介
冒頭、語り手(=ボルヘス)とビオイ=カサレスは、夜中に別荘で鏡を眺める。
そしてビオイ=カサレスが、鏡と交合は人間の数を増殖するがゆえにいまわしい、といったというウクバールの異端の教祖の一人のことばを思い出した。この記憶に値することばの出所を尋ねると、『アングロ・アメリカ百科事典』のウクバールの項にのっている、と彼は答えた。(じつは家具付きで借りたのだが)別荘にもこの事典が一セット置かれていた。
しかし、事典ではなぜかウクバールの項が見つからない。後日、ビオイ=カサレスが手持ちの事典を確認すると、はたしてその本にはウクバールが存在した。だが、国立図書館で調べても実際にウクバールへ訪れた者の記録は見つからなかった。非実在の国が挿入された海賊版があるのか?
第2部で語り手は、亡くなった鉄道技師あての郵便物を開封する。オルビス・テルティウスと記されたスタンプつきの包みの中身は「トレーンを扱った最初の百科事典第十一巻」なる大著だった。これは別の天体トレーンに関する事典で、専門家の集団が手分けして執筆したフィクションと推察された。
ここから、語り手によるトレーンの説明が始まる。トレーンは唯心論から成り立つ世界で、確かな物がない。言語には名詞が存在せず、北半球では動詞を使い、南半球では副詞を使って名詞を表現する。同様に、科学さえもひとつの理論に収束しない。何より、トレーンの思想はトレーンの現実に影響しているというのだ。
トレーンのもっとも古い地方では、失われた物体の複製も珍しくはない。二人の人間が一本の鉛筆を捜している。第一の人間がそれを見つけ、何にもいわない。第二の人間が、これに負けないくらい本物らしいが、しかし彼の期待にいっそうぴったりした第二の鉛筆を発見する。これらの第二の物体はフレニールと呼ばれ、形がくずれているが少々長めである。つい最近まで、フレニールは粗忽と忘れっぽさの偶然の産物だった。その組織的な生産はわずか百年前に始まったというのは嘘のようだが、第十一巻にははっきりとそう書いてある。
我々の世界と異なる因果関係が成り立つトレーンでは、考古学的発掘を行うからこそ品物が出土するのだ。このパートで、読者は架空理論を無邪気に味わえるだろう。観測問題を連想してにやつくかもしれない。
ボルヘスは作中で、数世代にわたってトレーンの百科事典を編纂する秘密結社の存在を明らかにし、トレーン学が創作であることを強調する。小説の中でわざわざ「これはフィクションです」と札を掲げるようなものだ。ところが、結びを前にして、本作は不穏な急旋回を見せる。
1947年の追記として、最終部では前段の後に起きたことが語られる。なんとトレーン由来の小物の実物や、百科事典の四十巻フルセットが発見されたというのだ。トレーンは国際的に報道され、入門書や要約が世にあふれる。そして学校で教えられる歴史はすでに修正され、生物学や数学も時間の問題だと述べられる。変わりゆく世界の中で、語り手はただホテルで静かに翻訳の校正を続けるつもりである。
作中の現実は作中のフィクションに侵食され、本作は侵略もの・世界の終末ものとしての側面をあらわにする。少数の者たちが作り上げた秩序ある妄想が、既存の世界を支配する筋立てはディストピア小説ともいえるだろう。追記の前段では、語り手が以下のように楽観的なのがまたリアルだ。
(前略)いくつかの大衆雑誌は、トレーンの動物学と地誌について紹介した。その透明な虎と血の塔は、おそらく、あらゆる人間の持続的な関心に値しないと思われる。
いやしかし「透明な虎」とか「血の塔」なんて言われたらワクワクするでしょう。また、満足できない日常をひっくり返してくれる存在を待ちわびる気持ちもわからんでもない。私は好奇心で軽率にトレーンを呼びこむ自分が目に浮かぶ。
ともあれ、作中世界はトレーン化の流れから逃れられないという。語り手が世界の変化を気にせず、ホテルで翻訳を校訂するつもりだという最後はずいぶんと象徴的だ。
この話は、別荘で始まり、ホテルに引きこもる予定で締めくくられる。どちらも普段の生活から隔絶した住まいだ。優雅な非日常にはJ・G・バラードを思い出す。バラードの描く破滅は美しく、彼の自伝では上海の租界や収容所すらもところどころ輝かしく興味深いものとして描かれる。そして、ちょうどバラードが上海にいた時期は本作の執筆時期と重なっている。
また、翻訳とは解釈を固定する作業であり、校訂とは解釈を修正する作業だ。つまり、語り手は解釈がひとつに収束しない世界で、無用な古い世界の規範を守り続ける気でいる。
(もちろん、ここに時代性を読みとろうが、普遍性を読みとろうが、孤高のヒーロー性を読みとろうが、後は読者次第である)
モチーフの反復
ある架空ルールに規定された集団(社会)という筋は『伝奇集』の他の収録作にも現れ、秘密のルールに縛られた国(「バビロニアのくじ」)や宗教(「フェニックス宗」)といったバリエーションが見られる。
「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」がとりわけ素晴らしいのは、トレーンの設定の創造と、作中現実への侵出で物語にひねりが加えられた点だ。想像したもののカタログにとどまっておらず、物語を駆動するエンジンとしてすごいやつを搭載している。
もうひとつ、印象的な構造は、人間の創造物が人間を呑みこむ〈胡蝶の夢〉のような、ニワトリが先かタマゴが先かというサイクルだ。これも魔術師がひとりの人間を想像し生み出す「円環の廃墟」にも共通するし、先述の「バビロニアのくじ」の結末も類型である。無から有が生み出される奇術が一冊の中で反復され、それ自体が円環を形作る。
あわせて読みたい
さて、仮に「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」が好みなので、こういう感じのおかわりが欲しいと言われたら、何を出すべきだろうか?
鏡の魔力と、侵略の恐怖、やがて来る世界の終わりをもう1度味わいたければボルヘス『幻獣辞典』の「鏡の動物誌」が最適だ。この章のどれだけがつくりごとや不完全な伝聞の産物かも気になるところだが、とにかく中国の伝説の紹介というていである。かつては人間の世界へ行き来できた鏡の世界のものたちは、現実を侵略しようと試みて黄帝に封じられ、映る動作を反復する「奴隷的な反射像」にされてしまった。しかし、いつか黄帝の魔法が解ければ、こちらへ再び攻め入ってくるはずなのだ。これは同じ製造者による同じ味のおかわりである。
チャイナ・ミエヴィルの『言語都市』は異星が舞台で、発声口が2つある原生種族アリエカ人が、その身体に依拠した言語と世界のとらえかたを持つ設定をつぶさに描いている。存在しない文化の緻密な描写に喜びを感じる読者は、こちらと相性がいいだろう。ちなみにこの本において人間は侵略者で、変化をもたらす側だ。同じミエヴィルの著書の『都市と都市』は、同一箇所に併存する異なる都市を舞台にしており、現実にはありえない文化習俗がもちこまれた異色警察小説である。
異なる世界の見かたがぶつかりあい、世界が書き換えられてしまうくだりに興奮する読者には、グレッグ・イーガンの「暗黒整数」(『プランク・ダイヴ』収録)がおすすめだ。この世界とは別の数学を基盤とする異世界と、未証明理論で陣取りゲームを行う。すべての陣を失い、敗北した世界は消失する。互いに相手の世界は感知できず、こちら側ではコンピュータの画面上でマッピングされた図像のみを頼りに、相手の攻撃の意志の有無を推し測る。共存できずコミュニケーションもままならない相手と、手探りで境界線を引き直すのだ。
なお、前日譚「ルミナス」も「暗黒整数」も、サイバーパンク~エスピオナージュ仕立てで「ルミナス」は上海が舞台だ。
ついでに紹介したいのはカリン・ティドベックのAmatka(2012, 英訳2017, 日本語訳なし)だ。都会から派遣された辺境の異世界(異星)には、洗面台やスーツケースといったあらゆるものや部屋に名前を掲示し、定期的に読み上げるという絶対のルールがあった。認識が世界を規定し、維持する設定と、監視社会の薄暗いムードが遠くで共鳴している。
ところで
『伝奇集』は直訳すれば『小説集』だし、「八岐の園」は「分岐する道の庭」である。ロマンの皮や装飾部品を剥ぎとると、やはりボルヘス作品はしくみだけがむき出しになるのではないか。
次回予告
全作をレビューする予定はないが、引き続き『伝奇集』から「記憶の人、フネス」を取り上げ、おまけに完全記憶・完全記録をテーマにしたSFを紹介したい。
読み返してみると、円城塔の中編2作が収録された『これはペンです』は思った以上に『伝奇集』を下敷きにしていそうなことに気づいた。『これはペンです』収録の「良い夜を持っている」が『伝奇集』の「記憶の人、フネス」と「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」を引っ張ってきているのは露骨で親切だが、円環構造は「これはペンです」にも継がれている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
