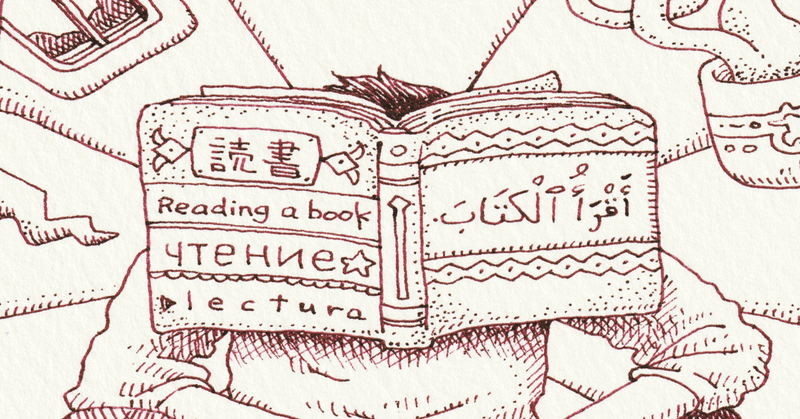
【抜書き】『読書からはじまる』~「7 読書する生き物」
こんにちは。4月30日(土)です。連休始まってますね。
今回のnoteは、通算132回目となるオンラインでの読書会(5月2日21時から開催)用の抜書きです。前回4月25日開催分から、会の名称を「正解を出さない読書会」として運営しています。noteをお読みいただいた方からのご参加も歓迎しております。以下、第7章となる「読書する生き物」からの抜書きを記載してまいります。◯で囲った数字は、本文に添えられた「小見出し」に割り振った連番です。
* * *
①目安をもちにくい時代
・人は、記憶する存在です(略)いま、ここにある自分の位置を、わたしたちは意識しようとしまいと、しばしば、自分のもつ記憶からの距離で測っています。
・記憶というのは、言い換えるなら、それぞれにとっての記憶の仕方のことです。
・日本人の道の記憶の仕方、あるいは場所の記憶の仕方。そういったところでの確かな目安、当てにできる目印というのが、日々の光景のなかにだんだんになくなってきています。
・記憶というのは具体的な目安が手がかりなのです。
②記憶の容れものの問題
・ニュースによって自分自身の位置を知るということが、メディアの進化とともに容易になったかと言うと、そうではなくなっています。
・今日を象徴するのは、ニュースに代わって、情報です。
・情報の荒野の、どこか目安もないようなところに立たされているような、あてどない感覚がのこるのは、情報の主人公はどこまでも情報であって、あなたでもわたしでもないためです。
・情報の言葉は、それによって自分の位置を知るための言葉でなく、それによってそれまで知らなかったことを知るための言葉なのです。情報の言葉は、先んじることがまずもって優先される、競争する言葉です。
・ただ問題は、絶えず新しくされてゆかなければならないために、情報というのは人の記憶の目安にはならないということです。
③いつ、だめになるのか
・ところが、そうした真新しい記憶装置というのは、何年ももたない。しかも目の前には、記憶の目安、目印のない日々の光景しかない。そうであればこそ、一人一人の場所で確かめられなければならないのは、わたしたちの記憶というもののつくり方です。
④この奇妙なものは何か
⑤三人目の老人の答え
・老人は言います。「それは、人が自分で働いて暮らすということをやめてしまったからです」
・その「わからない」「知らない」ということは、じつは人びとの記憶というものに係わっています。それが謎だというのは、その謎に答えられるだけの、記憶のもちあわせがないからです。
⑥記憶の目安
・問われたことに答えられたのは、頭がよいからではありません。それに答えるだけの記憶をもっていた、それもゆたかにもっていた、ということにためです。
・問われているのは、わたしたちが記憶の働きを、自分のものとして、元気な心の働きとしてもちえているかどうか、ということなのです。
・ひとを現在に活かすものとしての、記憶の目安です。記憶の目安があってはじめて、自分たちにとってのとりかえのきかない記憶が引きだされる。そうして確かにされた記憶から、日々に必要な物語がつくられる。
⑦心のなかにもっている問題
・記憶の目安を確かにするのは、ひとが心のなかにもつ問題です。
・読書というのは、実を言うと、本を読むということではありません。読書というのは、みずから言葉と付きあうということです。みずから言葉と付きあって、わたしたちはわたしたち自身の記憶というものを確かにしてきました。
・記憶をたしかにするということは、自分がどういう場所にいて、どういうところに立っているか、東西南北を知るということです。
・心のなかにもっている問題を、自分で自分にちゃんと指さすことができるかどうか。そのことが人の言葉との付きあい方の深さを決める、そう思うのです。
・言葉で言えない、かたちはとりにくいけれども、はっきりそこにあると感じられる問題というものを、一つずつ自分の心になかに発見してゆくということがひとが成長すること、歳をとるということだろうというふうに、わたしは思っています。
・言葉で言い表すことができないものがあるというのは、言葉というのは表現ではないのでないかということです。
⑧言葉は表現ではない
・言葉はむしろどうしても表現できないものを伝える、そのようなコミュニケーションの働きこそをもっているのでないかということを考えるのです。
・むしろ、その言葉によって、その言葉によっては伝えられなかったものがある、言い表せなかったものがある、そういうものを同時にその言葉によって伝えようとするのです。
・「これは社会です」となにかを指して言うことのできない、そういう言葉があります。そのような言葉で言い表せるものというのは、その言葉によってそれぞれが自分の心のなかに思いえがくもののことです。
⑨読書のコミュニケーション
・情報とコミュニケーションというのは比例するものではなくて、本当は反比例する性質をもっています。
・コミュニケーションは情報によって代替できないことを、もっとも対照的に示すものは、読書のコミュニケーションのあり方です。
・答えの決まっていない、あるいは答えというもののない、答えはないけれども、問いがあり、問いはさらなる問いを問い、問いを求めて答えを求めない、ある意味で落着を求めないコミュニケーションというのが、言葉のコミュニケーションというものだろうというふうに思えます。
・言葉から、あるいは言葉によって、そうした沈黙、そうした無言、そうした空白というものをみずからすすんで受けとることのできるような機会をつくる(略)
・言いたいことを言えば、たがいにわかりあえるだろうというのでなく、何をどう言ってもうまく語れない、言葉がとどかない、たがいにわかりあえないというところからはじめて、自分の心のなかにある問題を、あくまで切り捨てない。
・忘れたくないこと、確かめておきたいことは、一つです。記憶する生き物としての人間をつくるのは、あるいはつくってきたのは、そう言ってよければ、読書する生き物としての人間だ、ということです。
* * *
今回の範囲は以上となります。次回5月9日(月)は、最終章の「失いたくない言葉」「あとがき」「解説」を扱います。最後までお読みくださいましてありがとうございました。それではまた!
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
