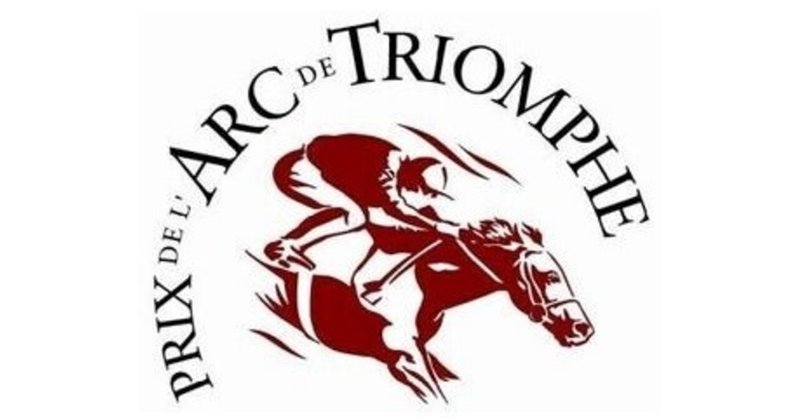
凱旋門賞を終えて
今年もドキドキしながら凱旋門賞を迎え、落胆して翌週を迎える、お馴染みの時季となりました(笑)まぁ言ってみれば毎年恒例の儀式みたいなもんですからねぇ。いつになったら終わるのか、と誰もが考えるものの、かといってそうそう終わらせることもできず、何とも悩ましい10月の頭です。
今年の凱旋門賞は期待薄だった
今年の凱旋門賞は戦前から期待が薄かったですね。あれ?そんな事ない?そうですかねぇ・・私は世界最高峰のレース凱旋門賞を見るという意味ではドキドキしましたが、日本馬の活躍は微塵も期待していませんでした。
だって日本の大将格であるタイトルホルダーは、宝塚記念からのぶっつけですから頭はまずありません。後述しますが、凱旋門賞は休み明けでは勝てないとデータが涙ながらに訴えているのです。なもんで、タイトルホルダーはどんなレースを見せるのか、という一点だけを注目していました。
次に前哨戦のニエル賞でボコボコにされた日本ダービー馬ドウデュースですが、こちらは前哨戦の負けっぷりからしてあまり期待が持てませんでした。一瞬、良い脚を使ったんですが、あの負け方を見て、休み明けで太かったから絞れた本番は勝負になる!と思うのは盲目的かなと思いました。ディープボンドとステイフーリッシュについては、ハナから期待していません。
■返り討ちに遭う
んで、レースはどうなったかと言えば、皆さんご存じの通り、ボコボコに返り討ちに遭いました。直前の雨が・・という声もありましたが、前日のロワイヤリュー賞では10段階で7番目に重い「TRES SOUPLE」(重)でしたし、騎乗した武さんが、「悪過ぎることもなく例年の秋の、ロンシャンの感じ。これ以上、あまり雨が降らないといいけどね。」とコメントしていたように、前日から馬場は悪かったのです。ただでさえ馬場の悪化で分が悪いのに、そこにレース直前の降雨で、わずかに残った希望すら打ち砕かれてしまったわけですね。最終的に「TRES SOUPLE」で施行されましたが、関係者は、ホントどうしろってんだ!!という気持ちだったでしょうね。
重い馬場でも走れるタイトルホルダーですら、直線入口まで先頭で集団を引っ張ったものの、残り300mでアルピニスタに馬なりで交わされると、そのままズルズルと後退し、2.41秒差(ざっくり12馬身)の11着に敗れました。ディープボンドとステイフーリッシュはさらに1~4秒ほど遅れて入線し、ドウデュースは勝ち馬から8.77秒差(ざっくり42馬身)の19着と大敗しました。いつぞやのフィエールマン並みの惨敗ですね。
なお、上位陣と日本馬のタイムおよび上がりは以下の通りです。
1着アルピニスタ 2分35秒71、上がり39秒91
2着ヴァデニ 2分35秒82、上がり39秒39
3着トルカータータッソ 2分35秒89、上がり39秒52
11着タイトルホルダー 2分38秒12、上がり42秒73
14着ステイフーリッシュ 2分39秒16、上がり42秒79
18着ディープボンド 2分42秒88、上がり46秒72
19着ドウデュース 2分44秒48、上がり46秒30
※最初の1000m通過は63秒96
■想定通りでも馬券は的中しない
ここまで想定通りだと逆に悔しいです。なぜこの想定を馬券に生かせないのかと思わざるを得ません。だって凱旋門賞の馬券はルクセンブルクとオネストからミシュリフ、トルカータータッソ、アルピニスタ、ヴァデニだったんですよ。
日本馬全切りで、前走で勝利した馬の内、感覚が概ね1ヵ月以内で、重馬場でも走れそうな馬を頭に持ってきたらルクセンブルクしかいなくて、それじゃあ心配だからって前走2・3着まで範囲を広げたらオネストとヴァデニが浮上してパリ大賞で長い所を勝ってるオネストを2頭目にチョイスしたのです。
そこから好きなミシュリフ、間隔が1ヵ月半のアルピニスタ、距離不安で評価を下げたヴァデニに、直前の雨で追加したトルカータータッソに流したら見事な縦目。日本馬全切りまで良かったのに・・・今年は多頭数だったし、仕方ないとは思いますがね~・・・下手クソだなぁと自己嫌悪です。
凱旋門賞に挑むべきか否か
んで、ここからが本題。今回の結果を受けて、様々なメディア、SNS上で改めて日本馬の凱旋門賞に対する姿勢が問われました。タヴァラは「日本とは別の競馬なんだから大目標にしなくてもいい。」とコメントしてましたし、タイトルホルダーの生産者、岡田牧雄氏も「時計がかなり違う凱旋門賞は日本馬には合わないレース。どうしてそれを目指さなければいけないのか。この狂騒曲を終わらせたい」と常々話していましたね。
これは個人差があると思うのですが、まず前提として競馬に何を求めるかで結論は変わってくるのですよ。
■競馬に求めるのは名誉しかない
金か、名誉か、それ以外か・・・・私は古い人間ですので現代の一般的な競馬ファンと考えが違うかもしれないと思いつつ、私個人の考えを述べるなら競馬は馬主が名誉を求めるスポーツだと思うのです。
だってどう考えたって馬主の利益になるスポーツじゃありませんよ。クラブ法人は別にして個人で考えるなら、世界でも特に高額な賞金の日本競馬でも儲かっている馬主はほんの一握りです。むしろ居ないんじゃないかってレベルです。
であればなぜ競馬をするのか。それは名誉が欲しいからです。他の馬主より速い馬が欲しい。他の馬主に負けない強い馬が欲しい。強い馬同士で戦い、勝って名誉が欲しい。それがスタンダードな考えだと思うのですよ私は。だからこそ、強い馬が揃う場所で戦い、勝利を掴みたいのです。それが名誉に繋がるから挑戦したいのです。
■日本馬の世界トップクラスはまやかし?
確かに日本馬に合わない凱旋門賞に挑戦し続けるのは無謀かもしれませんし、不利な条件だらけで挑戦するのはどうなの?って気持ちも分かります。でも、現状の日本競馬を見てください。日本馬は世界トップクラスと高い評判を得ていると関係者は口を揃えて言いますが、日本馬が世界相手に戦う場所ってどこですか?パッと思いつくのは香港とドバイです。それ以外の場所は参戦すら珍しいですよね。
逆に言えば、香港とドバイくらいしか世界と戦える場所が無いのです。香港にしろドバイにしろ、世界各国の馬がメイチで仕上げて大目標とするようなレースでしょうか。辛うじてドバイは分からなくもないですが、香港を大目標にする欧州馬や米国馬、豪州馬はどれくらいいるでしょうか。
やはり世界のホースマンが目指すのは、春から秋の欧州GⅠであり、ケンタッキーダービーやBCシリーズなのです。そこを目指して様々な臨戦過程から、様々なタイプの強者が集い、覇を競うのです。だからこそそうしたレースには競馬の根幹たる伝統と格式が備わるのですよ。
香港やドバイのレースに伝統と格式が備わるのはまだまだ時間が掛かるでしょう。そんなレースに歴戦の強者がどれだけ揃うのか。どれだけ大目標とされるのか。そんなレースを勝って果たして自分たちは世界一だ、と声を大にして言えるのでしょうか。
つまり、この根底部分をまず考えた上で、「競馬に何を求めるか」を考えるべきではないでしょうか。そうでなければ結局、関係者の立場や考え方が違えば結論だって違うのに、あの人はこう言ってた、この人はこう言ってた、だからこの結論が正論だ、と考えの違う人たちの間で不毛な議論が続くだけだと思うんですよね。
凱旋門賞に挑むならどうすればいいか
私個人は前述したとおり古い考えの人間なんで、馬主をするなら名誉を求めたいし、伝統と格式のあるレースを勝ってこそ名誉が得られると思いますので凱旋門賞には挑戦するべきだと思います。ただ、岡田氏のように目指したくないという人を非難するつもりはありません。それは競馬に対する考えが違うだけですから。とは言っても、日本のトラックのような走りやすい馬場や、同じように日本馬にとって走りやすい香港やドバイに限定して引き籠るのはどうかと思いますがね。
■方針は大きく分けて2つ
で、ここから凱旋門賞に挑む前提の話ですが、日本と欧州の馬場が全く別次元だというのは誰もが理解しているところです。では、どうやってアジャストすればいいのか、これが課題なんですね。今回のタイトルホルダーに限らず、クロノジェネシスやゴルシといった中山や阪神など日本競馬でも荒れやすい競馬場で活躍した馬でも、本場の重馬場では通用しませんでした。
一方、エルコンやオルフェといった成功例を見てみると、前者は長期遠征で欧州仕様の馬体に変化させた、後者は持って生まれた馬場適性が大きく影響していると思います。それを考えれば、凱旋門賞を勝つための方針は2つ。ひとつは長期遠征を敢行する、もうひとつは馬場適性の高い馬をより多く生産することです。
前者の方針は「敢行」と言うだけあって、無理を承知で思い切って行う必要があります。まぁよっぽど凱旋門賞を勝ちたい、そしてそれ以外は全て捨てても良い、という個人馬主で、かつそれ相応の馬を所有し、それを全面サポートしてくれる関係者が居る事が前提ですので、非常に難しいと思います。武豊で凱旋門賞を勝ちたいと豪語するドウデュースの松島正昭オーナーがどうしてもって懇願しても、サポートしてくれる関係者いるかどうかってところでしょう。それくらい関係者から止められる方法なんですよ。
ただ、エルコンやディアドラの成功例を軽視しすぎだと思うんですよね。特にエルコンは、遠征当初はキャンターもまともにできないくらい酷い走りだったそうです。馬場に慣れず、調教で動く馬が動かなくて、すぐに疲れてしまったと。それでも調整を続けると、徐々に筋肉の付き方も変わっていき、結果、素晴らしい成績を残しました。ディアドラにしても5月頭に英国に到着してからプリンスオブウェールズを挟んでナッソーSまで丸3ヵ月滞在して結果を出したのです。その後、愛英のチャンピオンSで3・4着に入るなど、滞在の成果は出ていると見るべきでしょう。
もちろん、エイシンヒカリやオルフェのような馬も居ますが、適性によるところもあります。ディープ産駒が欧州GⅠを勝っているように、適性に期待するより環境から変えて、アジャストさせる方がスポット参戦より結果が出ると思いますよ。
後者はもっと難しいです。だって生産者にならないといけないんですから。そもそも日本馬で海外挑戦できるレベルの競走馬を生産しているのは、天下の社台グループをはじめとしたほんの一部です。そこは不確実性の高いロマンで競走馬の生産を行うのではなく、商売として行っているので、当然、賞金の高い日本競馬で活躍できるタイプの馬を優先的に生産するわけですよ。今年の生産馬の半分は欧州狙いで作りましたなんて天地がひっくり返っても言うわけありません。
となると、単に欧州血統というだけでなく、日本競馬の良い点である豊かなスピードを受け継ぎつつ、欧州の極悪馬場にも対応できる適性を持った馬を自分で集めて配合するしかないのです。そんなん金子オーナーでも無理だって。可能性があるとすれば、欧州である程度走った日本馬を買って配合することでしょうか。例えば、父はオルフェやキズナ、エイシンヒカリなど、母ならディアドラとかでしょうか。牝馬の欧州遠征自体が少ないので、母は欧州から買ってくる方が早いですね。
■方針が決まっても臨戦過程の検討は必要
凱旋門賞を勝つには前哨戦が重要です。これまでの日本馬は国内からぶっつけで本番に挑むケースをよく見ますが、凱旋門賞は休み明けでは勝てないのはデータが証明しています。
他の記事でも何度も書きましたが、近年の凱旋門賞における最長ブランク勝利は1965年のシーバードが記録した2ヵ月29日です。一応、1946年のカラカラが6/21のアスコット金杯から直行して勝利した3ヵ月14日という記録がありますが、さすがに76年前の記録ですからねぇ。まぁそんな事を言えばシーバードだって57年前なんですが。
私のデータでは、1991年以降の勝ち馬32頭の中で2ヵ月を超えたのはわずかに2頭(ラムタラ、ワークフォース)であり、実に25頭が中20~28日という参戦過程です。残りの5頭も8月中旬からの中1ヵ月半ですから、これだけ見ても前哨戦を使う重要さが分かるでしょう。
にも関わらず、「休み明けも力を出せるから」と言って参戦し、ボコられ続けるなんて頭おかしいと思いますよ。失敗から何を学んだんだ、と。日本では休み明けで問題無くても、それが海外遠征で、しかも大一番なら前哨戦を使う事は当然の選択ではないでしょうか。疲れを残さないためとか言うならそもそも勝利を目指せるレベルではないのでしょう。
スミヨンだって凱旋門賞を「他のレースにはない特殊な要因や、いろんな運も左右するのかもしれない。世界最高峰にして、本当に勝てそうで勝てない難しいレース」と評していました。能力も、適性も備えた馬が、さらに天候や運を引き寄せてやっと勝てるレースなんですよ凱旋門賞は。
■前哨戦は何を使う?
前述した勝ち馬32頭の前哨戦は、ニエル賞が最多の10回、愛チャンピオンSが6回あり、その他はヴェルメイユ賞が4回、バーデン大賞が3回、フォワ賞やヨークシャーオークス、キングジョージが2回となっています。その内、25頭が勝っており、負けた馬の最低成績は4着(トレヴ、ソットサス)です。
2着だった日本馬4頭も前哨戦は3勝、2着1回でしたし、前哨戦をしっかり勝つ事は重要なんだと分かります。負けても大敗しない事は最低条件なんだなと。そうなると仮に前哨戦で大きく負けたりしたら、凱旋門賞をキャンセルして英チャンピオンSに回れと言いたいですね。そっちの方が頭数も少ないし、距離も短いし、ワンチャンあるんじゃね?とか思いません?
逆に国内の前哨戦を選択したのは札幌記念の4頭のみで、いずれも大敗を喫しています。唯一6着に検討したハープスターは軽斤量、かつ後方一気で着を拾う形だったので勝負にはならず、それ以外は宝塚記念を勝ってから参戦を決めて直行したケースや、怪我や疲労などで前哨戦を使えなかったケースですね。ディープは3着入線でしたが、渡仏後に体調一息で、少頭数だった事を考慮すれば大敗とまでは言えませんが、失敗例に近いと考えていいでしょう。
つまり、馬場にアジャストできるようにしっかりと前哨戦を使えって事です。ムーアだか、デットーリだかが言ってましたね。「凱旋門賞を狙うなら前哨戦を使え」って。こういう一流騎手の言葉の意味も考えないといけませんね。
■まとめ
とまぁズラズラと書き殴ってきましたが、まとまりがありそうでない記事になってしまいました。まとめると、長期遠征or馬場適性の高い馬の生産を前提とし、前哨戦で良い競馬をして本番に臨めってことでしょうか。これを言うために6000文字以上書いたのか・・・疲れるなぁ~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
