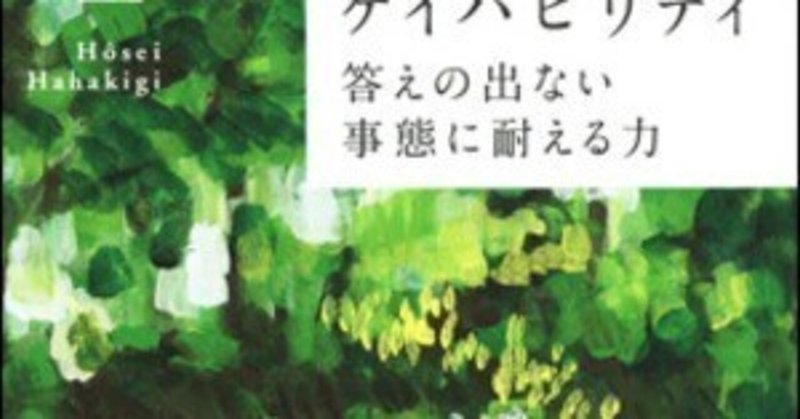
「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉に妙に惹かれる僕
この感覚は、「ハチドリのひとしずく」の時に似ている。
「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉を、
汐見稔幸先生の監修している保育雑誌
「エデュカーレ」で知った時、衝撃が走った。
すぐに、講義で学生らに伝えた。
この考えは、保育者にぴったりだと、
いや、職場時代からずっと自分自身の感じていたなんとも言えない感覚を
言葉で明確に示してもらえた感じがしたからだと思う。
そして、大好きな辻 信一さんの書籍を読んだときにも、
この言葉が登場する。
帚木蓬生さんという方の名前が
あまりにも難しく、でもなんかカッコよく、
いつか、必ず読むことになるだろうと思っていた。
そして、その時が偶然、いや必然のようにやってきた。
保育士養成に携わる3人で、ある研究会に向けてZOOMで
打ち合わせをしていた際に、
ある一人の方が、「敢えてまとめるならば・・・」
「ネガティブ・ケイパビリティかと」と言ったのだ。
僕は何も言っていないのに・・・。
そして、もう一人の方ともそのZOOM前にメールでやりとりをしていて、
「ネガティブ・ケイパビリティ」ですね。
と書いてあった。
つまり、3人とも一度もそのことについて
述べていなかったのに、3人ともそれぞれの場で
行き着いていた言葉だったのだ。
「おー!!」となり、注文。
そして、数日前から読み始めた。
しかし、第1章で大きく躓き、
「なんか違ったかも・・・」となりかけるが、
2度読んで、それなりに少しつかめたところで
第2章へ進み。
「うんうん」となり始め、
いまは、第5章までいっきに進む。
もう止まらない感覚。
「すごい、すごい、帚木蓬生さん」という感じ。
きっと、僕の大変尊敬する方も、
とうの昔に、この概念にたどり着いているのではないかと
頭に浮かんだ。
今度もし直接聞く機会があったら聞いてみよう。
「先生は、『ネガティブ・ケイパビリティ』をいつ知ったのでしょうか?」
きっとすごい前のような気がする・・・。
だって、もうかなり前から実践されているから。
「すごいなぁ~!!」と思うと同時に、
俺、全然知らないことだらけだと反省です。
このつづきが楽しみです!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
