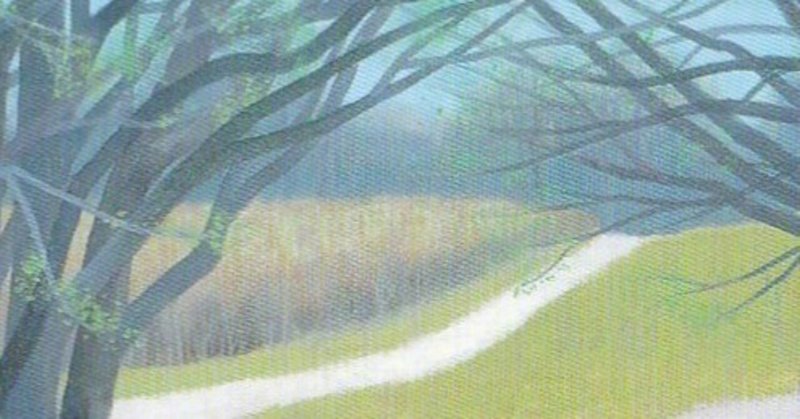
未来を舞う 羽生結弦Ⅺ
「どこかに通じる大道を僕は歩いているのじゃない
僕の前に道はない
僕の後に道は出来る
道は僕のふみしだいて来た足あとだ
だから
道の最端にいつでも僕は立っている
なんという曲がりくねり
迷ひまよった道だろう、、、、、、」高村光太郎<道程>の冒頭
聖マリア デル フィオーレの聖歌隊席を飾るルカ デッラ ロッビアの、見事な子供たちの群像のレリーフをV.ニジンスキーは彼独自の舞踏譜に記したようであったが、いったい彼の脳の中にはどのような舞が繰り広げられていたのであろうか?
無機的で静謐な造形舞踏から有機的で動的な身体性へ、相反する性質を包含した舞踏形態を追究するV.ニジンスキーは、目まぐるしく陽気に動き回るそれぞれの子供たちの笑い声が生々しく聞こえてくる、ルネッサンス真っただ中の L. デッラ ロッビアのレリーフに何を感じたのであろうか?
おそらく、彫刻家が大理石に刻んだ自由奔放な子供たちの姿に、人体に潜在する束縛されることのない本能の自由な表出の美を彼は見たのではなかったか? 私は、A.ロダン作のブロンズ像に表現されたV.ニジンスキーの肉体内に漲る本能の輝きを思い浮かべる。
若かりし頃,R.ヌレイエフがあるインタヴィゥーに答え「既にロシアで成功を収めていた頃から気付いていたのは、既存の成功やファンの要望に自分を委ねることはできない、と。何故なら、彼らの熱狂の真意も疑わしいし、もしそれらに満足していたら、私はそれらの奴隷になって、遅かれ早かれ潰されてしまうだろうから。私は常にそれらの前を歩いてゆかなければならない、と考えていた。私の思考や新しい方向性への変革を示しながら新境地を開き、彼らを(私の芸術の美へ)導いて行かなければならない。」
今日、羽生結弦が立っている岐路は、かつてV.ニジンスキー、R.ヌレイエフのような究極の美を探求する人々が、踏み込まざるを得なかったプロセスである。特に.R.ヌレイエフについて言えば、旧ソ連を脱出した最も重要なモティーフが、当時”自由への脱出”などと世界が喝采したそんな生易しいものではなく、己の内部に沸き立つ抑えきれない新しい生きた芸術への渇望と情熱、それを探求し実現させるためには、生まれ育ち名実ともに舞踏家として成した祖国での大成功と熱狂するファンを振り捨ててでも、旧態依然とした祖国を去らなければならなかったのであった。
以前にも記したように、羽生結弦のフィギュアスケイトへの未知の可能性を貪欲に探索する情熱は、R.ヌレイェフの舞台芸術としてのバレエへの深遠な研究と努力によってのみ可能に至る新しい身体表現芸術を全世界に提供したいという姿勢にオーヴァーラップする。
新型コロナウイルスによるパンデミックは、羽生結弦のスケイト人生に非常に重要な<影と光>を刻んだ。幼少の頃から背負ってきた要注意の健康上の問題を考慮すれば、当時のような状況では日本に帰国することが最上の選択であったのだ。しかし、それは彼が本拠地としてきたコーチ陣の下から離れることを意味していた。おそらく、彼自身、パンデミックがこんなにも長期にわたるとは想像していなかったに違いない。彼は同僚の選手たちが、依然として何不自由なく其々のコーチの下で練習に励んでいるあいだ、リモートでアドヴァイスを仰ぐことがあったとしても、たった独りで日々試行錯誤しながら、より合理的な練習方法を模索したに違いない。それは実に想像を絶する絶望と苦難の連続であったであろう。そのような日々の中で、延び延びになっていた大学の卒業論文を彼は完成させた。フィギュアスケィトにおけるジャンプをテーマにしたその論文は、多方面から賞賛されたのだが、おそらく彼の意図に反して、この論文の斬新的な内容が旧態依然としたスケイト界を敵に回してしまうという理不尽な結果を呼んでしまうことになったようである。AIによる技の判定は、他のスポーツでは常識になったいる今日、フィギュアスケイト界では、未だに正確さに欠ける(避けることのできない多分に私情が関与する)ジャッジ達の目視のみによる判定なのである。もっとも、モドキ演技はさることながら、姑息なまやかしジャンで点数を稼ぐ連中にとっては、AIなどに判定されてはたまったものではないが、、、、。
ともかく、長引いたパンデミックの中で、羽生結弦は独りで自らを鍛え磨き驚くほど見事に困難を克服していった。それは過酷な、自分への挑戦と試練であったに違いない。容易なことではなかった筈だ。しかし、このような状況であったからこそ彼は、あらゆる意味において自分を高めることに成功したのである。成人した男としての精神の強靭さを、より研ぎ澄まされた技術、それが無ければ実現不可能なより洗練された躍動的な高度な身体表現の美しさを完璧に演じてみせた。それが2020年全日本の<天と地と>である。
もはや、羽生結弦は過去の栄光から脱皮しなければならい。何故なら彼が目指す、より完成された総合的な美の世界は、現状の澱んだフィギュアスケイト界の人々には、とても理解し難い高度なレヴェルの領域であるから。
彼は名実ともにプロフェッショナルなフィギュアスケイターとして独立した、正解である。もっとも、彼は競技選手時代から、己の技術、演技共に自らを律するプロフェッショナルなスケイターではあったが。
私はスケイトの技術そのものには、全く門外漢である。しかし、澱むことなく滑らかに重力を感じさせない羽生の滑りには何か特別な秘めた技があるのではないかと、常日頃感じていた。そうしたある日、彼はスケイトシューズを2,3年に一度取り換える、と何気なく語った事実を知った。普通のスケイターは2,3か月に一度、ということだそうである。そこで私はハタと気が付いたことがある。おそらく彼は、必要以上に足に体重をかけず、空(クウ)に身体を預けているのではないか、と考えざるを得ないのだ。レントでもアダージョでもモデラートでもプレスティッシモでも、彼のスケイテイングの滑らかさは変わらない。そんなことが可能なのは、おそらく足の裏から頭のてっぺんに至る身体の軸が宇宙の中心から吊り下げられているからではないか?これはV.ニジンスキーのジャンプを当時の人々が形容して云ったフラーゼである。当然羽生のジャンプも然り。
一点の陰りもない完璧な技術が、彼がExpremereする演技には必要不可欠なのである。
180度の舞台芸術をM.ベジャールは360度、果ては立体にして見せた。それまでのバレエ界の常識を覆した、恐るべき革命であった。それまでは想像もし得なかった新しいバレエの魅力を展開したのである。
最新のテクノロジーを駆使して、今、羽生結弦は全く新しい形式でスケイトの魅力を世に提供しようと試みているようである。彼の美的感覚から生まれるであろうそのㇲペクタクルが、いったいどのような形で我々の目前に現れるのか、私は興味津々である。
M.Grazia T.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
