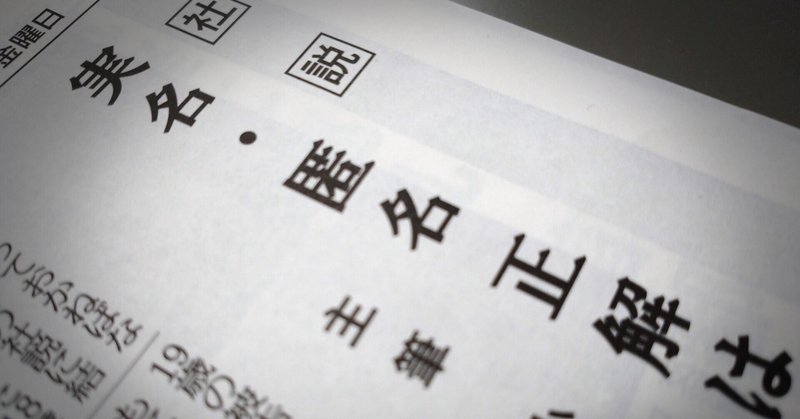
実名・匿名 正解は
※文化時報2022年4月29日号に掲載された社説です
初めに断っておかねばならないが、今回の社説に結論はない。起訴された18歳と19歳の実名報道を可能にする改正少年法が施行された件である。
甲府市内の夫婦が殺害され住宅が全焼した事件で、甲府地検は今月8日、殺人と現住建造物等放火の罪で19歳の被告を起訴するとともに、氏名を発表した。1日の改正法施行後、初めてのケースだったが、報道機関の対応は分かれ、朝日、毎日、読売、日経、産経の各紙がいずれも実名を載せたのに対し、東京新聞は匿名で報じた。
少年法は20歳未満を少年として扱っている。ところが、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、整合性が課題となった。そこで18歳と19歳を「特定少年」と位置付け、17歳以下とは処遇を変えた。
法務省は、18歳と19歳について「社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になった」と捉えており、改正少年法にもそうした考え方が反映されている。
特定少年の氏名や写真の掲載に関しては、「記事等の掲載の禁止の特例」として、法68条で可能になった。ならば、どの報道機関も実名報道に踏み切ってよさそうなものだが、東京新聞はなぜ匿名にしたのか。
9日付1面の社告「特定少年 匿名報道を続けます」には、こうある。
「20歳未満については健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、死刑が確定した後も匿名で報道してきました。少年法の改正後もこの考え方を原則維持します」
日本新聞協会は、2006(平成18)年12月に発行した冊子『実名と報道』で「国民の『知る権利』がまっとうされるために、実名は欠かせないと考えます」とうたった。一方で「実名発表と実名報道とは別」とし、人権尊重の立場から匿名報道を選択するケースが増えていると指摘した。冊子の発行から15年余りが経過した今、東京新聞の判断は当然のように見える。
だが、件の社告で引用した箇所の直前には「東京新聞は、事件や事故の報道で実名報道を原則としていますが」という部分がある。つまり20歳以上の犯罪者に関しては、実名報道を続ける、というわけだ。
果たして、そこで思考を停止してしまって良いのだろうか。
ネット空間に拡散した個人情報を、消すのが困難な入れ墨に例えて「デジタルタトゥー」と呼ぶことがあるが、犯罪歴がいつまでも残ることは人権侵害であり、実名報道の弊害といえる。
医師の日野原重明さんは「鳥は飛び方を変えられないが、人間はいつからでも生き方を変えられる」との言葉を遺した。罪を犯した人間は、少年に限らず何歳からでも立ち直れるはずだ。
もちろん、匿名報道による弊害もある。事件や事故を報じることの少ない弊紙も、実名報道が原則だ。それでも実名・匿名を巡る問題は、報道機関が安易に結論を出すのではなく、読者と共に考えるべきである。
【サポートのお願い✨】
いつも記事をお読みいただき、ありがとうございます
私たちは宗教専門紙「文化時報」を週2回発行する新聞社です。なるべく多くの方々に記事を読んでもらえるよう、どんどんnoteにアップしていきたいと考えています。
新聞には「十取材して一書く」という金言があります。いかに良質な情報を多く集められるかで、記事の良しあしが決まる、という意味です。コストがそれなりにかかるのです。
しかし、「インターネットの記事は無料だ」という風習が根付いた結果、手間暇をかけない質の悪い記事やフェイクニュースがはびこっている、という悲しい実態があります。
無理のない範囲で結構です。サポートしていただけないでしょうか。いただければいただいた分、良質な記事をお届けいたします。
よろしくお願いいたします。
サポートをいただければ、より充実した新聞記事をお届けできます。よろしくお願いいたします<m(__)m>
