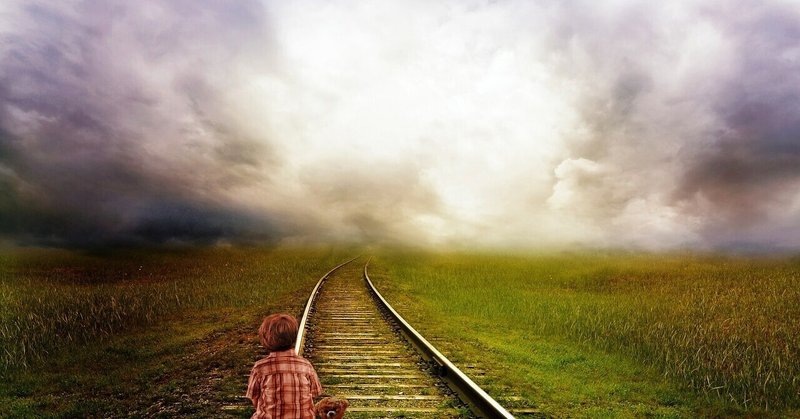
【本】地下沢中也「預言者ピッピ 1巻」感想・レビュー・解説
内容に入ろうと思います。
珍しく続けてコミックを読んでいます。
主人公は、ピッピ。タミオといつも一緒にいて、二人は仲良し。
二人はいつも一緒にいて育ったけど、二人には大きな違いがある。
ピッピは、未来を予知出来る。
ピッピは、科学者が総力を結集して作ったロボットだ。例えばピッピは、パチンコ台のようなものに卵を落とし、どういう経路を卵が通るのか、正確に予測することが出来る。卵の初期状態におけるありとあらゆる情報を収集・分析し、それらを数学的・統計学的に処理することで、未来がどうなるのか完璧に予測出来てしまうのだ。
ピッピは、日本の地震研究所で管理されている。そして、ピッピに直接入力される情報(たとえばタミオと喋ったりしたことなど)以外は、地震に関係する情報しか入力されないように厳しく管理されている。人間は、技術的にはクローン人間を作り出せるけれどもそれをしないように、ピッピはありとあらゆる未来予知が出来るのだけど、地震予知だけに留めておくよう科学者は自分たちを戒めているのだ。
しかし、ピッピを取り巻く状況はどんどんと変わっていく。
ピッピは地球上でたった一体しかない、前例のない存在だ。そのピッピが、前例のない状況に次々と置かれていく。人間は、ピッピを使いこなすことが、管理しきることが出来るのだろうか…。
というような話です。
これはメチャクチャ面白い!凄いなこの作者。ちょっとびっくりした。
僕がこの著者のことを知ったのは、「コミックいわて」という、岩手県が発行したアンソロジーコミックです。岩手出身・在住の漫画家の作品を集め、岩手県が発行するというなかなか斬新な企画で、本書の著者である地下沢中也も「コミックいわて」に作品を書いていたのでした。
僕は「コミックいわて」に掲載されている作品の中で、地下沢中也の作品が一番気になりました。話としてはまったく理解不能で、なんだかよくわからないまま終わったんですけど(褒めてるんですよ、これ!)、メチャクチャ気になる作品でした。
それで、地下沢中也の作品が気になると言ったら、この「預言者ピッピ」を教えてもらえたのでした。
僕の場合本当にタイミングがよかったんです。「預言者ピッピ2巻」がつい最近発売になったんですけど、実はそのお陰で1巻が重版されたのでした。
もし2巻が出るタイミングでなかったら、僕は1巻を手に入れることは出来なかったでしょう。なんだか凄くいいタイミングだったなぁ、と思いました。
本書の何がいいのか、というのは、非常に伝えにくい。マンガなのに、という表現はマンガに失礼かもしれないけど、普段マンガを読まない僕としては、マンガという土俵でこんなに深く考えさせられる物語が存在するんだなぁ、とか思ってしまいました。
ピッピの存在は、麻薬のようなものです。ピッピの能力は、未来のありとあらゆるすべての予測を完璧に正確にすることが出来る。麻薬のように、それは危険な存在だ。麻薬は、人間に多大な快楽を与える。そして、一度依存してしまうと、それなしで生きていくことが難しくなる。
ピッピの存在は、多大な快楽を与える。それは、『未来を知ることが出来る』という、ただそれだけの単純な快楽ではない。ピッピの存在が、どんな快楽を引き起こすことになるのかは、是非本書を読んでほしいのだけど、なるほど、という感じだった。ピッピの予言が引き起こす快楽は、ちょっと後戻り出来そうにないほど恐ろしい。そしてそれは、ピッピの不在を許さないほどの強いものになる。
そう、『ピッピの不在が許されなくなる』ということが、ピッピの存在の最大の問題であり、最大の魅力である。例えばすでに、携帯電話というものの不在は、僕らの世界では許されないだろう。突然携帯電話の使用が禁止されるとか、製造が中止されるなどしたら、世界中からとんでもないブーイングが来るだろうし、暴動だって起こりかねない。
ピッピは、携帯電話と比較にならないほど、その『不在』が許されなくなる。
何故ならピッピは、『人を救う』ために作られ、存在し続けているからだ。
この、『人を救う』というのも、非常に難しい問題をはらんでいる。
本書では、こういうセリフが要所要所で出てくる。
『なぜ目の前の救えるものを救わないの?』
『それじゃあ君は、今目の前の救えるものを、救わないというのか?』
これは僕には、終末医療や移植なんかを通じて、今の僕らでも充分直面しうる問題だと思う。
例えば自分の両親が自宅で倒れたとする。過去既に何度も同じような状態になり、その度に救急車で病院に運んだ。既にかなりの高齢で、抱えている症状が好転することはないとしよう。
そこで、この問いを突きつけることは出来る。『目の前の救えるものを救わないのか』と。
現代の医療をもってすれば、そのまま生かし続けることは可能だ。病状は好転しないものの、点滴やらなんやらで死の淵から引き戻すことは出来る。しかし、それは死のギリギリのところに留めているというだけの話であって、果たして救っているのか。
またこんな例も考えられる。
日本では、正確には覚えていないけど、まだ臓器移植はきちんとした形で認められていないのではなかったか(そのために、海外に治療に行くというような人が時折ニュースになる)。臓器移植をすればほぼ間違いなく助かる命があり、しかもその患者にぴったりと合ったドナーも存在するとしよう。しかし、日本の法律が国内でその臓器移植を許さないとしたら。技術も環境も、目の前の命を救う体制が整っているのに、それが許されない。
ピッピの存在も、そういうものに近いような感じがある。ピッピはその能力を使い、様々な形で人の命を救うことが出来る。地震予知、という形で既に多くの人を救ってはいる。しかし、ピッピの能力を最大限に活かせば、もっと広範囲で、もっと色んな形で人々を救うことが出来る。
だから本書では繰り返し問われる。
『目の前の救えるものをなぜ救わないのか』と。
これは、ピッピの能力を最大限に使うことに反対するとある科学者に向けられる言葉だ。その科学者は、ピッピの能力を解放することで、直接的に自らが利益を得ることが出来る立場にいる。しかしその科学者は、それが分かった上で、それでもピッピの能力を解放することに反対する。
その立場は、凄くよくわかる。僕もその科学者と同じ立場だったら、自らの良心に従って、ピッピの能力の解放には全力で反対するだろう。
印象的な言葉がある。あんまり内容を引用してこれから読む人の興を削がない方がいいのだろうけど、次の二つだけ。
『我々には迷う自由も間違う自由だってあるはずなんだ。しかしそれすらなくなるよ。行う前にそれが充分間違いだとわかったなら。考える前に答えが出てしまったなら』
『問題は人間だ。問題なのは我々人間が、答えのない説明のつかない問題を不安なままずっと持ち続けるよりも、たとえ証明されていなくてもいいから、とりあえずなんらかの確信を持てる方に簡単に安心を感じてしまうこと。まだ訪れてもいない未来をまるで現在と同等に扱って、すでに決まった運命には従うしかないとあきらめてしまうこと』
これは非常に重い言葉だと思う。僕たちの世界には、まだこういうセリフがぴったりくるような状況というのは存在しない。唯一、狂信的な信者を有する宗教団体はそれに近いかもしれない。教祖の言葉を『必ず起こるもの』と信じることで、ピッピの予言と大差ない状況を生み出すことが出来るけど、僕にはなかなかそういう環境も想像出来ない。
迷う自由も間違う自由もある、というのは、その通りだと思う。ありきたりの表現だけど、未来はわからないからこそ面白いし、僕らは生きていける。未来が確定してそれを知った上で、僕らは生きていくことなんかまず出来ないだろう。それがどんなに素晴らしい未来であったとしても、未来が分かってしまっている、という事実が、未来を一瞬にして曇らせてしまうだろう。
そして何よりも、後者のセリフの重さは凄い。これは、未来の話として読まなければ、近い状況を想定することが出来る。
例えば、東日本大震災や福島第一原発の人災などだ。
まさにこれらに直面した人々の多くは、『問題なのは我々人間が、答えのない説明のつかない問題を不安なままずっと持ち続けるよりも、たとえ証明されていなくてもいいから、とりあえずなんらかの確信を持てる方に簡単に安心を感じてしまうこと』という状態に陥らなかっただろうか。それがまるで根拠のない、むしろ悪影響を及ぼしかねない情報であったとしても、『健康に良い』『放射能を防げる』と喧伝されていれば、たとえそれが証明されていないことであっても、信じるという確信とともに、簡単に安心を感じてしまう。まさに同じ状況だ。
あの震災と原発の事故の際の、ありとあらゆる人の不安や揺らぎや混乱などを見ていると(もちろん自分も含みます)、もしピッピが現実にいたとしたら、本書で危惧されているような状況にあっさりと転んでしまうだろう。ピッピという、『絶対に未来予知を間違えない存在』というのは、そういう様々な意味で危険な存在だ。
しかし、欲や権力や金に目の眩んだ連中は、そういう危険性に目を瞑る。これも、原発事故と似たようなところがある。ピッピを管理する委員会は、科学者の反対にも関わらず、あっさりとピッピの能力の解放を決めてしまう。それがどんな自体を引き起こすのか、精密な検証をすることもなく。
全能に近い能力を手に入れたピッピは、もはや人間の手には追えなくなってしまう。ピッピの能力を解放したような連中は、所詮ロボットなんだから、自分たちが管理できないはずがない、と高を括っているのだろう。しかし、物語はどんどんと不穏な展開を見せる。唐突に現れたと思える、船上のサルの物語も進行する。物語がどんな風に進んでいくのか、全然分からない。
本書は2007年5月に発売された。2巻がつい最近発売になったから、実に四年半ぶりに続きが出たということになる。待ち望んでいた人はきっと多かったことだろう。僕は、すぐ読める。これは幸運だなぁ。
凄い物語です。マンガを読んで感動する、ということは、これまでの僕の人生にはありませんでした。マンガのことはよく分かりませんが、コマ割りが凄いとか絵がムチャクチャ上手いとか、そういう感じはないような気がします。でも、なんだか落ち着かないような、心をざわつかせるような物語を描く。
そしてそれは、3.11よりも後に読んだから、という理由も大きいのかもしれない、と思う。僕は最近いくつか新書を読んでいて、そのどれもが僕に『自分の頭で考えろ!』と強く訴えかけてくる。それぐらい、今の日本は(僕も含めて)自分の頭で考えない人間が多い。その怖さを、本書が増幅して提示して見せてくれた。そんな気がします。是非読んでください!
これから僕は、オススメのコミックはなんですか?と聞かれたら『預言者ピッピ』と答えることにします。
サポートいただけると励みになります!
