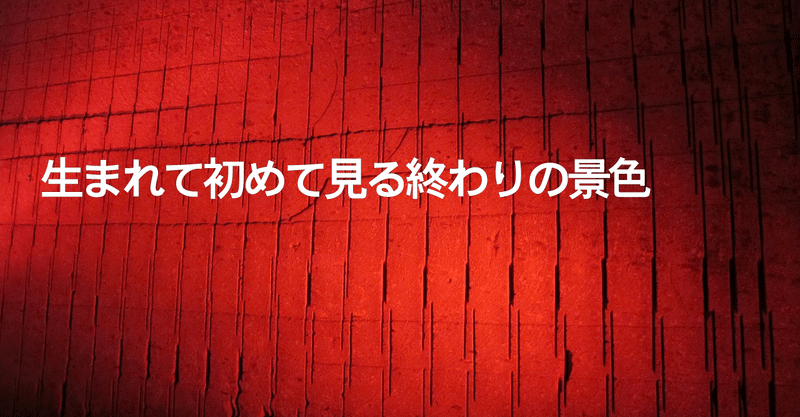
終の棲家デザイナ 太田健司の日常5
「おっしゃっている意味がよくわからないのですが」
目の前の客、奥山香さんは端正なたたずまいの50代、いや、40代半ばかもしれない女性である。背もたれなどないかのように背筋を伸ばして椅子に腰掛け、両手をテーブルの上でゆるやかに組んでいる。きれいに整えられた指先、服装、話し方にも、すきがない。そして、余裕が感じられる。
事務所に入ってきた時のその雰囲気から、本日の依頼は、「屋敷」「邸宅」と呼ぶことができるものの設計依頼、いや、別荘や、運用物件のリノベーションにちがいないと確信していた。
「ですから、ごみ屋敷を終の棲家にしたいんです」
「はぁ。どうやらわたしにお手伝いできることはないかと思うのです」
「他人がつくったごみ屋敷では嫌なんです」
「ま、百歩譲ってそれには同意します」
「マイごみ屋敷が欲しいのです」
客に失礼であるとわかっていたが、わたしは頭を抱え机に伏した。事務の山本さんが両手の人差し指で小さくばつを作るのが、目の端に入った。
*
わたし、太田健司は建築デザイナである。
学生時代の卒業制作の棺で受賞したために仲間内から「棺桶屋の健ちゃん」と呼ばれている。卒業制作とは無関係なのだが、独立後、亡兄の縁で制作を請け負っている「天空の棺」がプロフィールで“代表作”とされることもある。
普通の住宅やビルも数多く設計しているのだが、なぜか、ホスピスや終の棲家の専門家のように思われており、 受賞作品もあったりするため、いまでは、その筋の専門家と世間から見られている。
仲間には「なんでそんなものばかり作るんだ」と言われるたびに「そこに施主がいるからだ」と半ばやけくそで答える。
建築デザイナであるから、建築物であれば原則なんでも作る。海の家も作ったし、コンサートホールやスタジアムも手がけたこともある。だが、さすがにごみ屋敷を新築でというオーダーは初めてである。そもそも、注文ごみ屋敷というものが存在するのだろうか。
だめだ、そんなことを考えては、好奇心こそ悪魔のささやきだとわかっていても、後戻りできない自分にも気がついている。
終の棲家を最期の晩餐のメニューと勘違いして、変な依頼も数多くある。女子高生になって過ごせる家とか、蚊の目線で生活できる家という依頼は断ったが、奥山さんは屋敷をつくるといった。だから、たぶん大丈夫だ。建築デザイナの仕事であるにちがいない。
わたしは禁断の一歩を踏みこんだ。
*
「奥山さんはなぜ、ごみ屋敷をご希望なのでしょうか」
「わたくし、生まれてから今日まで、両親に守られ、学校でも職場でも仲間に助けられ、何不自由なく、いえ、裕福ということではないのですよ、寝る場所もあり、心身がひどく傷つけられることもなく生きてこられました。それが当たり前だとおもっておりました。結婚も、出産子育ても経験いたしました。唯一、つれあいと早くに死別したことがつらいことではありましたが、わたくしが特別というわけではございませんでしょ」
「若いころに一人で子育てというのは大変だったことでしょうね」
「ツレアイが亡くなったのは昨年です。子どもたちもみな成人して、社会に出ております」
40代というのは見当違いか。いや、18でデキちゃった結婚なら、子どもが成人してもおかしくない。
「それで、わたくしも還暦を越えまして」
「えっ」
裏返った声で驚くわたしに、奥山さんは微笑みだけを返してくる。
「子どもらも若いんだから再婚すればと言いますが、一回限りの人生で同じことを何度も繰り返すことに意味がもてなくて」
「もしかして、その信条ゆえの、ごみ屋敷ですか」
「太田せんせ、ごみとごみ以外の線引きはどこにありますの」
ちょっとメンドクサイ人なのかな、と思いつつも、好奇心に負けてしまう。
「一般家庭の場合、リサイクルショップが買い取ったり、ほかの家や人が引き取ってくれるもの以外の廃棄物。ただし、自治体ごとに資源ごみと区分されているもの以外。最終的には生ごみや、鼻をかんだティッシュなどでしょうか」
「でも、それですらごみ屋敷の人にとっては価値のあるものとして扱われ、ごみ屋敷に持ち込まれた後は、屋敷の主の所有物として扱われるわけですから、ごみではないですよね。ごみ屋敷ではなく、未リサイクル屋敷というのが正しくありませんか」
かなりメンドクサイヒトと認定。
「ごみかそうでないかは、おっしゃるように所有権の有無ではないのかもしれません。ごみとごみでないものの線引きは、ごみの種類や状態ではなく、ごみになる前の所有者及び利用者の心のありように過ぎないかもしれませんね」
「わたくしはわたくしの物ですよね。そのわたくしが死んだとき、死んだも同然と思ったとき、このわたくしはごみですか」
「亡骸をごみと称するのが心理的道義的に良いかどうかは別として、カラであることは確かですね」
「でしたら、それをごみ屋敷に置いておくことは至極まっとうではありませんか」
「えーと、飛躍し過ぎではないでしょうか。ごみ屋敷に住んでいる段階では生きているわけですから、ごみではないですし、死んじゃったら、それはそれで、困りませんか」
「なにも、腐りたいわけじゃないのですよ。ごみに埋もれて生きてみたいというだけですから」
ああ、もうだめだ、ついていけない。
考えにはついていけないが、金には尻尾を振る。喜んで。
*
事務の山本さんに言わせると空前の終の棲家ブームなのだそうだ。
「せんせ、いま稼がないで、いつ稼ぐんですか」とはっぱをかけてくる。全産業平均並みの給与を支払っているのだから不足はないはずだが、なにか大きな買い物でもしたのか、投資で失敗でもしたのかもしれない。
これから超高齢多死社会がくると言われているが、なぜ住宅消費と関係するのか意味が解らない。
大半は住宅メーカー側が煽っているだけなのだろうが、若いころは、10年後に病気になったらどうしようなど考えずに過ごすし、まして、それに備えて家を建てようなどとは考えない。心配性というのは加齢に特有の症状に違いない。
高齢者は致死率百パーセントで、なおかつ、若いときとちがって明日死んでもおかしくないのに、わざわざ大きな買い物をしようとする。
どこで死ぬかなどは自分で決められるものではないのだから、終の棲家を手に入れたとしても、本当にそうなるかどうかなどは運である。最後は自宅でと考えていても、道端で、出先でころっと死ぬこともある。
わたしは終の棲家デザイナを名乗っているが、それは、終までの過程を生きる空間でなければならないと考えている。
そのようなお題目では、財布のひもは緩まず、家が売れない。リフォーム市場も縮小してしまう。
だから、老後の安心のためにといってサイフの紐を緩めさせている。わたしもそのおこぼれにあずかっているのだから大きなことは言えない。
終の棲家に限らず家は、どれだけ施主の意を反映したものであっても引き渡し時点では未完成の家である。自分ではその最期は見届けることはできない家である。サグラダファミリアだ。
*
奧山さんの財布のひもはすでに十分緩んでいるようだが、もう一つだけ確認をすることがあった。
「では奥山さん、まずは、ご自分のごみ箱を選ぶところから始めませんか」
「といいますと」
「ご存じかと思うのですが、弊社では天空の棺の設計施工を引き受けております。そのご縁で棺の注文なども受けているんですよ」
「棺が自分のごみ箱とおっしゃるんですか。少々悪趣味な言いようですが、わかりました」
「では、山本さんお願いします」
この事務所には棺桶の法則という、客選びの手法がある。何回か繰り返すうちにわかったことなのだが、棺桶体験に尻込みするような客は見込みがない。逆に面白がって棺桶体験をするような客はまずまちがいなく成約に至る。終の棲家は、たどっていけばそう遠くないところに自分の死の場面が結実する。終の棲家を考えることは、自分の死の覚悟につながっている。だから、入棺体験ぐらいで尻込みするような客は見込みがないのである。
めんどくさそうな客をこれで追い返すことにも使う。
この法則に最初に気がついた事務の山本さんは、「それでは棺桶部屋へどうぞ」と奥山さんを誘導する。棺桶部屋には見本の棺桶が数基置いてある。
「あらーぁ」
奥山さんが目を輝かしているのがわかるような声をあげた。
「これもいいわね。でもやっぱりあちらかしら」
立てた人差し指を唇に当てながら迷っている奥山さんに、「こちらが天空の棺と同じものですよ」と声をかけると、「体験ですものね、これにする」と言った。「あ、でも、こっちも体験させてください、せんせ」
まるでウェディングドレス選びに嬉々とする花嫁だ。
「蓋を閉めますが、すぐに窓を開けます。蓋は軽いので、中から手で持ち上げればすぐに跳ね上がるので安心してください。時々、パニックになる方もいますので」
棺に横になった奥山さんに山本さんがいつも通りの注意事項を伝え、蓋を閉める。
「いかがでしょうか」
「さすがに暗いと息がつまるわね。死んでいれば関係ないでしょうけど」
山本さんは両手を広げ肩をすくめてみせると、窓を開ける。
小窓の中でニコニコしている奥山さんに「せっかくですから、天空の棺の疑似体験をなさってください」と声をかけたわたしは部屋を暗くし、プラネタリウムを作動させる。
「すてきっ。太田せんせ、わたくしこれをいただくわ」
奥山さんのはしゃいだ声を聴きながら、どうやらこの商談は成立してしまうようだとわたしは思った。
*
奥山さんのマイごみ屋敷建設予定地を訪ねる。いまの住まいと同じ敷地内だという。
都心から私鉄に乗り小一時間、快速は停まるが特急は停まらない駅で降りる。駅前ロータリを囲むように低層のビルがあるが、その先は空が広い。
駅前交番で場所を確かめる。警官は外に出てきて、ロータリーからまっすぐ続く道の先を指さす。
「あの木立の中にホテルみたいな洋館が見えるでしょ。あそこです」
富士山や高いビルが近くに見えるのと同じで、歩く先に洋館はずっと見えているのに、なかなか近づかない。最寄り駅までの迎えを断った自分を呪った。
一人住まいの別棟を建てることができる広い庭がある程度と思っていたのだが、門前に着いてみると、想像を超える邸宅であった。
門の両側に丹精に刈り込まれた植栽が植わった低い石積みの塁が、その端が見えないくらい遠くまで続いている。
インタフォンを押す。
そういえば、駅から門まで一度も角を曲がらずに来たなぁなどと思っていると、応答があり、名前を告げると、くぐり戸の鍵が外れる音がした。
くぐった頭をあげても屋敷は見えない。両側を植栽で縁どられた透水舗装の車道が緩やかに右に曲がっている。来客予定を重ねることはないだろうから、道の真ん中を歩いていく。
植栽の道を右に曲がりきると、駅から見えた洋館の全貌が目に入った。アールデコ調の想像以上に大きい屋敷だ。
屋根付き車寄せのある玄関の扉が開いて、出てきた女性がドアを抑えるようにして一歩下がる。
奥山さんが出てきて、こちらに一礼した。
自分でドアを開けない人種が、ごみ屋敷ですか。
「ようこそお出でくださいました。歩きでは大変だったのではありませんか」
「はぁ、まぁ。周辺環境を知ることも大切ですから」と負け惜しみを言う。
わたしは、東京なら戸建て住宅一つは建てられる玄関ホールから、玄関すぐ横の応接へ通された。
ここは、洋間づくり。高い天井、高く広い窓、暖炉。直線的な硬さをつややかに磨かれた梁や柱、腰板壁が和らげている。見ていて飽きない、居心地の良い空間である。アールデコを感じさせる様式は、この屋敷が大正から昭和初期に建てられたものだと類推させる。それはつまり、奥山家がその当時これだけの屋敷を建て、現在にいたるも維持するだけの資産家であることを示している。駅から門までまっすぐに続いた道もその証のひとつにすぎないのかもしれない。
「文化財指定されそうなお屋敷ですね」
「とんでもない、曽祖父が金に飽かして作っただけの道楽屋敷です」
「設計はどなたなのでしょうか。建築当時の記録は残っていれば拝見できるとありがたいのですが」
「書庫にあると思います。あとで、ご案内いたします」
静かなノックに続き、イメージ通りの白いエプロンの手伝いさんが、食器の乗ったワゴンを室内に運び込んできた。
音もたてず静かに茶を淹れ、「しつれいいたします」と一礼し、立ち去っていく。ワゴンはドアの近くに置いて出ていった。置き場所は設計時から定められていたに違いない。この部屋用に作られたワゴンが置かれることで欠けていたピースがはまり、部屋が完成した。これで、季節によっては使われるであろう暖炉が灯ればコンプリートだ。
「あのー、この質問は予想されていると思いますが、あらためて、なぜごみ屋敷なんですか」
「この屋敷があるのに、ですか」
「ええ、まあ」
「わたくしはこの屋敷のいわゆる家付き娘です。ほかで暮らしたことはございません。この家はわたくしの家ではなく、わたくしがこの家のために存在しているだけなんです。縛り付けられているといった被害者感情は全くありません、というより、そういうことは考えないように育てられたんでしょうが」
「おっしゃりたいことはなんとなくわかります」
「ですからこの歳になって、未来という時間の単位が、十年、数年単位から、一年、数か月単位となるにつれ、自分の家を建ててみたくなりました。曽祖父は一代で築いた権勢を示すためにこの家を建て、権勢を維持拡大するためにこの家を使いもしたのだと思います。ここには暮らしはありません。団らんもありません。すべてが年中行事やショーの舞台なのです」
「わたしは建築デザイナですから依頼があれば、犬小屋でも建てますが、作った後に問題になることはありませんか。たとえば、ご家族の中でとか、有力者も多くいらっしゃるであろうご親戚の筋から」
「家族にはすでに話しております。離れを、隠居所をつくると」
そういって奥山さんはいたずらっ子のように、お前も仲間になれと目で訴えてくる。
「離れですかぁ、いや、まいったな。ご家族は、陶芸やデッサンなどご趣味のアトリエをイメージされているでしょうね」
「太田せんせ、大丈夫です。クレームが出てご迷惑をおかけするようなことは絶対にありませんから」
「いや、そうはいっても、ごみ屋敷自体が世間的にはクレーム案件ですからねぇ」
「お金にいとめはつけませんと申し上げたいところですが、それこそ、クレームが出てもいけませんから、その点だけご注意いただければ」
「はぁ。それでは、お建てになる場所を拝見させてください」
建築予定地は広い屋敷地北側に広がる屋敷林というには広い雑木林の西はずれ。木立越しに母屋は見えるが、住民の居室の窓はこちらには開いておらず、勝手口から、収納する物品ごとに分けられているという三つの蔵へ続く通路からも隠れている。北西側の屋敷地の境には瓦屋根の乗った築地塀がめぐっている。
「塀の向こうはいまでもほとんどが田畑です」
こんな風光明媚な地に、わたしはごみ屋敷を建てるのだ。棺桶屋の健ちゃんにつづくあだ名はごみ屋の健坊かな、と考えながら、スケールを取った。
母屋にもどり、今生活している屋敷の中を拝見しながら、部屋の大きさやその他設備に関する本人の希望をうかがう。
家事スタッフがおり、文字通り、ちり一つなく清められ、自室に続くクローゼットも必要な物がすぐに見つかり、季節ごとの入れ替えも容易で、見事としか言いようがない。収納の教科書のようである。
対極のごみ屋敷、オーダーメイドとはいえ、我慢できるものだろうか。
最後に書庫に通していただき、建築資料から、屋敷の設計者が蓑原巳三郎とわかった。聞いたことのない名前だが、当時の建築史に名を残す人なのであろう。上棟の際の写真の裏には、屋敷を建てたのが、かつては日本各地にいた大工集団のうち、どんなものでも自在に建て、技巧も凝らしていた東北の集団が建てたことがわかった。棟梁佐藤清率いるかれらが未知のアールデコ様式に嬉々として挑んだことだろう。そして、ここで手にした技巧を日本のどこかで披露しているはずだ。
最近では、わたしのような零細な事務所にも卒業を控えた建築科の学生のインターンがくる。一緒に調査に来ても良いかと尋ね、快諾を得て、次に伺うときのために、勝手口から家を後にした。
*
設計図面に奥山様隠居所とタイトリングして取り掛かった。さすがにごみ屋敷とは書けない。
平屋のこじんまりとした家の図面は取り立てて難しくなく、ごみがあってもなくても、快適な家である。
母屋までとはいかないが、それなりの材を使っている。室内の設備は今後年を重ねる奥山さんの未来を考えて、選び抜いた。将来に必要になるかもしれないない設備については、床や壁、天井の下地に補強をいれてある。終の棲家に限らないが、わたしは、施主さんの今の希望を叶えるだけではなく、未来の施主さんにも信頼される設計を心がけている。
無事に家は完成した。
落成記念に一席設けられ、祝儀をもらって帰っていった大工や電気などの工事関係者は知らないことだが、これからそれらが見えなくなるほどごみを積み上げるのだ。
「さて、奥山さん。あとはご自分で育ててくださいね」
「太田せんせ、わたくしはごみをだしたり積み上げたりしたことがないんです。どうしましょ」
わたしはヒィェヘッヘと乾いた笑いを返すしかない。
「しかしですね、マイごみ屋敷という以上、奥山さんに作っていただかないと」
「ふつうのごみ屋敷の中の暮らしというのはどうなっているんでしょうか」
「しりません。ただ、一つ言えるのは、おなじものはひとつとしてないのではないでしょうか。オンリーワンのごみ屋敷です」
「マニュアルとは言いませんが、ガイダンスとかヒントはございませんか」
施主さんの希望は絶対だ。
あらゆるつてをたどり、馬鹿にされ、呆れられ、恩を着せられ、ようやく、ごみ屋敷の中を見学させていただく機会を得た。
*
「西川さん、本日は無理を聞いてくださってありがとうございます」
「あんたも酔狂だね。役所の回し者じゃないことはわかったけれどさ、どんなふうに暮らしているか知りたいって」
「いや、知り合いにどうしてもと頼まれまして」
敷地に積み上げられたいわゆるごみのなかに、家主しかわからない道をたどり進む。
「玄関までずいぶんとありますね」
「玄関はもう通り過ぎた。いまは使ってない。勝手口から入るんだ」
使ってないではなく、使えないですよね、と心の中で突っ込みながら必死についていく。得体のしれないごみでなければ、ジャングルジム的な遊具だ。
「ここからはいるんだ」
そこは本来の勝手口ですらなく、地面と室内は平面でつながっているが、部屋の腰高窓だとわかった。
「このゴ、いや、品物はどこになにがあるのかわかっていらっしゃるんですか」
「ま、だいたいはな。見つからなければ、外に行けばいいから」
「えっ。はぁ。なるほど」
「勝手口は閉めて」
「はい」
部屋の向こうに見えるドアに向かってすり鉢状になっている斜面を中腰になって下り、ドアだった場所を潜り抜ける。気分は洞窟探検隊である。腹ばいになって進まないだけ幸運だったかもしれない。
「こういう状態になってどのくらいたつのですか」
「そうだねぇ、10年ぐらいかな」
天井までの残りの高さから推し量ると部屋の床面は130センチほど下にあるはずだ。地層の一番下の状態は考えないことにする。
現在の床面の要所要所にすり鉢状の小さな空間がある。
「ここが台所」
「これがトイレ」
「風呂場はこっち」
戦場で築かれるという蛸壺壕とはこういうものにちがいない。
床面から生活空間に降りる際は滑り落ちればよいのだが、戻るときはどうするのだろうとみていると、ごみ屋敷の主西川さんにしか見えない足掛かりるようで、ボルダリングの選手のように軽やかに戻ってくる。
試しにわたしもすり鉢の底に降りさせてもらった。台所は疲れたら腰を下すとまではいかないがもたれて休めるような窪みがあり、下から見ると、ゴミの壁に微かに足掛かり手掛かりがあるのがわかった。
修験者が岩山に長年かけて刻んだ足跡である。
ごみ屋敷は一日にしてならず。
これはつくるのは容易なことではないと、奥山さんのごみ屋敷を引き受けた自分を呪った。
「食事はどこで召し上がるんですか」
「ま、その時の気分だね。あっちの居間の時もあれば、寝床の時もある」
居間とは、すり鉢の底にこたつテーブルがある場所のことらしい。
寝床は風呂場のようにごみの奈落の底を想像したが、ごみの上に布団が敷いてる。存外キレイなシーツや枕である。
「寝ごこちいいよ」
「いいですか、横になっても」
「どうぞ」
すぐ天井が迫っている。天井とごみの隙間に滑り込む感じだ。背中に多少の凸凹間は感じるがすでに体重で圧縮されているのだろう、寝返りを打っても音はしない。
「どうだい、思っていたより快適だろ。ここはさ、俺の終の棲家と同時に墓場だよ、せんせ」
ごみ屋敷のなかは、やはり不快だ。ごみだからというわけではない。他人が創った、その意図も意味もくみ取れない、落ち着かなさゆえの不快である。その裏返しとして本人はいたって平然としているわけである。自分で作った王国の王として君臨している。
西川さんの家はごみ屋敷の方でもましなほうだと聞いていたので、事実そうなのだろう。ましでないほうは、個人的にはひどく興味を持つが、奧山さんの参考にならないと言うか、参考にしてほしくないので、またの機会にする。
「ご自宅を拝見させていただいたお礼になにかお手伝いできることはありませんか。申し上げたようにわたし、建築デザイナです」
「とくにないけどなぁ。あぁ、前から欲しかった、分別用のごみ箱を作ってくれるとうれしいな」
「わかりました」
本人がそれを置くという場所を教えてもらい、寸法を測り、辞去した。
できれば事務所に帰る前にシャワーも着替えたかったが、公園のトイレで着替えただけで事務所に帰ると、事務の山本さんが鼻を摘まみ「クンクン」と声を出しながら近寄って来て「臭います」と言う。
わたしは「加齢臭です」と一蹴して、十年物のごみ屋敷をどのように作ればよいか、取り掛かった。
*
「浴槽に入らせてらいましたが、いまにも崩れてきそうで、ゆったりなんかできせんでしたよ。ご本人も近所のスーパー銭湯に行くことが多いと言ってました。奥山さんは最悪母屋の浴室がありますけど」
ごみ屋敷のなかの写真を見せながら、奥山さんに説明する。
「ここまで作り上げるのに10年かかっているそうです。いかがなさいます」
「わたくしにはごみを作りだす能力がございません。せんせ、よろしくお願いします」
施主の希望は絶対だ。
新築の物件をリフォームすることになった。当然、別料金である。
西川さん宅を拝見した経験から、いきなり、10年ものは生活が困難かつ危険も予想されるので、床がほぼ見えなくなる3年もの、ごみを積み上げた高さにして膝丈程度になるように、“あんこ”を設置することにした。住み始めは、実際のゴミ袋はその上に一段だけとなる。
ゴミが少ない当初は、固い素材では踏みこんだ時の足触りにごみ感がないだろうから、ウレタンフォームやすり鉢の曲線も加工しやすい発泡スチロールを組み合わせてつくる。
家を建てた大工に頼むことは忍びないので、東京の舞台美術の業者に、「金持ちが道楽で家の中にキャッチウォークとドッグランを作るんだ」と言って、頼んだ。
奥山さんにはせっせとごみを作っていただいた。自宅にある自分の服や持ち物、まだ遺品整理していなかったご主人の物も袋に詰め込んでもらう。母屋から奥山自身が運ぶことも考え、ゴミは袋の半分まで、歩いたり寝転んだ時にけがをしないように、飾りやボタンは外していただく。
「どのくらい必要でございますか」
「たくさんです。多すぎて困ることはありません」
わたしの事務所でも山本さんがシュレッダーゴミをせっせと袋詰めしていた。
あんこの設置が終わった家に、最後にわたしが運び込んだのは、奥山さん専用ごみ箱である。
奥山さんが「これください」といったサイズでは寝返りがうてないのでセミダブルサイズに拡大した。
ごみで埋まっていくさまを見ながらわたしは、奥山さんのマイごみ屋敷は、現代の装飾古墳だと思った。
権力者の墓とはいえ、死者が見るだけの豪華な装飾は無駄である。死後の栄華を祈る意味はあっただろうが、なによりも、豪華な装飾絵画は、造営時には、墓を使う人間がまだ生きていたからであろう。完成時に、生きている死者が、自分の終の棲家を確認する。
たには、古墳完成時に都合よく死んでいることもあっただろうが、完成後しばらくは生きている死者が、自分の現世の権勢の大きさに浸り、来世の安寧をひたすらに願ったに違いない。墓に入り出るという儀式で、権力の再生不滅を演出したかもしれない。
奧山さん宅の室内を埋め尽くすごみ袋の中身は、彼女が生前愛してやまなかった、品々だ。それらが、ごみでありながら時に幾何学的に、ときに印象派の絵のような色のさざめきを見せ、家=古墳の周囲に積み上げられたごみ袋は埴輪だ。
さすがに良家の元お嬢様が腰高窓から出入りするのはどうかと思うので、古墳の横穴式石室の入口にみたて、玄関がほぼ見えないほど積み上げたごみの壁を右に左に最後は腰をかがめてくぐる仕掛けにした。
家に直接ゴミ袋が接すると傷むし、不快な虫や獣が繁殖するかもしれない。でも、なにもないと、物足りないだろうから。周囲にはフレコンバッグに土砂を入れてところどころ配置した。中に、種や苗を仕込んだので、時間が経てば自然な感じに荒れてくれることを期待している。
古墳はその姿を隠すことなく誇示したであろうが、ゴミ屋敷である。母屋から見えないとはいえ、家の周囲は植栽で囲み、衛星やドローンでも飛ばさない限り、そこにぽつんとごみ屋敷があることは気づかれない。
わたしは仕上げに、奥山さん専用のゴミ箱から見える天井にプレゼントを残し、住める新築ごみ屋敷は完成した。
「イメージ上のごみ屋敷は作りましたが、このあとは、生涯をかけてご自分で育てください」
*
奥山さんは大満足でゴミ屋敷に暮らし日々、ゴミ屋敷も順調に成長しているようだ。引き渡しから一年近く経過した今でも、なにか発見があるたびに、嬉々とした声で電話をかけてくる。
「太田せんせ、天井の星座はなんですの」
奥山さんが、彼女専用のゴミ箱の上のわたしのプレゼントに気づいたのは引き渡しから10日もたってからだ。
「奥山さんが生まれたときの星座です」
その後も「家の外のゴミから花が咲きました」と写真付きのメールをよこし、「芽が出てきましたからまた花が咲くのかと思っていましたら、にょろにょろと伸びまして、お手伝いの猪村さんが言うにはカボチャじゃないかと」電話をしてくる。
仕込みの成果が無事に現れて電話のこちら側で安堵している。
ときに予想外のことも起きる。
「太田せんせ、野良猫が住みつきました。つきましては、ミーゴ、猫の名前です、のために、ブルーテントハウスをお建てください。テントハウスと言えば橋の下が決まり事。ミーゴの家にはそのへんもぬかりな……」
奥山さんは祖父の血を濃く受け継いだ、一風というか、かなり変わった普請道楽なだけだ、このとき気がついた。
当初は、「金に目がくらんでゴミ屋敷なんて、営業に響きますよ」と嫌味を言っていた事務の山本さんも、実際、相場よりは多い設計管理料だけでなく追加のリフォーム代まで振り込まれ、さらにこまごまとした注文が重なると何も言わなくなった。
それどころか何か買いたいものがあったりすると「ワイヤーハンガーでつくった鳥の巣なんてどうですかね」などと奨めてくる。たぶん今では、ネットの検索ワード「ごみ屋敷」に、当社がヒットするように手を加えているのは間違いない。
普請道楽の奥山さんの道楽魂に火をつけるビッグプロジェクトをこのわたしが自ら奨める日がくるとは、当然、この時のわたしは気がついていない。(完)[2022.02.09. ぶんろく]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
