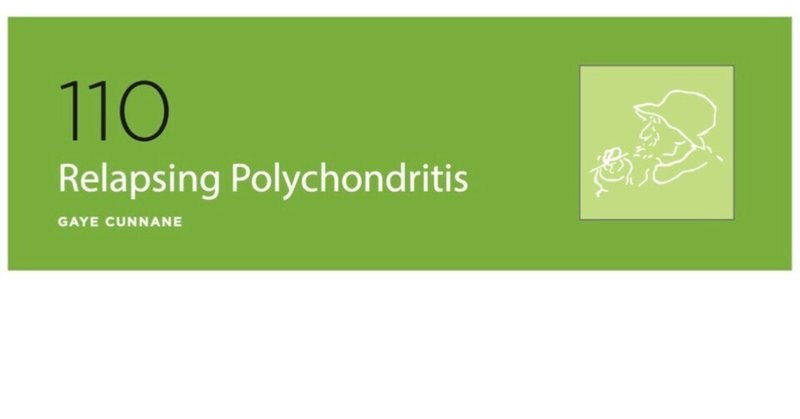
110 再発性多発軟骨炎 Relapsing Polychondritis
Firestein & Kelley's Textbook of Rheumatology, Eleventh Edition
キーポイント
・再発性多発軟骨炎(RPC)は、軟骨構造のエピソード性炎症を特徴とする、まれな全身性自己免疫疾患である。
・古典的な臨床所見としては、「カリフラワー耳」や「鞍鼻」の変形がある。
・RPCは、上気道、目、内耳、腎臓、血管に重大な病態を引き起こす可能性があり、生命を脅かす結果をもたらす可能性がある。
・この疾患は原発性の場合もあれば、骨髄異形成症候群、血管炎、その他の自己免疫・結合組織障害などの他の疾患と関連して発症する場合もある。
・RPCに特異的な検査マーカーはないが、診断は古典的な臨床的特徴を観察することによってなされ、罹患組織の特徴的な組織学的所見によって確認されることもある。
・この疾患は多臓器に及ぶため、診断と管理には幅広いアプローチが不可欠である。
・治療法は経験的であることが多いが、これは病態が多様であり、対照試験がないためである。しかし、免疫抑制が治療の中心である。
はじめに
・再発性多発性軟骨炎(Relapsing polychondritis:RPC)はまれな原因不明の自己免疫疾患で、全身の軟骨構造(耳、鼻、上気道、胸壁、関節など)の間欠的な炎症を特徴とする。軟骨以外の組織が侵されることもあり、特に眼、内耳、心臓、血管、腎臓などプロテオグリカンが豊富な組織が侵される。
・血管炎や骨髄異形成症候群などの関連疾患は、症例の3分の1にみられる。炎症過程の重症度により、免疫抑制剤の使用がしばしば必要となる。その名が示すように、RPCは激しい炎症が周期的に起こる。
・予後は様々で、5年生存率は臓器病変や疾患・治療合併症にもよるが、45〜95%である。
Pearl:軟骨組織には3つのタイプ:ヒアリン(硝子)軟骨、弾性軟骨、線維軟骨があり、細胞外マトリックスの組成が異なる
comment:There are three types of cartilage tissue (hyaline, elastic, and fibrocartilage), which differ in the composition of the extracellular matrix.
・軟骨の細胞成分は軟骨細胞からなり、細胞外マトリックスは、II型コラーゲンの相互結合線維、その他のコラーゲン、親水性プロテオグリカン凝集体、および様々なマトリックスタンパク質から構成されている。 このようなタンパク質の一つであるマトリリン-1は、成体では呼吸器、耳、胸腺にのみ存在し、骨格が成熟する前の関節軟骨にのみ存在する。
・軟骨は無血管構造であり、隣接する組織から必要な栄養素を得ている。軟骨の組成は、外からの圧縮力に対する弾力性を与えている。健康な成人では、軟骨成分のターンオーバーは遅く、修復過程は不完全である。

・関節軟骨には、血管・神経がないため、それ自体が疼痛の原因にはなりません。軟骨がすり減って軟骨下骨がこすれると疼痛を生じると考えられます。
RPCの軟骨組織
初期段階では、軟骨周囲に炎症細胞が浸潤し、ヘマトキシリン・エオジン染色でリンパ球(CD4 +T細胞)、マクロファージ、好中球、好酸球、形質細胞が認められるが、軟骨の構造は影響を受けていないように見える。免疫蛍光検査では、軟骨-軟骨間接合部に免疫グロブリンと軟骨成分の沈着が認められることがある。
その後、炎症細胞は軟骨に侵入し、マトリックスメタロプロテアーゼやカテプシンなどのタンパク質分解酵素を放出する。軟骨が破壊されると、軟骨は好塩基性染色を失い、弾性線維やコラーゲン線維は破壊される。壊死と軟骨成分の減少が観察される。
軟骨はその後、石灰化を伴う線維組織に置き換わる。浸潤部には肉芽組織やゼラチン嚢胞が観察されることもある。
Pearl:RPC患者ではII型、IX型、XI型コラーゲンに対する自己抗体が、また、呼吸器病変を有する患者では、マトリリン-1および軟骨オリゴマー蛋白(COMP)に対する自己抗体が検出される
comment:Researchers have observed autoantibodies to types II, IX, and XI collagen in patients with this disease,and autoantibodies to matrilin-1 and cartilage oligomeric protein (COMP) have been detected in those with respiratory tract involvement
・II型コラーゲンのネオエピトープは活動性の患者の尿中に検出される。最近では、RPCの疾患活動性のバイオマーカーとし て、血清中の可溶性骨髄系細胞発現受容体-1の値が 挙げられている。
・Ⅱ型コラーゲンがRPCではメインの対象抗原である認識でしたが、その他のコラーゲンにも抗体が産生されるようです。
・人体にはおよそ30種類のコラーゲンがあります。
診断基準

再発性多発性軟骨炎:生存期間と初期症状の予測的役割。 Ann Intern Med 104:74-78, 1986.
Myth:耳介軟骨炎は、RPCの典型的な症状であり、多くの患者がこの症状で発症する
reality:Although classic for RPC, this is the presenting feature in only 40% of patients, although this feature eventually develops in as many as 85% of patients during the course of their disease
・RPCの最も特徴的な症状は耳介軟骨炎であ り、外耳の軟骨上3分の2(耳朶を除く)に 急性の疼痛、発赤、腫脹を生じる。片側性または両側性で、数週間のうちに自然に治る。このような症状を繰り返すと、耳は変形して弛緩し、 いわゆる カリフラワー耳となる。RPCの典型的な症状ではあるが、この 徴候は患者の40%にしかみられない。
Pearl:RPC患者は、伝音性難聴と感音性難聴の両方を生じることがある
comment:Such swelling of the outer ear causes temporary conductive deafness. However, sensory-neural deafness may result from an associated vasculitis of the internal auditory artery or its branches, leading to additional vertigo in some patients.
・このような外耳の腫脹は一時的な伝音難聴を引き起こす。しかし、内耳動脈またはその分枝の血管炎に伴って感覚神経性難聴が生じ、さらにめまいを生じる患者もいる。
再発性多発軟骨炎の臨床的特徴


Pearl:挿管や気管支鏡検査によって気道閉塞が誘発されることがある
comment:The lower bronchial airways may also be involved. Obstruction may be precipitated by attempts at intubation or bronchoscopy.
・来院時には患者の10%しか確認できないが、 RPC患者の約50%が最終的に呼吸器障害を発症し、予後 の悪化につながる。嗄声、発声障害、持続的な空咳、前頚部圧痛は、喉頭または気管疾患の可能性がある。気管気管支の炎症は気管軟化症、動的閉塞、急性呼吸不全を引き起こすが、炎症エピソードを繰り返すと声門下狭窄、慢性呼吸困難、感染症感受性の増加を引き起こす。
・下部気管支気道も侵されることがある。閉塞は挿管や気管支鏡検査の試みによって誘発されることがある。肋軟骨炎の発症により胸痛が生じ、呼吸器症状が増 加することがある 。
・上気道病変の管理には特別な配慮が必要であり、外科的介入を行う前に、麻酔チームに上気道病変を認識させる必要がある。症候性気道閉塞の場合、気管切開、気管ステント留置、または睡眠中の気道虚脱を防ぐための夜間陽圧換気が必要になることがある。
・気管支鏡検査は、上気道に不注意な損傷を与える可能性があり、呼吸不全を誘発する危険性があるため、特に適応がある場合にのみ行う。
・というわけで、RPC患者さんが気管支鏡や挿管をするシチュエーションでは、気道閉塞の危険性を呼吸器内科や麻酔科のDrに事前に伝えておく必要があります。
Pearl:大動脈の炎症は、大動脈起始部または弓部で最も起こりやすく、動脈瘤形成や大動脈閉鎖不全を引き起こす
comment:Inflammation of the aorta, most likely to occur at the level of the root or arch, leads to aneurysm formation and aortic incompetence, which may develop acutely with minimal prior symptoms.
・大血管や小血管の疾患は、RPCの 経過中に10%もの症例で発生する可能性がある。このような合併症は、免疫抑制が行われている場 合でも、病勢が確立している患者に典型的に発症する。
・大動脈の炎症は、大動脈起始部または弓部で最も起こりやすく、動脈瘤形成や大動脈閉鎖不全を引き起こす。弁膜症は男性に多い。大動脈弁疾患は、局所的な炎症ではなく、大動脈輪の進行性の拡張の結果である可能性がある。僧帽弁逆流は弁膜炎または乳頭筋の病変に起因することがある。
Pearl:RPCに伴う強膜炎は、他の自己免疫疾患と比較して、両側性、壊死性、再発性で、視力低下につながる可能性が高い
comment:Recurrent inflammation can lead to thinning of the sclera, giving a bluish appearance to the eye.Scleritis associated with RPC is more likely to be bilateral, necrotizing, recurrent, and linked to some visual loss compared with other autoimmune disorders.
・RPC患者の65%が眼疾患を発症し、最も一般的なのは上強膜炎と強膜炎である。炎症が再発すると強膜が薄くなり、眼が青っぽく見える。RPCに伴う強膜炎は、他の自己免疫疾患と比較して、両側性、壊死性、再発性で、視力低下につながる可能性が高い。
Pearl:MDSを合併したRPCでは、粘膜皮膚病変の合併が多い
comment:Skin and mucous membrane changes develop in approximately 50% of patients with RPC. Rashes are present in as many as 35%
of patients with primary RPC, whereas 90% of patients with associated myelodysplasia have mucocutaneous involvement. Oral aphthous ulcers are the most common symptom.
・皮膚や粘膜の変化はRPC患者の約50%にみられる。発疹は原発性RPC患者の35%にみられるが、骨髄異形成を合併した患者の90%では粘膜皮膚病変がみられる。口腔アフタ性潰瘍は最も一般的な症状である。結節性紅斑に類似した末梢結節は患者の約15%に認められる。
・急性白血病では65%に口腔内病変、慢性白血病で30%という報告があります(Indian J Dermatol.2020 May-Jun; 65(3):241-243.)。MDS単独で粘膜皮膚病変や口腔アフタがそれほど増えるという報告もなさそうですが、RPC+MDSで粘膜皮膚病変がぐっと増加するのはなんか不思議です。
・今回のkelleyにはVEXAS症候群の記載はありませんでしたが、この皮膚粘膜病変を高率に合併するMDS合併RPCのなかには、VEXASの症例が含まれていると考えると納得感があります。
①関節病変
・筋骨格系の症状は一般的で、経過中に患者の75%に発現する。少関節性〜多関節性で、最も一般的には足首、手首、手および足が侵される。胸鎖関節、肋軟骨関節、胸骨半月関節に繰り返し痛みが生じることが報告されている。しかし、仙腸関節を含む他の関節にも炎症が認められることがあるが、仙腸関節炎の存在が脊椎関節症の併存に関係している可能性もある。
・RPCに伴う関節炎は、一般的に非対称性、エピソード性、非びらん性であり、RPCの活動性とは相関しない。
②関連疾患
・RPCは、リウマチ性症候群、血管炎性症候群、血液学的症候群など、他のさまざまな疾患との関連が報告されている。
・ベーチェット病と共存することから、MAGIC症候群(炎症性軟骨を伴う口内および性器潰瘍)という略語が生まれた。
・高齢の患者、特に男性では、RPCは骨髄異形成と関連している可能性があり、予後が悪い。

③VEXAS症候群(Kelleyには記載なし)
・VEXAS:vacuoles,E1 enzyme, X-linked,autoinflammatory,somatic症候群
・蛋白のユビキチン化にかかわるE1酵素をコードするUBA1遺伝子の体細胞変異が、成人男性で同定され、VEXAS症候群として提唱されている。
・臨床所見:発熱92%、皮疹88%、肺病変72%、耳鼻軟骨炎64%、静脈血栓44%、大球性貧血96%
・骨髄検査:骨髄球系・赤血球前駆細胞に特徴的な空胞”vacuoles” 100%
・診断・分類基準に合致する炎症性・血液疾患:再発性多発軟骨炎(60%)、Sweet病(32%)、MDS(24%)、多発性骨髄腫・MGUS(20%)、PAN(12%)、GCA(4%)
(PMID:33108101)
・アメリカの報告では、UBA1遺伝子変異は50歳以上の男性では4269人に1人、50歳以上の女性では26238人に1人、全体で7931人に1人であった(PMID: 36692560)
・VEXAS症候群の最も多い、再発性多発軟骨炎(RP)の中からVEXAS患者をピックアップするためのアルゴリズムもある(PMID: 33779074)


Pearl:RPCには3つの臨床表現型がある
comment:A retrospective study of 142 patients with RPC suggested three clinical phenotypes of this disease: a) “hematologic,” associated with blood-related malignancies and an increased inci- dence of skin disease and cardiac abnormalities; b) “respiratory,” with predominant tracheobronchial involvement; and c) “mild” disease with good therapeutic responsiveness and improved prognosis.
・RPC患者142人のレトロスペクティブ研究から、この疾患には3つの臨床表現型があることが示唆された:a)血液関連の悪性腫瘍を伴い、皮膚疾患と心臓異常の発生率が増加する「血液型」、b)気管気管支病変が優勢な「呼吸器型」、c)治療反応性が良好で予後が改善する「軽症型」。
Myth:RPCが疑われる患者で呼吸症状があれば、肺機能検査を行う
reality:Clinicians should conduct pulmonary function tests in all suspected cases of RPC, even in patients who are asymptomatic at presentation. These tests (including spirometry, lung volumes, and inspiratory/expiratory flow-volume loops) should be repeated in the event of new respiratory symptoms. If the test results are abnormal, CT of the chest is recommended to detect the presence of tracheal or bronchial stenoses or dynamic airway collapse, which may be evident only during the expiratory phase of the respiratory cycle.
・臨床医は、来院時に無症状の患者であっても、RPCが疑われるすべての症例で肺機能検査を実施すべきである。これらの検査(スパイロメトリー、肺活量、吸気/呼気流量ループを含む)は、新たな呼吸器症状が出現した場合に繰り返し行うべきである。
・検査結果に異常がある場合は、気管や気管支の狭窄、あるいは呼吸周期の呼気期にのみ明らかな動的気道虚脱の存在を検出するために、胸部CTを行うことが推奨される。
・肋軟骨炎による肺外疾患が、肺機能検査で拘束性パターンを引き起こすことがある。

RPCに対する非外科的治療

・生物学的製剤の使用については、いくつかの症例報告や小規模なケースシリーズがある。通常、コルチコステロイドの使用を減らすために、特にメトトレキサートのような経口疾患修飾薬が炎症のコントロールに成功しなかった場合に開始される。
・TNF阻害薬が最も頻繁に研究されており、抗B細胞薬(リツキシマブ)、抗IL-6薬(トシリズマブ)、抗IL-1薬(アナキンラ)、抗T細胞薬(アバタセプト)、そして最近ではヤヌスキナーゼ阻害薬(トファシチニブ)のデータが少数ながら報告されている。
・治療開始後6ヵ月間の部分寛解率は63%で、完全寛解は19%に過ぎなかった。奏効率はアバタセプトやアナキンラと比較して、抗TNF薬、トシリズマブ、リツキシマブで高かった。
Pearl:各生物学的製剤の治療効果は、臓器によって異なる
comment:Furthermore, limited data suggested that the therapeutic response may depend on the organ involved. TNF inhibitors (particularly infliximab) and tocilizumab, displayed efficacy in the presence of pulmonary involvement; tocilizumab was additionally helpful for nasal/auricular chondritis; anti-TNF agents worked best for arthritis.
・限られたデータではあるが、治療効果は臓器によって異なることが示唆された。TNF阻害剤(特にインフリキシマブ)とトシリズマブは肺病変がある場合に有効であった;トシリズマブは鼻・耳介軟骨炎にも有効であった;抗TNF剤は関節炎に最も有効であった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
