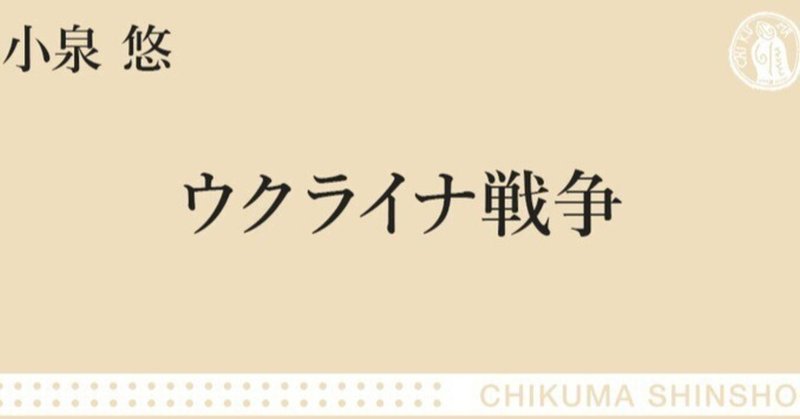
小泉悠『ウクライナ戦争』
ようやく読めました
就職してから読書をする気力やきっかけを失ったので、今回この本を読み切れたことに達成感を感じています。2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻当時、私は病気休暇中でしたが、突然大きな事件が始まったかのような印象を受けました。ですがこの戦争はいきなり勃発したわけではなく、それなりの経緯があって起きたものということがわかりました。いつか読もういつか読もうと積読してきたわけですがようやく読めてホッとしました。
突然始まった戦争ではない
この記事では本書を通じて得られた「気づき」を整理したいと思います。まず前述のとおり、この戦争にそれなりの前史がありました。2014年のロシアによるクリミア半島占領を覚えている人はどれくらいいるでしょうか。本書によるとあれが「第一次ロシア・ウクライナ戦争」であり、今回の戦いは「第二次」に該当するようです。第一次戦争以降、現在もロシアはクリミアを実効支配していますが、ウクライナ東部ではウクライナとロシア側の武装勢力による紛争がぶすぶすと続いていました。プーチンは今回の侵攻目的の一つにウクライナ東部で起きている(と主張する)ロシア系住民の「迫害」を食い止めることを挙げているわけなので、当然、無縁の出来事ではありません。
もちろん歴史的事実として上記の事態を全く知らなかったわけではありませんが、いざ戦争となるまであまり注目できず、詳しく把握できなかったことは当事者意識に欠けているようで反省の念に駆られます。
開戦するまで
ロシアは開戦の一年以上前からウクライナ周辺に軍事力を集結させたり撤退したりを繰り返していました。直接の動機はアメリカでトランプからバイデンに政権交代したことに対する「牽制」の意味合いがあるそうです。トランプは当選した時の2016年大統領選挙でロシアが介入した疑惑を持たれていますが、果たしてトランプは個人的にはかなりロシアに甘い人物でした。アメリカの国家戦略の大枠を揺るがすほどではありませんでしたが。一方でバイデンは次男がウクライナの大企業の重役にいるそうで、就任直後にクリミア占領を認めない宣言を改めて出したりと、ロシアにとって警戒すべき存在に映ったのだと思われます。ちなみにクリミア占領当時バイデンは副大統領でしたが、アメリカはウクライナに積極的な支援はできませんでした。
ウクライナでは2019年にゼレンスキーが大統領に当選します。実はこの人は大統領になるまでロシア語しか話せなかったようです。それでいてコメディアンとして活躍できるわけですから、いかにロシアとウクライナが文化的に親和性の高い地域であるかが理解できます。無理やりたとえるならドイツとオーストリアみたいなものでしょうか。ゼレンスキーは就任してからロシアとの紛争を解決すべくプーチンとの直接対話を何度か試みますがいずれも失敗に終わりました。ゼレンスキーは開戦してから亡命せずに国民にエールを送るリーダーシップを発揮して立派な指導者という印象を受けますし事実そう感じますが、意外にも戦争前は政治的にはけっこういいとこなしな人物だったのでした。
ウクライナがしどろもどろ?しているうちにロシアは既存の条約や協定を事実上破棄して侵攻を開始します。具体的な内容は忘れましたが、①ウクライナ東部に特別な政治的地位をウクライナ政府が承認する、②ロシア側を含む武装勢力を撤退させる合意が2015年に成立したのですが、ウクライナは②を先に履行したい、でもロシアは②より先に①を履行せよと揉めていたのでした。(第二次ミンスク合意)交渉が難航しているうちにロシアが攻めてきたという流れです。
ウクライナの善戦
周知のとおり、開戦からしばらくウクライナは非常に善戦しました。平たくいえばウクライナ国民の士気が非常に高かったことが要因の一つです。一年以上前から侵攻準備をしていたであろうロシア軍は意外にも脆弱でした。ロシアは当初、①ウクライナ指導部を無力化する「斬首作戦」、②ウクライナ内部の内通者を利用した全面侵攻をもくろんでいましたがいずれも失敗します。そして三番目にウクライナ東部の「解放」を掲げますが、ウクライナが主戦場を南部へ移動させるとそれに引っ張られて右往左往します。争いの主導権は開戦前からずっとロシア側にありましたが、徐々にウクライナ側に移行します。
ロシアもウクライナを舐めていましたが、欧米諸国も同じくらい舐めていました。開戦当時、ウクライナがとあるヨーロッパの有力国(恐らくドイツ)に助けを求めた際、「あと数十時間で事態は終わるのになんであなた方を助けないといけないのだ」と言われたそうです。ニュースばかり見ていると欧米諸国は最初からウクライナを全面支援していたように感じますが、ウクライナがここまで奮闘しなければ大きな支援を得ることも難しかったでしょう。更に欧米諸国は核兵器を持つロシアとの「全面戦争」を避けながらウクライナを支援しなければならないというジレンマを有しています。
ロシアの思惑
プーチンは何が目的でウクライナを攻めたのでしょうか。表向きはロシア系住民の保護やNATO拡大を防ぐ等を云々していますが、どれも客観性に欠けます。もちろん主観的な思い込みに駆られたパターンもあるはずですが、ロシアとウクライナの民族的一体性を主張する民族主義的野望が動機にあるようです。前述のとおり両者は文化的にかなり近い間柄で、プーチンいわくウクライナという国家自体がソ連時代に人工的に作られた枠組みということです。だからといって現ウクライナの国家としての独立を表立って否認はしていません。否定しないがウクライナは可能最大限、文化的にも政治的にもロシアに近い地域であらねばならないのでしょう。ただしこのような強硬姿勢がウクライナの人びとの心をロシアから遠ざける逆効果になっていることは間違いないと思います。
最後に
めちゃくちゃ曖昧な記憶を頼りにした要約なので間違っているところがあれば申し訳ないです。著者の小泉氏はTVでかなり冷静かつ的確、建設的な意見を発信していたのが印象に残り、本書を買うに至りました。前著の『現代ロシアの軍事戦略』も積読していますが、いつか挑戦したいです。(第一次ロシア・ウクライナ戦争について詳しく触れているとのこと)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
