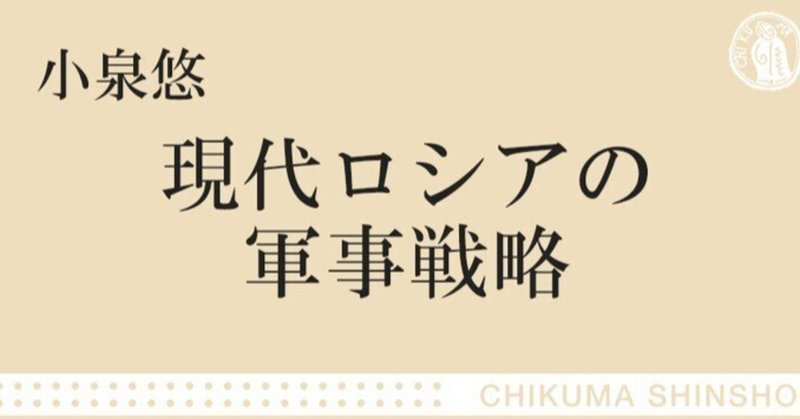
小泉悠『現代ロシアの軍事戦略』
ソ連崩壊後に弱体化してなお、「軍事大国」として一定の存在感を発揮し続けているロシアの「強さ」の秘密に迫った一冊。国家としてのロシアの軍事思想、戦争観を浮き彫りにしている名著だと思う。
サイバーテロなど非軍事的な闘争手段を駆使して戦いを有利に推し進めようとするロシアの意識の裏には、自分たちは西側諸国との「永続戦争」に置かれているという状況認識がある。ロシア語で「抑止」には、先んじて相手に多少の実害を加えて振り払う意味合いが込められているらしい。既にロシアは西側諸国に様々な手段で包囲攻撃されている、象徴的にはNATOの東方拡大によってロシアの首都は容易く標的となりうるようになった。兵器開発ではアメリカなどに追いつけるだけの予算もない。
純粋な軍事力では太刀打ちできないからこそ、あの手この手で自国に有利な状況を作り出すだけの資源を開発する独創性と執念深さが今のロシアにはある。もちろん古典的な軍事力もまた、こうした「状況」を作り出す貴重な鍵となる。両者は相互に協力しつつロシアの「戦争」を遂行する。
21世紀においては、戦争状態と平和の間の相違が取り払われる傾向があります。戦争はもはや宣言されることなく始まり、我々に馴染みのある形式によらず進行します。(…)もちろん「アラブの春」は戦争ではないのだから、我々軍人が学ぶことなどないのだと口にするのは簡単です。しかし、もしかするとことは逆であって、これらの出来事こそが21世紀の典型的な戦争なのではないでしょうか?
思い返せばレーニンも、「その国の情報機関を握ることは一個師団を有するのと同等の価値がある」と述べていたらしい。本書ではレーニンの戦争観はクラウゼヴィッツと同じく戦争の核心を「暴力」に求める古典的な思想だったと紹介されるが、ただの戦争ではなく「革命戦争」を目指したレーニンが非軍事的闘争の重要性に目を付けていたのは当然のことだろうと思う。21世紀の西側諸国でもネグリとハートが『マルチチュード』で現在を「第四次世界大戦」の時代と位置付けているように、主権国家の正規軍が正面衝突することを戦争とイメージしていれば平和を語れる時代は既に終焉している。
政治、経済、文化など、ありとあらゆる事象がロシアの戦争行為と解釈してしまうのは「戦争」の定義すら揺らいでしまいそうなのだが、おそらくロシアの指導者にとっては大した問題ではない。すでに西側諸国があらゆる手段でロシアを屈服させようと「戦争行為」を仕掛けているのだから。軍事演習でテロリストの鎮圧を想定する際も、かれらを手先として操る西側諸国がいるものとみなされる。主権国家を主役とする点でイスラームのテロリズムと一線を画しながらも、テロリストを含む多様な非国家主体を駆使して軍事力を行使するロシアの戦い方は、やはり21世紀独特の新しさを感じさせる。
余談だが、ロシアの「大国意識」を無視してロシアの国家戦略を理解することはできないと思う。これは本書でも少し触れられており、やはり重要な問題であると思う。国家のプライド、自尊心と言い換えてもいいかもしれない。ソ連崩壊後もロシアは西側諸国と価値観を共有することはなかった。権威主義的な政治体制を維持し、周辺諸国をソ連時代のようにとはいかないが、引き続き自己の勢力圏に置こうと努力した。ロシアにとって自国の独立は他国の支配と引き離せないものなのであり、それゆえドイツや日本のように敗戦後たやすく敵国に屈した輩は「真の主権国家」とは言い難いことになる。ウクライナ侵攻を擁護する向きにプーチンの独立主義は賛美され(そして現在の日本の対米従属の罵倒に利用され)ることもあるが、他国を現実に蹂躙してよい理由にはならないだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
