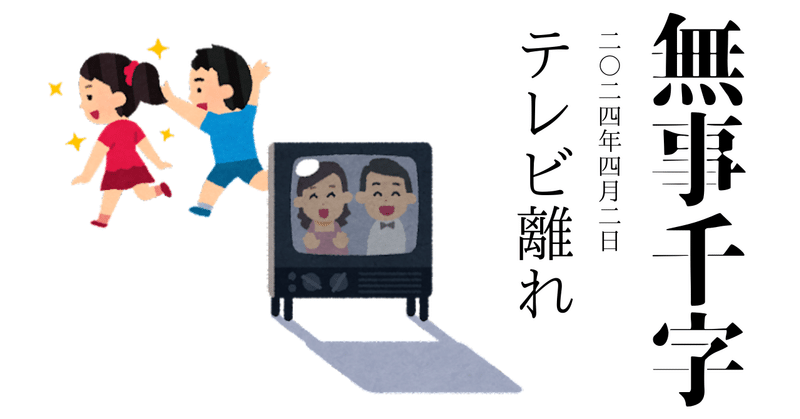
無事千字 二〇二四年四月二日 テレビ離れ
正真正銘、完全無欠のテレビっ子だった僕がテレビ離れをしたのは、ここ数年、よく見聞きする「テレビが面白くない」というソフト面の理由からではなくハード面だった。地上波アナログ放送が終わりを告げたタイミングでテレビを手放したからだ。調べてみたら、2011年7月だったらしい。
2008年ころからだろうか、高校生以来のラジオ熱が再燃。ポッドキャストもあったりして、聴くメディアが楽しくなり、テレビと距離を置くようにはなっていた。
「テレビ観れなくなっちゃうから、新しいの買わなきゃなぁ」と思いながらも、今思えば会社を畳んで約1年、新しい仕事に就いたものの、離婚を経て、借金もあったりして、そこに割く予算が無かった。
その後、10年近くはテレビ無しの生活で、観たいものがあればノートPCで、まぁまぁの確率でYouTubeで観られたし、その2〜3年後にはTVerや配信プラットフォームが台頭してきた。でっかい画面で観たい場合もあったけど、それはテレビを新調するまでの理由には至らなかった。
3年ほど前に、いよいよテレビを買おうかと思ったときに、大きいのが欲しかったけど、スペースを取られるのが嫌だなぁと思い、照明と一体型のプロジェクター「Aladdin」と、それに対応するTVチューナーを選んだ。日中に観たいときには、部屋を暗くしなきゃならないけれど、観る時間帯はほぼ夜だし、そこにさほどデメリットを感じていない。
テレビが無くなると、番組表もチェックしなくなり、当然オンタイムで観ることが無いし、録画するなんてことも無くなる。そういった行為と執着が一切無くなる。TVerの見逃し配信が前提になるから、どこの放送局で何曜何時に放送されているのかもさっぱりわからなくなる。
その環境に慣れてしまうと、プロジェクターを買うタイミングで検討したHDDの購入もあっさり必要なしとなる。録画する、保存版にするといった、テレビ&ビデオの時代に散々やってきた行為をしなくなった。
確かにソフト面での物足りなさも感じている。ドラマにしろ、バラエティにしろ、配信プラットフォームと比べたときの予算の違いは明白だし、”不適切な時代”のテレビ番組を謳歌した世代なのだから。
加齢による集中力の低下かな?とも思うのだけど、とにかく画面にかぶりつきで観る(観たい)と思える番組が、1クールに何本かしかなく、ほとんどが、ながら視聴。そのうち、観ることに疲れてきて、好きなラジオ番組を聴きながら眠りにつくというのが習慣になってしまった。
いま読んでいる、放送作家の藤井青銅さんの著書「トークの教室」にあったフリートークのネタについての記述にこんな感じのことが書かれていた。普通に暮らしていて、そんなにドラマチックなことがそうそう起きるわけはなく、暮らしの中の些細な話でも、切り口を変えることで面白くなる、と。友達との酒場での駄話を思い出すと、まさにそうだよなぁと思う。
ものを書くのが好きだし、そんな仕事もちょいちょい依頼されるけれど、もっと書く仕事ができるように練習をしようと思いながらも始めていなかった。
青銅さんの本を読んで、特に変わったことが無い日常を、1,000字程度で、なるべく毎日(ここが難関)という3点を縛りにして書いてみようと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
