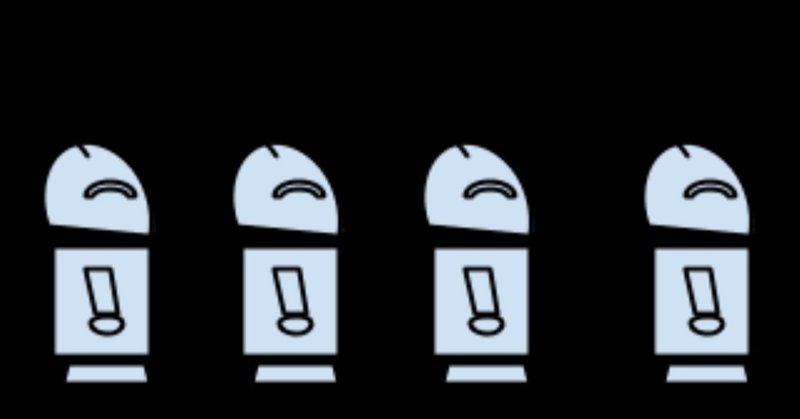
第三章 存在と思考 2
2
ベースに戻ると、Kポッドが待っていた。
「ご苦労様でございます。お疲れになられましたか?」
「ああ、Kポッドありがとう」
丸っこい体のロボットの労いに素直に返答してから、ヤマトは複雑な気分になった。
Kポッドはマリアの側にも回り込み、やはり労いの言葉をかけている。ヤマトが何気なくその様子を見ていると、マリアは涼し気な笑みを浮かべながら、Kポッドの頭をひと撫でして、ありがとう、と言った。
素っ気ない表情をするわけでもない。Kポッドのようなアンドロイドに、愛想良く接する姿は意外だった。
「私からお二人にご報告があります。本日の捜査本部で、新しい情報が配信されました。以下、捜査本部の報告会の録画映像をご覧いただきます」
Kポッドがエアスクリーンに捜査本部で報告をする刑事の映像を投影した。
新たな情報は、地取り捜査からもたらされたようだ。
仲間の刑事がエアスクリーンに何かの書類を映し出している。
エアスクリーン越しのエアスクリーンというのは、画像の不鮮明さが際立って、とても見にくい。
「Kポッド、映像の中のエアスクリーンをこっちにも見せて」
マリアが小さな声で、Kポッドに言った。
「かしこまりました」と、Kポッドが言うが早いか、二つ目のエアスクリーンに鮮明な映像が映し出された。
ヤマトは、Kポッドにこれまでと異なる感覚を抱く自分を感じていた。かつては、Kポッドは優秀な秘書だと認識していた。ごく自然な感覚的なものだ。擬人化してとらえていたというわけでもない。人型でもないのに、秘書として接していたし、Kポッドもそう振る舞っていた。実際、Kポッドは実に優秀な秘書の役割をこなしていた。
だが、Kポッドの一挙手一投足が、自律思考ではなく、プログラムが動かしているものだと考えると、先ほど、自分が発した「ありがとう」も寒々しく感じてしまう。
そんなことを考えているうちに、新しい情報の伝達が終了した。
捜査本部の設置から一日経っていたが、本部にはたいした動きはなさそうだった。
要は、被害者のジョー博士が大学を休職する直前まで懇意にしていた同僚が見つかったという情報だった。休職後からの数年間、交友関係がほとんどなかったジョー博士につながる証言者が発見されたというのは、大きなニュースだった。
同僚の名は戸倉カナといった。ジョー博士と同大学に勤務する教育職員、つまり大学教員だ。宇宙工学を専門とする教員ということだった。
「どうしますか?」
マリアが問いかける。話を聞くために、会いに行くかどうかを聞いているのだろう。
時間を確認すると、まだ昼前だった。この捜査には、タイムリミットがある。一つでも、真相に近づく何かを見つけなければならない。
「そうだな。すぐに会いに行こう」
ヤマトは、Kポッドに相手とのアポイントを取るように指示を出した。
Kポッドが先方にアポイントを求める手続きを進めている間に、ヤマトとマリアは、その他の新しい情報を探る。使えそうな情報の取捨選択だ。エアタブレットに流れ込んだ捜査情報に目を走らせていく。
ヤマトはこの作業だけは、ロボットたちには任せられないと思っている。優秀なKポッドにさえも、任せる気にはなれない。
刑事の勘とでも言うのだろうか、玉石混交の中にも、これは、と思う見過ごせない情報が混ざっている。
有益情報の洗い出しは、早い段階で機械化された。人工知能が情報を分類し、事件と情報との密接度を測り、有益情報の重みづけをしている。専用プログラムに方々から得た情報をひとまとめにして突っ込めば、有益な情報だけがランキング形式で吐き出されるという優れものだ。事件と無関係と判断された不要な情報はトラッシュされる。
人間の調査より信頼できると言う刑事までいる。
しかし、ヤマトは疑問を禁じ得ない。人工知能からは、不要と判断される些末な情報でも、刑事の自分が掴めば、何かの糸口になり得るのではないかと思うのだ。実際、トラッシュされた情報を綿密に調べ上げたおかげで、真相に辿り着いたという事はこれまでにあった。刑事の経験値が教えてくれたことだ。
人工知能がスルーする情報に、引っかかりを覚えるというのは、やはり、人間にはあって、人工知能にはないもの、感情が作用しているのだろうか。違和感を科学で説明しろと言われれば、難しいだろうが、確かに存在する感覚だ。
「羽川巡査長、どうだ?何か引っかかることはあったか?」
マリアがエアタブレットから顔を上げた。
「そうですね。リンダはリエゾンマインド社の製品ということですが、量産品ということで間違いないのでしょうか?」
確かに一部の富裕層向けの商品には、購入者の希望に合わせてカスタマイズ可能な特注のアンドロイド商品もある。
大学教授のようなステータスを持った人間ならば、特注アンドロイドを所有していてもおかしくない。殺人アンドロイドが普及品というよりは、特注品の方が、世間の理解も得られやすいかもしれない。リンダ逮捕後の発表会見における言い訳めいた打算も頭に浮かんだ。
「確かに、家政婦アンドロイドがどんな発注を受けた製品か、気になるな。羽川巡査長、いい視点だ。Kポッド、リンダの品番が普及品なのか特注品なのか調べてくれ」
「わかりました。お待ちください」
Kポッドは一度に複数のタスクを並行でこなすことができる。処理速度も高速だ。人間がひとつの頭脳でひとつの仕事しかできないのに比べると、優秀であるのは当たり前とも言えた。
視線を感じた。マリアがまだこちらを見ている。
「どうした?」
「私のことは、羽川、もしくはマリアで結構です」
巡査長という肩書がいやなのだろうか。
「そうか。じゃあ、マリアと呼ばせてもらおう」
ヤマトがエアタブレットに再び集中していると、Kポッドからピピピと軽やかな音がした。何かを受信したのだろう。
ヤマトの注目をよそに、Kポッドは、ヤマトの手元のエアタブレットに情報を流してきた。
リンダの購入証明書だった。発行元にはリエゾンマインド社の名が記されている。そこに記載されている品番は、商品管理上、リンダが大量生産品であることを決定づけていた。
マリアも同じ情報を確認しているようだった。
これで、リンダのケースが特殊なものであるという都合のよい申し開きができなくなった。
マリアは、まだリエゾンマインド社の証明書を見つめていた。
再度、Kポッドが受信音を発した。
「アポイントが取れました。戸倉カナ博士は本日、出講日とのことで、大学におられるそうです。三限目の時間帯が、オフィスアワーだそうですので、研究室でお待ちになるとのことです」
「ありがとう」
人工知能の何たるかを思い知らされた後だというのに、いつもの通り、Kポッドに向かって、礼の言葉を口にしていた。
これが人間か、ヤマトは思った。
「念のため、教員人事を取り扱う部署にもアポイントをお取りしました。休職に至る書類等をご用意いただけるとのことです」
「さすがだな。助かるよ」
「そんな、もったいないお言葉です。お役に立てたならば、嬉しいです」
Kポッドが頭のランプをチカチカと点滅させた。
Kポッドには表情というインターフェイスはないが、確かにKポッドの照れと自負が伝わってきた。ヤマトの言葉を受けて、喜んでいるように思わずにはいられなかった。
「では、マリア、戻ったばかりで慌ただしいが、大学に出向くぞ。カナ博士から話を聞こう」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
