
サハラ砂漠という夢、そしてタンジール
砂が、特にサハラの砂が、というかその砂漠がとても好きなんです。
初めてサハラ砂漠を見たのは1991年の12月のことで、エジプト・アスワンの郊外でした。大学の研修でエジプト滞在中だった私、アブ・シンベル神殿を見に行ったときのことです。それは広大なサハラ砂漠の東の端っこで、まだまだ砂漠の入り口にしか過ぎない場所でしたが、その圧倒的な光と熱に、瞬く間に惹きこまれました。
すくい上げた砂は小さな小さな粒で、半透明の赤みが強い琥珀色。かつての黄金が(夢が)風と光にさらされて、より永遠に近くなった姿なのだと想像すれば、そこから飛び出してくる膨大な物語に飲み込まれ、心揺さぶられる思いでした。その日から私は、呆れるほどその色に夢中なのです。
アスワンの砂はケイ酸の純度が高く、ガラス材料になると言われています。大部分が石英粒で、赤い色調は鉄分によるものです。石英の最も純粋なものが水晶ですから、大げさに言えば、北アフリカに広がるあの広大な砂漠は水晶の微粒子でできているというわけです。黄金色の水晶の砂漠って、ちょっとファンタジーですよね。
大切に持ち帰った砂は小さなガラス瓶に入れましたが、あんな雄大なものをそんなちっぽけなものに閉じ込められるとは思いませんでした。けれどそれしかできないのだから仕方ありません。だからでしょうか、瓶の中の砂が、12月の日差しと思い出を失うことなく輝いているのを見た時、きっと砂漠がその大きな心で許してくれているのだと思わずにはいられませんでした。

そんなサハラ砂漠といえば、ベルナルド・ベルトルッチ監督の「シェルタリング・スカイ」。完成された素晴らしい映画だと感動しましたが、その登場人物たちの心の機微も驚くべき物語の展開も、実はあっという間の心を駆け抜けて行ってしまいました。後に残ったのは、広大な砂の海とその上に広がる空、そして主人公キットの足を飾ったヘナ・タトゥのみ。
この映画を思い出すたび、その絵(シーン)だけがどんどん深まって、物語はより稀薄になっていきました。けれど一方で、この映画の原作者であるポール・ボウルズは、タンジールという魅惑の言葉とともに、私をその砂漠の西へと連れ去りました。
タンジールは北アフリカ・モロッコの北の端、狭いジブラルタル海峡に面した港湾都市です。対岸はスペイン・アルヘシラス。50年代のそこは、松岡正剛氏の言葉を借りれば、欧米社会のすべてに最初の幕を下ろす、異様で、セイントで、猥雑で、エロティックなトポスであり、20世紀最後の無国籍エデンだったりします。
この町の存在を知った時、私は言葉にならない衝撃を受けました。そして、ボウルズたちの日々を追いかけるように、ミッシェル・グリーンの「地の果ての夢・タンジール」を読んで悶絶し、ダニエル・ロンドーの「タンジール、海のざわめき」を読んで若干心穏やかになったものの、どうにも表現しがたい情熱に取り憑かれたまま、私の終焉の地はここしかないと思い込んだわけです。
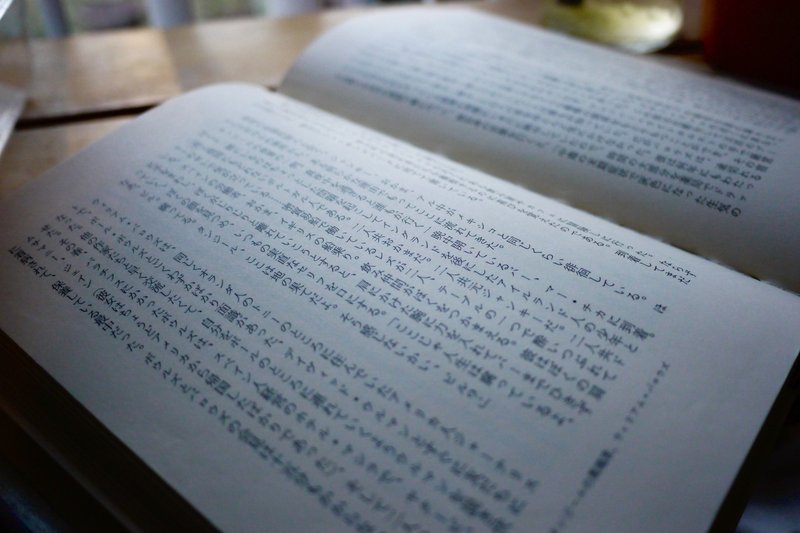
縁あってイスラム文化を学び、正則アラビア語をかじった私でしたが、エジプト研修中はオレンジ1個も気軽に買えない状況を嘆くこともしばしばでした。そればかりは受け入れ難く、疲れて誰とも口をききたくない深夜に、レジに黙って持っていくだけで、いつでも問題なく買い物ができるコンビニを恋しく思い、思わず東京に逃げ帰りたくなることもありました。
それでも、オアシスという名にふさわしい緑濃くナイルの水香るアスワンも、その外に広がる嘘のように美しいサハラ砂漠も、(そこから離れた場所ではありますが)形骸化したヨーロッパの残り香が漂うアレキサンドリアも好きで好きでたまらず、最終日にはエジプトを離れがたく思ったものです。
その当時の私が、砂に住むことを夢見ていたのは言うまでもありません。しかしそれはベドウィンでもなければ叶わないことでしょうし、だからと言って、観光地としてしか砂漠に向き合えないというのは寂しすぎると思っていた時でしたから、ボウルズの生き様を見てはっとさせられたのです。
彼が「シェルタリング・スカイ」を書くために移り住んだ町は、ヨーロッパの熟れすぎた甘美なる腐敗の下で迷宮のような時間を作り出す一方、余分なものなど一切必要としない簡素な日々の中で、砂漠からの熱い風を忘れることなく息づいていました。だからこそ、ボウルズはそこを終の住処に決めたのだと、私も大いに納得したのです。
私とて別に、ドラックやら奔放な性生活やらに憧れたわけではありません。そんなものは無数の人間がうごめく町の一つの顔にしか過ぎない。もっと言えば、そんな反面があるからこそ、ストイックなまでの文学への思慕と、純粋すぎるほどの砂漠への憧れが、枯れることなく在り続けられるのかもしれない、そう思うのです。
タブーへの挑戦のような生活や、背徳的行為を推奨する気はありません。誰が何を選び取るかはその人次第ですし、そこに干渉しようとも思いません。と言って、助けを求める人に手を差し伸べないわけではありません。ただ、きれいごとではない現実と、人間の弱さや脆さは、そのままあるがまま、受け止めるべきだと思うんです。

「地の果ての夢」にはダークな側面が余すことなく書き連ねられていて、多分読者は、そのめくるめく世界に傾倒し、酔わされることと思います。知らないものを垣間見ることの密かなる高揚感は、簡単にコントロールできるものではありませんからね。
かくいう私もそんなタンジールの日々に酩酊し、そこに生きる人たちの姿を想像しつくしました。それが自分に合うかどうかはさておきです。けれど興味深いことに、ボウルズ本人はいっこうに浮かれてはいなかったのです。そこにあったのは憂鬱であり失望であり、しかしそれこそが、ボウルズの言う自分の感覚の裏側を表現することに繋がっていたのかもしれません。
「シェルタリング・スカイ」を書きながら砂漠を旅していたボウルズは、人里離れたペンションに泊まり、ベッドの中で仕事をすることが多かったと言われています。タンジールという熱とは別に、彼がどれほど砂漠という孤高の静寂を求めていたのかがわかるような気がします。私も同じように、その孤独なる甘美な時間を感じたいと思わずにいられませんでした。
砂漠という圧倒的な存在は、それに対峙する人間の心を、あの時代のあの町に蔓延っていたどんな麻薬よりも強く酔わせるのだと思います。そして、そこからさらに奥深いものを求めて、心が焦がれて痺れて熱を持つためには、己の中の無限の想像力が何よりも大きな力なのだと感じました。それは、誰かから与えられる何かでは、決して成し得ないものなのです。
遠く離れた今も、砂漠は私を魅了し続けます。けれど物事というのは、離れれば離れるほど、美化されるものなのかもしれません。砂漠という本来の自然現象が持つ、命の瀬戸際のような厳しさは鳴りを潜め、私の前には今日も、月に照らされた青い砂漠が浮かぶ夜や、乾いたスークの風が人恋しさを掻き立てる午後が浮かび上がります。それらは明らかに偏った側面ではありますが、今だからこの場所だからこそ感じられるものであり、それはそれで面白い体験だと思うのです。
もちろん創作意欲をかき立てる場所はまだまだ多くあります。曇り空の下の荒涼たるムーアにも、花咲く白亜の断崖絶壁にも、霧雨降る広大な田園風景にも、大いなるケルトの森にも心奪われてときめきます(って、圧倒的にウェールズ寄りですが、苦笑)。それでも、その上に燦然と輝くのは、やっぱり黄金の砂漠なのです。もしかしたらこれはもう、完全なる別物なのかもしれません。

そう言いながらも、私は今のタンジールを知りません。1947年という遥か遠い時間に花開いたものが私の中で今も咲き誇っているだけなのです。すでに全く違う町にすり替わっている可能性も否定できませんが、そうであっても構わないと思うのは、もはや究極のえこひいきでしょうか。けれど、そんな風に表面が変わってしまったとしても、きっとそこには忘れ物のような気配が漂い続け、訪れる人を魅力するのは間違いないと思うのです。
それは人も同じで、熱病のように抱いていた私のタンジールへの憧れも少しずつ形を変え、ロンドーが書いたような、遠く海が見える丘の上の家のイチジクやらオレンジやらが実る庭で、その木陰にテーブルを出し午後のケーキを大切な人に焼くことが、今の私の夢だったりします。それでも、思い立てば砂漠に向かい、気がすむまでその静寂さと苛烈さの洗礼を受けることができるという、そのバランスだけは失われることがありません。
タンジールが果たして終焉の地となるか、はたまた、あれは青春の妄想だったと逃げ帰るのか、それはわかりませんが、いつの日か足を運んでみようと、今日も黄金の果てしない砂の海に思いを馳せつつ思うのです。
サポートありがとうございます。重病に苦しむ子供たちの英国の慈善団体Roald Dahl’s Marvellous Children’s Charityに売り上げが寄付されるバラ、ロアルド・ダールを買わせていただきたいと思います。
