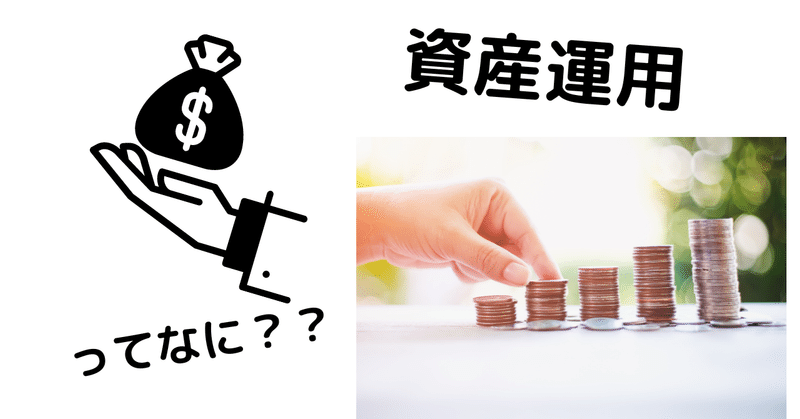
もう遅い?50代からの資産運用-小額でも始められるおすすめ6選
「資産運用なんて必要ない!」「銀行預金が一番安全!」そう思ってはいたものの、近頃急に資産運用を意識し始めた。そんな50代の方も多いのではないでしょうか。
世の中は低金利や年金の先細り、退職金の減額など、心配なニュースばかりが目につきます。
とはいえ、資産運用の知識はないし、まとまったお金もない。できればリスクも負いたくないと戸惑う方もいるかもしれません。
そこで今回は、資産運用が気になり始めた50代の方に向け、以下の項目を解説します。
50代で資産運用を始める方がよい理由
50代の資産運用の注意点
50代で始めるおすすめの資産運用方法
資産運用シミュレーション
この記事を読めば、50代で資産運用を始めるのに必要な知識と、運用方法のヒントが得られます。ぜひ最後までお読みください。
みんなどうしてる?50代の資産運用
まず50代のお金事情を調べてみました。
現在の50代は、終身雇用を前提として社会に出た最後の世代ともいえます。働くことこそが経済的安定と教え込まれ、バブル崩壊とリーマンショックを目の当たりにしているため、投資に対し疑念を持つ方も一定数いるようです。
一方でライフサイクル上の50代は、子供が成長し、学費負担から解放される時期といわれますが、個別の経済事情は異なります。
50代の資産保有状況を見ると、平均値と中央値の乖離があるなど、データにばらつきがあることがわかるでしょう。50代2人以上世帯の金融資産保有高は平均1386万円、中央値が400万円です。
さらに注視すべきは資産非保有が23.2%、100万円未満が8.9%を占めることです。単身世帯では、非保有率がさらに高まります。
こうしてみると、50代からの資産運用を始めとするマネープランは、同年代の動向を参考にできず、個別に立案するしかなさそうです。
参照:「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]」(令和3年以降)
それでも50代で資産運用を始める方がよい理由
50代から資産運用を始めるのは、遅すぎるでしょうか?結論から申し上げますと、決して遅くはありませんし、運用するメリットは充分あります。
確かに50代は、20代や30代のように運用に時間を掛けられません。そのため運用期間に応じて得られる利殖が少ないことや、リスクを取りにくいことから「今さら資産運用したところで遅い」と考えられがちでしょう。
それでも資産運用をすれば、将来設計に応じた資産形成がそれなりにでき、インフレによる資産の目減りをある程度防げるのです。
特に、10年以上などの長期で資産運用をすれば「複利」の効果で、銀行預金より効率的にお金を増やせる可能性も高いです。
仮に100万円の資産を現金や普通預金で所持し続けたとしましょう。現在は100万円の価値の商品を現金で買えます。5年後・10年後はどうでしょうか?物価上昇率を加味すると、5年後には100万円の現金では購入できなくなってしまいます。つまり、それだけ資産が目減りしてしまうのです。
しかし物価上昇率より高い金利で資産を運用すれば、目減りをカバーできます。また、目標を定めて一定額を運用に回す習慣を身に着けることも、今後の長い人生を見据えれば重要でしょう。
50代が資産運用で失敗しないための注意点4つ
50代で資産運用を始める場合には、以下の4つの点に注意しましょう。
老後に必要なお金を試算しておく
余裕資金だけで行う
リスクを抑え、分散する
勧められるがままに契約しない
それぞれ確認していきます。
老後に必要なお金を試算しておく
50代で資産運用を始める際の最初に注意すべき点は、具体的な運用方法を決める前に、老後に必要なお金を試算しておくべきということです。
まず、これからのライフイベントを整理します。
子供の独立や結婚
定年と実際に働きたい期間
住宅リフォームなど
いつ、どんな費用が必要になるかを把握できたら、大まかな支出額と見込める収入額を計算し、資産運用の金額や時期のゴールを決める目安にします。その際に生活費だけでなく、住宅改修費や医療費・介護費用などの臨時出費を見越しておく方がよいでしょう。
もし詳細な計算の仕方を知りたい場合は、FP(ファイナンシャルプランナー)へ相談するようおすすめします。
余裕資金だけで行う
資産運用は、当面使う予定のないお金だけを運用に回すことが肝心です。
まず、手持ちの資金を次の3つに分けて考えましょう。
当座の生活費
使うことが決まっているお金
使う予定のないお金
この中で、生活に使うとわかっているお金を運用するのは避けるべきです。もし短期でお金を引き出してしまうと、運用益が少なく損失が出やすいからです。
2番目の使い道が決まっているお金は、あまり運用しない方がよいものの、予定が何年も先であれば、運用してもよいかもしれません。
資産運用に回すお金は基本的に、3番目の使う予定のない余剰資金だけを充てるようにしましょう。
リスクを抑え、分散する
50代で資産運用を始める場合は、なるべくリスクを抑えましょう。具体的には、運用する先やタイミングをできるだけ分散することで、リスクを最小限にできます。
例えば運用先を株式・債券・外貨などに分散することで、ひとつがマイナスになっても他でプラスになり、損失をカバーできる可能性が高まります。他にも、国内外の銘柄で分散するなど、エリアで分ける方法もあるでしょう。さらに、一時金でなく積立方式で運用すれば、運用のタイミングを分散できます。
50代では、若い方のように長い運用期間を取れず、大きな損失を出した場合のリカバリーが難しいため、リスク抑えめの運用を心がけましょう。リスクを分散する具体的な方法は、資産運用を始めると決めたら積極的に調べてみましょう。
勧められるがままに契約しない
勧められるがままに商品や金額を決めず、必ず他の情報と照らし合わせてから判断しましょう。
一般に窓口や営業担当者は、会社や担当者の成績になる商品を勧める傾向があります。たとえ長年信頼している担当者の勧めであっても、すべてお任せにせず、考える時間をもらい、不明な点は確認するべきです。
老後資金ともなれば、ある程度大きな金額もしくは、長い期間での運用になるでしょう。途中で損失が発生しても、担当者が責任を取ってくれるわけではありません。
そうなったときに後悔しないよう、自分の財産を預ける限りは、自分で判断し、納得できる運用を心がけましょう。
50代で始めるおすすめの資産運用
ご自身のライフプランと必要資産が把握で来たら、実際の運用方法を検討しましょう。
50代で運用を始めるのにおすすめの方法として、少額から始められ、比較的低リスクの運用方法を6つ紹介します。
外貨預金
積立投資信託
NISA
iDeCo
債券投資
個人年金保険
ひとつずつ見ていきましょう。
外貨預金
外貨預金とは、日本円ではなく外貨で預け入れる預金です。日本より金利の高い国の通貨で預金すれば、日本円より高い利息が得られることが利点です。銀行窓口やネット銀行で取り扱っており、米ドルなら1ドル、ユーロなら1ユーロから始められます。
手続きとしては、ただ口座を開設するだけなので、難しい知識は必要ありません。ただし、為替レート次第で損をするケースもある点には注意が必要です。
外貨預金は、少額から手軽に資産運用をしたい方におすすめです。
積立投資信託
投資信託とは、多数の投資家の資金をまとめて専門家が投資、複数の銘柄で運用する運用方法です。取扱機関は証券会社や銀行で、100円から始められるところもあります。
少額でも運用先が分散され、リスクを抑えられるのが特徴です。
投資信託には公社債投資信託・株式投資信託などがあり、比較的ローリスクとされますが、不動産投資信託「REIT」はミドルリスクに分類されます。
運用は運用会社の専門家(ファンドマネージャー)が行うため、投資の専門的な勉強をする時間がない方にもおすすめです。
NISA
NISAとは商品名ではなく、毎年一定金額の範囲内で、購入した株式・投資信託などから得られる利益が非課税になる制度のことです。取扱機関は証券会社や銀行で、月額100円から始められるところもあります。
毎年120万円まで最長5年間、投資の利益が非課税になることがポイントです。
※なお、現在のNISA制度は2023年で終了となり、2024年から運用先別の2階建ての制度に変更になります。2階建ての制度では、1階部分の非課税枠は20万円、2階部分の非課税枠は102万円です。
NISAは、節税しながら手軽に資産運用を始めたい方におすすめです。
iDeCo
iDeCoとは、個人型確定拠出年金つまり、自分で拠出した掛け金を自分で運用する年金制度のことです。取扱機関は証券会社や銀行で、月額5,000円から拠出できます。
預金・保険(元本確保型)か、投資信託のどちらかで自由に運用でき、運用次第で受け取る年金額が変動します。ただし年金制度のため原則、60歳以降まで引き出せません。運用益は非課税で、受け取り時は退職所得控除または公的年金控除の対象となり、税制上優遇されています。
iDeCoは、節税しながら老後資金などの長期資金を形成したい方におすすめです。
債券投資
債券は、国や企業が資金を集める際に発行する証券のことで、国が発行する国債と、企業が発行する社債があります。発行者によって元本と利息の支払いが約束されている点が特徴です。
国債の取扱機関は証券会社と銀行で、社債は証券会社です。個人向け国債は額面1万円から、普通社債は10万円単位、外貨建て債券は為替レートにより数万円から購入できる場合もあります。
債券は銀行預金より金利が高く、元本と利息が約束されているものの、発行者が破綻した場合には償還されない点にだけ注意が必要です。
債券は、ハイリターン運用よりも安定運用をしたい方におすすめです。
個人年金保険
個人年金保険とは、保険会社が取り扱う年金受け取りを目的とした貯蓄保険です。取扱会社と契約条件によっては月1万円台から始められるものもあります。
個人年金保険は、一定の基準を満たす場合に「個人年金保険料控除」を受けられる税制上の優遇があるのも利点です。
払い込み期間は通常10年以上、受け取り期間には「終身(一生涯)」「有期(生存の場合に一定期間)」「確定(生死にかかわらず一定期間)」があります。
加えて契約時に年金額が確定している「定額個人年金保険」と、運用実績により年金額が変動する「変額個人年金保険」とに分類されます。
定額の場合には契約時に、年金額が確定しているため安心ですが、途中解約した場合には元本割れをする可能性があるためご注意ください。
個人年金保険は、拘束力を利用して確実に貯めたい方におすすめです。
50代からいくら殖える?資産運用シミュレーション
ここで実際に資産運用のシミュレーションをしてみましょう。
運用シミュレーションは、金融庁や民間のサイトで金額や運用期間を入力すれば、手軽に行えます。以下に、10年間積み立てをした例を2つ挙げますので、参考にしてください。
年利3%で月1万円積み立てて10年運用、いくらになる?
月々定額の、もっともシンプルな積立例です。金融庁の資産運用シミュレーションを利用して計算してみました。
積立元金1,200,000円が、10年で1,397,414円。運用収益は197,414円です。
やはり複利の効果は大きいといえます。収益金で旅行なども可能、物価上昇リスクにも備えられそうです。
初期投資50万円・月1万円で10年間の運用で200万円受け取るには、年利何%必要?
今度は目標金額と投資金額が決まっている場合に、年利何%で運用すればよいか?というシミュレーションです。(みんかぶによる資産運用シミュレーション)
表題の場合、10年間で必要な利回り(リターン)は2.60%(年率)となり、これに近い金利の運用方法で運用すれば目標金額に届くことになります。
このような逆算は、住宅資金や老後資金など、将来使う資金の運用を考える際に有効です。
FP(ファイナンシャルプランナー)に相談すれば、細かい係数を用いて詳細な計算作成が行えます。FPの保有資格により個別商品の斡旋ができない場合もありますが、運用の方向性を多角的に見てもらえるので、まずは相談するとよいでしょう。
まとめ:【まだ間に合う!】50代初心者ができる資産運用方法はある
今回の記事では、50代から始める資産運用の注意点、おすすめの資産運用方法、シミュレーションについて紹介しました。
金利低下・退職金や年金の目減りなど、将来のお金に対する不安要素が多い中、これまで預金でしか持たなかった資産を、いかに運用するかがポイントになってきます。何より、不安のあまり「もう遅い」と諦めず、少額でもできることから始めることが重要です。
まずは現在の資産をキチンと把握すること、ライフプランを立てることから始めましょう。FPに相談するのも有効です。その上で、ご自身に合った運用方法を選び、計画的に無理のない資産運用を行いましょう。
よろしければサポートお願いします(^^) 頂いたサポートはクリエイターのみなさまのサポートやボランティア資金にします♪
