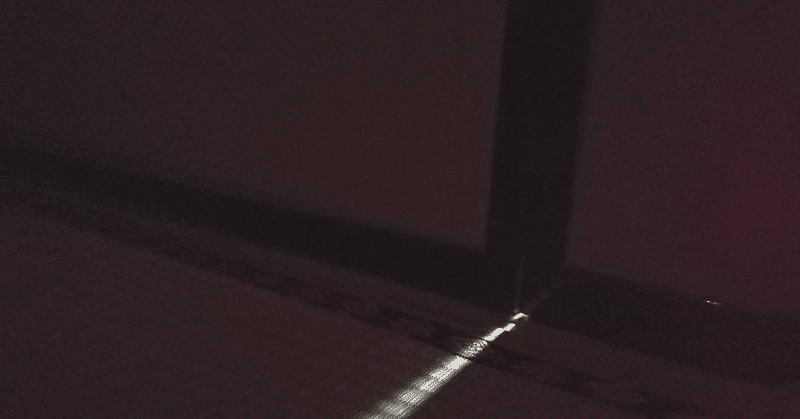
職人の朝は早い
アラームが鳴った。
「ふあぁ…もうそんな時間か…」
すぐにスマホの画面を左に滑らせた。
黒い画面に一瞬寝ぼけた僕が写る。
生まれて早29年。
どうでもいいことかもしれないが、
アラームは機械的な電子音が最適だと思う。
好きなアイドルの曲にしていた時期もあったが、
曲を聞くたびに朝の憂鬱が思い出される。
気づけば彼女らまでも嫌いになってしまった。
チェキを見るたびに身体が起きねばと逆立つ。
何かを恨まないためにもやはり感情のない電子音がいい。
眠り眼を擦り、壁に掛けた時計を見る。
午前2時30分と45秒。
しかし、僕の部屋の時計は秒針が曲がっており、
いつも時間がずれている。
そのため結局毎回スマホで時刻を確認することになる。
しかしこれが一種のルーティーンとなっていた。
今から始まる戦いのための。
窓の外では信号の黄色がせわしなく瞬きし、
部屋の内にいる自分が見つめている。
上京前まで都会は眠らないものだと思っていたが、
僕の周りはしんと静まり返っていた。
ここが思ったより都会でないだけなのかもしれない。
「そろそろ準備しなきゃ…」
鏡の辺にカビの生えた洗面台で顔を洗い、
一昨日洗ったばかりのタオルで拭いた。
そして4畳半の畳に腰を下ろす。
僕は両手で頬を叩く。
パシンと部屋に破裂音が響く。
昔から気合を入れるときにはこうしていた。
子供の頃に見たアニメの影響だと思うが、妙に気に入っている。
「よし、今日も張り切っていきますか…!」
僕は机の上に置いてあるモノのつまみを回した。
「今週も始まりました!
みちしるべのオールナイトニッポン!」
僕はいわゆる『ハガキ職人』というやつだ。
毎週水曜深夜27時に始まるお笑いコンビ「みちしるべ」のラジオに、
いつもメールを送っている深夜ラジオリスナーだ。
メールであるが、あくまでハガキ職人と呼ぶ。
友人に話したときに、和紙を作る人みたいなイメージを持たれたこともある。
ラジオというのは基本的にリスナーのお便りで成り立っている。
その話からパーソナリティーが話を広げ、番組が作られていくのだ。
もちろん構成作家などもいるが、
リスナーも番組における重要な要素を担っている。
暗い趣味だと思うかもしれない。
実際、僕はハガキ職人をしているとあまり人には言わない。
趣味を聞かれると映画鑑賞と嘘をつく。
誇りはあるが、後ろめたくもあるのだ。
しかし、ハガキ職人から放送作家になった人だっている。
馬鹿には出来ない。
そのうち僕だって…
そしたらみんなを見返してやれる。
「その年でまだコンビニバイトやってるのか」と嘲けたみんなを。
だから胸を張って、ハガキ職人をやっているつもりだ。
ネットの"あいつら"とは違うんだ。
僕は"あいつら"を嫌悪する。
アラーム音になり、死んだ曲のように。
YouTuberにスパチャを送ってるような奴らだ。
本質的には同じものではあると思うが。
ファンがお便りを送って本人に読んでもらう。
そしてその反応を楽しむもの。
しかしあっちにはセンスがいらない。
金さえ包めば誰でも読まれるんだから。
僕のはいつだって考えて、考え抜いたものだ。
一文字にだって妥協しちゃいない。
僕に言わせればスパチャは邪道だ。
曲がってしまった秒針だ。
そんな僕は『明後日のカレー』という名前でメールを送っている。
その界隈では有名なリスナーだと自負している。
面白いメールの月間MVPに選ばれたことだってあるのだ。
小さなトロフィーが箪笥の上で鈍く光る。
僕の名前を聞けば、「あぁ!いつもの!」
と、みちしるべの二人もわかるくらいには。
「いや~最近めっきり寒くなってきましたねぇ、
ということで今回は個人的に寒かった話でメールを募集しております!」
「飯田はなんかある?」
「そういえばこの前ね…」
二人がエピソードトークを始めた。
大体今からならお便りを読むまで15分といったところだろう。
ハガキ職人は瞬発力が大事である。
まず書く内容の選定、
そしてそれが採用されるほどの面白さや
話が膨らむ余地をはらんでいるのか。
それらを一瞬で判断し、面白おかしくメールを書かなくてはならない。
ある意味アスリートに近いのではないかとすら思う。
今日も僕は
渾身のエピソードを考え、
それを面白おかしく整え、
パソコンからメールを滑り込ませる。
10分ほどが経った。
「そろそろお便り読みましょうか~。それでは東京都、ラジオネーム…」
(来い!!!!)
「『明後日のカレー』さん、
(よし来た!!!)
みちしるべさん、こんばんは…(はい、こんばんは)」
今日は運がいい。
まさか初手で読まれるなんて。
あまりないことなので、
テンションが目に見えて上がる。
しかし気を抜いてはいけない。
二人の反応は…?
「いや~やっぱり『明後日のカレー』はいつもおもろいなぁ。」
僕は小さくガッツポーズをする。
認知されていることも嬉しいが、
笑ってくれたことに対してだ。
本当は声を上げたいが、壁が薄いため我慢する。
スタジオ内に笑いが起こり、
僕の話から連想されたエピソードを二人は話始める。
いいぞ、完全にハマった…
僕は小刻みに震えている。
人が見たら気味悪がるだろうな。
客観的にそう思う。
そこから連鎖的にほかのリスナーのメールが読まれ、
番組が盛り上がる。
自分も負けじとキーボードを叩き、メールを走らせる。
(さっきよりも面白いやつを書いてやるぞ…)
事件が起きたのは
番組が終わる10分前だった。
「それでは最後のお便りいってみましょうか!」
「東京都、ラジオネーム…」
「『明後日のカレー』さん」
「えぇ!?」
思わず大きな声が出る。
壁が薄いことを忘れていた。
僕は隣人に怒られぬよう
急いで口を抑える。
本日2回目の採用。こんなことは初めてだ。
3年ほど職人をやっているが、高揚感がとまらない。
「みちしるべさん、先ほどのメールの続きなのですが…」
また僕は大きな声を上げた。
壁の薄さなど気にも留めなかった。
先ほどとは打って変わって悲鳴に近い金切り声を。
こんなことは書いてない。
知らないエピソードが自分の名前で読まれている。
読み終えた二人は大爆笑している。
いつもならガッツポーズしているところだ。
今はそれどころではない。
何が起きているのか。パニックだ。
この『明後日のカレー』は誰なんだ。
何が目的で?
必死に頭を巡らせる。
ズキンズキンと脳の奥の方で鳴っている。
血流を感じ、奥歯が痛む。
身体のサイレンのようなもの。
呼吸が荒くなる、瞼が重い。
僕は今、
夢でも「見て」いる。いや「聴いて」いるのか。
気づくと番組が終わる寸前であった。
「それではまた来週~!!!」
「待って!」
声には出なかったが、僕は確かに言った。
午前5時、空が白みはじめた。
窓の外では瞬きをやめた信号機が赤い目をしていた。
そこからは早かった。
次の週も『明後日のカレー』が読まれる。
しかし、ガッツポーズはしない。
できない。
僕ではない『明後日のカレー』がそこにいる。
ことごとく僕のメールは読まれなくなった。
秒針は曲がったまま、間違った時を告げる。
この偽『明後日のカレー』は
一体何が目的なんだろうか。
数年前に、
ラジオイベントで顔が見えないこといいことに有名リスナーを名乗り、
他のリスナーに性的な行為を強要し逮捕されたという事件を目にしたが、
そういう目的なのだろうか。
その効果はなしていないが。
しかしなぜ僕のメールが読まれないんだろう。
スタッフのいたずらか何かなのか。
一番気に食わないのは、
絶対自分の送るメールのほうが面白いのだ。間違いない。
偽『明後日のカレー』のお便り。
客観的に見ても面白くないメールだと思う。
今、客観的に見れているのかはわからない。
あいつのメールは
昔、流行ったものの焼き増しで、オリジナリティに欠ける。
しかしスタジオは爆笑しているのだ。
それが非常に歯がゆい。
そのメールが僕の作品と思われるのも嫌だ。
この気持ちはどこにぶつければいいのだ。
誰に訴えればいい?
「盗まれたんです!何って!自分を!」
警察は動かないだろう。
直接被害を受けたわけでないから。
昔の記憶がよみがえる。
高校の文化祭だった。
僕のクラスは出し物が決まらず、学級会で話し合っていた。
あーだこーだと意見を述べる者。
友人同士で耳打ちする者、窓の外を見つめる者。
いろいろな意見が出るが、いまいちで皆がうなだれている。
クラスに暗いムードが流れていた。
黒板がいつもより濃く見える。
そんなときだった。
クラスの陽キャグループの一人が言った。
「お化け屋敷とかでいいんじゃね?」
すると皆がうなづき、トントン拍子で意見がまとまった。
鶴の一声のお手本のようなものだった。
しかし、僕は気づいていた。
実はその意見は停滞していた時にクラスの目立たない女子が、
一度あげていたアイデアだ。
彼女は黙ったまま、隣の机の脚を見つめていた。
何かいるわけでもないだろう。
重要なのは『何』をしたのかではない。
『誰』がしたのかなのだ。
思い知った秋の夕暮れだった。
でもそれを認めたくなかった。
だから匿名で、
同じスタートラインで戦えるハガキ職人が好きになったのだ。
29歳になった僕に、
あいにく鶴は鳴いていない。
僕も黙るしかないのだろうか。
「それでは続いてのメールです…」
「お疲れ様で~す!」
「お疲れ様、今日もいい感じだったよ。」
「ありがとうございます!」
午前5時半、ラジオ局の廊下をお笑い芸人の
みちしるべの二人が歩いていく。
二人はADなどに頭を下げている。
お笑い芸人としては中堅といった立ち位置だが、
いくつになっても、
ああいった謙虚さは忘れてはいけないなと思う。
それが仕事にも表れているんだろうか。
大きなあくびをしながら、
二人はエントランスを出ていく。
スタジオにはディレクターが一人残されている。
ディレクターは首を後ろに曲げ、くるりと回す。
コキコキと骨が鳴り、力が抜ける。
おもむろに立ち上がり、ドアを開けた。
そして先ほどまでみちしるべが座っていた椅子に腰かける。
飯田が座っていた席だ。
机には今日読まなかったメールが束になって置かれている。
その中から彼は一通のメールを手に取った。
昨晩、自分が出したメールだ。
ふーっと息を大きく吐いた。
何かを覚悟したかのような眼だ。
彼が語りだす。
「これはあくまで独り言なんだが…」
「あのYoutuber…実は政府の役人らしいぞ。」
「今じゃインフルエンサーなんてのはほとんど政府側の人間と聞く。」
「インスタもツイッターも作られた流行だ。」
「みんな気づいていないんだ。」
「私たちは大きな何かの支配下にある。」
「救う救われるのレベルにはもうない。」
「革命なんてのは起こらないんだ。」
「誰かを倒してハッピーエンドな桃太郎じゃないんだ。」
「我々だって大きな何かの一部なんだから。」
「誰のせいでもないが、誰かのせいだ。」
「視聴回数だって本物かなんてわかりゃしない。」
「ちょっと圧力をかければいじれるさ。」
「自分は上げて、不適切なものは下げる。」
「可愛いは作れるなんて言葉が流行ったが…」
「そりゃそうだろう。」
「視聴者はなにを見てると思う?」
「数字だよ、数字。」
「面白いから見るんじゃない、人気があるから見るんだ。」
「可愛いから人気じゃない、人気だから可愛いんだ。」
「結局『何』をしたのかではないんだから。
あくまで『誰』がしたのかなんだよ。」
「逆にそこしか人は見てない。」
「何をしたかは重要じゃない。」
「そうやって少しずつ紛れ込ませる。」
「都合のいいものを良いものと宣伝する。」
「悪いものはしない。」
「無意識に民衆の思考を固めていくんだ。」
「そうすりゃうまい具合に操れるってことなんだろうな。」
「そういうシステムなんだよ。」
「人々を動かす、そのコンテンツを操る。」
「次にそのシステムは何をするのか。」
「邪魔なものを排除していくだろう。」
「邪魔になるのは今、人気のものだ。」
「それがある程度の力を持っていることを知っているからだ。」
「するとシステムはどうするんだろうか。」
「既存の破壊、または成り代わりを行うだろう。」
「システムに迎合できないものは壊す。」
「時にはBANしたり、おススメに出ないようにする。」
「その中で利用できるものは合理的に利用するのかもしれない。」
「人気のあるものの再利用。リサイクルだ。」
「非常に簡単だ。首だけ挿げ替える。」
「誰が気づけるんだろうな。」
「あの人気ブロガーも小説家、
ハガキ職人までも今はAIだなんて。」
「何かが今日も変わっていく。」
「失われていく。」
「誰もそれには気が付かない。」
「気が付けない。」
「そういうことになってるんだ。」
捨て台詞を吐いた彼はため息をついた。
そして足早に部屋を去っていった。
マイクの電源はついていない。
