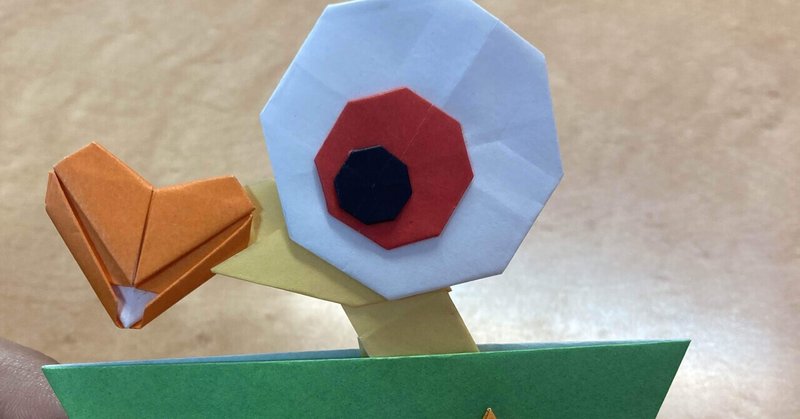
苦手なこととの付き合い方
私の最近の疑問は「人は苦手なことをわざわざやるべきなのか」だ。
この疑問に対し、自分なりにやや断定気味に回答してみる。
「人は苦手なことを一度はトライすべき。
そしてトライした結果にはこだわらず、またその都度選択すべし」
ただ、そもそも苦手と感じているということは、何かしらのこれまでの経験に基づいて判断しているわけだ。となると、苦手なことを一度はトライすべき、という文脈は矛盾しているように思える。もう少し深く考えてみる。
例えば私は、人にわかりやすく伝えることや教えること、自分の好きなものを魅力的に伝えることにとても苦手意識がある。(特に即興で話し言葉で語ることに強い苦手意識がある。)
それまで自分が何かを伝えようとするたびに言葉が出てこなかった経験が積み重なって私の苦手意識は形成された。
具体の経験が私の「教えるのが苦手、うまく伝えるのが苦手」という抽象化した苦手意識を生み出している。
ただ、この人生、迫りくる事象はただ一つとして同じものはない。なのにそれを私たちは自分自身で、これは得意、これは不得意、と自分で分別しているのではないだろうか。
そのため、何かの事象が迫ってきたときに、「これは苦手なやつだ」とポイっと分別してしまいがちだが、個々の事象は全く別のものなんだと再認識し、トライしてみるとその分別してたはずの境界が溶けていき、「意外にやったらできる自分」が出来上がるんじゃないだろうか。それって楽しくないか。
実際に、私は同級生に宿題聞かれてもうまく教えられないという経験が多くて教えることに苦手意識を持っていた。しかし大学の時、バイトの後輩の頼みでその子の妹の家庭教師を嫌々ながら引き受けてしまった。するとどうだろう。その生徒との関係性が良好だったのも後押ししてか、自分が思ってるよりもうまく説明できた。理解してもらえる伝え方ができた。教えるのが楽しいとすら思えてきた。その時、苦手が苦手でなくなった。自分が広がった気がして嬉しかった。
苦手なことがやってきた時はとにかくぶちあたってやってみると意外に面白いとわかることもある。だからこそ私は、抽象化された苦手意識に引っ張られず、どんな事象も自分の糧だと思ってトライしてみるのを全力でオススメする。
話は戻るが、最初にこの「苦手なこととの付き合い方」という問いについて考えた時は、苦手なことをすべきかしなくてもよいか、の2択で回答を出そうと思っていた。なぜなら、これまで私が聞いてきた世間的文脈が以下のような二項対立的なものだったからだ。
①苦手なことこそできるようになろう
②苦手なことではなく得意なことを伸ばそう
ビジネスの世界などは特に、①の、できないことや苦手なことができるようになることを自身の成長とし、それを求める傾向が強いと感じる。表面的には得意なことを伸ばしていくことを推奨しながらも実際の現場レベルでは苦手なことを埋めていくことを求められがちだ。
それへの反発として私は最近②の、得意なことを伸ばして、苦手なものはわざわざやる必要ないのでは?という思考を強めていたところだった。
だがしかし気づいた。私も二項対立に陥っていたのだった。苦手なものから離れるでもなく、真正面なら全力で向き合うでもない方法。
ちょっと齧ってみる、触れてみる。
そんな気楽な付き合い方が一番良さそうだ。
それでもってだめならだめで、「やっぱり私はダメなんだー」と悲観的になるのではなく、「ま、こーゆうこともあるよね、はい次!」くらいのテンションでやっていけたらいいなと思う。もちろん、ほんとに苦手なものはあると思うので、どうしてもこりゃ無理だなーという直感的な否であればやる必要はないと思う。
ただ何でもかんでも、苦手そうなものとして避けていくとどんどんネガティブな自分の固定化が進んでしまい、偏った人間になってしまうし自分の可能性を閉ざすことになりかねない。
どうしても、経験によって裏打ちされると「自分はこーゆう人間だ」という思考になりがちだが、そうではなく、「今回のケースは自分にはフィットしなかっただけですわー」くらいの感じで一個一個の行動を細かく見ていけば、自分の固定化を避けられそうだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
