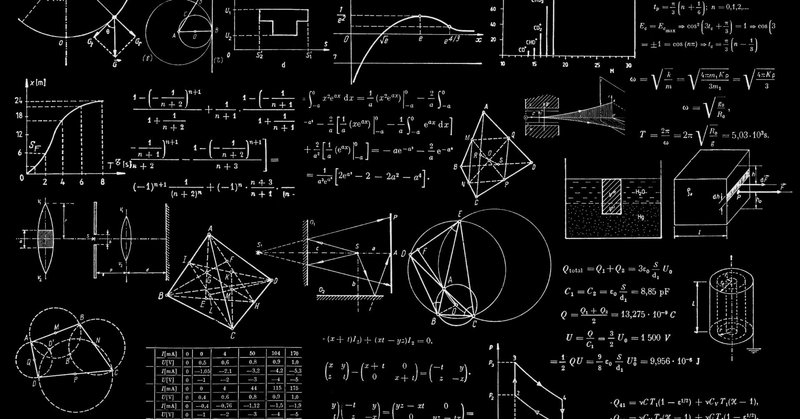
『スパイス』 第4章 逆襲
まさかジェシカをくすぐる時が来るとは思わなかった。以前に一度だけ、ほんの少しだけ、仕返しを試みたことがあるが、あまり上手くいかなかったばかりか、何倍と例えるのも気が遠くなるほど凄まじいお返しを食らった。それ以来楓は仕返しをしようなどという邪念は抱かなくなっていたが、ライリーの後ろ盾があるとなれば話は別だ。
そういう訳で楓は、ジェシカが出張に行っている数日の間、ライリーと共に作戦を練っていたのだった。今日の朝早くに帰ってきたジェシカが眠りにつくと、ライリーから作戦決行の合図が出た。
「ねぇ、やっぱりまだ疲れてるんじゃない?」
「もう10時間よ。そろそろ良いんじゃない?」
ジェシカが眠りについてからかなり時間が経った頃、楓とライリーはいよいよ計画を実行しようとタイミングを伺っていた。
そっと部屋に入り、音を立てないようにベッドに近づく。ジェシカは切れ長の目をしっかり閉じて寝息を立てている。普段は隙のないジェシカの無防備な姿に楓の方がドキッとする。
ライリーから拘束具を受け取り、手首にそっと巻きつける。誰かをくすぐるのもそうだけれど、誰かを拘束するのもドキドキする。相手がジェシカだからというのもあるけれど、それを除いても、これまで自分がされていたことを視点を変えて再体験するようで身体の奥がぞわぞわする。
そうでなくても、きつくないだろうか、痛くないだろうか、とあれこれ考えると手間取ってしまった。拘束って意外と大変だ。
「ずっと起きなかったらどうする?」
「大丈夫。じきに気づくわ」
その言葉の通り、程なくして
「ん――え?ちょっと何これ―――」
ジェシカが目を覚ました。手を動かそうとし、しかし動かないことが分かって混乱の表情を浮かべる。
楓はまたしてもドキッとした。自分が初めてくすぐられた時を否が応でも思い出してしまう。あの時とまったく同じ状況だ。目を覚ますと身体が拘束されていて、何が何だか分からず恐怖が募り、そしてその通り翻弄され、すべてが始まった一年半前のあの日―――。
「カエデ!」
状況に頭が追いついたジェシカが声を上げる。
「カエデ、あなたなの?」
「えっ、わたし―――」
「私に仕返ししたいの?」
「あ、その――」
「だけど一人では不安だからライリーと協力することにしたの?」
「えっと――」
「ジェス、私よ」ライリーが助け舟を出した。
「私が誘ったのよ。カエデが余りにも悔しそうだったから」
「なるほどね。それで私がいない間に策を練ってくれてたのね。あなたたちが私をどうしてくれるのか、楽しみだわ」
ジェシカは怖がっている様子も怒っている様子もなく、というより寧ろどう見ても―――楽しんでいる。
「……いいの?」
「今さら何言ってるのよ。その気なんでしょう?」
「本当に?」
「もしかして私をくすぐるのが怖いの?」
「怖くない!」
楓は反射的に叫んだ。まだくすぐってもいない内から負けてなどいられないと、楓の方も心が決まる。急に緊張してきたが、もはや後戻りはできない。
「まずはここでしょ?」
震える手をそっとジェシカの脇腹に添える。一つだけ知っているジェシカの弱点。身を捩らせるか、声を上げるか。そんな反応を期待していたが―――
「あれ、違ったっけ」
「フフフ、そうみたいね」
ジェシカは笑ったが、それはくすぐったいからではないことは楓にも分かる。少し指をずらしてもう一度トライしてみるが、ジェシカの様子は変わらない。
「我慢してるの?」
「してないわ」
「うそ」
「本当よ。あなたじゃあるまいし」
「なにっ」
「頑張って、カエデ」ライリーが声援を送る。
「本当にここら辺だったのよ!」
「その時はどうやって見つけたの?」
ライリーに聞かれて、楓は記憶を辿った。あの時ジェシカの弱点をどうやって見つけたか――少しずつ指をずらし、そして表情を見る――そうだ。
楓はジェシカの顔を見ながら場所を変えていった。挑戦的な瞳に見つめ返されるが、めげずに手を動かし続ける。絶対に見つける。その思いで少しずつ、少しずつ指を動かしていった。すると突如、ジェシカの眉がピクリと動いた。
「アッ」
ジェシカが声を上げ、そして腹筋に力が入る―――ここだ!
「やった!」
「おめでとう、カエデ」とライリーが微笑む。
もう一度、今度はすぐにやめずに長く続けると、ジェシカは身を引きながら笑い出した。
「わぁ………」
うそ。すごい。あのジェシカがくすぐったがっている。
「かわいい…すごい…」
綺麗に上がった口角、艶やかな笑い声、乱れた呼吸。これまで見たことのないジェシカの姿は、どうしようもなく楓を煽った。楓が少し指を動かすだけで、ジェシカはそれ以上に反応する。楓のくすぐりで、楓の指の動きで、楓によって、ジェシカが身を捩って笑っている。誰かをくすぐるって、こんな感覚なんだ。楓の心で何かが弾けた。
他の場所ではどんな反応をするんだろう。もっと大きい反応をするかもしれない。その好奇心と期待が楓を駆り立てる。
ベッドの端に移動し、足の裏にそっと触れるとピク、と一度跳ねた。案外すぐに返ってきた反応に楓の心も跳ねる。しかしそれ以外の反応はなかった。その後も色んな場所をくすぐってみるが、楓の期待するような反応は得られない。
すると、
「そこじゃないわよ」ジェシカが言い、楓は指をずらす。
「もう少し右よ」今度は右。
「いや左かも」え、反対?
「上かもね」
「ねぇ!」
「アハハ。単純なんだから」
自分が操られていたことにやっと気づき、悔しくてたまらない―――くすぐってるのは私なのに!
「ジェスったら、もう少し手加減してあげても良いんじゃない?」
「私が何を手加減するって言うの?手足を拘束されているのに?」
「もう―――カエデ、気持ちで負けたらいけないわ」
「そんなこと言ったって、効かないんだもん」
「そんなに早く諦めてもいけないわ。効かなかったからってすぐに場所を変えるのは勿体ない」
「ちょっとライ」
「同じ場所でも触れ方を変えたら効くかもしれない。爪か、指か、その間か。覚えておきなさい、指先は使い様」
そう言われ、今度は少し爪を立ててみる。そのまま長く線を描くと、ジェシカの脚がピクッと震えて拘束具がカタッと鳴った。
「やった!」
「お見事」ライリーが優しく微笑んだ。
ジェシカは声こそ出さないが、短く呻いては顔をしかめる。耐えているのだと楓には分かった。ジェシカが耐えている。楓のくすぐりに耐えている。その事実が楓の心を躍らせた。
反対の足も同じように触れると、ジェシカは歯を食いしばって脚を引き攣らせた。
「やるわね、カエデ」
悔しそうにそう言って、ウ、とまた呻く。普段は余裕を漂わせ楓を翻弄してばかりいるジェシカを、今は自分が翻弄しているのだと思うと、楓は嬉しくてたまらなくなった。
「それしか言えないよね?いつももっと、これの何倍もひどいこと私にしてるもんね」
「あらカエデ、そんなこともできるようになったの?」
「どういうこと?」
「ライリーの教育が良いのね」
「私は何も教えてないわよ。あなたじゃないの、ジェス」
「たしかに私は色んなことを教育してるわ。ね、カエデ?」
「え?色んなことって、私がジェシカから教わってることなんて――」
自分が何を言っているかに気づいて急に恥ずかしくなった。
「何?私に何を教わってるか、ちゃんと言いなさい?」
「やだ!言わない!」
いたたまれなくなって楓はジェシカの足にまた爪を立てた。くすぐられながら平然と喋るジェシカも一瞬なら止められる。
「ダメよ、そういう使い方をしては。自分の苦し紛れに人をくすぐってはいけないわ。くすぐりは相手を苦しませるためにするのよ」
「じゃあもっと苦しんでよ」
そう言って楓はベッドの中央に戻り、今度は脇に触れた――が、
「えっ」
ちゃんと触れられていなかったのではないかと思い、もう一度しっかりと触れてみる。
「えっ?」
確かに触れているはずなのに、ジェシカはびくともしない。
「くすぐったくないの?」
「えぇ」
「そんな訳ない!」
信じられない。脇がくすぐったくない人がこの世にいるはずがない。
「どうして…なんで…」
本当に信じられない。しかし何度指を滑らせても同じことだった。
「…触れられてる感覚はあるんだよね?」
「アハハ、あるわよ、それは」
「信じられない…」
「カエデ。なぜ信じられないか、教えてあげるわ」
「何?」
「あなたとびきり弱いものね、脇?」
「えっ、違っ、なにっ」
「何が違うの?あ、そうか全部?ごめんなさい、全部弱かったわね」
「もう!」
助けを求めてライリーを見るが、ライリーは呆れたように笑っている。
「笑わないでよ、ライリー」
「ごめんなさい、カエデ」
大して謝っているように見えないライリーを睨んでから、今度は首に触れてみる。爪か、指か、その間か。指先の使い方を変えながら、優しく、ゆっくり、色んな場所に指を這わせる。
「それにしても上手ね、カエデ。普段ジェスにくすぐられているだけあるわ」
ライリーが感心したように言った。
「本当、上手よ」とジェシカも賛成する。
「ほんとに?それじゃ――」
「くすぐったくはないわ。残念」
言葉の通り、ジェシカは首をくすぐられてもまったく平気そうだ。
「えー、上手だけど効かない人がいるってこと?」
「下手でも効くくらい弱い人がいるならね」
「え――もう!また!」
「私はあなただなんて言ってないわよ」
「私も私だって言ってないから」
首なら効くと思っていたので残念だが、しかしそれなら、と楓はあることを思いついた。
ジェシカの首筋の少し内側に指を当てる―――ジェシカが出張に行く前、二人が楓に試した方法。ライリーにあれは何だったのかと尋ねたら教えてくれた。首筋に手を当てて質問し、目を見て呼吸を感じることで、脈拍や瞳孔の収縮、呼吸の変化からそれが本当かどうかを見分ける嘘発見法だということ。首に手を当てるから、くすぐりに弱い楓には効き目がないということも。しかしそれは、裏を返せば、ジェシカには効き目があるということだ。
楓はジェシカの首筋に片手を当てたまま、もう片方の手で脇に触れてみる。本当は我慢しているのではないだろうか。ジェシカの先程の反応が、楓は未だ信じられずにいた。
「くすぐったい?」
そう聞くと、ライリーとジェシカが同時に吹き出した。
「カエデ、それは聞くことじゃないわ」
「一応答えてあげるけど、ノーよ」
「えー!」
「仕方ないわ。効かないものは効かない」
「ジェシカの身体、おかしいんじゃない?」
「どちらかというとそれはあなたの身体の方よ」
「いや、ジェシカ」
「あなたよ、カエデ」
「ライリー、どっちだと思う?」
「どっちって――」
呆れたようにライリーが言う。
「どちらもね。ジェスは強いし、カエデは弱い」
面白くない答えに楓は膨れた。
「でも強いて言うならカエデ、あなたね。あなたが弱すぎる」
「そんなこと――」
「「あるわ」」
ライリーとジェシカの声が重なる。
「そこで揃わなくてもいいじゃん」
悔しくなって楓はまたジェシカの脇腹をくすぐった。ポイントはもう押さえた。笑うジェシカを見て少し気分を取り戻す。
「やっぱりここは弱い!ここがいちばん―――というより」楓は気づいた。
「ここしか弱くないんだね」
結局のところ、ジェシカはこの場所を除けばほとんど効かないのだ。多少動いたり笑ったりしないこともないが、少しすると慣れてしまうか我慢されてしまう。そうなると楓の心は折れそうになる。
「ねぇ、無理だよライリー。ジェシカ、強い」
楓は遂にジェシカをくすぐるのをやめ、ため息をついた。
「諦めるの?」
「そうじゃない。難しすぎるってこと」
「難しい?」
「だってそうでしょう?強い人をくすぐる方が難しいに決まってるもん」
ジェシカに触れられる感覚がない訳でも楓のくすぐりが下手な訳でもないとすれば、それはもう感度の話なのだ。強ければ難しく、弱ければ簡単。それだけの話だ。だから、
「私がくすぐりに弱くて良かったね、ジェシカ」
そう言って楓は疲れた頭に手を当てた。くすぐるのは、意外と頭を使う。ふぅ、と息をついて手を下ろす―――と、急に手首を掴まれた。
え、と驚いてその主を辿ると、妖しく光るジェシカの目があった。
Next Episode…「他作自演」
仕返しの伏線回収。実は始めから主導権を握っていたジェシカ、そんなことは露知らぬ楓、その間でダブルフェイスを使い分けていたライリーの独白。
これまでのお話
登場人物紹介
前作(ぐら目線)
前作(ぐり目線)
スピンオフ
Happy Lesbian Visibility Day!
レズビアン可視化の日にクィア小説をアップできてよかったです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
