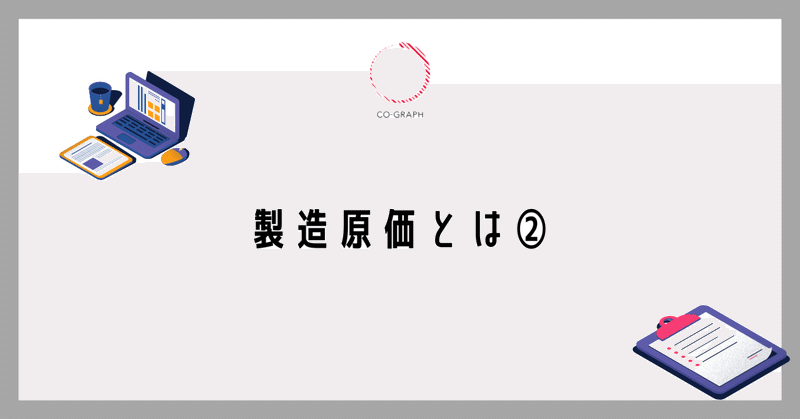
製造原価とは②
こんにちは!NSD事業部たかいです。
今回は前回の続きで「製造原価」について!
前の記事はこちらから
売上原価との違い
売上原価は販売した製品の仕入れにかかった費用もしくは製造にかかった費用のことをいいます。製造原価は生産した製品にかかる費用なので、販売たかどうかに関わらず計上されます。

製造原価の計算方法
製造原価は下記の計算式で算出できます。
当期製品製造原価=当期総製造費用+期首仕掛品棚卸高-期末仕掛品棚卸高
まずは「製造原価とは①」で説明した6種類の合計値を算出、
これが当期総製造費用となり、当期の製造にかかったすべての費用です。
ほとんどの企業は、期末時点ですべての製品が完成しているということはなく、完成途中の製品(仕掛品)が存在すると思います。完成していない製品については、製造原価に含めてはいけません。
そこで、期首時点の仕掛品=期首仕掛品棚卸高と当期総製造費用を合算し、期末の仕掛品=期末仕掛品棚卸高をそこから引くことで、当期に完成した製品のみの原価を算出することができます。
仕掛品と同様、未使用の材料費も製造原価には含めません。
なので材料費は、下記の計算式により当期に使用した分のみを算出します。
当期材料費=当期材料仕入高+期首材料棚卸高-期末材料棚卸高
NetSuiteと製造原価
多くの製品を作っている企業では、製造原価の計算の時間や手間は膨大になると思います。そのために欠かせないのが効率的に原価計算をすることができるシステムやツールの導入。
NetSuiteもその一つで、製造原価の計算だけにとどまらず、製造管理の一助となってくれます。今日は私が考えるメリットをご紹介します。
・発注処理や製造設定を行うことで、簡単に製造原価が分かる
日々の発注の記録や従業員のリソース設定をすることで、どの製品にどれだけの原価が発生しているかが自動で計上されていきます。
・人員やタスクの稼働時間を設定、タスクの進捗を可視化できる
製品製造におけるタスク管理や稼働時間の管理をすることができ、またその内容を可視化することができるため、視覚的にわかりやすい情報を得ることができます。
・どの製品になんの材料が使われるのか設定・バージョン管理も可能
製品の設定において、どの材料をどれだけ使うかを設定、またリニューアル等のバージョン管理も可能です。
まとめ
細かいことを書くと、製造原価の計算ってもっと複雑だったりNetSuiteの機能ももっとたくさんあると思いますが今回はここまで。
今後は知識を増やしてさらに詳しい記事を書いていきたいです。
ではまた次回!
