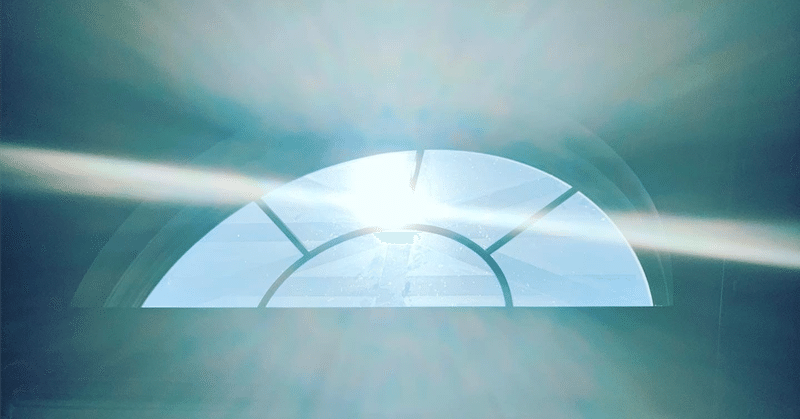
【小説 喫茶店シリーズ】 Ⅰ. 純喫茶「風車」 (vol.4)
薄明光線のような光芒の中で、響子さんは泣いているようだった。
僕はどうしていいのか、「ほんとだ、綺麗だ。朝日のあたる家だね」
そんなことを言って、それ以上言うこともなくクリームソーダに口をつけた。
味はわからなかった。でも、炭酸の刺激が救いとなった。
「ねぇ。そろそろ『罪と罰』の講義を開始しなくちゃ。お昼前には、下の常連さん達がやって来てここ占拠しちゃうから」と、響子さんは振り向いて言った。
僕の逆光で眩んだ目には、響子さんの顔はヴェネチアングラス越しに見ているようで、泣いているのか笑っているのか。
叔母さんの手芸の店の常連客たちも、響子さんのことを心配して、日曜日には毎週のようにやってきて励ましてくれるのだそうだ。それは、お母さんと叔母さん両方の同期の人たちで、もうみんな客というよりは、がやがやと親戚のおばさん達状態だそうだ。
「そのお陰で、この店もなんとかやっていけてるのだから、感謝しているの」と言う。
「でもね、わたしこの先もずっとみんなのお世話になって生きていくのだとしたら、わたし何のために生きているのか、というか、生かされてるだけなような気がして、、、。こんな話、姉にも叔母さんにもできないでしょ。姉なんか、わたしのために自分を犠牲にしてきたのよ。小学校の高学年からずっとよ。自分は行きたかった美大も諦めて、わたしを東京の短大に送り出すために結婚まで諦めて、未だに、ただの事務員としてひっそり静かに働いているわ。そんな姉に申し訳なくて。叔母さんは叔母さんで、自分の子供そっちのけでわたしの事ばかり気にかけてくれて。あぁ。わたしどうしたらいい? ねぇ」
「ごめんね、こんなどうしようもない身の上話に付き合わせて。でも、誰もいないのよ。他に、こんな話ができる人が、、、」
ヴェネチアングラスの向こうで、小さな黄色い光がキラキラと輝きながら落ちた。
「わかりました。僕でよかったら喜んで弟になります。僕は、おばあちゃん子で一人っ子なので、大人の話を聞くのは慣れてます。自分のこと話すよりも聞くこと自体が好きなんです。そうして育ったし、失敗であれ成功であれ経験を積んできた人の話を聞いていると、たまにですが、何かしら啓示があります。その人本人からではなく、その人のした行為とその結果との不合理、つまり、その人自身が意図しないばかりか反対の、とも違う、これはもう神の創造力でしか為しえないような、まったく予期しない新たな方向へと事態が動き出していくダイナミズムが感じられることがあります。どんな日常の些細な出来事であってもです。だから、おばあちゃんの独り言みたいな話を聞いてるのが大好きでした。ただジッと聞いてるだけです。その話の内容が面白いのではなくて、その事態、物事が展開していくその流れを司っている者の気配を、感じることがあるんです。上手く言えませんけど。それに比べたら、同世代の友だちなんかは、正直幼稚すぎて、本気で付き合ってるのが苦痛なぐらいでした。今もですけど。昨日見たテレビの話か、新しいラーメン屋に行こうとか、そんなことばっかりです。あ、人の悪口は、止めます。自分の価値を彼ら同等、それ以下にする行為ですから。決めたんです。一切、悪口は言わない。と」
泣いてる女性を目の前にして、一対一で話すのが初めてだったので、『何とかしなきゃ、でもどうしたらいいんだろう。この先の展開どうなるんだろう』と内心慌てふためき、それで何か保護回路が誤作動したようで、ともかく時間を先延ばしするような、変な独白をしてしまっていた。
しかし、これ以上自分で話の展開をコントロールできない状態になって、そこでちょっと黙り込んだ。
もうそろそろ、昼が近い。気がつくと、高窓からの光芒が壁際まで後退していた。
「ふふふ。ちょっとカタッ苦しいなぁ。ヒロシくんは。でも、好きよ。一生懸命、正直に自分をさらけ出してる感じがするし、自分の秘密を伝えようとしてる。きっと、そんな話するの初めてよね。それがわたしだってことがとっても嬉しいわ」
もう初めの笑顔に戻って、響子さんが言った。(八重歯さえ覗かせてる)
言われたことは、ズバリだった。
『一体どうしたんだろう? こんなこと、人に話したのは初めてだ』
自分でも話しながら、どうも文語調だな、とは思っていた。でも、口に出して言ったこと自体が初めてなんだから、それは仕方のないことだった。
神なんて、簡単には言いたくなかったし。
けれども、確かに感じていたあの「物事を思わぬ方向へと展開させる何か強大な力、何か恐ろしいほどのものは、その正体は、」と人の話の中に、見えないものを見ようとしていたのだから、それを人に平易に説明するのは至難の業だった。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
