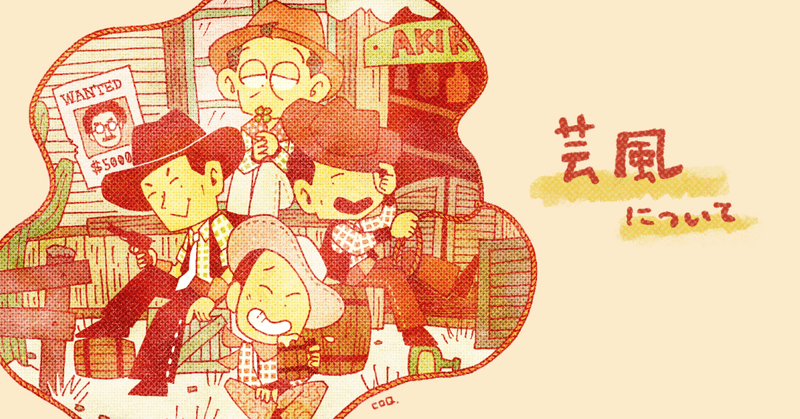
(25)芸風について①/あきれたぼういず活動記
▶︎あきれたぼういず結成まで書いたので、今回は一息つきつつ、彼らの芸風について少し考えてみたい。
※あきれたぼういずの基礎情報は(1)を!
【エンコに拾う人気者】
あきれたぼういずが開拓した新たな芸風とは、どのようなものだったのか?
彼らのレコードは聴くことができるが、当時のステージは見ることができない今、その全貌を掴むことは難しい。
しかし、ステージの様子が伝わる貴重な記事があるので、まずはこれを見てみたい。
1938(昭和13)年夏、都新聞で「エンコに拾う人気者」という連載企画が組まれた。
エンコ(=浅草公園六区)の芸人達を取り上げ紹介していくものだが、その第一回に選ばれたのがあきれたぼういずだ。
いつの公演か不明だが(8月1〜10日公演の吉本ショウ「軍事読本」か)、西部劇ものをやっている。
エンコに拾う人気者①
暑さを吹ッ飛ばす
呆れたボーイズ
ゲラ・ゲラ・ショー
「又も出ましたあきれたぼーいず、暑さ寒さも吹き飛ばし僕らのリズムはジャズリズム、浪花節から八木節まで、愉快にうたえよ、ハリキレハリキレ」などとうたいながら四人が四人ギターを弾きつつ目高みたいにマイクにロを寄せて来る
今週はカウボーイの扮装「HEIパンパン」と拳銃の音「われはケンタツキーの健児」「おお見渡すかぎり雪の原」「ナニ、ケンタッキーに雪が降るか」「イヤわしは満洲じゃ」「サテハ貴様は馬賊よな」「イヤ吉本興業の専属さ」
ここで「ケンタッキーの歌」の四重奏――目高みたいに口を寄せて川田義雄がソプラノをやるがこれがなかなかの澄んだ声で、益田喜頓のバス、芝利英のテノル、坊屋三郎がメゾソプラノというところで、哀韻嫋々たる、ちょいとしんみりした唄も見せる
忽ち、芝が向うむきになって何かやり出したと見ると、付け髭だ「おお、五千弗懸賞犯人!」と他の三人、人相書きを眺める
付け髭の男「ナニ、犯人だと」「貴様は何者だ」 「俺は悪者ではない、俺は後家殺しのグルーチョ」「さては、五干弗懸賞の犯人だ」「ナニ、五千弗、五千弗なら俺が俺を捕縛する」と矢庭にわがネクタイを両手に掴み上げ、グルーチョの倒れ方で、勇敢にバッタリ倒れる

「微風に乗って聞え来るは、そは懐しのカロリナの歌であった、淡き男女の物語るは甘き恋の囁きか――」と川田が静田錦波張りの名調子、舞台下手に急造のスクリーンがスルスルと降りて来て、其前に立った益田のジャック、坊屋のメリー、これが毒茸のようなボンネットを冠って、ライトがチラチラと照らすところ今や銀幕の名優名花が熱演の場面と来る
「おおわがいとしのジャックよ、君に捧ぐ幸福のシンボル四つ葉のクローバを」「おお愛らしのメリーよ、わしゃ四つ葉より三つ葉のおひたしが欲しい」
ギャグとスピーディの連続、舞台一杯に「新時代」をフンダンに撤き散らして、兎に角あきれたぼーいずは、特異な存在を主張している
「日本勝った勝った萬歳々々、萬歳々々、
萬々歳、勝った勝った、萬々歳」と急テンポの合唱、坊屋がおもちゃのような日の丸を振って――ワッという手が来る
途端に下手から上手ヘ一條の縄「おお、何だ、これは?」「これは国策の線」「さらば、国策の線に沿って――」と足並揃えての引込み、味なところを見せる
①ごった煮
あきれたぼういずの芸風で、一番大きな特徴はその「ごった煮」要素にある。
お笑い評論家・芸能史研究家の西条昇は『日本の喜劇人100』(白泉社)の中であきれたぼういずの芸風を「和洋折衷のごった煮パフォーマンス」と表現している。
あきれたぼういずを最も端的に表す言葉として筆者も気に入って使わせていただいている。
では具体的に、何をどう「ごった煮」にしているのか?
ひとつは、「音楽」のごった煮。
あらゆるジャンルの音楽を掛け合わせ、混ぜ合わせる。
例えばオペラ「ある晴れた日に」のメロディで民謡「佐渡おけさ」を歌ったり、浪曲が途中からジャズの流行歌になったりする。
そのミスマッチさ、パロディの面白さこそ、あきれたぼういずの面白さの「核」であるといえる。
「ボーイズ」の芸とは、二人以上が楽器を持って集まって、音楽をベースの歌と笑いである、といっていい。
で、その中身はパロディであり、諷刺であり、編曲であり、曲のメドレーである。
もっとズバリといやあ、「あきれたぼういず」そのものが「ボーイズ」である。
…(中略)…
ガラリ替って、モダン虎造節の川田節になるこの見事さ、凄さ、これがボーイズの骨頂であろう。シャンソン、タンゴ、義太夫、浪曲、童謡、ジャズ、漫画の声、タップ、民謡、端唄、小唄から歌曲と、ありとあらゆる音楽のジャンルを自分の世界に取り込み、それらを駆使して、ギャグ、諷刺。そしてそれはあくまで音が中心をなしていなければ駄目で、テーマ曲と終りと、途中の二、三曲を唄うのに楽器を伴奏としてのステージはボーイズではない。それは「楽器漫才」である。
この「音楽のごった煮」については、『ギターは日本の歌をどう変えたか』(北中正和)にも面白い考察がある。
この本ではギターに焦点をあてて日本の近代音楽史を考察しているが、「浪曲の三味線のフレーズをギターでストレートに模したレコードを作ったのは、彼ら(=あきれたぼういず)がはじめてだった」というのだ。
ギターは洋楽を弾くもの、もしくは洋楽的に弾くもの、というのがまだ常識だった時代に、ギターで三味線のフレーズを弾くことは彼らにとってはギャグのネタだったはずだ。
しかしそのアイディアは、音楽史的な面から見ても画期的なものだった。
この「ギター浪曲」をトレードマークにしていることにも、彼らの芸風がよく表れている。
(そもそも、ショウの出演者が自分達自身で楽器を演奏するというのも珍しかっただろう。)
また、「新しさ」という点では、あきれたぼういずの面々はジャズ喫茶に通って、新しいレコードで最新の音楽を勉強していたようだ。
それと同時に新内、竹本義太夫、常磐津のような日本の伝統音楽、伝統芸能も熱心に研究した。
ふたつめに、「芸」のごった煮。もっといえば、形式の変化だ。
歌(メンバー個人のソロの場合もあれば、四人のコーラスの場合もある)と漫才、さらにはコント、そして物真似など、あらゆる形式の芸をどんどん繰り出す、そのバリエーションに富んだ演出。
さらにその変化の早さ。
「(17)グラン・テッカールの浅草進出」の回で述べたように、東京吉本興業ではレヴューと色物(漫才や漫談等)を一緒に舞台に出す独自の演出にこだわった。
そして吉本ショウではさらにそれを進化させて、色物陣をレヴューショウの中に入れ込み、一つ一つの演し物の時間を短縮し、全体で一つの筋のある構成となるようにした。
この形式を踏襲し、さらに濃縮して四人で全部やってしまったのが「あきれたぼういず」だといえるだろう。
矢野 「あきれたぼういず」は寄席全部を見せちゃうというところがあるでしょう。
小沢 先取っているのは、今日の“分きざみ芸能”というか、同じものを一分やっていたらだめだという、次から次へと変化する急テンポ。いま軽薄短小というか、長いものはみんなお断りというような、そういうののはしりでしょう。
矢野 日本の古典的な起承転結とぜんぜん違うんですよね。あの辺がぼくは新しいセンスだと思う。
「エンコに拾う人気者」で紹介された西部劇のステージも、非常に目まぐるしい。
その形式の移り変わりに注目してみると、
主題歌のコーラス→漫才→コーラス→コント→活動弁士の物真似と映画コント→コーラス
のように次々と切り替わり、一つ一つのネタはごく短く、スピーディに展開している様子がわかる。
『コミックソングがJ-POPを作った』(矢野利裕)の著者は批評家であるとともにDJとしても活動しているが、あきれたぼういずのレコード「四人の突撃兵」を例に挙げ
「この連続性と切断性のバランスには本当に、DJ的なミックスのセンスを強く感じる」と述べている。
また、当時日本でも注目されつつあった前衛的表現としてのモンタージュ論とあきれたぼういずの「ごった煮パロディ」とを関連づけて考察されており、非常に興味深い。
したがって、あきれたぼういずに通常の意味でのオリジナリティは見出しにくい。 …(中略)…
あきれたぼういずはむしろ、その見事なコラージュのセンスに鮮烈さが宿っている。
(次回に続く)
【参考文献】
『ニッポンの爆笑王100』西条昇/白泉社/2003
『ギターは日本の歌をどう変えたか』北中正和/平凡社/2002
『コミックソングがJ-POPを作った:軽薄の音楽史』矢野利裕/Pヴァイン/2019
『アサヒグラフ』1995年12月1日号/朝日新聞社
『東京人』1989年12月号/都市出版
『東京人』1998年8月号/都市出版
『広告批評』1990年10月号/マドラ出版
都新聞/都新聞社
「あきれたぼういず讃」野口久光/CD「ぼういず伝説」掲載/1993(※CD発売は2005)
▶︎(7/30UP)芸風について・続き
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
