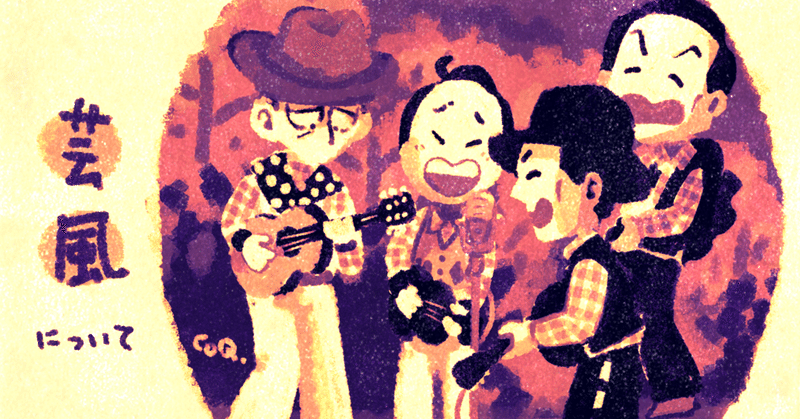
(26)芸風について②/あきれたぼういず活動記
▶︎あきれたぼういずの芸風について、前回はその特徴の1つ「ごった煮」的要素について考えてみた。今回はその続き。
※あきれたぼういずの基礎情報は(1)を!
※今回のnoteでは、前回note冒頭に引用した記事「エンコに拾う人気者」について触れていますので、ぜひ併せてお読みください。
②スタンドマイク
芸風的特徴の一つと言えるのか微妙だが、個人的に象徴的だと思うのが「マイク」だ。
榎本健一らが浅草オペラで活躍していた時代にはステージにはマイクがなく、歌も芝居も地声でやっていた。しかし、あきれたぼういずが登場した頃には、ステージにマイクが普及。
私が浅草に出た頃には、「ヴェロシティ」なんていうマイクロフォンがあって、特に私の芸はマイクロフォンの拡声を利用したネタが多かったんです。たとえば、笙篳篥(しょうひちりき)の音や、戦闘機を撃墜する音、爆弾や機関銃の音は全部マイクロフォンの拡声器を利用した。
坊屋は吉本ショウのオーディションでも、カンカン帽をマイクに向けて音を出してみせたことは (20)吉本ショウ始動の回で書いたが、マイクの効果を生かしたネタをいろいろと編み出していたようだ。
「エンコに拾う人気者」では、四人でコーラスする際に「目高みたいにマイクにロを寄せて」という表現が出てくる。
一本のマイクに四人が集まりコーラスをする、というと、ダーク・ダックスやデューク・エイセスのような男性コーラスグループが思い出される。
あきれたぼういずは、当時人気のあったアメリカのジャズコーラスグループ「ミルス・ブラザース」をかなり意識していたようだ。
あきれたぼういずがビクターで最初に吹き込んだレコード「アキレタ・ダイナ」のジャンル区分が「ジャズコーラス」になっていたことからも、「コーラス」の要素がかなり重視されていたことがわかる。
(その後は「あきれたこうらす」なるジャンル名が付けられている。)
また、演芸の分野でスタンドマイクを使うといえば、漫才がある。
横山エンタツ・花菱アチャコの漫才コンビが登場し、「しゃべくり漫才」が誕生したのが昭和5年。そこからまだ10年も経っていないこの時代、あきれたぼういずは広義の「漫才」として捉えられることもあった。
音楽評論家の瀬川昌久は彼らを「ヤンキー式ジャズ漫才チーム」と表現している。
「エンコに拾う人気者」でも、冒頭のネタ振りで漫才的な掛け合いをやっている。
ただし、「それはあくまで音が中心をなしていなければ駄目で、」「もっといやあ、ボーイズに喋りは不要である、あるとしたら、ほんの音、休止符程度のフレーズでいい。あとは全部歌と音楽であって欲しい。」(『アサヒグラフ』1995年12月1日号)と立川談志が語っているように、あくまで音楽を軸にして、その潤滑油としての漫才、という形がより「ボーイズ的」と捉えられるようだ。
あきれたぼういずでは、浅草で活動したオリジナル(第一次)時代、また分裂後の川田が再結成したミルク・ブラザースがこの「音楽中心」スタイルである。
関西に拠点を移した第二次あきれたぼういずでは、漫才的な喋りの比重が大きくなっているように感じる。
ともかく、このスタンドマイクに「目高みたいに口を寄せて」コーラスや漫才をやる姿は、「コミックバンド」と「ボーイズ」の違いを象徴するもののように思われる。
また、彼らのネタはコーラスや漫才だけではない。
ソロの歌、モノマネ、また先に紹介したような坊屋のマイク芸などもある。
こういう場合には、一人がマイクを占有し、残りのメンバーは一歩下がって伴奏や合いの手にまわる。
レコーディングの際に動き回るので注意されたという逸話もあるが、マイクとメンバーとの位置関係の変化が、ネタの移り変わりを視覚的に表している点もボーイズならではで面白い。
③時代の反映
あきれたぼういずが結成されたのは、日中戦争が始まったのと同じ1937(昭和12)年である。4年後には、太平洋戦争が開戦している。
こうした戦争や、それに伴う社会情況の変化はあきれたぼういずの芸風やその内容とも無関係ではない。
むしろ、密接に関わり合っている。
当時は舞台興行もレコードも検閲が行われ、「風俗壊乱」「安寧秩序紊乱」にあたらないかを取り締まられた。
検閲の規準も時局の変化とともに目まぐるしく変化していく。
また、不適切なものを規制するだけでなく、国は積極的に演芸娯楽に「広報」としての役割を担わせようとしていた。
1940(昭和15)年に改正された「興行取締規則」(警視庁令)の中には、
「興行場ニ於ケル演劇興行ハ努メテ国民精神ノ涵養又ハ国民智徳ノ啓培ニ資スル脚本ヲ上演スヘシ」
という文言が記されている。
あきれたぼういずのレコードや当時の資料を見る限り、それ以前からもこのような働きかけはすでにあったようだ。
「国策に沿った」内容が歓迎される風潮があったことは、彼らのレコードからも伝わってくる。
当時あきれたぼういずの出演する浅草花月劇場に通い、メンバー達とも交流があったという音楽・映画評論家の野口久光がとあるネタを紹介している。
レコードでは表現しようがないギャグにこんなのがあった。さんざん歌って暴れた出し物の結びのコーラスが終わったところに舞台の両ソデにかけて1本ヒモが4人の目の前にあらわれる。「これはなんじゃ」「これは国策の線だ」「さらば国策の線に添ってわれら行かん」といったせりふで、ヒモに従って下手に引き下がった。時局に便乗したギャグであり、たしかに皮肉もこめられていた。
「エンコに拾う人気者」のカウボーイネタのオチにも、まさにこの「国策の線」が使われている。
時局に迎合しているようで、その裏返し、諷刺や皮肉でもあるというこの駆け引きには、この時代の芸人ならではの苦心・工夫がみられる。
〈あきれたぼういず〉は、再三、歌やせりふについて当局から注意されたり、レコードの場合カットされたり、中止させられたりしながら心の中で自由や平和を願っていた国民大衆に鋭い風刺やユーモアあふれる歌とコミカルなスキットをミックスしたステージ・エンタテインメントを提供してくれていたのである。
また、『広告批評』1990年10月号で組まれたあきれたぼういず特集に、電気グルーヴの石野卓球がコメントを寄せている。
「日本語ヴォーカルの見本」と題し、あきれたぼういずの日本語の歌い方を評価した内容であるが、最後に興味深い言葉を付け加えている。
いま一つもの足りなく感じさせる点があるとすれば、「死」の匂いではないだろうか。
日中戦争が始まり、新聞紙面には連日「名誉の戦死者」が掲載されていたこの時代。「死」の匂いは、おそらく大衆に求められていなかったのだろう。
意識的にしろ、無意識的にしろ、あきれたぼういずは「死」の匂いをあえて消し去っていたのかもしれない。
というより、「死」の匂いのない笑いが大衆に支持されていったというべきか。
それが、平成の時代になって聴いた石野には「もの足りなく」感じたのだ。
「笑い」は、時代を映す鏡だ。大衆に向けられた笑いは、大衆が求めたものの反映である。
あきれたぼういずの笑いを通して、私たちは当時の人々の心持ちを知ることができるかもしれない。

【参考文献】
『ニッポンの爆笑王100』西条昇/白泉社/2003
『ギターは日本の歌をどう変えたか』北中正和/平凡社/2002
『コミックソングがJーPOPを作った:軽薄の音楽史』矢野利裕/Pヴァイン/2019
『アサヒグラフ』1995年12月1日号/朝日新聞社
『東京人』1989年12月号/都市出版
『東京人』1998年8月号/都市出版
『広告批評』1990年10月号/マドラ出版
都新聞/都新聞社
「あきれたぼういず讃」野口久光/CD「ぼういず伝説」掲載/1993)※CD発売は2005
(8/6UP)あきれたぼういず、躍進す!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
