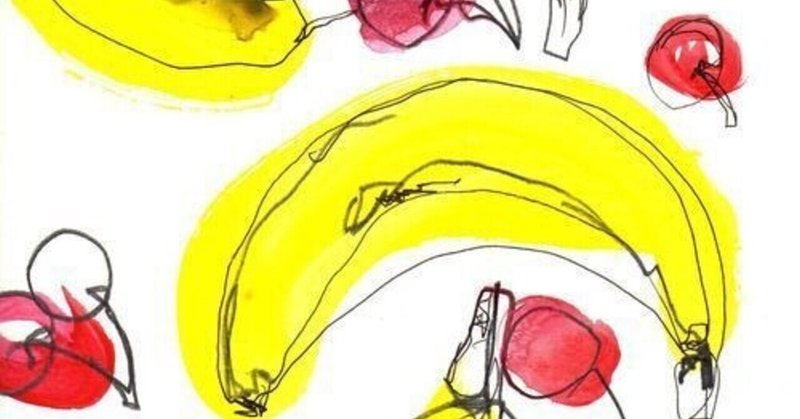
die#647 1.9
※ お疲れ様です!
今日は小説を紹介します。書き写しになります。模写ですね。では楽しんでください。
ジョン・チーヴァー
泳ぐ人
いかにも真夏の日曜日らしい、みんなが所在なく集まっては「ゆうべは飲み過ぎた」とつぶやきたくなるような日だった。教会から帰る途中の信者たちがひそひそ交わす話のなかにも、長袖の法衣に汗みずくになっている神父自身の唇からも、ゴルフコースやテニスコートからも、ひどい二日酔いに悩まされるアイオワ州オーデュボン支部のリーダーがいる野生生物保護区域からも、その言葉が聞こえてくるかのような。
「飲み過ぎたよ」とドナルド・ウェスタヘイジーが言った。
「飲み過ぎちゃってるのは、みんな一緒」ルシンダ・メリルが答えた。
「たぶんワインのせいよ」ヘレン・ウェスタヘイジーが引き取る。「あのクラレットを飲み過ぎたんだわ」
そこはウェスタヘイジー家のプールサイドだった。掘り抜き井戸から給水されるプールの水は鉄分が多く、かすかに緑がかっている。よく晴れた日だった。西の空に湧き上がる積乱雲は遠くに見える街――岸に近づく船の舳先から見る街――のようで、名前がついていても何の不思議もない。たとえばリスボン。あるいはハッケンサック。日差しが灼けつくようだ。
ネディ・メリルは緑色の水の傍らに腰を下ろし、片手は水のなか、もう片方の手はジンのグラスを握っていた。ネディはしなやかな体つきをしていた――若さ特有のしなやかさともいえた――が、実際にはもはやお世辞にも若いという年ではなかった。にもかかわらず、その日の朝も、自宅の階段の手すりをすべりおりると、玄関ホールの台に載ったブロンズのアフロディテ像の背中にパンチを食らわせ、コーヒーのいい匂いがただようダイニング・ルームに駆けこむようなことをしていたのだった。彼を夏の日にたとえてもいいだろう。ことに、日の名残りの数時間に。テニスのラケットや帆布カバンこそ持ってはいなかったけれど、ネディから受ける印象は、どう見ても青年そのものだった。
さきほどまで泳いでいたネディは、いま、荒い息を繰り返していた。肺のなかいっぱいに、この瞬間を、夏の熱気やはげしいよろこびを呑みこもうとでもするかのように。なにもかもが胸に流れこんでくるかのように。ネディの家は、バレット・パーク、ここから十キロほど南にあり、そこでは四人のかわいい娘たちが、昼食を食べたり、テニスに興じたりしていることだろう。不意に、ネディは南西の方角にジグザグの進路ではあるが、泳いで家に帰れることに気がついた。
ネディの交友範囲は広かったし、自分の発見に有頂天になってもいたので、そうしてはいけない理由など思いつかなかった。あたかも地図制作者の目で、プールをつなぐ帯が擬似水路となって、郡をカーブしながら横切っていくのを眺めているような気がする。自分は発見を、現代地理学に寄与するような発見をしたのだ。この水路を妻の名にちなんでルシンダと呼ぼう。別にわるふざけが好きなわけではなかったし、バカでもなかったけれど、人と同じことなどやりたくなかったし、自分のことをばくぜんと、ごく穏やかな感じ方ではあったけれど、どこか伝説の登場人物のように感じているところもあった。その日は美しい日で、長い距離を泳ぐことは、この日の美しさをいやますもの、ことほぐものであるようにも思えたのだった。
肩にかけていたセーターをとるとプールに飛びこんだ。ネディはプールに飛びこまない連中を自分でも理由がよくわからないままに軽蔑していた。ストロークのたびに息継ぎをしたかと思えば、四回に一回に切り換えたりする不規則なクロールで、頭の中のどこかで1、2、1、2、と数えながらばた足をする。長距離を泳ぐのに向いているストロークではなかったけれど、泳ぎをコントロールするのは、スポーツにいくつかの規則を押しつけることでしかなく、ネディによると、いわゆるクロールというのは習慣的行為になるのだった。緑色の水に身を預け、長く泳ぐことは、体の本来の状態に合わせて切り換えることにくらべ、泳ぐ喜びをそぐものでしかなかったし、できることなら水着さえもつけずに泳ぎたかったが、それはさすがに自分の計画を考えれば不可能だった。反対側の縁に着くとそこをよじのぼり――ネディは梯子を使ったことがなかった――庭の芝生を横切っていった。ルシンダが、どこへ行くつもり、と声をかけたが、それには、泳いで家に帰るんだ、と答えたのだった。
頼るべき地図も海図も記憶と想像に基づく頭の中にしかないものだったけれど、大丈夫、よくわかっている。まず、グレアム家、ハマー家、リア家、ハウランド家、クロスカップ家の順だ。それからディトマー通りを渡ってバンカー家に行き、しばらく陸路を行ってから、レヴィ家、ウェルチャー家、それからランカスターの公営プールだ。それに続くのは、ハローラン家、サックス家、ビスワンガー家、シャーリー・アダムスの家、ギルマーティン家、それからクライド家。気持ちのいい日だし、この世界は、慈悲のごとく、恵みのごとく、水は潤沢にある。胸は高鳴り、芝生を踏む足は小走りになった。生まれて初めての道をたどって家に帰る自分は、巡礼でもあり、探検家でもあり、運命を背負った人間でもある、その途上、いたるところで多くの友を見いだすのだ。友はルシンダ川に沿って列を成している。
ウェスタヘイジー家とグレアム家を隔てる生け垣を抜け、満開のリンゴの木の下を通って、ポンプやフィルターが格納されている物置を過ぎて、グレアム家のプールに着いた。
「あら、ネディ」ミセス・グレアムが言った。「驚いたわ。午前中ずっとあなたに電話してたのよ。こちらへいらして。お飲物を差し上げるわ」
そこでネディは、いかなる探検家でもそうするであろうように、目的地に到着するためには、歓待の儀礼と原住民の伝統には外交的見地から対処しなければならない、と考えた。奇妙なことをやっているとは思われたくなかったし、グレアム家の人々にたいして失礼な態度を取るつもりもなかったけれど、長居をする時間もない。プールを端から端まで泳いでから、降り注ぐ日差しのなか、グレアム家の人々に加わったけれど、まもなく天の助けのように、コネティカットから二台の車に分乗した友人たちが到着した。再会を喜びあう連中の大騒ぎのおかげで、ネディもそこからうまく抜けだせた。
グレアム家の正面にまわって、茨の生け垣をまたいで越えると、ハマー家の空っぽの駐車場を横切った。バラの手入れをしていたミセス・ハマーは顔をあげて、泳いでいるネディを見たけれど、それがだれなのかまでははっきりとわからなかった。リア家の人々は、リビングルームの開け放った窓から、ネディの立てる水音を聞いた。ハウランド家とクロスカップ家は留守だった。ハウランド家を離れてディトマー通りを渡り、バンカー家に向かう。家までまだ距離はあったけれど、パーティのざわめきが聞こえていた。
話し声や笑い声は水に反射したあと、そのまま宙に漂っているかのようだ。バンカー家のプールは小高くなっていて、階段を使ってネディがテラスに上がると、そこには二十五人から三十人の男や女が酒を飲んでいた。水の中にはラスティ・タワーズがただひとり、ゴムボートに乗ったまま浮かんでいた。ルシンダ川の岸辺は、なんと美しくも豊かな光景であることか。羽振りの良さそうな男女がサファイヤ色の水のまわりに集い、白いお仕着せに身を包んだ仕出し屋がよく冷えたジンを配っている。頭上では赤いデ・ハヴィランド社製の練習機が空をぐるぐる回っており、その音はブランコに乗った子供があげる歓声のようにも聞こえた。つかのま、この光景に対するいとおしさがこみあげてきて、集まっている人々に寄せる温かい思いが胸を満たした。まるで手で触れることさえできるかのようにはっきりと。
ネディを見つけたイーニッド・バンカーは、すぐに大きな声で迎えた。
「だれかと思ったら! ああ、驚いた。ルシンダがあなたが来られないって言ったときは、死んじゃいたくなったけど」
イーニッドは人混みをかきわけながらそばに来てキスすると、バーの方へ引っぱっていった。八人から十人の女性とキスしたり、多くの男と握手したりするために立ち止まるので、その歩みは遅々としたものだ。これまでに百回ほどパーティで会ったことのあるバーテンダーが、にこやかにジン・アンド・トニックを渡してくれ、自分の出発を遅らせるような話につかまらなければいいが、と思いながら、ネディはしばらくバーに留まった。
まわりに人が集まってきそうな気配だったので、ネディはプールに飛びこむと、ラスティのゴムボートに当たらないよう、端の方を泳いだ。プールの向こう側まで泳ぐと、にこやかに笑いかけるトムリンスン家の人々の前をジョギングしながらさっさと通り過ぎて、庭の小道に向かっていった。砂利を踏んで足の裏を切ったが、そのほかには不愉快なことはなにひとつなかった。
パーティのざわめきはプールのまわりだけで、母屋に向かうネディの耳には、明るい、せせらぎのような人の声も遠ざかり、こんどはバンカー家の台所から、ラジオの音が聞こえてきた。そこでだれかが野球中継を聞いているらしかった。
日曜日の午後である。ネディは駐めてある車の間を縫い、アールワイヴス通りと車寄せを隔てる茂みに沿って歩いた。水着姿で往来にいるところを見られたくはなかったけれど、車も通らず、レヴィ家の私道まですぐだった。「私有地」と看板が出ており、ニューヨークタイムス専用の緑色の新聞受けがある。
大きな屋敷のドアも窓もすべて開け放ってあったが、人の気配が感じられない。犬の鳴き声さえきこえない。プール目指して家の横手に回っていくと、レヴィ家の人々は、ついいましがたまでここにいたことがわかった。コップやボトル、ナッツが載った皿が、奥まった場所のテーブルの上に置いたままになっている。そこには更衣室や見晴らし小屋もあり、日本の提灯が下がっていた。プールで泳いだあと、ネディはグラスを取りあげて、酒を注いだ。飲んだのも、四杯目か五杯目になっていたが、ネディはすでにルシンダ川のほぼ半分を制覇していた。疲労はあったけれど、自分が清められ、この瞬間、ひとりきりでいることがうれしかった。なにもかもが愉快だった。
荒れ模様になりそうだった。積乱雲の固まり――雲の街――が発達しながら黒ずんできて、そこにすわっていると、雷鳴が遠い太鼓のようにまた響いてきた。デ・ハヴィランド訓練機は頭上でまだ旋回を続けており、ネディは昼下がり、喜びに震えるパイロットの笑い声を聞いたようにさえ思った。だが、もういちど雷鳴が轟いたので、家路を急ぐことにした。
列車の汽笛が聞こえて、いま何時ぐらいだろうと思った。四時? 五時? 地元の駅のこの時間帯の様子を思い浮かべる。上に羽織ったレインコートでタキシードを隠して列車を待つウェイター、新聞紙でくるんだ花束を抱えるちんちくりんの男、ずっと泣いていた女も各駅停車を待っているだろう。
にわかにあたりは暗くなった。そのとき、愚かな小鳥たちがやってくる嵐を鋭く察知して、雨の歌を歌い始めた。つぎの瞬間、鋭い、水の噴き出す音が、蛇口をひねりでもしたかのように、背後のオークの木のてっぺんから聞こえてきた。やがて噴水がざあざあ降り注ぐような音は高い木々のこずえ全体から聞こえるようになった。
なんで自分は嵐がこんなにも好きなんだろう。ドアがばたんと開いて、雨風が階段の上まで叩きつけるのを見ると、どうしてわくわくしてしまうのだろう。どうして単純な仕事、たとえば古い家の窓を閉めるようなことが、そうしなければならない重大な任務のように思えてくるのだろう。どうして暴風が吹きつけたときに最初に聞こえる雨音が、まごうかたなき良いニュース、よろこばしく胸躍る吉報のように思えるのだろうか。爆発音が轟き、火薬のような臭いがたちこめたかと思うと、雨が日本提灯に叩きつけた。レヴィ夫人が一昨年かそこらに京都で買ったものだ、もっと前だったか。
嵐が治まるまで、レヴィ家のあずまやで雨宿りすることにした。雨のせいで空気はひんやりとしてきた。赤や黄色に染まったカエデの葉が風に吹き飛ばされ、芝生やプールに散っていく。いまは真夏だから、おそらく木が枯れているのだろうが、ネディは秋の兆しを感じて、ものがなしい気分に浸った。肩に力をこめて、グラスを干すと、ウェルチャー家のプールに向かって歩き出した。そのためにはリンドレー家の乗馬コースを横切らなければならなかったのだが、おどろいたことに草がぼうぼうと繁り、跳躍台がすべて壊れてしまっている。リンドレー家の人々は、馬を売るか、避暑に出かけるあいだ、馬をどこかに預けたかしたのだろうか。一家や馬のことで何か聞いたような気もしたが、はっきりしなかった。湿った草を裸足で踏みながら、ウェルチャー家の方に歩いていったが、そこのプールは水がすっかり落としてあった。
自分の川が断ちきられたのを目の当たりにして、ネディは道理に合わないほどに落胆し、なんだか自分が奔流を求めて川をさかのぼっていたら、そこが干上がっていたのを発見した探検家になったように感じた。がっかりもしていたけれど、狐につままれたような気もする。夏のあいだ、どこかへいくということはよくある話だが、プールを干上がらせるようなことは、ふつうならしない。どう考えてもウェルチャー家は越していったのだ。
プールの備品は折り畳んで積み重ねられて、上から防水シートがかかっていた。更衣室は施錠されている。家の窓はすべて閉め切ってあり、私道から正面にまわると、木に『売り家』という札が打ちつけてあった。ウェルチャー家の話を最後に聞いたのはいつだったか、つまり、自分とルシンダが、ウェルチャー家に食事を招待されて、行くのがいやだと最後に思ったのは、いつのことだったか。一週間か、そんなものだろう。
記憶力が減退したのか、それとも不愉快な事実は抑圧するように自分を訓練した結果、事実を知覚する能力の方が歪んでしまったのだろうか。そのとき、遠くの方からテニスの試合をしている音が聞こえてきた。そのおかげで気分が明るくなったネディは、不安な気持ちを払いのけ、曇のたれこめた空も冷たい空気も何でもないのだ、と思おうとした。今日はネディ・メリルが郡を泳いで横断する日なのだ。いい日じゃないか! そうしてネディにとってはもっとも厄介な、陸路の行程に着手していった。
その日、日曜日の昼下がりのドライブに出かけた人なら、ネディを見かけたかもしれない。裸に近い格好で、424号線の路肩に立って、横断するチャンスをうかがっていた姿を。犯罪に巻きこまれたのだろうか、と考えた人がいても不思議はない。車が故障したのだろうか、それとも単に頭がおかしいのか。ハイウェイ脇のゴミの中――ビールの空き缶や、ぼろきれ、タイヤの切れ端――に裸足で立って、冷やかしや嘲笑を浴びるそのさまは、哀れなものだった。
最初から、行程にこの箇所があることは頭にあった――ネディの地図にも載っていた――のだが、行き交う車の列を前に、夏の日差しの中を這うように進んでいくための心の準備まではできていなかったことが思い知らされた。笑われ、囃したてられ、ビール缶を投げつけられたが、この情況では威厳を持つこともできなければ、おもしろがることもできなかった。
引き返すこともできるのだ。ウェスタヘイジー家に戻れば、ルシンダは未だに日差しを浴びてすわっていることだろう。署名したわけでもないし、宣誓したわけでも、約束を交わしたわけでもない、自分自身に対してさえ。いかに人間が頑固であったとしても常識には道を譲る、と信じているネディが、どうして引き返すことすらできなくなってしまっていただろう。もしかしたら自分の命を危険にさらす羽目になるかもしれないのに、なぜ自分の行程を完了させずにはおれないんだ? ほんのいたずら、ほんの冗談、ちょっとした気まぐれが、いったいどこで、ここまでのっぴきならない話になってしまったんだ?
引き返すことはできない。はっきりと思い出すことすらできない。ウェスタヘイジー家の緑色の水も、自分が深く胸に吸いこんだその日のさまざまなものも、飲み過ぎた、と言う穏やかでくつろいだ声も。たかだか一時間ほどの時間が、引き返すことも不可能なほどの距離をあけてしまっていた。
ハイウェイを時速25㎞ほどで走っている老人が渡らせてくれたので、ネディは道の真ん中、草の生い茂る中央分離帯のところまで行くことができた。こんどはそこで北行きの車が浴びせる嘲笑にさらされることになり、十分か十五分してからやっと渡ることができた。そこまでくるとランカスター地区のレクリエーションセンターまではほんの少し歩けばいいだけで、そこにハンドボールのコートと公営プールがあるのだ。
水が及ぼす音響効果、鮮やかさを増した声が空中にとどまっているかのような錯覚は、公営プールもバンカー家のプールと同じだったけれど、こちらの方がずっと騒々しく、がさつな声やキンキン声もたくさん混ざっていた。混み合う囲いのなかに入ったネディは、たちまち厳しい管理に直面することになった。
・泳者はプールに入る前にシャワーを浴びること
・泳者は足洗い槽に入ること
・泳者は認識票をつけること
ネディはシャワーを浴び、濁って冷たい液体に足を漬け、プールサイドまで歩いた。塩素の臭いが鼻をつき、プールは台所の流しのように見える。
救助員がふたり、左右に分かれた監視台から、ほぼ一定の間合いを置いて警笛を吹いては場内放送を使って、泳いでいる人々をあしざまに罵っていた。バンカー家のサファイア色のプールを懐かしく思い出しながら、自分が汚染されるかもしれない、自分の羽振りの良さや、魅力といったものが、この淀みで泳ぐことによって損なわれてしまうかもしれない、と思ったのである。だが、自分は探検家だ、同時に巡礼でもあるのだ、と思いだし、これは単にルシンダ川の淀みにすぎないのだ、と考えた。
嫌悪感を押して、塩素のなかに飛びこむと、人にぶつからないように頭を水の上に出して泳がなければならなかったが、それでも人には突き当たる、水をはねかけられる、押されもする。浅くなった端までたどりついたところで、救助員がふたりそろってがなりたててきた。
「おい、こら、認識票をつけてないじゃないか、すぐプールから出るんだ」
ネディはプールから出たが、救助員が追いかけてくるはずもなかったので、日焼けオイルや塩素の悪臭のなかを抜け、風除けフェンスから外へ出て、ハンドボールコートを突っ切った。道路を渡って、木の茂るハローラン家の敷地に入る。木々は手入れがされておらず、足下が不安定で歩きにくかったが、やっと芝生とプールを囲んでいる刈り込んだ生け垣のところにたどりついた。
ハローラン夫妻は友人だった。巨万の富を抱えた初老の夫婦で、共産党員ではないかという疑いにおおいに気を良くしているらしかった。ふたりは熱心な改革派ではあったけれど、共産党員ではなかった。にもかかわらず、告発を受ければ、ときには破壊活動の嫌疑だったこともあったのだが、ふたりは満足し、おもしろがっていたのだった。プールのまわりの生け垣が黄色くなっていて、ネディは、ここのもレヴィ家のカエデのように枯れている、と思った。ハローラン夫妻に、こんにちは、こんにちは、と声をかけて、自分の来たことを前もって知らせ、ふたりの生活に侵入する罪を、いささかなりとも軽いものにしようとした。夫妻は、ネディはその理由を聞いたことはなかったけれど、水着をつけないのだ。確かに、説明がなくても何ら問題はない。水着を着ないことも、ふたりの改革に寄せる妥協を許さぬ情熱の一部なのである。ネディも礼儀正しく水着を取ってから、生け垣の戸をくぐった。
白髪で穏やかな表情を浮かべ、でっぷりと太ったハローラン夫人は、タイムズを読んでいた。ハローラン氏の方はひしゃくで水に散ったブナの葉を掬っている。ネディの姿を見ても、驚いたようすも気分を害したようすもない。おそらくここのプールはアメリカ国内でももっとも古い部類に属する、天然石で作られた長方形のもので、小川から吸水されていた。フィルターもポンプも通していない水は、くすんだ金色をしている。
「郡を泳いで横断しようと思ってるんです」ネディが言った。
「おやまあ、そんなことができるなんて」ハローラン夫人は驚いて大きな声を出した。
「ええ、ウェスタヘイジー家から始めたんです。6㎞ほど来ました」
ネディは水着を深い方に置いてから、浅い方に歩いて行って、そこに向かってまっすぐに泳ぎ始めた。プールから上がろうとしていると、ハローラン夫人の声が聞こえた。
「ネディ、いろいろうまくいかなかかったのは残念だったわね」
「うまくいかなかったって? どういうことか、よくわからないのですが」
「あら、あなたが家を売って、それで、お気の毒なお嬢さんたちが……」
「家を売った記憶はありませんよ。娘たちも家におりますし」
「そう」ハローラン夫人はため息をついた。「そういうことなのね……」夫人の声にはこの季節にはふさわしくない憂鬱なニュアンスがこもっていたが、ネディは快活に言った。
「プールを使わせてくださってどうもありがとう」
「ええ、そうね。行程を楽しんでらして」そうハローラン夫人は言った。
生け垣を越えたところで、ネディは水着を身につけ、紐を結んだ。水着が緩くなっているので、まさかこの午後のあいだに痩せたわけでもあるまいに、と不思議に思った。寒くなってきたし、疲れてもいた。おまけに裸のハローラン夫妻や濁った水のことを思うと、気持ちが塞ぐ。泳ぐのが体力的にきつくなってきていたが、朝、手すりをすべり降り、ウェスタヘイジー家で陽を浴びた人間に、どうしてそんなことが予測できるだろう。腕は水をうまく掻けなくなっていた。脚はゴムにでもなったようで、関節が痛む。最悪なのは、骨の髄まで冷えきって、もう二度と暖かくならないような気さえすることだった。木々の葉が落ち、たきぎの煙のにおいが風に乗って運ばれてくる。この季節にだれが焚き火などしているのだろう?
一杯やりたかった。ウィスキーを飲めば暖まる、気持ちを盛り上げ、残りの行程をやり遂げさせてもくれるだろうし、郡を泳いで横断することは独創的で勇敢な行為なのだという気持ちをよみがえらせてもくれる。海峡横断泳者はブランディを携えているのだ。気つけ薬が必要だった。ハローラン家の屋敷の前の庭を横切り、小道を進んでいった。そこには夫妻が一人娘のヘレンのために建てさせた家があり、ヘレンはそこに夫であるエリック・サックスと暮らしていた。サックス家のプールは小さく、ヘレンとヘレンの夫はそこにいた。
「あら、ネディ」ヘレンが言った。「母のところにお食事にいらしたの?」
「正確にはそうじゃないんだ。確かにご両親のところにはうかがったんだけどね」
説明はこれで十分のようだった。「おじゃまして申し訳ないのだけれど、冷えるんで、一杯いただけないかと思って」
「もちろんそうしたいところなんだけど、この家にはそんなものは何もないのよ、エリックが手術を受けてからというもの。もう三年になるかしら」
自分は記憶喪失にでもなったのだろうか。見たくないことを見まいとする自分の資質のせいで、自分は家を売ったり、娘たちがトラブルに巻き込まれたり、友人が病気だったり、といった出来事を忘れてしまったのだろうか。ネディの目はエリックの顔から腹部へとすべりおち、そこに血の気のない色合いの縫合の傷跡が三つあるのを見た。そのうちふたつは少なくとも三十センチはある。臍を取り除いてしまった、とネディは考えた、外科医の機敏な手は、臍をどう作るのだろうか。夜中の三時の就寝点呼のときの人型のように、臍のないところから新たな臍を作るのだろうか、出生とは関係のない、受け継いできたものに反する臍を。
「ビスワンガーさんのお宅に行ったら、きっとお酒が飲めると思うわ」とヘレンが言った。「あのひとたち、そりゃたくさん持ってるから。ここからだって聞こえるでしょ、ほら!」
ヘレンが顔を挙げると、道を越え、芝生を越え、庭を越え、木立を越え、敷地を越えて、ふたたび、あの水の上に漂うきらめくようなざわめきが聞こえてくる。
「さて、ひと泳ぎするとしよう」そう言いながら、相変わらず、どうやって帰るかに関しては、自分には選択の自由などないのだ、と感じていた。サックス家の冷たい水に飛びこんで、あえぎ、溺れそうになりながら、自分の進路に従ってプールの端から端まで泳ぐ。
「ルシンダもぼくも、ふたりにはずっと会いたかったんだ」ネディは顔をビスワンガー家の方に向けたまま、肩越しにそう言った。「長いこと連絡しなくてすまなかった。すぐにまた電話するから」
ビスワンガー家に向かって空き地を横切っていくうちに、バカ騒ぎが聞こえてきた。あそこならネディに飲み物を出すことを名誉に思うだろうし、喜ぶに決まっている。ビスワンガー家では、ネディとルシンダを年に四回、六週間も前から招待してくれるのだ。いつもはねつけられているにもかかわらず、招待状を出し続ける彼らは、社会の厳然たる非民主的現実を決して理解しようとしない。カクテル・パーティで物の値段を取りざたし、ディナーの席で市場の動向の情報交換を行い、ディナーが終われば、女性を交えた席で猥談を始めてしまうような連中なのだった。彼らはネディの仲間ではなかった――ルシンダの出すクリスマスカードのリストにさえ入っていなかった。
ビスワンガー家のプール目指して歩くネディの胸中は、投げやりな気分と、恩着せがましい気分、それに、一年で一番日が長いころではあっても、あたりは徐々に暮れてきたために、少々不安な気分までもが入り交じっていた。そこに着いたときは、パーティは騒がしく大勢の人が集まっていた。グレイス・ビスワンガーは言ってみれば検眼師と獣医と不動産屋と歯科医を誘うような女主人なのである。だれも泳いではおらず、プールの水に反射する夕日は、冬の日の輝きのようにも見えた。バーがあり、ネディはそちらへ歩いていった。グレイス・ビスワンガーが気がついてやってきたが、その顔にはネディが当然の権利のように思い描いていた愛想の良さなど微塵もなく、敵意が浮かんでいる。
「ま、このパーティにはなんでもあるんだけど」と大きな声を出す。「招かれざる客までね」
こんな女に自分が社交的な一撃を食らうことなどありえない――疑いの余地もないことだし、事実、ネディはひるまなかった。「招かれざる客の一人として」と礼儀正しく言った。「わたしは一杯の酒ぐらいの値打ちはあるのでしょうかな」
「勝手にすれば。あなたたちには招待状なんてどうだっていいみたいだから」
グレイスは背を向けて客の中に入っていき、ネディはバーに行ってウィスキーを一杯頼んだ。バーテンダーは出してくれたのだが、その手つきはひどく乱暴だった。ネディの世界では、仕出し業者であっても社会的な評価を受ける世界だったから、たとえ臨時のバーテンダーが原因でも、断られるというだけでそこの評価はマイナスになる。もしかしたら、単にその男が新米で、無知なだけなのかもしれないが。そのときグレイスが背後でしゃべっている声が聞こえた。「あの人たち、たった一晩で破産しちゃったのよ――所得の他は何もかもなくしちゃったの――だから、日曜日に一杯飲みに来て、ウチに五千ドル貸してくれ、なんて言うわけ……」グレイスはいつも金の話だ。エンドウ豆をナイフで突き刺して食べるよりひどいじゃないか。ネディはプールに飛びこむと、端から端まで泳いでそこを後にした。
彼のリストによると、つぎのプールは、最後から三番目、ネディの古くからの愛人であるシャーリー・アダムズの家にあった。たとえビスワンガー家で傷を負ったとしても、ここでなら癒されるはずだ。愛――実際には性的な乱痴気騒ぎというようなものだったが――は究極の万能薬であり、鎮痛剤であり、足の運びに弾みを取り戻す色鮮やかな錠剤であり、心に宿る生きる喜びだった。ふたりは先週も、先月も、昨年も情事を持った。よくは覚えてなかったけれど、優位な立場にあったネディの側がその関係を終わりにしたのだ。プールを囲む壁にしつらえた入り口から中へと足を踏み入れながら、ネディの頭は、ほとんどうぬぼれだけが占めていた。ある意味で、自分のプールと言ってもいい。恋人、ことに不倫相手の所有物を、神聖な婚姻関係では知り得ない支配力を駆使して楽しむのだ。
シャーリーはそこにいた。真鍮色の髪はそのままだったけれど、彼女の姿、あかりのついたプールサイド、セルリアンブルーの水の傍らのシャーリーを見ても、思い出が体の奥深くから湧いてくるようなこともなかった。ずっと、とネディは考えた、お手軽な情事だったのだ、終わりにしたとき彼女は泣いていたけれど。シャーリーが自分を見て当惑したような顔をしていたので、ネディは、まだ傷ついているのだろうか、と考えた。また――勘弁してくれよ――泣くんだろうか?
「何がお望み?」
「郡を泳いで渡ってるんだ」
「ああ、もう、いい加減に大人になったら?」
「どうかしたのか」
「お金だったらもう一セントだってあげるつもりはないわよ」
「一杯飲ませてくれないか」
「そんなことをするつもりはないの。わたし、一人じゃないから」
「さて、泳ぐとしよう」
ネディはプールに飛びこんで泳ぎ、端に着いてから身体を引き上げようとして、腕にも肩にも力が残っていないことに気がつき、はしごまで水を掻きながら歩いてからそこを昇った。肩越しに振り返ると、灯りのついた脱衣所には若い男の姿があった。暗い芝生には、菊かマリゴールドの匂い――いずれにせよ、確かに秋の香――が夜気に混ざってただよい、ガスのようにはっきりと嗅ぎ分けることができた。見上げると星が出ていた。なぜアンドロメダやケフェウス、カシオペアが見えているのだろう? 真夏の星座はどうしたのだ? ネディは泣き始めていた。
おそらく大人になってから泣いたのは初めてだった。こんなにも惨めで寒く、疲れ果て、途方に暮れたことはない。仕出し屋のバーテンダーも、かつてはネディの膝に取りすがってズボンを涙で濡らした愛人も、どうしてあんなに無礼な態度を取ったのか理解できない。あまりに長い距離を泳ぎ、長い時間水に浸かっていたので、鼻も喉も水のために痛くなっていた。いま自分に必要なのは、一杯の酒と、友だちと、清潔で乾いた服だ。道路を渡ってまっすぐに自分の家に帰ることもできたのだが、ネディはギルマーティン家のプールに向かった。
ここでは、生まれて初めて、飛びこまずに階段を使って氷のような水に入り、子供のころに習ったような気がする横泳ぎでひょこひょこ泳いでいった。クライド家に向かう途中、疲労のあまりふらふらになったネディは、プールの長さを歩いて進み、何度も立ち止まっては、腕を縁に置いて休みながら進んだ。はしごをのぼるときには、家まで戻るだけの体力が残っているのだろうかと思った。ネディは自分がやりたかったことをやった、つまり、郡を泳いで横断したのだ。だが疲労困憊のあまり頭がぼうっとして、満足感すら定かには感じられない。身をかがめて門柱につかまって体を支え、自分の家の車寄せを見上げた。
家は暗かった。みんなベッドに入るほど遅い時間なのか。ルシンダはウェスタヘイジー家で晩ご飯の時間まで一緒にいることにしたのだろうか。娘たちも母親とそこにいるのだろうか、それともどこかへ行ったのか。いつも日曜日はそうしているように、どんな招待も断って、家で過ごそうとみんなで決めていたのではなかったか。ガレージのドアを開けて、なくなったのはどの車か確かめようとしても、扉には鍵がかかっていて、ドアの取っ手の錆が手についた。家に近づいていくと、先ほどの雷雨のせいで、雨樋が外れているのが見える。雨樋は、ちょうど傘の骨のように玄関のドアに垂れ下がっているが、ともかく明日の朝に直せばいい。家には鍵がかかっていたので、馬鹿なコックかメイドが鍵をかけたにちがいない、と思った。だがそこでメイドもコックも雇うのをやめて、ずいぶんたつのを思い出した。ネディは怒鳴った。ドアを叩き、肩をぶつけてなんとか破ろうとし、それから窓をのぞいてみると、家の中は空っぽだった。
The End
では失礼する!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
