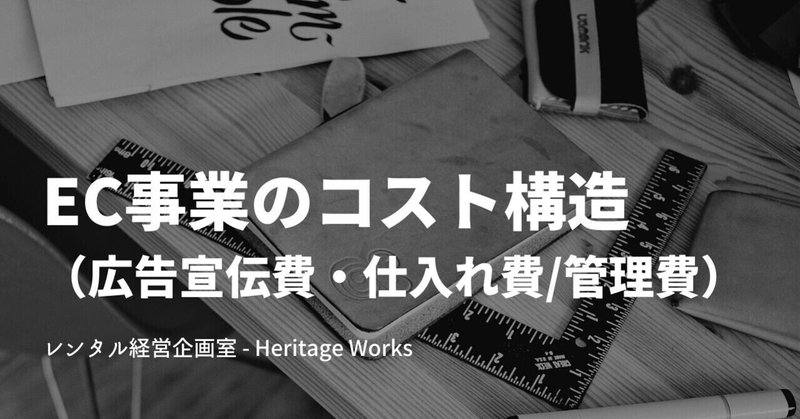
EC事業のコスト構造(広告宣伝費・仕入れ費/管理費)
■本記事の目的
ECサイトで何にコストがかかるかというと、大きく3つのものにコストがかかります。
① 人件費(バックオフィス費)
② 広告宣伝費
③ 仕入れ費/管理費
という話や人件費(バックオフィス費)については前回noteに記載してきました。今回は、広告宣伝費と仕入れ費/管理費について説明していきましょう。
■広告宣伝費の基準
諸説ありますし、皆様が販売されている商品によって異なりますが、
広告費=売り上げ×30%
が基準と言われています。
まず今どの程度の広告費をかけているか理解しましょう。
■広告宣伝費の使い方
これが一番大事です。まずは、何のために広告を打つかです。大きく3つの箇所に広告を打つのがいいと言われています。
① 集客数UPのため(Webページへの集客)
② 購入UPのため
③ 再購入のため
①と②は同じように見えますが、実は全然違います。それを理解することが大事です。例えば、皆様の商品がWebページにさえ来てもらえれば買われる商品なら、①にコストをかけるのがいいでしょう。
Webに来たあとでもあと一押ししないと購入されにくい商品なら、②にコストをかけるのがいいでしょう。
※広告宣伝費について勉強したことのある人なら、広告宣伝費と販売促進費両方について話しているのをお気づきかもしれません。
今回のnoteで記載している広告宣伝費*1と販売促進費*2を広告宣伝費とひとまとめで記載していきます。
*1広告宣伝費:不特定数の方に向けて宣伝効果を意図して支出する経費。例えばリスティング広告やディスプレイ広告など。
*2販売促進費:消費者に対して直接的なアプローチをする経費。例えばクーポンなど。
■どのように何にお金を使うのがいいのか
本記事の目的にある①~③の目的の中で何にお金を使えばいいのかですが、それを知るために、”EC事業の売上構造の整理”で説明したモニタリングをすることが重要です。
そのモニタリングの結果を受けて、どこの指標を上げることが重要かを見つけて、その箇所にお金をかければいいです。
ただここで注意しておくべきことは、まずは予算にキャップをつけておくことと、そのコストがスポットでかかるものか、ずっとかかるものかを分けて管理することです。
例えば、1000万円/月の売上をあげる商品で、②の購入UPに課題のある商品の場合、
月当たり、1000万円×30%、つまり300万円までは広告に使えます。
では①〜③の目的ごとに、①には100万円、②には150万円、③には50万円というように予算を分散します。
その中でできる施策を検討すればいいと思います。
少し発展系ですが、1000万円/月の売上をあげる商品で、②の購入UPに課題のありそうな商品の場合、月当たり、1000万円×30%、つまり300万円までは広告に使えることまでは一緒なのですが、
課題を見つけて、施策を検討してもらうのに、外部のコンサルタントに1ヶ月入ってもらうのもいいかもしれません。例えば、月200万円払ってコンサルタントに入ってもらいます。
すると、①〜③の目的のためには100万円しか使えないのかとなります。ただ、そうではありません。ここが、「スポットでかかるものか、ずっとかかるものかを分けて管理する」ということです。コンサルフィーは1ヶ月で終わりますので、300万円のルールに入れずにコスト計上しましょう。
そのコンサルフィーが妥当かの判断方法ですが、外資コンサルタントに頼むといくら、ITコンサルタントに頼むといくらのような相場はもちろんありますが、その人が入って見込める売上向上額が何ヶ月でコンサルフィーを超えるかの期待値で判断しましょう。
例えば、毎月その人に任せれば、20万円は売上が上がりそうと期待できるとします。その人に200万円払うので、10か月で回収できます。
これはあくまでも感覚で、決めるものですが、私ならこの程度の期待値のコンサルタントには仕事を頼みません。
月に40万円程度の売上向上期待ができるのなら、頼むでしょう。あくまでもこれは自分の感覚ですが、半年くらいで回収できるのなら頼んでもいいと思っています。これは皆様の会社の資産状況などにもよるので一概には言えませんが、判断の考え方のみ参考にしてもらえれば幸いです。
■仕入れ費/管理費について
これはどのように考えていくのかについてですが、まず使っている金額ごとの項目を洗い出し(確定申告などで洗い出しているはず)、どの項目が下げれる可能性があるかを考えることです。
諸事情も色々あり、難しいコストもあるかもですが、思い切って項目ごとに施策を打っていくのが重要です。これは一般的なことが言えないので、具体例を出しながら、観点のみお伝えします。
■仕入れ費/管理費の下げ方について
(A) 昔からの関係でなんとなく仕入れ先が決まっている
(B) 在庫の作成分量はなんとなくの経験で決めている
皆様の商品で上記 (A)か(B)にあたるものありませんか?今まで色々な経営者の方と話していく中で上記のようなことがよくありました。
(A) はなかなか判断しきれないことだというのは重々承知の上ですが、自社商品の売上、特に利益をあげるために必要なら判断が必要かと思います。
また、昔からの関係の会社しか、その商品を作れない or その工業機器を作れない可能性があるので、付き合いをやめるのが怖いなど色々な壁があるでしょう。
ただ、今は面白いサービスもあり、キャディ株式会社が行っている「特注加工品の発注者と全国の加工工場をテクノロジーでつなげるプラットフォーム」はまさにここを解消するサービスでしょう。
本当に自分たちがほしい工業機器を適正価格で手に入れることができるというものです。
このようなサービスを使い、(A)にメスを入れるのもいいかもしれません。
(B) についても、夏はよく売れるので多めに作るや冬は売れないので少なめに作るなどのなんとなくの経験で商品の在庫量を決めることはやめたほうがいいです。
もう少し本当の理由を探ることが重要です。
例えば、アイスクリームをあなたが売っているとします。それは夏だから売れるのではなく、正しくは気温が高いからよく売れるのです。
こういう分析をした上で、どういうときに売れるのかの数式をつくることをモデル作りというのですが、数学を使い、難しくやり、精度をあげて行うこともできるのですが、先のアイスクリームの例のように簡単に仮説を立てることはできます。
この程度の精度でいいのでまず何が売上にきいているのかを理解しましょう。その上で在庫量を作成すれば無駄もなくなります。
小難しく、在庫のモデルの話をしましたが、一番いいのは、発注後に発送商品を作成するビジネスモデルに変えれないかを検討することです。
団子屋をやっており、Webで予約がきて、3日後に納品すればいいのであれば、発注後作成してお客様に渡せば、在庫を抱えることがなくなります。
そのためには、すぐに材料を配送してくれる材料屋さんや、急な業務量の増加に対応できる従業員の構成を作ったりする必要はありますが、これができれば一番最高ですね。
■結論
・広告宣伝費については、どこが自分のECサイトの課題かを把握して、その課題に対して、お金を使いましょう。
・仕入れ費/管理費については今まで見ないふりをしていた箇所や、慣習化して気づかなかった箇所に対して、本当に必要?本当にあっている?と疑うことからはじめましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
