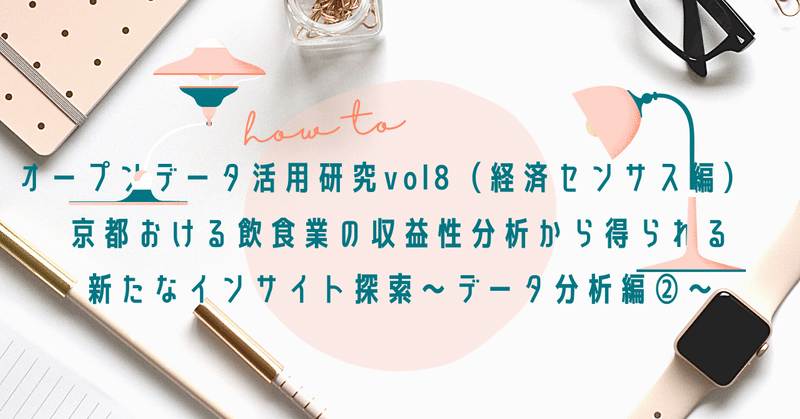
オープンデータ活用研究vol8(経済センサス編) 京都おける飲食業の収益性分析から得られる新たなインサイト探索~データ分析編②~
お疲れ様です。ムロイです。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
いよいよGWも終盤戦です。今年は国内外の旅行需要が前年比ですごい伸びを見せたようで、連日ニュースになっていましたがどこに行っても観光客でいっぱいだったようですね。こうやって徐々に日常に戻っていける喜びを噛みしめながら、日々確実に前進していければと思っています。
さて、前回は分析編第1回ということで京都市における、飲食業と宿泊業の収益性分析を行ってきました。結果コロナ前の古いデータではありましたが、経済センサスから取得したデータから見ていきました。飲食業や宿泊業の収益性観点では高いポテンシャルを確認することができました。
今回からは前回結果が京都市だけの傾向なのかどうか、ほかの都市と比較していきたいと思っています。地理的条件で比較的近隣、都市サイズが同規模対象になり得そうな、"大阪市"、"神戸市"の2都市と比較してみます。
1.大阪市の収益性分析
京都市同様の指標の取得、それと追加指標の計算結果をまとめると以下のようになります。京都市の各指標については前回記事を参考にしてください。
【大阪市の収益性指標】
売上(収入)金額【百万円】:1,447,518
費用 売上原価【百万円】:449,542
費用 販売費及び一般管理費【百万円】:714,812
売上高総利益【百万円】:997,976
売上高総利益率:68.9%
営業利益【百万円】:283,164
営業利益率:19.5%
事業所数:26,420
従業者数【人】:234,117
1事業所あたりの売上高【百万円】:54.7
1事業所あたりの営業利益【百万円】:10.7
1人あたりの売上高【百万円】:6.1
1人あたりの営業利益【百万円】:1.2
京都市と比較してどうでしょうか。まず注目されるのが売上高総利益率で9ポイント差がある点です。これは京都市の飲食業や宿泊業では大阪市のそれと比較して商品サービスの原材料費や加工費などのいわゆる製造原価が割安であると考えることができます。
一方、営業利益率との差では3.5ポイントに縮まります。これは販管費が要因で、京都市が大阪市より販管費がかかるビジネスをしているということを示唆しています。
どちらも重要なビジネス指標になりますので興味深い点です。特に新規でビジネス立ち上げを検討している方は参考指標にしてみてください。
2.神戸市の収益性分析
次は京都市を神戸市と比較してみます。
【神戸市の収益性指標】
売上(収入)金額【百万円】:418,771
費用 売上原価【百万円】:86,123
費用 販売費及び一般管理費【百万円】:173,864
売上高総利益【百万円】:332,648
売上高総利益率:79.4%
営業利益【百万円】:158,784
営業利益率:37.9%
事業所数:10,686
従業者数【人】:73,628
1事業所あたりの売上高【百万円】:39.1
1事業所あたりの営業利益【百万円】:14.8
1人あたりの売上高【百万円】:5.6
1人あたりの営業利益【百万円】:2.1
神戸市との比較で注目すべきは、営業利益率です。京都市も一般的な指標と比較して高い数値となっていましたが、神戸市はさらに14.9ポイントも高い数値を出しています。超優良事業者がビジネスをする街、それが神戸市の実態ということが言えるかもしれません。
ただし、京都市と比較して神戸市は事業者数が3,138社多く、従業員数も5,189人多いという状態ですので、起業などを検討する事業者、転職を考えている方にしてみればライバルの多い環境であるとも言えそうです。
今回は以上です。いかがでしたでしょうか。飲食や宿泊ビジネスではポテンシャルのある京都市と比較することで、大阪市や神戸市におけるビジネス可能性や仮設設定もできることを実感いただけたのではないでしょうか。
次回はさらに他都市と比較して何か新たなインサイトがないかなどを見ていきたいと思っています。
ではまた次の機会に!
(おまけ)地方事業者向け気になるニュース紹介
今回も私が個人的に気になるニュースをピックアップしています。
地方事業者の目線で役に立つ情報を中心にご紹介です。
抽出期間:2022/4/24~2022/5/7
ニュース転載元:EnterpriseZine(エンタープライズジン)
スノーフレイク、今年度の目標に日本国内の支援体制拡充を掲げる
企業のデジタル化が進まない原因の一つに、安くて簡単でいい感じのデータ基盤がないという問題がありました。snowflakeはこの問題をブレイクスルー可能性を秘めたサービスです。私も実際にトライアル利用してみましたが、正直驚きました。すごい時代に突入するなぁと思っています。
デジタル庁、2代目デジタル監に浅沼尚氏 生活者視点のサービス作りに意欲
立ち上げ前から話題となっていたデジタル庁ですが、最近はどうなんでしょうか。法規制や行政調整など様々な課題はあるようですが、一国民として次のリーダーにはぜひ使いやすい利用者目線のサービス設計にこだわってほしいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
