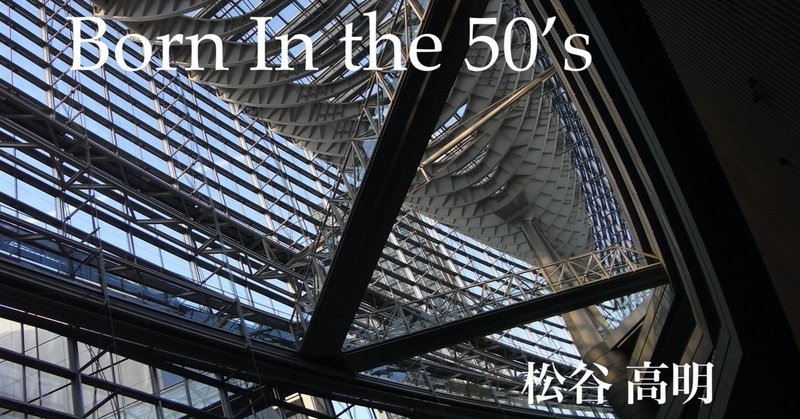
Born In the 50's 第四話 初七日
初七日
石津は国分寺駅で電車を降りると南口に出た。バス通りをそのまま東に向かい、公園の先の交差点を過ぎたところで右に曲がり住宅街へと進んでいく。
前を見ると、どこかで見たことのある男がのんびりと歩いていた。グレーの上下を着てはいるが、揃いのものではないようで色調がちょっと違った。
スマートフォンを片手になにかブツブツつぶやきながら歩いている。
石津はそのまま歩くスピードを少し上げて、男のすぐ後ろまで近づくと声を掛けた。
「濱本、お前か」
「おどかすなよ」
濱本はのけぞるようにして石津を見ると、答えた。
「すまんすまん」
石津は濱本の肩を軽く叩くとそのまま歩き出した。
濱本もまた同じように歩き出した。相変わらず手に持ったスマホを弄っている。
「どうした?」
「どうしたって、初七日だろ」
石津の問いかけに濱本が答えた。
「でも、葬式のときにいっしょにやったろ」
「あれは遠方から来る親戚とかのためだろ。俺たちは友だちだったしな。線香上げにいってもいいかと思ってさ。お前だって同じじゃないのか」
濱本がいった。
「まぁな」
石津は素直に頷いた。
しばらく歩くと右手に早見の住んでいたマンションが見えてきた。エントランスに向かう。自動ドアが開くとそこにはオートロックのパネルがあった。
早見の部屋の番号を押すと、そこでしばらく待った。
「どなた?」
スピーカーから映子の声が聞こえてきた。
「石津です。あと、濱本もいっしょだけど」
石津が答えた。
「どうぞ」
映子の声とともに入り口のドアが開いた。
石津は濱本といっしょに中に入ると、そのままエレベーターに乗り四階に向かった。
エレベーターを降りると部屋に向かう。
マンションのグレードはこの廊下ですぐに判る。ただコンクリートを敷いただけのマンションはそれなりのものでしかない。しかし、早見が住んでいたこのマンションは違った。廊下の壁の装飾を含めて、細かなところまで配慮がされている。
玄関でチャイムを鳴らすと、すぐにドアが開いた。
「いらっしゃい。さぁ、あがって」
映子が玄関口でふたりを待っていた。
石津と濱本は用意されていたスリッパに履き替えると、そのまま映子に導かれるように中へと入った。
リビングの奥の和室には祭壇が設けられていて、線香の煙が立ち上っていた。
「とりあえず初七日だから」
石津が口を開くと、映子は頷いた。
「ありがとう。それじゃ、あっちへ」
石津と濱本はそのまま祭壇の前に座った。
まず濱本が線香に蝋燭の火を移した。
鈴を鳴らして手を合わせると静かに眼を閉じた。
終わると濱本が同じように線香に火を移して、手を合わせた。
「お茶でいいかしら」
映子が声を掛けた。
「ありがとう」
石津が答え、ふたりはそのままリビングに移動するとソファに座った。
「わざわざありがとう」
映子はふたりにお茶を出しながらいった。
そのまま向かい合うようにソファに腰を下ろす。
「不調法者で申し訳ない。考えたら手ぶらできちゃったよ」
石津が頭を掻いた。
「いいのよ、こうして来てくれるだけで。そういえば三十分ほど前に、近藤さんも見えたわ」
映子が答えた。
「そうか、あいつも来たのか」
濱本がお茶に手を延ばした。
「奥さんの具合はどうなのかしら」
映子が心配そうな顔で訊いた。
「うん、よくないらしい。抗がん剤とか放射線とかいろいろとやっているらしいけどね。いつ訊いても、相変わらずとしか答えないんだ」
石津が答えた。
「そうなのね」
映子がぽつりといった。
「いろいろ大変だったろ」
石津がいたわるようにいった。
「ううん。局の方が全部やってくれたから、わたしはただお飾りのように座ってただけ。ほとんどなにもしてないのよ」
映子は首を振っていった。
「それにしても突然だったよな」
濱本がぼそりとつぶやいた。
「ええ。事故で死ぬってこういうことなのかしら。まだ実感なんて湧かないのよ。どこかに出張へでもいっていて、夜になるとただいまって帰ってきそうで……」
映子は寂しそうに笑った。
「公安庁から局へ移ってまだそんなに間がなかったんだっけ?」
石津が尋ねた。
「辞令が出たのは去年だったの。実際には秋頃だったかしら、異動したのは」
映子が答えた。
「国家安全保障局だからなぁ。ごついやつがごろごろいそうだ。表向きはどうかわからないけど現場でいろいろと活動する局員もいるんだろう」
石津は頷いた。
「どこへいっても俺は事務屋だから仕事は変わらないっていってたわ」
映子は思い出しながら答えた。
「あいつらしいな」
石津はお茶に手を延ばした。
「今月のはじめぐらいだったかしら。暗い顔して帰って来るなり部屋に籠もるようになったのは」
映子は気にかかるようなそぶりで口を開いた。
「仕事の悩みを顔に出すやつじゃなかったんだがなぁ」
石津が答えた。
「あいつが悩んだ顔をしていたときは、だいたいスターウォーズのグッズが手に入らないときぐらいだったよな。大学のときから大ファンだったじゃないか」
濱本が話しに加わった。
「スターウォーズが大好きなのは大学の頃から変わらないけど、部屋に籠もってスターウォーズのグッズなんかを眺めているときとは顔つきが違ったわ」
映子は頷きながら答えた。
「できたばかりの局でいろいろと衝突なんかもあったかもしれない。警察に自衛隊、それに公安庁のスタッフを無理矢理くっつけたわけだからさ」
「そうね、人間関係でなにかあったのかもしれないわね」
映子は、石津に頷いてみせた。
「なにかできることがあれば遠慮なくいってくれ」
石津はやさしくいった。
「ありがとう」
そのあと小一時間ほど思い出話を語り、石津と濱本は早見宅を辞した。
駅へと向かう道すがら石津はiPhoneを取り出すと電話した。
「近藤か、いま大丈夫か? おまえ、早見の家にいったそうじゃないか」
近藤が電話に出ると話しはじめた。
「ああ、俺も濱本といっしょに、いま線香を上げてきたところだ」
石津が頷きながら話す。
「どうだ、今夜、家で打合せをしないか? そう、例の件だよ。こっちは準備も終わったし。わかった、夜なら大丈夫なんだな。じゃ、待ってるよ。ああ、わかった、濱本にも伝えておく」
石津は電話を終えると、iPhoneを胸ポケットへと滑り込ませた。
「なんだって?」
濱本が確認するように訊いた。
「あっちも準備は終わったらしい。今夜、家で打ち合わせしよう」
石津が答えた。
「たまには鍋でもつつくか?」
濱本が肘で石津を突きながらいった。
「中年男三人で、春先に鍋か」
石津はちょっと首を捻った。
「まぁ、久しぶりだし、早見を偲んでということでどうだ」
濱本がいった。
「じゃ、準備しておくよ。お前どうする」
石津が尋ねた。
「いったん会社に戻ってデバッグしてからいくよ」
濱本は意味ありげに頷いてみせた。
その濱本が石津の家にやって来たのは、夜の八時近くになってからだった。
石津はあの後帰宅すると、抱えていた原稿をひとつ仕上げ、近所のスーパーへ鍋の買い出しに出かけた。日が暮れかかる頃には卓上のガスコンロを引っ張り出してきて、大ぶりの鍋をセットし、食材も適当なサイズに切ったりと準備を整え、ふたりの来訪を待っていた。
ほどなく近藤が訪れ、ふたりは濱本を待つのももどかしく、とりあえずビールの栓を抜いて飲みはじめた。
ついつい話は思い出話になる。
やがてビールが一本空になり、濱本のやつは遅いなといいながら、待つのにじれてしまい、ガスコンロの火を点けた。二本目のビールも空き、そろそろ焼酎でもどうだという頃に、濱本がやってきた。
「遅かったじゃないか」
近藤が濱本に声を掛けた。
濱本はすまんすまんといいながら、持ってきた一升瓶を石津に渡した。
「焼酎だ。明るい農村という銘柄だ」
濱本が笑顔でいった。
「美味いのか?」
石津が受け取りながら訊いた。
「いや、いつも酔っぱらってしまって味を覚えていない。でも、なんとなく名前だけ記憶にあったから買ってみた」
濱本はそういうと椅子に座った。
「明るい農村か。俺たちには、明るい明日はあるのか?」
近藤が茶々を入れた。
「大丈夫。バッチリ、デバッグしてきた。おかけでちょっと遅くなったがな。これでいつでもやれるぞ」
濱本は自信ありげに頷いた。
「まず、飲め」
石津がさらにビールの栓を抜き、濱本のグラスに注いだ。
「しかしなんだ、労働の後のビールは堪えられんな」
濱本はそういいながら一気に飲み干した。
「それで、どうする」
石津が真顔で訊いた。
「車はどうだ?」
濱本が近藤に尋ねた。
「ステーションワゴンでいいんだろ。一台用意したよ。警備会社風の塗装になっている。でも、現金輸送車じゃなくていいのか?」
近藤が訊き返した。
「システムのメンテナンス要員という設定だから、その方がいいんだ。現金輸送車だと目立つかもしれないしな」
それに石津が答えた。
「なるほど。で、プレートを複数用意したけど、それは?」
近藤がさらに尋ねた。
「Nシステムがあるからな」
今度は濱本が答えた。
「あのナンバーを自動的にチェックするやつだな」
近藤が頷いた。
「高速だけじゃなく、主要な幹線道路にも導入されている。途中途中でナンバーを入れ替えれば追跡できないだろ」
濱本がいった。
「制服は?」
石津が近藤に聞いた。
「すべて揃ってるよ」
近藤が頷き返した。
それを聞いた石津はその場を離れるとリビングへいき、デスクの抽斗からなにかを取り出して戻ってきた。
「これ、銀行のカード」
そういいながらカードとメモ用紙をふたりに渡した。
「クレジットカード?」
近藤がカード確認しながら口を開いた。
「それで買い物もできるし、口座から金を引き出すこともできる」
石津が頷いた。
「通帳はないのか?」
濱本が石津に訊いた。
「オフショアの銀行だぞ。確認はみんなWebだ。あと、そのメモに暗証番号と、なにかあったときの確認用の質問と答えが書いてある」
石津が答えた。
「これが俺の番号だな。ああ、これありがちな質問だよな。母親の出身地とか、母親の名前を答えるってやつだろ」
濱本がしたり顔で頷いた。
「やり取りは英語だからな。問い合わせ先もそこに書いてある」
石津の答えにふたりは頷くと、それぞれ財布やバッグにカードをしまった。
「あと、一度に多額の引き出しをするのは止めた方がいい」
石津は鍋を箸でつつきながらいった。
「それはどうして?」
近藤が訊き返した。
「海外の銀行口座から、日本のATMを介して引き出すわけだから、一気に下ろすとチェックされる可能性がある。もしどうしてもそれなりの金額が必要になったら、海外の銀行の支店にいって、そこのATMを使ってくれ」
石津はふたりの顔を交互に見た。
「わかった」
ふたりは声を揃えるように答えた。
近藤はビールを飲み干すと、濱本が買ってきた明るい農村の栓を開け、氷をたっぷりと入れたグラスに半分ほど注いだ。
濱本も同じようにテーブルに置かれたアイスペールから氷をグラスに移すと、そこへ注ぐ。
石津も黙って焼酎をグラスに注いだ。
三人はお互いの顔を見合うと、だまってグラスを持ち上げて乾杯の仕草をした。
ひと口、オン・ザ・ロックの焼酎を飲む。
「おい、これ美味いぞ」
石津が濱本にいった。
「そうだな、だから酔っぱらうまで飲んでたのか」
濱本が笑いながら頷いた。
「ところで、利息って年に二回じゃなかったっけ?」
指を折りながら計算していた近藤がぽつりといった。
「それは普通預金の話だろ。世の中には定期預金ってやつがあるんだよ。これは預け入れた日からの指定日で計算するから、毎日だれかの口座で利息が計算されることになるんだ」
石津がかみ砕くように説明した。
「普通口座しかないんだろう、お前」
濱本がからかうようにいった。
「まぁ、自慢じゃないが貧乏人なんでね」
近藤が明るく笑った。
「で、いつにする?」
濱本が石津に尋ねた。
「週明けと週末近くは現金の補充があるかもしれないから避けたいな」
石津が考えながらいった。
「じゃぁ、次の水曜日だ」
濱本は宣言するようにいった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
