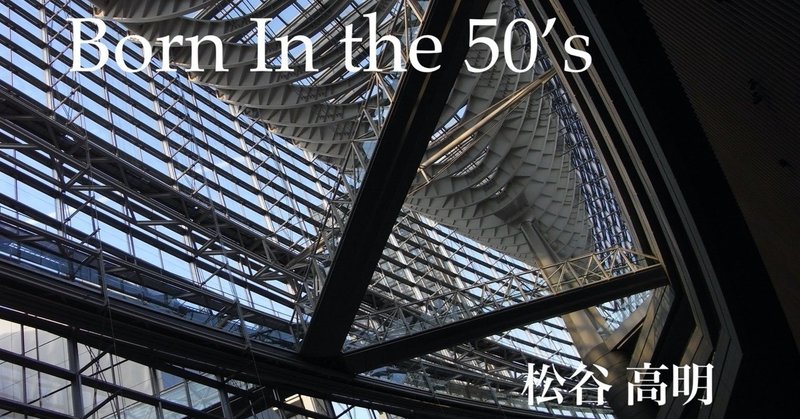
Born In the 50's 第六話 水曜日
水曜日
春の訪れは残酷なほど美しい。
桜が開きかけていた。もうすぐ満開になるだろう。そして、満開になった桜は風に吹かれながら散っていく。その散り方を見ると、石津はいつも残酷という単語を頭に思い浮かべてしまう。
戦場での取材とどこか結びつく感覚があるのかもしれない。
それが歳を重ねるごとに重くなっていく。
警備員の制服を着た石津はマンションからすこし離れた暗がりで近藤たちの到着を待っていた。左手につけたG-Shockで時間を確かめる。
十時三十四分。火曜日の夜だ。
歩道に植えられた多くの桜が、街灯の明かりに照らし出されていた。
散りはじめるのは週の終わりだろうか? それとも来週の半ばか?
そのとき、俺はどうしているんだろう?
生きているのか、それとも死んでいるのか。あるいはどこかに留置されているのか、それとも散っていく桜を見ながら、のんびりと酒を飲んでいるんだろうか。
車のエンジン音が石津の思考を中断した。
ステーションワゴンがゆっくりと近づいてきた。石津の前で駐まると、そのままハザードを点滅させる。助手席から濱本が降りてきて、うしろの座席へと移った。入れ替わりに石津がナビシートに座った。
シートベルトをしながら石津はふたりの顔を見た。
普段とは変わらないはずだが、それぞれが同じように制服を着ているからかどこか緊張しているようにも見える。
「どこへいく?」
石津は振り返って濱本に訊いた。
「ああ、日本海がいい」
濱本はすぐに返した。
「なぜ?」
石津は訊き返した。
「ほらな、やっぱり理由を訊くだろ? 車手配するときに俺も訊いたんだよ、理由を。とくに意味はないんだって。ただ、東京から離れた場所へいきたいだけだって」
近藤がハンドルから手を離すといった。
「ほんとうなのか?」
石津は濱本の顔を見た。
「地方銀行のATMの方が回線が混んでないかなと思っただけさ。それになんとなく人が少なそうなイメージがあるだろう、日本海沿いって」
濱本は暢気に答えた。
「それ単なる思い込みじゃないのか?」
石津はさらに訊いた。
「まぁ、いいじゃないか。侵入できる回線があればそれでいいんだし、東京のど真ん中であれこれやっていたら目撃される確率も高くなりそうだろ。だから日本海かなって」
「濱本がそういうならそうしようか」
石津は仕方なく頷いた。
「ちょっと待ってくれ」
そのとき近藤の携帯が鳴った。
「ああ、俺だ。いや仕事で帰るのは明日になるかな。悪いけど、明日、病院頼むよ。それじゃ」
近藤はそういうと携帯を閉じた。
「お袋さんか?」
石津が尋ねた。
「ああ、明日、女房の見舞いにいって欲しいと頼んでおいたんだ」
近藤はそう答えると胸ポケットに携帯を仕舞った。
「それにしてもお前、まだガラケーなの?」
濱本が身を乗り出すようにして近藤にいった。
「え? じゃ、お前はなに?」
近藤が訊き返す。
「Android。iOSは雁字搦めで窮屈だからな。あれこれ自分なりにプログラム突っ込んだり改造するなら、Androidの方が楽なんだよ」
濱本はスマートフォンを手に話した。
「あれ? 石津は?」
「iPhoneに決まってるだろ。いまどきガラケーなんて使ってるの、機械のことがからっきしわからない年寄りだけだぞ」
石津は軽く笑った。
「濱本、パソコンはなに使ってるんだ? やっぱりWindowsか?」
石津は濱本の顔を見て尋ねた。
「馬鹿いうな。MacにLinux突っ込んで使ってるよ。一応、窓も入れてトリプルブートできるようにしてるけど、基本はLinuxだな」
「なんだそれ? 窓とか、トリプルなんとかって」
近藤が訊き返した。
「詳しい説明聞きたいか? ガラケーのおじさん」
濱本がからかうようにいった。
「いや、いい。どうせ聞いてもわからないし」
近藤はきっぱりというとハザードの点滅を止め、右のウインカーを点滅させる。
「とりあえずこのまま環八から関越に入ればいいな?」
そういうと近藤は返事も待たずに車を走らせた。
春休みの期間とはいえ、平日の夜の道路は空いていた。五日市街道を東に進み、左折して環八に入ると、まっすぐ北上する。途中、笹目通りへと進み、谷原の交差点で左折して目白通りに入ると、そのまま練馬インターから関越に乗った。
三時間ほどかけて高速を走り続けると、越後川口サービスエリアでいったん休憩を挟む。
近藤は駐車場の端の方に車を止めると、リアのドアを開けて工具を取り出して、プレートの入れ替えをはじめた。
高速道路や交通量の多い主要な国道には自動車ナンバー自動読み取り装置が設置されている。ナンバープレートを自動的に読み取り、手配してる車両などを追跡するためだ。
基本的にはシステムを通過した車両はすべて記録される。
高速の料金所では搭乗者も撮影されるため、三人は移動中ヘルメットを目深に被りなるべく顔が写らないようにした。サングラスは逆に怪しまれるが、マスクなら大丈夫だろうと前の座席に座っているふたりはマスクを着用していた。
近藤が作業をしている間、だれか近寄ってくる者がいないかどうか石津と濱本は車の周りに立って確認していた。明け方前の人が少ない時間帯ということもあるんだろうが、こうやって制服姿の男が立っているだけで人は近寄ろうとはしないものだ。
作業が終わると、時間を調整するために二時間ほど休憩することにした。運転を続けてきた近藤を仮眠させると、石津と濱本は手順を話しあった。
それからガソリンを補給して、ふたたび車を走らせる。
長岡ジャンクションで北陸自動車道に入ると柏崎で高速を降りた。
市内を抜けてそのまま海沿いの道を走る。朝陽を浴びた海が碧くきらきらと輝いている。石津は残酷さとはまた別の春の柔らかな息吹を感じていた。
港からマリーナへと車を走らせ、海水浴場をすぎたあたりで近藤はいったん車を駐めた。路肩に車を寄せて、エンジンを切る。
「このあたりか?」
石津が振り返り、後部座席に座っている濱本に訊いた。
「もうちょっと先にATMがあるはずなんだよな。見あたらないか?」
「時間はどうなんだ? いま七時半だろ、ちょっと早くないか?」
石津が訊いた。手順についてはすべて濱本任せだ。
「確かに。八時すぎがいいんだよね。ATM使えるのが八時四十五分からだから、その三十分前ぐらいがちょうどなんだよな」
濱本がパソコンを操作しながら答えた。
「二十四時間営業じゃないんだ」
近藤がハンドルに凭れるようにしていった。
「そうじゃないATMを探したんだ。この近くのはずなんだがなぁ」
濱本はMacBook Proでマップを確認していた。
「どうする? 長時間、車を駐めてるとヤバくないか?」
近藤が振り返って濱本にいった。
「そうだな、ちょっと車を走らせながら探そう」
石津が頷いた。
近藤はふたたびエンジンをかけると、車を走らせた。そのまま海沿いの道を上越市の方へと走り出した。
すぐに濱本が声を上げた。
「あったあった、ここだ」
近藤はすぐには止まらず、二十メーターほど通り過ぎてから車を路肩に寄せた。エンジンはかけたままだ。
反対車線の脇にそのATMはあった。
車が三台ほど駐まれるスペースにポツリと建っている。ちいさなプレハブ小屋のようだった。中には二台のATMがある。石津はその場所を頭に刻み込むと、G-Shockで時間を確認した。
「どうする濱本。まだ時間は早いのか?」
「そうだな、あと十分ほど走ってから、戻ったらちょうどいいかもしれない」
MacBookから顔を上げると濱本が答えた。
「わかった。じゃ、十分ほど走ってから戻ればいいな」
近藤が車をふたたびスタートさせた。
ほどなく道は北陸道に合流した。さすがに交通量がある。さきほどまでとはまったく違い、行き交う車が多い。ちょうど朝の通勤時間だからということもあるんだろう。
しばらく走っていたが側道へと近藤はハンドルを切った。
「そろそろこのあたりで方向転換してみるか」
そういって近藤は石津の顔を見た。
石津は時間を確認すると頷いた。
「いいだろう、いこう」
側道からさらに細い道に車の頭を突っ込ませると、すぐにバックして方向を変える。近藤のハンドルさばきは的確だった。
ふたたび国道に合流してしばらく走り、また海沿いの道へと進んだ。
「プレハブの手前で駐めてくれ」
濱本の言葉に近藤は頷いた。
ATM の手前のスペースに近藤は車を駐める。石津は濱本とともに車から降りて、小屋へと近づいた。
濱本は小屋へと延びている配線を確認していた。
電柱から延びている回線が小屋の裏側へと引き回しされている。濱本はなにかブツブツといいながらその配線を辿って裏側へと回った。石津もそれに着いていく。
「大丈夫だ、この回線で間違いない」
濱本は石津の顔を見て頷いた。
石津はそのま車に戻ると、リアのドアを開けて脚立を取り出した。ちょうど背丈ほどの高さのあるものだった。左肩に乗せるようにして脚立を運ぶ。
小屋の裏側へ回ると濱本はMacBook Proを開いて、準備をしていた。
石津が近づくと親指大のボックスを渡した。その両側にはクリップがあり、鰐口で線を挟み込むことができるようになっていた。
「トランスミッター。このクリップで線を挟んでくれ」
濱本はボックスを渡しながらいった。
「どっちの線だ?」
脚立をセットしながら石津が訊いた。
「線が二本繋がってるだろう? 片方が映像用の回線なんだ。見た目では判断できないから両方試してみてくれ」
「解った」
石津は頷くと脚立を登った。
二本の線が束ねられてそのまま小屋の中へと引き入れられていた。石津はそれを確認すると、片方の線をクリップで挟んだ。もうひとつのクリップも同じ線を挟む。
「OK。挟んだぞ」
石津は濱本を見下ろしながらいった。
濱本は石津に頷き返すと、しゃがみ込んでMacBook Proのキーボードをタイプする。画面をのぞき込みながら何度もタイプし直してから、ふたたび顔を上げると首を横に振った。
「そっちじゃないな。別の線の方を試してみてくれ」
濱本の指示に石津は頷くと、クリップをひとつずつもう一方の線に移し替えた。きちんと挟み込んでいるのを確認すると、濱本の顔を見た。
「挟み直したぞ」
石津の声に濱本はまた頷いた。
ふたたびMacBook Proに向かう。何度もキーボードを叩きながら、独り言なのかぶつぶつとなにかをつぶやいている。ひとしきりキーボードを叩いたあと、腕組みをして考えはじめた。
「どうした?」
石津は脚立から降りると濱本と同じようにしゃがみ、彼の顔を見た。
「おかしい……」
濱本は石津の顔を見てポツリと答えた。
「なにが……」
「どちらも画像データじゃない……」
濱本は溜息をついた。
「どちらもって、あのボックスがちゃんと機能していないんじゃないのか?」
石津が尋ねた。
「いや、そんなことはない。何度もテストした。さまざまなタイプのラインで確かめたからトランスミッターに問題はない。事実、ボックスからデータはちゃんと送られてきている。でも、これは画像データじゃない」
濱本がキッパリと言い返した。
「じゃ、線が違うんだ」
石津はそういって立ち上がった。
「そんなこというけど、他に引き込まれているラインなんてないだろう?」
濱本も膝に乗せていたMacBook Proを地面に置くと、同じように立ち上がった。
石津は小屋に近づいた。正面を通って向こうへいこうとしたとき、濱本に腕を掴まれた。
「正面は絶対に駄目だ。通っちゃいけない。カメラに撮られる」
「カメラって、どこの」
石津が訊き返した。
「小屋の中に正面を撮るカメラが最低一台は設置してある。場所によっては左右の画像を撮るために二台以上セットしてあるところもある」
濱本が答えた。
「なんでだ?」
「以前、ブルドーザーで小屋ごと壊して金を奪った事件が続いたことがあるだろう。あれ以来、カメラの台数が増えたんだよ。おまけに、ATMを破壊するとインクが噴き出して金が使えなくなることもある」
濱本は説明した。
「そうか、わかった。じゃ、どうやってあっちにいくんだ?」
石津は頷いた。
「正面が駄目なら、裏を通る。簡単なことだろ」
濱本は笑った。
「裏って……、この裏はブロック塀があってやたらと狭いぞ」
「でも、そこしか通れないもの」
濱本は笑ったまま答えた。
首を振るとやれやれといった風情で脚立を肩に乗せ、石津はプレハブ小屋の裏を通って向こう側へと進んだ。
狭いだけではない。ゴミが散在している。おまけに雑草も生えていて歩きにくかった。
「なんだってこんなことをやってるんだか」
石津がこぼした。
「そりゃ、金のためだろ」
濱本は独りごちた。
しばらくたって脚立をセットする音が濱本の耳に聞こえた。
「どうだ?」
裏の狭い通路越しに濱本が尋ねた。
向こう側から石津が覗き返す。
「線があったぞ。こっちは一本だけだ」
「じゃ、クリップ頼むよ」
濱本はそういうとふたたびしゃがみ込みMacBook Proに向かった。
拝むような気持ちでキーボードを打ち込んだ。画面にウインドが開く。さっきはこのウインドにただの文字列しか表示されなかった。
左端にコマンドプロンプトが点滅している。
──signal。
さっき何度もタイプした文字列をもう一度打ち込んだ。
すると不意にそのウインドが六分割され、それぞれに画像が映った。
「やった!」
濱本は拳を力強く握った。
「大丈夫だ、ちゃんと映ったよ」
濱本は立ち上がると小屋の向こう画にいる石津に声を掛けた。
「よし!」
石津も力強く返事を返した。
「ちょっと待っててくれ。画像をこのまま録画する」
「どれぐらいだ?」
「五分」
濱本はそう答えると、ポケットからスマートフォンを取り出して、画面に表示されたソフトキーボードにコマンドを打ち込み、画像の録画をはじめた。
小屋に引き込まれている線を通って送られている画像データをトランスミッターがMacBook Proに転送し、さらにそこから濱本の手にあるスマホに転送して録画している。
五分が経過すると、濱本は録画を止め、石津に声を掛けた。
「録画は終わったよ」
「どうすればいい」
石津が訊き返した。
「録画した画像を、今度はこっちから送り返すから、それまで待っててくれ」
濱本は今度はMacBook Proに向かった。
「要するにいま録画した画像を、この線を使って画像のチェックをしているはずのセキュリティ会社に送るということだな」
石津が尋ねた。
「そういうこと」
そう答えると、濱本はスマホを手に立ち上がった。
そのまま小屋の正面を通って、向こう側の石津のところへと歩いていった。
小屋の裏側から向こう側を覗き込んでいた石津の肩を軽く突く。
「うおっ!」
石津は思わず驚きの声を上げてしまった。
「脅かすなよ。もう大丈夫なのか?」
石津は胸をなで下ろしながらいった。
「ああ」
濱本は頷くと、脚立を上り、トランスミッターのすぐ近くの壁にスマホをポケットから取り出したガムテープで固定した。
「なんだ、このスマホが画像を送ってるのか?」
「そういうこと。形はちいさくてもコンピュータの端くれなんだぜ。これでATMを操作しても映像は残らないし、セキュリティ会社にはだれも映っていない画像しか送られないというわけだ」
濱本は脚立を下りると笑ってみせた。
石津は頷くと脚立を片付け、そのまま肩に乗せて車に向かった。
車の中では近藤が待っていた。
「遅かったじゃないか」
しびれを切らしたように近藤がいった。
「ちょっと画像のラインを確認するのに手間取った」
それだけいうと石津はリアのドアを開けて脚立を仕舞い、点検中と書かれた黄色いプラスティック製のちいさな看板を取り出した。
「いこう」
運転席の近藤に声を掛けた。
近藤は頷くとヘルメットを被り直して車から降りた。そのまま石津と一緒に小屋へと向かった。
石津は歩きながら腕時計を確かめた。八時四十三分。
そのまま小屋の前に看板をセットすると近藤の肩を叩いた。
「だれも近寄らせるなよ、ガードマンの近藤君」
「わかった」
近藤は短く答えるとその看板の横に両腕を後ろに回して立った。
石津と濱本はそのまま小屋の中に入った。
濱本はMacBook Proを広げると左側のATMの操作パネルのところに広げた。
「さてと、あとはこのATMが作動する時間を待つだけだな」
石津は濱本にいった。
「そういうことだ」
濱本が自信ありげに答えた。
石津はもう一度、腕時計で時間を確認した。
八時四十四分四十八秒。
「あと十秒ほどだ」
石津の声に、濱本はただ頷き返した。
「よし、いいぞ」
石津がいうのとほぼ同時にATMのパネルが点灯して、いつでも使える状態になった。
濱本は大きく息を吐くと、右手に持ったカードを、そのままスロットに挿しこんだ。しかし、中に入らない。ちょっと首を捻って、カードを押し込もうとした。それでも、すんなりと入ってくれない。
左手で額をぬぐった。
「どうした?」
その様子を見ていた石津が尋ねた。
「カードが入らない」
濱本はそういって右手に持ったカードを石津に見せた。
そのカードの片側からはフラットケーブルが延びていてMacBook ProのUSBポートに繋がっている。
「カードってさ、なにか操作しないと入れられないんじゃないのか?」
石津が冷静にいった。
「操作って?」
濱本が早口で訊いた。
「ほら、残高照会とか引き出しとか」
「ああ、そうか」
濱本は納得したらしく、パネルに置いたMacBook Proを石津に預けると、タッチパネルの「残高照会」を押してから、カードを挿しこんだ。今度はすんなりとカードが入る。
「おまえ、意外に冷静だな」
濱本はそういいながら石津からMacBook Proを受け取ると、またパネルの上に置き、キーボードを打ちはじめた。
「伊達に戦場にはいってないからな」
石津はすこしだけ寂しそうに答えた。
「大丈夫だ、これでプログラムが送れる」
濱本は自分自身に言い聞かせるようにいった。
その外では近藤が両足を肩幅ほどの間隔を開けて黙って立っていた。
ふと左の方に目をやると、白髪の老婆がゆっくりと近づいてきていた。国道からひとつはずれた道だ。用事がなければ出歩かないだろう。その老婆はバッグのついた手押し車、いわゆるシルバーカートを押しながらひょっこりひょっこりと歩いている。カートを押しているから必要ないだろうと思うが、その右手には杖が握られていた。
──まさかこのATMに用事があるわけじゃないよな。
そう祈るような気持ちで近藤はその老婆をちらりと見た。
そのとき老婆も近藤の顔を見た。思わず視線があってしまった。
なにやら嫌な予感がした。
一歩一歩老婆はその踏み出す足を確かめるように歩いて近づいてきた。
近藤のすぐそばまで来るとカートから手を離して、それまで屈めていた腰を伸ばした。それでも近藤の胸のあたりぐらいの身長しかなかった。
「なにをしておる」
その顔の皺と同じぐらいしゃがれた声だった。両手を持っていた杖に置く。
「点検中なんですよ」
近藤が優しい声で答えた。
「だから、なにをしておる」
老婆は睨むようにいった。
「いや、だから点検しているんです」
近藤はゆっくとり、しかししっかりとした声で答えた。
「なにを、じゃ」
老婆はさらに続けた。
「ATMです。点検しているんですよ」
近藤は同じ口調で答えた。
「どけ」
そういうと老婆は近藤を押しのけて中に入ろうとした。
「駄目だってば」
近藤はそういいながら老婆を押しとどめた。
「孫の小遣いを下ろすんだから、どけ」
老婆はそういって近藤を睨んだ。
「だから点検中なので、ちょっとだけ待ってください」
近藤は老婆の両肩に手をやり、なだめるように話した。
「ここは使えんのか?」
老婆は右手に杖を握りしめた。
「いまATMを点検してますから、もうすぐ使えるようになりますよ」
「いますぐ下ろしたいんじゃ」
老婆はそういうと右手の杖で近藤の頭を小突きはじめた。
「痛いって」
近藤は右手で頭を庇いながら、左手で老婆の杖を押さえようとする。
老婆は今度は両手で杖を持ち、振り回しはじめた。
「石津、なんとかしてくれ。こっちは大変なんだから」
近藤は溜まらず小屋の中に声を掛けた。
杖が近藤のヘルメットに当たってコンコンと音を立てている。
そうこうするうちに原付バイクが近づいてきた。
近藤はそのバイクを見て血の気が引いていくのを感じた。白で塗られたそのバイクは警察官が使っているものだ。近藤たちのところでバイクを駐めると小太りの巡査が下りて、歩み寄ってきた。バイクに乗っているためかヘルメットは被ったまま。腰には拳銃と警棒を下げている。
「どうかしましたか?」
巡査の声はのんびりとしたものだった。
「いや、この方が点検中なのに中に入ろうとされて」
近藤は頭を庇いながら、しどろもどろの口調で答えた。
「あ、こりゃ白石のばあさんじゃないか。ちょっと止めなさい」
巡査はそういうと老婆の杖を両手で掴んで振り回すのを止めさせた。
「だから金を下ろすんじゃ」
老婆は今度は巡査を睨みつけた。
「ばあさん、いいから、ちょっと待ちなさい。いま、点検中なんだから」
巡査は慣れているようで、老婆にいった。
「点検てなんじゃ」
老婆は杖を振るうことができず、仕方なく巡査にいった。
「お金が下ろせるように、いま機械を調べているから、ちょっと待ちなさい」
巡査はそういう近藤の顔を見た。
近藤は左手で額の汗をぬぐっていた。
「待てばいいんだな」
老婆はようやく納得したようで、頷いた。
「ところで、どれぐらいかかりそうですか?」
巡査は近藤に訊いた。
「もう終わると思います。なるべくお客様には迷惑をおかけしたくはないので、早めに終わらせるつもりだったんですが」
近藤はそういうと頭をヘルメットの上からかいた。
巡査は近藤の返事を聞いて、ちょっと考えると、小屋の中の様子を伺った。
一歩小屋の方へ踏み出した。
近藤は思わず眼を閉じた。
そのときドアが開き、中から石津と濱本が出てきた。濱本はMacBook Proを抱えている。
「あ、お待たせしました。もうお使いいただけますよ」
石津がにっこり笑うと巡査に答えた。
「そうですか」
巡査は頷き返した。
「ばあさん、もう使えるそうだ」
巡査は老婆の方を向くと、そう話しかけた。
「それでは、わたしは」
そう石津たちに告げるとバイクに跨った。
エンジンを掛けたが、しかしなにか考えているようであたりの様子を伺っている。
「まだなにか?」
石津が笑顔を作りながら問いかけた。
「いや、なにも」
巡査はそういうとバイクをスタートさせた。
近藤は去っていく巡査の後ろ姿を見ながら大きな溜息をついた。
三人はしばらく動くことができずにただその場に突っ立っていた。
「どけっ」
その背後で老婆が声を上げた。
近藤が飛び退くように道を空けると、老婆は左手でカートを押し、右手で杖を突きながら悠然と歩いていった。
ゆっくりゆっくりと歩いていく。
ちいさな背中がしかしなかなかちいさくなってはいかない。
近藤はぐっしょりと汗をかいた右手をズボンでぬぐいながらその後ろ姿をぼんやりと眺めていた。
「近藤、撤収だ」
石津がその耳元にいった。
「ああ」
近藤はただ頷いた。
石津は車に戻ると、脚立をふたたび肩に担いでセットしたトランスミッターとスマホを回収するために小屋に戻る。
近藤は車に戻ると、エンジンを掛けて石津のすぐ近くまでやって来た。
「濱本、もうこれ外していいのか?」
石津が後部座席に座っている濱本に声を掛けた。
「ああ、大丈夫だ」
その声に頷くと、石津はトランスミッターとスマホを回収して車に戻った。
「びびったよ」
近藤が石津にいった。
「だろうな」
石津が頷いた。
「お巡りのバイクを見たときには心臓が止まるかと思ったよ」
近藤が何度も頷きながらいった。
「これからどうする?」
石津は後ろに座っている濱本にいった。
「ちょっと待ってくれ。いま、プログラムがどうなっているのか確認しているから」
濱本はMacBook Proの画面を見たまま答えた。
「車はどうするんだ?」
石津が近藤に尋ねた。
「これはこのまま廃車にする。スクラップ工場があるのでそこへ捨ててくるよ。エンジン番号と車台番号は削ってあるけど、そのまま潰しちゃうのが一番だろう」
近藤がようやく落ち着いたのか、いつもの口調で話した。
「その間、おれたちはどうすればいい?」
さらに石津が訊いた。
「着替えてからどこかでお茶でも飲んでてくれ。別の車を手配してあるんだ。ときどき取り引きする中古車屋があって、車を用意してもらってる」
近藤が説明した。
「わざわざこのために一台買ったのか?」
石津が尋ねた。
「いや、ハチロクがどうしても欲しいって客がいてさ。探していたらちょうど知り合いの中古車屋にあったから、譲ってもらうことにした」
「なんだついでに商売もしてるのか」
石津がちょっと呆れたようにいった。
「これが一石二鳥ってやつだな」
近藤は笑って頷いた。
「OK、辿り着いたぞ」
濱本が興奮気味に口を開いた。
「どうしたんだ?」
石津が確かめる。
「さっき送り込んだプログラムが銀行のシステムに乗っかった。あとは、このままオンライン上に広がっていけばいい」
濱本が答えた。
「それって、ウイルスと同じじゃないか」
石津が訊いた。
「そうだよ、根本的な考え方はウイルスそのもの。使い方によってはこんなこともできるってわけだ。あとは口座に入金されるのを待つだけだ」
濱本が大きく頷いた。
「しかし、とんでもないプログラマだなお前って」
石津が見直したような口調でいった。
「人ってさ、思いついたことはおおよそ実現できるようになっているんだ。もちろん、やる気があればの話だけど」
濱本は自分に言い聞かせるようにいった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
