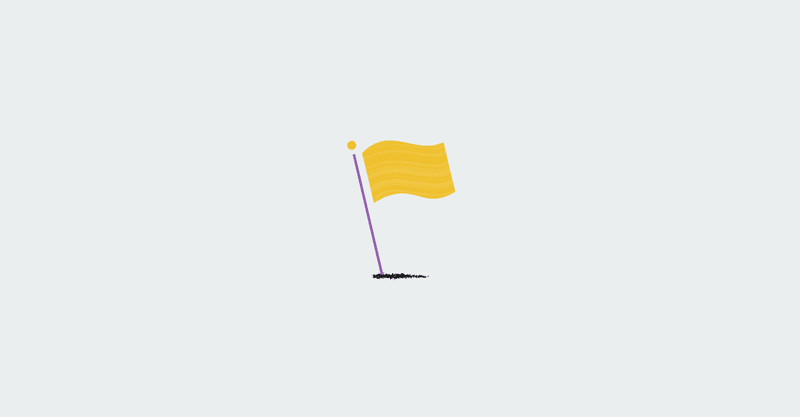
10.できないものに対して白旗をちゃんとあげるということ
きのう・15日締め切りのメトロアドコンペを出そうと思っていたのに出せなかった。
2年前か3年前も広告代理店のインターンの課題を出したかったのに出せなかった。出した人の企画を見してもらうとどれもおもしろい。だけど、それは才能ではない、
と言ってしまうと一見失礼にあたりそうな言葉だけどここ数年、広告業界で有名な人たちのセミナーにいって話を聞くとアイデアというのは神のひらめきやテクニックなどではなく、諦めない力だということに気づく。
コンペでよく出る「〇〇を話題にしてください」というお題の受賞作品を見て、おもしろいなーなんでいいんだろうって分析するのは好きだけど、いざ自分でやってみるともう吐くほど辛い、全然できない。12月後半くらいから友達を誘ってやってみたい、一緒にやらない?と声をかけたのは私なのに全然課題と向き合おうとしなかった。
企画をする人はよく「諦めないことが大事」と言う。
その言葉が実際にこういうコンペに取り掛かると痛いほどわかる。おもしろいことを考えるのが好きだったはずなのに、全然出てこないのだ。それが辛くて、あとまわしにしてしまって、結局できなかった。
受賞してる人はもちろんとてもすごいが、企画を提出した人もとても尊敬している。みんな諦めなかった人たちだ。
私がいままで感じていた新しいことを発想していた脳の筋肉と〇〇を話題にする方法を考える筋肉は違うらしい。脳の回路が違うから後者を考えるにはその筋肉を使う必要がある。でもその筋肉を鍛えて、ちゃんと企画までもっていけるようになるにはいったん限界を突破して回路をつくらねばならないのだ。そしてそれにはとてつもないエネルギーを使う。なにか突破する人の力の動力源ってスキっていう気持ちだと思う。
コンペで落ちたり、自分のアイデアが評価されなかったり、アイデアが全然出てこなかったり、、そんな状態でもスキだからやっている。
自分のことを天才という人はなかなかいないが、周りから天才と言われてる人はたくさんいる。それは、なにかが好きでとにかくそれをやっているのが楽しいから、結果的にその分野に長けていって、それが周りから天才と呼ばれる人だと私は思っている。でも本人からしたらスキだからやっている。大変な時もたくさんあるけどスキだから続けられている。
周りから天才と呼ばれているけど飄々としている当人をみて、きっとそういうことなんだろうと解釈した。
わたしは企画を考えるまでの苦し楽しの経験が9対1くらいの割合でその1をそんなに楽しめない人間だったということが最近分かった。
だから、白旗をあげることにする。
白旗をあげて、自分があこがれてるけどできないものではなく、わりと得意なものをまずは思いっきり磨いてとがらせていきたい。
自分のスキは得意なことと似ている。
最近読んだ本で
得意なことを認識するのは結構難しい。できないことの方がよくわかるから。
というフレーズを見てなるほど、と思った。
自分ができることは、自覚せずに簡単にできるからこそ気づきにくい。特に日本は平均的に伸ばす教育だから、平均以上にできることがあっても、できないことが平均以下ならそっちを上げなければいけないという考え方だ。
会社の歯車が誤作動を起こして動かなくならないように、平均的に仕事ができればまわっていた時代もあったが、人間よりも優秀なロボットたちが仕事を昔に比べたらだいぶしてくれるようになったので、人間は人間にしか考えられないことを求められるようになった。
だから平均的にもっていくよりも自分の得意なところをとがらせた方がいいのだ。
自分が新しいアイデアを考えるのが得意だと思っていたから、全然できなかった状態、そして伸ばそうという気力も起きなかった状態を認めるのは自分に対して失望する。だけど、挑戦してるふうに見せかけてあきらめてるのを続ける方がもっとよくない。
6年柔道をやって、このまま柔道のことだけしか知らない人間になるのが怖くなって、大学4年間はいろんなことをやった。
だけど、柔道6年、いろんなこと4年やって、結局いろんなことに応用できるのは柔道の考え方だった。バイトでも、留学でも、仕事でも困ったときには柔道の考え方で物事を考えられたから、1つの世界を語れるようになると全く違う世界も理解がすすんで語れるようになった。もし大学で柔道をやってたらこのことには気づけなかっただろうから、いろんなことをやった4年間を価値がないとは言わないけれど。
白旗をあげて、自分のスキなことにちゃんと意図的に向き合う期間を始める。
【今日のおすすめBOOK】
就活終盤くらいに出会った本。独立したけど、働く目的を失ってたくさんの数のセミナーを受けた著者がその共通項を編み出して作った本。2番目の動画だけでもだいぶ分かりやすく伝えられている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
