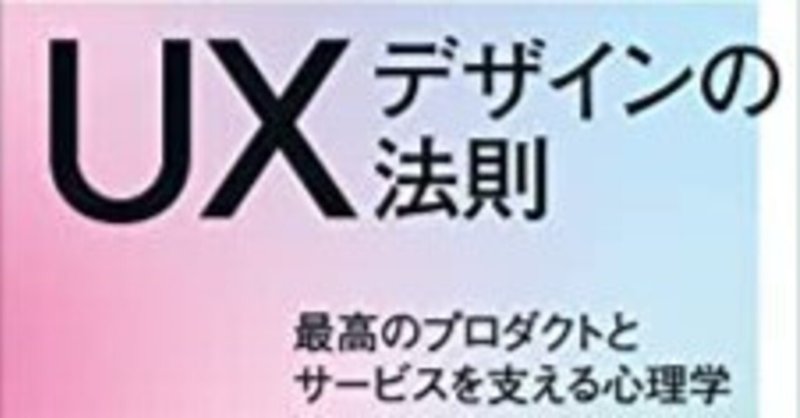
UXデザインの法則からデザインを考える上で重要なこと
UXデザインを行う際には、感覚(良さそう)ではなく複数のロジック(マテリアルデザインのような言語化できるデザイン)を活用することで、より精度の高いデザインを作れる。そのデザインをユーザーが利用する場合、ユーザーの感覚や行動心理学などをしっかりと理解することがデザイナーとしてより一歩成長できます。
今回紹介するのは、複数あるUXデザインにおける法則のうち、代表的なデザインの法則。これからデザイナーを目指すものなら、これは押さえておきたい。
ヤコブの法則
インターフェイスの摩擦をできるだけ無くしてユーザーが目標を達成しやすくなることがデザイナーの目指すべきところ。
既存のサービスの応用
ユーザが慣れ親しんだプロダクトと見た目が似ていれば、同じように動くことを期待される
すでにあるメンタルモデルを活かせれば、ユーザは新たなメンタルの学習なしにタスクに集中でき、ユーザ体験の質が高まる。
変更時の違和感を最小限に止めるためには、慣れ親しんだバージョンを使い続けられる移行期間を設けよう。
心理学上の概念 「メンタルモデル」
システム、その振る舞いによって、私たち自身がどう理解しているかという概念
まとめ
ユーザーが新たな体験を理解するためには過去の経験を活かす必要がある。
⇨既存のメンタルモデルに関連した一般的な慣例を検討する
慣例から逸れた道を進むのであればデザインをユーザーテストにかけてユーザーに振る舞いが理解されるか確かめる。
フィッツの法則
ターゲットに至るまでの時間は、ターゲットの大きさと近さで決まる。

タッチターゲットには、ユーザーが正確に押し寄せるために十分な大きさが必要
ターゲット同士は、十分な感覚が空いていなければいけない
ターゲットは、インtなーフェース内で、ユーザが簡単に到達できる場所に置かれていなければいけない
ユーザがタッチターゲットのような対象に到達するまでの時間は、ユーザビリティの重要な指標になる。
ヒックの法則
意思決定にかかる時間は、取りうる選択肢の数と複雑さで決まる

応答に時間がかかって意思決定が遅くなっているときは、選択肢を最小殿にまで減らす
タスクが複雑なら、小さなステップに分解して認知負荷を減らす
ユーザーが情報量に圧倒されないように、おすすめの選択肢を目立たせる
段階的なオンボーディングを採用し、新規ユーザの認知負荷を最小限に
単純化によって抽象的になりすぎないように
⇨ユーザーが達成したいことを理解して、達成にプラスにならないことを排除する
インターフェイスの理解とインタラクションにかかるメンタルのリソース(そもそも何をしたかったのか)の総量を認知負荷
ミラーの法則
普通の人が短期記憶に保持できるのは、7(±2)個まで
電話番号や車のナンバーなど
無用なデザイン制約を作ってはいけない
コンテンツを小さな塊に分けることで、ユーザーがその情報を扱い、理解し、記憶しやすくできる
短期記憶の容量は、個々人が持っている知識や状況、文脈によって大きく幅があることを覚えておく
私たちを取り巻く膨大な情報量は指数関数的に増加しているが、人間がその情報を処理するために使える心のリソースに限界がある
ポステルの法則
出力は厳密に、入力は寛容に
ユーザが取りう るアクションや、入力しうる情報全てに対し理解を示し、柔軟に対応し寛容であること
信頼性高くアクセス可能なインターフェイスを提供しながら、入力、アクセス、および機能の面で実際に起こりうるあらゆることを予測する
予測・対応できることが多ければ多いほど、デザインはより柔軟になる。
ユーザからの多様な入力を受け入れ、それを要件に合わせて変換し、入力の境界線を定義し、ユーザに明確なフィードバックを提供する
人と機械の間のギャップを埋めるのに役立つ。
ピークエンドの法則
経験についての評価は、全体の総和や平均ではなく、ピーク時と終了時にどう感じたかで決まる。
ディズニーランドで2時間も待っているのに苦じゃなく、楽しい思い出として残っているのはこの法則があるかららしい、、

ユーザージャーニ(実際の人間がどのように企業を認識し、どのように企業とやり取りするのか可視化したもの。)の中で最も重要な瞬間(ピーク)と最後の瞬間(エンド)に細心の注意を払う。
エンドユーザを喜ばせるためには、プロダクトが最も役たつ瞬間、最も価値がある瞬間、あるいは最も楽しい瞬間を見定めてデザインする。
人はポジティブな経験よりも、ネガティブな経験をより鮮明に思い出すことを心に刻む。
重要な瞬間に細心の注意を払うことで、その体験をポジティブに記憶してくれる
美的ユーザビリティ効果
見た目が美しいデザインはより使いやすいと感じれられる。
見た目が美しいデザインは、人の脳にポジティブな反応をもたらし、実際の場面でもよく機能すると受け取られる(信頼性を高める)
プロダクトやサービスの見た目が美しければ、人は些細なユーザビリティの問題に対してより寛容になる
ユーザビリティの問題を覆いかくし、ユーザビリティテスト中に課題を発見しにくくしてしまう
脳の思考モード

システム1(第一印象を形成するシステム)
自動的に働くため、ほとんど心理的な努力を必要としない。迅速で意図的には制御できない、直感・意図・印象といった類の反応
システム2
ゆっくりと動作し、注意力や精神的な努力を必要とする。集中・探求・演算処理といった複雑な問題解決のための思考モード
フォン・レストルフ効果(孤立効果)

似たものが並んでいると、その中で他とは異なるものが記憶に残りやすい
重要な情報やアクションを感覚的に目立たせる
視覚的な要素を強調する際には、お互いに競合したり、目立ちすぎて広告だと勘違いされないように抑制をかける
コントラストを伝えるのを色だけに頼ると、色覚障がい者やロービジョン(弱視者)を排除することにつながる
コントラストを伝える上で動きを使用する際には、動きに対し敏感なユーザに配慮する
ユーザを目標達成に導くために、視線をうまく誘導する
⇨他とは違う、目新しい、際立った刺激が人を惹きつける
バナーブラインドネス
広告だと認識されたものが無視される性向(性質の傾向)
有用と見なされないもの(広告)は全て無視し、自分の目標達成に役立つもののデザインパターンを探す傾向がある
テスラーの法則

どんなシステムにも、それ以上減らすことのできない複雑さがある。
複雑性保存の法則ともいう
どんなプロセスにも、その核となる部分にはデザインの工夫を持ってしても取り除くことのできない複雑性を抱えている。この複雑性による負荷を負うのは、システムかユーザだ
固有の複雑性をデザインと開発の過程でどうにかしながら、できる限りユーザの負荷を減らす
これ以上減らせず何処かにシワ寄せが必ずある(デザイナーかエンジニアか)
シンプルにしすぎてインターフェースが抽象的になりすぎていないかを気にする
知っておきたいUI/UXデザインの法則17選
どれだけプロセスがシンプルにできたとしても、プロセス全体としては何処かに取り除けない固有の複雑性が存在していることを認識しなければならない
ドハティのしきい値
応答が0.4秒以内の時、コンピュータとユーザの双方が最も生産的になる
システムのパフォーマンス(応答時間)は優れたユーザ体験を届ける上で欠かせない
0.4秒以内にフィードバックを行うことで、ユーザの注意を引きつけ、生産性を高める
体感性能を改善し、感じられる待ち時間を減らす
アニメーションを入れることで、バックグラウンドで読みこみや処理が行われている間も、ユーザを繋ぎ止められる
プログレスバーは、正確であってもなくても待ち時間へ苛立ちを和らげる
ほとんど処理時間がかかっていない場合でも、意図的に遅延させることで体感性能が改善して信頼感の醸成に繋がる。
プログレスバーとは?活用方法や使い分けについて解説! | JetB株式会社
0.1秒程度の応答時間であればほとんど気づかない。しかし、0.1〜0.3秒の遅延になると目につくようになる。1秒を超えるとユーザはタスク以外のことを考え始める。
⇨注意散漫になり、タスクを実行する上での重要な情報はユーザの頭から抜け落ちる
結果として、タスクを続けるための認知的負荷が高まり、全体をしてユーザ体験が損なわれる
ブラーアップ
最初に極小サイズの画像を読み込んでおき、より大きな画像が読み込まれたらそれを置き換える。
ブラーを用いたサイトを見つけたので共有します。
今回紹介したのは、複数あるUXデザインにおける法則のうち、代表的なデザインの法則。デザインを学んでいくと心理学に精通していることがよくわかります。対ユーザーにアプローチを行う生業として避けては通れない分野であるので今のうちに知ることができてよかったです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
