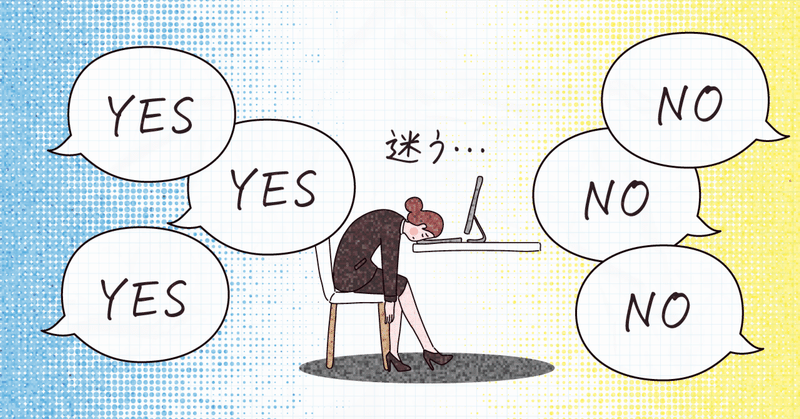
ビジネスでは、相手の期待する正解を探そうとしちゃダメ。
最近、社内外でセミナーや1on1をやっていて思った事です。
ある事象に対して「それってどうしてだと思う」「どう対応すべきかな」ってOJTやミーティング、ディスカッションの時に聞かれる事はありませんか?
普通は自分なりに理由や原因を考えたり、自分の経験から思いつく最善策を答えたりするかと思います。
ところが、時々時間をかけても発言ができない人がいて、なぜそんなに長い時間考えるのか?なぜ発言ができないのか?を尋ねてみたところ「質問している人はどういう回答を求めているのかを考えると、どうしても時間がかかってしまう」「質問している人がどう答えて欲しいのかがわからない」と答えてくれたことがありました。
つまり「質問をしている人はその質問に対する正解を知っている」そしていま自分には「その正解をみつけることが問われている」のだと。
この方は、おそらく学生時代の成績はとても優秀な方で、何か正解があるときにはその正解を的確に答えることができる方だったのではないかと思います。
しかし、当社のようなマーケティング会社をはじめ、多くのビジネスのシーンで意見を求められている、対応施策を検討している、等の判断をする等の場合には相手の求める正解を探そうとする事はしちゃダメなんです。
そもそも仕事には正解なんてないのです。
いくら正解を探したって問いをした相手もわかりませんし、自分の考えと同じ回答をもらっても大体がっかりされるだけです。だって、相手はわからないから聞いているのだし、自分の考えを遙かに超えるような素晴らしいアイディを求めていたりするのです。自分が考えている事を同じことばかりが返ってくると、もうあなたには何も求めず期待しないようになってしまいます。
現在のように変化が早く不確実性の高い世の中で「正解」を探そうとする行為に全く意味はありません。
学生時代は、何かの問いに対して教科書な立場や常識の中で最も確からしい事を探す(正解を出す)ことが求められてきました。これは、教科書的な知識や常識を判断基準にすればある程度の正しいと言われる判断にたどり着くという、ある意味でのトレーニングだったといえます。入試問題を解くときにも先生からは「正しい答えを出すためには出題者の意図を汲んで…」言われる続けていたかと思います。
ですので先出の方は教科書や常識の範囲で正解を見つけるのは得意だったものの、今はその判断の基準がわからなくなってしまい「質問者の求めているものは何か」といった判断基準を持ち始めてしまうという沼に落ちてしまったのではないでしょうか。
実はこうなるとビジネスの現場では「自分のアイディアをもたず、言われたことだけをやるだけの作業員」という風に思われてしまうのです。
ビジネスの最前線では学生時代とはまた異なる考え方や行動の判断基準が必要になってきます。
まずは判断に必要な知識取得をする必要があります。自分たちのいる会社のことや業界、取り扱っている商品やサービスの知識、社会環境や取引先の知識を得ていくという事は必要不可欠なことです。いわゆる常識と言われるものも、会社や業界によって異なってきますので、学校で学ぶモノやアカデミックな内容だけでは当然足りなくなります。ただ、このあたりの知識は会社の中や業界に所属していれば、経験を踏んでいけば研修や業務を通じて身につけていくことは出来るでしょう。
それに加えてもう一つ会社という仕事場コミュニティに所属する人として判断をしていくにあたって規範として必ず照らしてもらいたい事があります。
それがあなた自身が所属している企業や組織の理念、ビジョン・ミッション・パーパス、行動規範と言われるものです。
たとえば、ディズニーランドでは、
「私はディズニーランドが、幸福を感じてもらえる場所、大人も子供も、ともに生命の驚異や冒険を体験し、楽しい思い出を作ってもらえるような場所であってほしいと願っています」
というウォルト・ディズニーの言葉があります。
そしてそこで働く人の行動規範としては、「We Create Happiness ハピネスの創造」を実現するために、ディズニーテーマパーク共通の「The Five Keys~5つの鍵~」というものがあり、Safety(安全)、Courtesy(礼儀正しさ)、Inclusion(インクルージョン)、Show(ショー)、Efficiency(効率)という5つの行動基準を設けられています。(https://www.olc.co.jp/ja/tdr/profile/tdl/philosophy.html)
つまりディズニーランドで働く人達は、何か疑問や問いかけ、依頼が成されたときにこの考え方や行動規範に沿って、自らの考えで誰かの指示を待つことなく行動しているということなのです。そしてそれは、疑問や問いかけ、依頼が成されたときに、その疑問や問いかけをした人がどうして欲しいか、どう答えて良いかを察することではなく、行動規範に沿って自らが行動しているのです。
「決して、問や問いかけをした人がどうして欲しいか、どう答えて良いかを察することが正解ではない」のです。
多くの会社では、そこまでかっちりとした言葉になっているケースばかりではないかもしれません。
実は当社でもかっちりと明文化されていたり、社長に室に飾ってあったり笑、webサイトに記載されているわけではないのですが、当社でよく言われている事があります。それは
・5は目標管理をする会社である
・5は顧客をリードする会社である
・5は叡智のハブになる会社である
といった事です。
実はこれが、メンバーにとっては考え方や行動の判断基準なのです。
そして、これらに沿った判断や行動ができていれば経営とほぼ同レベルでの判断ができるとみなされるようになります。もちろん経験値や知識水準が異なりますので全ての権限が委譲されるわけではありませんが、少なくとも経営が不在に場合でも判断が大きくブレることはないでしょう。
ですので、何か行動をする時、何か判断をする時、何か発言をするときには
「それって、”目標を管理する会社”としてどうなの?」
「それって、”顧客をリードする会社”としてどうなの?」
「それって、”叡智にハブになる会社”としてどうなの?」
と自問自答をしてから、判断・行動をするようにしてみてくださいと常に説明をしています。
おそらくこれを読んでいる皆さんの所属する企業や組織にも、理念、ビジョン・ミッション・パーパス、行動規範が存在しているはずです。それに基づいた行動をおこなっていただければ、おそらく相手が発した質問や依頼以上の内容の何かを返すことが出来るようになるでしょう。
もちろん、最初は考えたことが合っているのかどうか、適しているかどうかが不安かと思います。でもその時には勇気を持って上長に対して「(会社の理念に照らして)こうしたいのですが、良いですか?」と疑問を投げかけてください。そりゃ適当に答えちゃダメですよ、必ず(私は会社の理念に照らしてこう考えた)というのが必要です。
そんなやりとりを続けていくと、上司もきちんとあなたの考えたことを評価してくれるようになります。そうなると「自分のアイディアをもたず、言われたことだけをやるだけの作業員」から脱却して、よりビジネスの現場でも活躍することが出来ることでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
