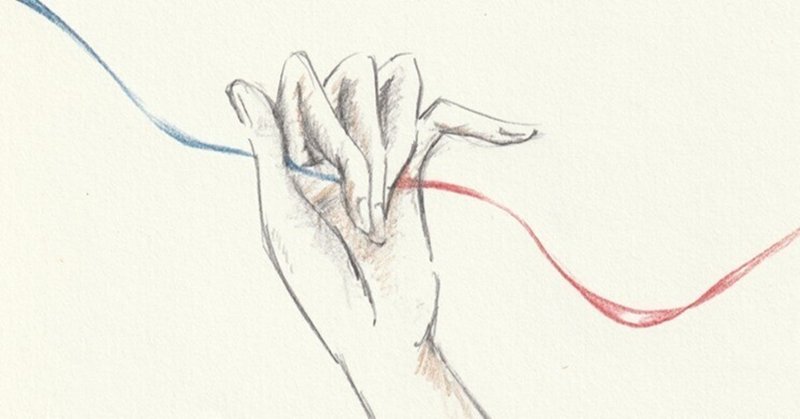
その名はカフカ Disonance 18
2014年9月ビュク
オーストリアとの国境まで僅か十キロメートルほどしか離れていないハンガリーの街ビュクが温泉地として知られるようになったのは、まだ半世紀ほど前のことだ。今では「Bükfürdő」の名で知られるこの地の温泉は、療養や休養を目的にやって来る多くの人で賑わう温泉リゾートとなっている。
高級ホテルに隣接する温泉水に満たされた大型プールの中ではしゃぐ観光客たちを白けた顔で眺めながら、アダムはプールサイドの日陰に設置されたビーチチェアに跨るように座っていた。
「やあ、待たせたね」
と背後からヴァレンティンの声が聞こえたが、アダムは振り向きもせず
「俺たちにとって史上最大と言っても過言ではないくらいの一大イベントが控えている時に、なんでお前はこんな浮かれた待機場所を選ぶんだ?」
と返した。
ヴァレンティンはアダムの隣に腰を下ろしながら
「イベント会場まで近いからさ。それに、これだけお客を集めているリゾートなんだ、ホテルは充実している。大事な仕事を任せる君たちに、せめて宿泊に関しては不自由な思いをしてほしくないと思ってね」
と言い、
「それから、これは余談なんだが、君の愛しいハルトマノヴァーは、どうも変なおじさんに気に入られてしまったようだ」
と笑った。
「なんだ、それは?」
「おじさんを魅了するためには愛想よくしている必要も、美人である必要もないらしい」
「なにげに失礼な発言だな」
「その変なおじさんの大切なものが、今この街に滞在中らしいんだ」
「訳が分からん」
「灯台下暗し。その変なおじさんも、まさかこんなところにハルトマノヴァーが現れるとは思ってもみなかったらしく、今回は僕たちに関わろうとはしていないようだ」
アダムはヴァレンティンのほうを横目で見た。
「つまり、サシャの国境越えには関係ない話なんだな?なんで今この時に、そのような余計な話をする?」
「今後のためさ。君はくだらない世間話というのが本当に嫌いだねえ。ティーナやカーロイだったら、こういう話には食いつくのになあ」
「今はそういう話をしている場合じゃないだろ。本題に行け、本題に」
ヴァレンティンは鼻でふっと笑うと、それまでプールのほうへ向けていた視線をアダムのほうへ動かした。
「焦りは禁物だ。気が焦っていたり不安を感じていると、うまく行くものもうまく行かなくなってしまう。今更君に言うことではないとは思うけど」
「焦るも何も、もう十二時間後の話だろう」
「ハルトマノヴァーは予定通りこっちに向かっているかい?」
「ああ、昨日エミルにウィーンまで迎えに行かせたから、数時間前に一緒に出たはずだ。もうすぐ到着するだろう」
「彼女が到着したら、出発の時間まで思い残すことがないくらい存分に可愛がってあげてくれたまえ」
「……どういうことだ」
「明日の明け方、イベント会場は二つになる。ハルトマノヴァーは、サシャの国境越えには向かわず、別の場所に悪魔退治に行く。君はサシャの援護に向かってくれ。悪魔の位置は僕が把握しているから、ハルトマノヴァーは僕が連れて行く」
アダムはヴァレンティンのほうへ顔を向け、ヴァレンティンの目を見据えた。ヴァレンティンもアダムのほうを見てうっすら笑っているが、ふざけているようには見えなかった。
「なぜ、俺がレンカと一緒に行ってはいけないんだ?」
「君には無理だからだ、彼女を一人で外に放り出すっていう行為が。君がついて行ったら、きっと今まで通り彼女の隣に立って、相手が下手な動きをしようものなら一捻りに潰してやろうって顔で構えてしまうだろう」
「それの何がいけない?」
「これは、彼女の仕事だ。僕たちの、顔としての」
アダムはヴァレンティンの顔から目を逸らすと、眉間に皺を寄せたまま再びプールのほうへ顔を向けた。ヴァレンティンはアダムの顔を観察しながら、話を続けた。
「君にはサシャがカーロイと一緒にビュク近郊に到着したら、そこからオーストリアに入ってハルトマンからの一行にサシャを引き渡すまでの援護を頼む。その後はティーナが付く」
「ティーナは、来れるのか」
アダムの言葉に、ヴァレンティンは肩をすくめた。
「本人が来るって言うんだ。確かに、オーストリア国内での君の強みは主にハルトマンとの繋がりだから、一行と合流してしまえば、ティーナと交代したところで大差はない」
ヴァレンティンはそこまで言って一旦言葉を切ると、プールの方向へ顔を向け、プールの上の晴れ渡った空を見上げた。
「ティーナと交代したら、ここに戻って待っていてくれ。こちらの方が、先に終わる可能性もあるが。ハルトマノヴァーは、無事に返すと約束するよ。僕が今まで君との約束を守らなかったことがあるかい?ないだろう?」
「お前はそもそも約束をしたこと自体があまりないだろうが」
そう言うと、アダムは再びヴァレンティンのほうへ顔を向け、
「なあ、お前はなんでレンカを名字で呼び続けるんだ?嫌味のつもりか?」
と尋ねた。ヴァレンティンは、空を見上げたまま
「君は、彼女も僕のことを名前で呼ぼうとしない事実に気が付いているかい?」
と言った。アダムが
「それは、知らん」
と答えると、ヴァレンティンは
「もしハルトマノヴァーが僕のことを名前で呼んでくれるようになったら、僕のほうも彼女の呼び方を考えてあげてもいい」
と言って笑った。アダムは
「お前ら、そういう変に意地っ張りなところが似てるな」
と呆れたように言った。
ヴァレンティンは笑顔のまま立ち上がり
「そろそろハルトマノヴァーが到着する頃じゃないか。迎えに来る前に電話すると伝えてくれ。その際、彼女のITスナイパー君の身の振り方にも指示を出す。……まったく、君たちは一人の人間にどれだけの役割を押し付けているんだろう」
と言うと、その場を後にした。
アダムはヴァレンティンには既に聞こえないと理解しつつも
「それだけあいつは優秀なんだ、しょうがないじゃないか」
とつぶやいた。それとほぼ同時に、ヴァレンティンが去って行ったのとは逆の方向からレンカとエミルが近づいてくるのに気が付いた。
レンカはアダムを見つけると、満面の笑みを浮かべ、歩調を速めた。アダムは、この数ヶ月でレンカが感情を素直に表に出すようになったことは喜ばしいとは思ってはいたが、それと同時に少し戸惑ってもいた。どこでも誰に対してもこれでは、場合によっては問題だよな、そんなことを考えながら、アダムは立ち上がりもせず、二人が傍に来るのを待った。
レンカはアダムの前まで来るとしゃがみこんでアダムの膝に両肘を置き、アダムの顔を下から覗き込んだ。アダムはまず「お前は犬か」と言いそうになり、それから「家の中じゃないんだ、ちゃんと椅子に座れ」と注意したほうがいいのか、と迷ったが、「ああ、こいつはサシャが無事ここまで辿り着いたことが嬉しくてしょうがないんだな」と思い至り、何も言わなかった。
レンカは笑顔のまま
「あと一息ね」
と言った。アダムは「その一息が、けっこう重そうなんだがな」と思いながら
「ウィーンでの交渉は全部予定通り終わったんだな?」
と聞いた。
「ええ。クレイツァル弁護士も、ほとんど初めて話したけど、すごくいい人だったわ。打っておくべき手は全部打って手配してくれて、私は単にお願いに顔を出しただけ」
「その顔を出すっていうのが、お前の大事な役目だろう」
「そうね、顔と名前だけでも、役に立てて良かったわ」
「そういうつもりで言ったんじゃない」
アダムのいつになく強い語調に、レンカは少し驚いた顔をしてアダムの目を見つめ直した。
「どうしたの?最後まで問題なく運ぶか、心配なの?」
そう言うと、レンカは右手を伸ばしてビーチチェアの隣のテーブルの端に置かれているアダムの左手を握った。そして
「まるで私がアダムを励ましてるみたい。こんなの初めて」
と言って、また笑った。アダムは「自分でも気が付かないうちに明日のことで神経質になっているのかもな」と思い、無表情のまま、自分の手を握っているレンカの右手を親指で撫でた。
暫く黙って二人の様子を眺めていたエミルは
「とりあえず、中に入りませんか?部屋はもう用意されてるんですよね?」
と言って、肩越しに右手の親指で背後にそびえ立つホテルのほうを指し示した。
アダムはエミルのほうへ顔を上げると
「そうだな、休めるうちに休んでおいたほうがいい」
と答えて、まずレンカの両手を掴んで立ち上がらせてから、自身も腰を上げ、ホテルに向かって歩き出した。
レンカはアダムの隣に並んで歩きながら
「ボスは来たの?」
と聞いた。
アダムは「あいつの言ってたことは本当だな」と思いながら
「なんだ、その『ボス』っていうのは」
と返した。
「だって、私には『貴公子』も『エフ』も使いづらいのよ、何だか、上から話してる感じがして」
「あいつには普通に名前があるじゃないか」
「……サシャは、あの人にどんなあだ名を使ってるのかしら」
「それはサシャに聞け。きっとお前は怒り出すだろう」
「そうなの?どうして?」
「お前なら、ヴァレンティンにはもったいないと言いそうだ」
「なんだか、すごく気になるわ。教えてくれないの?」
「だから、サシャに聞けと言っている」
アダムの言葉に、レンカは微笑むと
「もうすぐ、会えるね」
と嬉しそうに言った。そこで初めて、アダムはヴァレンティンがまだレンカに明日の計画を具体的に知らせていないことに気が付いた。つまり、俺から話せと言いたかったわけか、とアダムは心の中で大きなため息をついた。
アダムは
「ああ、もう少しの辛抱だ」
とだけ言うと、ホテルのエントランスに足を踏み入れた。アダムは、これまた煌びやかなインテリアだな、どうしてこう小洒落た趣味の奴ばかりに囲まれる人生を歩むことになったのか、という思いにしばし囚われた。それから、隣にいるレンカと半歩後ろを歩くエミルを見て、二人にはこの内装が好印象らしいことを見てとると、「こいつらが嬉しそうな顔をしてくれるのなら、これでいいということなんだろう」と思い直した。

【地図】

🦖🦕🦖🦕
