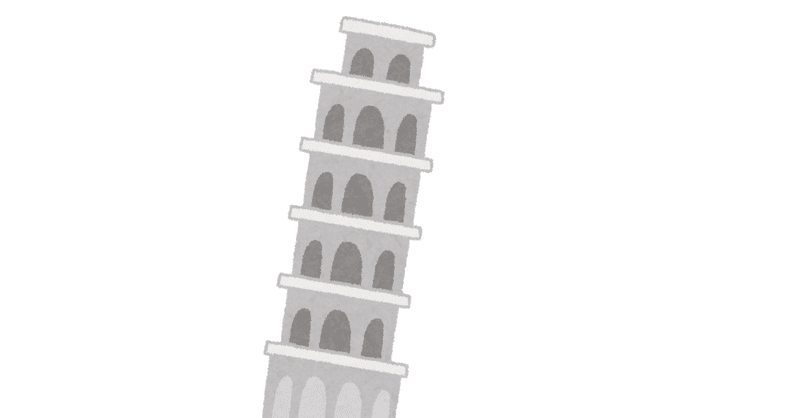
完成されたものは変わらない
突然ですが皆さん、『キャリバー50』というものをご存知でしょうか?
正式にはブローニングM2重機関銃と言います。
「え、何この人急に銃の話なんか始めたんだけどこわ…」
という人も引かずに少しお付き合いいただきたいです。
今回はタイトルの通り、完成されたものは変わらないという話をしたいと思います。
最近の技術進歩はすさまじく、あらゆる分野がデジタル化しており、もはやITを利用することがビジネスの前提となっております。
そんな昨今の風潮もどこ吹く風で存在しているのが前述したM2です。
基本設計は80年以上前に完成しており、いまだ現役で採用されているすごい奴です。工業製品の完成形の一つと言えると思います。
太陽光発電における「完成形」は何か?
さて、ここから本題に入っていきたいと思います。
日本の太陽光発電で、「完成している」ものは存在するのでしょうか?
発電所の構成要素ごとに分けて考えてみたいと思います。
・ソーラーパネル
・パワーコンディショナー
・ケーブル類
・蓄電池
・送電網
・架台
以上の6項目についてです。
ソーラーパネル
ソーラーパネルは完成しているか?というと答えはNoです。
これは決してネガティブなNoではなく「日進月歩で技術革新が起きている」という意味です。これから更に高効率、省コストで長寿命かつリサイクル性が向上したソーラーパネルが登場することは確実かと思います。
パワーコンディショナー
パワーコンディショナーは太陽光発電所において最も故障が起こりやすい部分です。もちろんパネルなどもメンテナンスフリーではないですが、より注意が必要な部分でしょう。
ケーブル類
ケーブルは太陽光発電所において、かなり完成している部分だと思います。価格と伝導率を考えると銅ケーブルが最善ですが、気になるのは昨今の銅価格の高騰です。そこで、主にアルミケーブルを使用して、幹線は銅ケーブルを使用するなど、運用に工夫の余地があるのではないかと思います。
蓄電池
蓄電池は太陽光発電所において必須の要素ではありませんが、個人的には「今後必須になる」と考えています。特に九州では既に天候や需要の関係で出力制限がかかるようになり、他の地域でも同様の問題が発生するのは時間の問題かと思います。蓄電池を設置することによって、作りすぎた電気は貯めておき、必要な時に系統に流すといったことが可能になります。これにより、太陽光発電の不安定さ、特に夜間全く発電に貢献できない問題が幾分解決するものと思います。しかし、蓄電池のコストや安全性の問題、メンテナンスの必要が生じるので、制度設計も含めて課題が山積みです。
送電網
電力の需給バランスは同時同量が基本なので、必要な電力を需要地に届けるために送電網は欠かせないものになります。そして、地域間での電力の融通を大幅に強化するというニュースが最近話題になっていました。
私は素人なので、最近のニュースを見て国が急に脱炭素社会に舵を切ったかのように感じていましたが、経産省の資料を見るに結構前から検討が進んでいたようです。( ↓ 経済産業省、資源エネルギー庁の資料 )
私の個人的な予想もとい妄想では、
『日本の最も優れた点は全国津々浦々まで張り巡らされたインフラ網、特に電力インフラが充実していることだが、少子高齢化が進み地方が衰退するにしたがって送電網が維持できなくなり、地方からオフグリッド、マイクログリッド化が加速する』
と考えておりましたが、どうもそうはならず、逆に送電網を強化することによって、不安定になりがちな再エネを日本中で融通しあう方針のようです。これは高度な天候の予想や情報ネットワークによって可能になる…のでしょう。今後の進展に目が離せない分野ですね。
架台
さて、最後に架台です。個人的には架台は完成に近いものが作れると考えています。【完成している】ではないところに引っかかる方がいらっしゃるかと思いますが、現行制度においては、架台は完成させてはいけない場合があります。特に、ソーラーシェアリングに関してはそういった側面が強いと感じています。
何をもって完成した架台と言えるのか?ですが、基本的に構造物の土台は堅牢であるほど台風や地震に強くなります。(不同沈下に注意が必要ですが)また、最初期に過剰性能なくらいで設計していた方が、経年劣化した際にも十分な性能を維持でき、長期にわたって使用が可能となるでしょう。
架台は完成させてはいけない、というのは、原状回復が容易に行えることが設置の条件であることがままあるからです。借地に野立てを建てたり、ソーラーシェアリング用の一時転用などですね。
これは悪いと言っているのではなく、20年の固定買取を終えた後に発電事業の採算が合わないとなれば、容易に撤去できて土地は別用途に利用したほうが合理的です。慈善事業ではないのですから、20年必要十分な強度を維持できるラインであれば、なるべく初期コストを抑えた方が利益を得られます。
ここからはあくまで私の考えた完成形ですが…
20年とは言わず40年、更にその先までを見越して土地の造成を行い、堅牢な架台を作りパネルなどは更新しやすい立体的設計にする。パネルの下部空間にバッテリー設備やソーラーシェアリング、植物工場などを設ける…電気が不要になる未来は恐らくないでしょうから、超長期の運用であれば投入コストをペイしつつ、日本の重要なエネルギー・食料拠点として機能する設備ができるのではないでしょうか。
誰が作るのか
さて、私なりに調べたことをまとめてみたつもりですが、残念なことに私は
『今まで書いた内容について一切寄与できません』
私は社会においてミジンコのポジションですし、極端な話、明日心停止した状態で見つかる可能性もあります。40年以上の先を見越したプロジェクトは個人では難しい。ですので他力本願で申し訳ないですが…
偉い人が予算を付けて、すごい人たちが知識・技術の粋を集めた設備をば(できれば鹿児島に)ドーンと建てていただきたい。私は3月に福島を訪れた際に「福島イノベーション・コースト構想」のパンフレットを頂いてきましたが、『この国はこうやって良くなる』というビジョンを体現したものを、各地方になじむ形で整備していただけると非常に助かります。
「これがこれからの日本なんだな~」と、見学しに行きたいです。なんとも他力本願な話ですが。私にできないことは、できる方々にしていただく他ないので、偉い人、何卒よろしくお願いします。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
