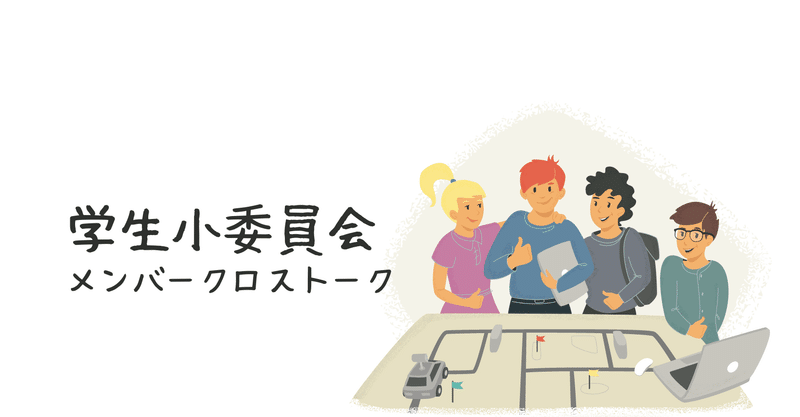
第1回!学生小委員会メンバー クロストーク
こんにちは!土木学会学生小委員会の北海道大4年・佐瀬です。
小委員会のメンバー3人で話す場があったので、クロストークと称し、今回はその内容について記事にしてみることにしました。
会話を文字に起こしたものなのでやや長いですが、最後まで読んでいただけると嬉しいです!
登場人物:土木学会学生小委員会のメンバーのうち3人でお話ししました。
・志賀さん (横浜国立大)
・村中さん (富山大)
・佐瀬(北海道大)
① なぜ土木を選んだ?
佐瀬)皆さんはなぜ土木を選んだんですか?ちなみに私は、家の近くにダムがあったことがきっかけで土木っていうものを知って、土木のスケールが大きい仕事に憧れをもって。中学生の時から土木かっこいいな~って思うようになり、そのまま今に至ります(笑)
志賀)土木を選んだ理由は大きく2つあるのですが、一つ目は父がハウスメーカーに勤めていて、構造物に興味があって、人の役に立つものを造りたいと思ったから。二つ目は福島県で東日本大震災を経験し、沿岸地域でほぼすべての家が流されてしまって。僕は家よりももっとスケールの大きい土木というアプローチで人々の生活を支えたいと思ったんです。村中さんはどうして土木に?
村中)僕は中学高校の時から「架空都市」に興味があって都市全体を作るのが好きで、よく授業中に内職していろいろ作ってました(笑)自分の大学、学科は土木や建築、情報系など色んな教授が集まってできた新規学部で、様々なことに又実務に近いところに触れられると思ってこの土木系の学部に来ました。
佐瀬)そうなんですね。実際土木にきてみてどうですか?
村中)先日公務員試験を受けてきたのですが、他の職種と一緒に受けていて土木系の受験生だけ試験時間が圧倒的に長くて、土木って守備範囲が広すぎてやることが多いなって思います(笑)
佐瀬)たしかに大学のカリキュラムの幅広さは土木の特徴ですよね。その大変さはあると思います。
② 土木の魅力を伝えるには?
志賀)土木の魅力を一言で言うのって難しいですよね。社会貢献度の非常に高い仕事を土木が担っているのは間違いない。でもそんな土木の魅力をどう伝えるかって難しいと思います。
佐瀬)橋とかダムとかっていう土木構造物はあるのが当たり前すぎて、土木の役割を改めて考える機会って少ないですよね。あと土木って建築系と比べると意匠のイメージが強くない。土木は一人の名前が表に出てきて、この作品どうだー!っていう感じではないですよね。
志賀)土木は対象が多いので、これ!っていう特定のものがすぐに思い浮かびにくいことも、土木の魅力を発信していくときに何を前面に押し出すのが良いのかわかりにくいことに繋がっているかもしれないですね。今後この学生小委員会も土木の魅力を伝える一助になれればいいですよね!
③ 「学生の交流」の目指す姿とは?
志賀)大学間での交流はやっていこうとしているけれど、自分の大学内での交流って多いですか?大学間で交流をするのも大事だけど、まず自分の大学のなかで交流の場が増えると良いですよね。
佐瀬)たしかに。
志賀)自分の大学では研究室が大きな括りで5つしかなくて、交流はしやすいのですが。
村中)自分の大学では同じ学科でも、そもそも研究室が入っている棟が違ったりしていて、研究室間での交流はし辛いかもしれないなと思います。そういう意味ではこの学生小委員会のようなオンラインでの交流の場が活発になっていけばいいなと。もちろん他大学に目を向けるだけでなく、まずは同じ大学の中での交流も大切にすべきだと思いますし、そのやり方も柔軟に考えていきたいですね。
佐瀬)交流の場に、いかに自大学内外の人を巻き込めるかが大事ですね。
志賀)交流会の開催に向けて、早速動き出していきましょう。
~座談会おわり~
本当はこれ以外にも色々な話をしたのですが今回はこの辺で。
違う大学に通う、バックグラウンドの違う学生と話してみると、同じ土木を学ぶ学生でも普段自分が考えないような切り口の話が聞けるので、とても刺激的です。
今後の私たちの活動にご期待ください!
