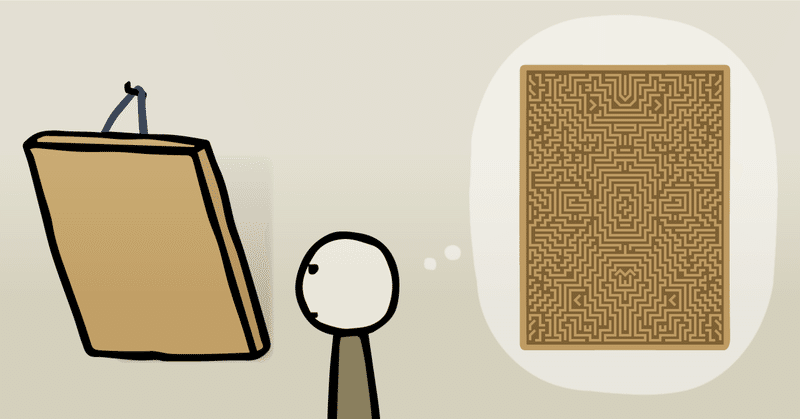
創造と発生のあいだ―「豊嶋康子 発生法─天地左右の裏表」
先日、東京都現代美術館で開催中の豊嶋康子の大規模個展「発生法─天地左右の裏表」を見た。初期作品から新作までおよそ500点にのぼる膨大な作品が、時系列にこだわらないかたちでひとつのインスタレーションとして展開されている。作家の全貌を掴むには絶好の機会で、新たな発見や気付きもあった。印象に残る展覧会だったと思うのと同時に、しかし違和感が残る部分もあった。そのことについて考えてみたい。
「創造」と「生成」と「発生」
東京都現代美術館では豊嶋康子展と同時にMOTアニュアル2023も開催されていて、こちらも同じ日に鑑賞した。今年のMOTアニュアルはメディアアートがテーマで、タイトルは「シナジー、創造と生成のあいだ」。各出品作家に「創造」と「生成」の違いについて質問し、その回答が展示のなかで紹介されている。確かに「生成」は、生成AIを始め、ジェネラティブ・アート、人工生命など、現在のメディアアートの潮流を表すのにうってつけのキーワードのように思われる。
では「生成」は「創造」と、なにが異なるのか? 自分なりに考えてみるに、「生成」は「創造」に比べ、何かが作られる(生まれる)その仕組み自体に比重が置かれる言葉のように思われる。メディアアートで「生成」がテーマとなる場合、生成を可能にする仕組み自体、すなわち生成AIならばAI、ジェネラティブ・アートならばコード、人工生命ならばそれを可能にするハードやソフトウェアの存在が意識されるだろう。その生成を自らの表現とする作者がいるとすれば、それはその仕組みを作った者やその仕組みを巧みに利用した者であるということになる。それに対して「創造」の作者はより直截的だ。創造されたものを作った存在こそが作者なのである。「生成」のように中間的な存在を中に挟まない。しかしそのぶん「創造」は、「生成」に比べると創造を可能にする仕組み自体はブラックボックス化されているように思われる。天地創造の主体が「神」であるように、創造行為の主体ははっきりしていても、それを可能にするシステムは謎に包まれており、神秘的な雰囲気が付きまとっている。
MOTアニュアルの「創造と生成」に対して、豊嶋康子展は「発生法」をタイトルとして戴いている。「創造」と違って「発生」は行為主体の存在を感じさせない言葉だ。「自然発生」のように無から何かが生じてくるというイメージがある。「生成」と違って、発生のためのメカニズムを考案したり、人為的にそのシステムを構築するというイメージも(とくに芸術表現の場においては)薄い。どちらかといえば「発生」とは自然に何かが起こったり、生じたりするというイメージが強く、行為主体の人格的な存在やそのメカニズムの神秘性といったものとは無縁である。そのため、芸術制作の場で「発生」の語を使うことは稀だが、こと豊嶋康子の作品に関しては、「創造」や「生成」よりも「発生」の語こそが相応しいことが本展を見るとわかる。
たとえば展覧会冒頭に展示されている《ジグソーパズル》(1994年)。既製品のジグソーパズルを無作為に手に取った順に横に繋いでいき、展示室の壁面に「線」を描く作品だ。そのルールが「創造」の作為性を排除しているのは勿論、それを「生成」のためのシステムと呼ぶにはあまりに単純な仕組みである。行為だけ見れば、むしろ「やってみた」に近い。やってみた結果、このようなジグソーパズルでできた「線」が発生しているのだ。
あるいは同じ展示室に展示されている《サイコロ》(1993年)。作者が振ったサイコロが、振られて転がったその状態で展示されているだけ、という作品だ。会場で配布されたリーフレットには「片手に一握り、箱ごと一気に、アンダースローで、など私が決めたさまざまな振り方によってサイコロの目が出る」という作者による作品解説が掲載されているが、これがナンセンスであることは言うまでもない。どんな振り方をしようともサイコロの目の出方は偶然性によって支配されており、そうでなければサイコロとしての用をなさない。つまりこの作品において作者はあくまで創造主体として振る舞っているが、その結果としての表現物=振られたサイコロの状態は、「創造されたもの」や「生成されたもの」よりも、偶然「発生したもの」と表現するのが相応しいのである。
創造の神秘性を忌避するストイシズムと「私」
このように豊嶋の作品では既存の「創造」における作者の主体性やそれに伴う神秘性が頑なに否定される。表現された結果に対して作者の造形的な意志は可能な限り排除され、創造のメカニズムも限りなくプレーンで単純明快である。芸術表現にありがちな創造の神秘性は微塵もない。
しかし、それと矛盾するようであるが、豊嶋の作品においては表現主体である「私」の存在がなによりも重要となる。豊嶋の「私」に対するこだわりはほとんど偏執的と言っていいほどだ。たとえば受け取った郵便物に書かれた自分の名前(「豊嶋康子」)の部分だけを切り抜いてコラージュした作品《書体》(1999)、小学校から高校までの自身の通知表を展示した《発生法2(通知表)》(1998年)、これまで受け取った表彰状や卒業証書などを一堂に集めた《発生法2(表彰状コレクション)》(1998年)など、「豊嶋康子」として社会的に規定された「私」の客観証拠を執拗に作品として提示する。銀行口座の開設や生命保険への加入を扱った作品でも、展示されるキャッシュカードや通帳、保険証書などに記載される作者自身の名前がなによりも重要なのだと思われる。
《書体》において受け取った郵便物の宛名を書いたのは作者以外の他人であり、書体を「表現」として見るならば、この作品における表現主体は豊嶋ではない。私が表現したものと言うよりも、「私」を表現したものなのである。《通知表》や《表彰状コレクション》も同じだ。私が表現したものが「私」を表すというのが旧来の芸術表現における理解だが、豊嶋はその安直な構図をきっぱりと拒否する。展覧会に合わせて発表されたインタビューのなかで豊嶋は、学生時代にきちんとわかってもいないのに描けてしまった抽象表現主義風の絵が安易に評価されることへの疑いがあり、それが現在のコンセプチュアルな作風への転換とつながっているという話をしている。言い換えればそれは芸術表現=「創造」の神秘性に対する懐疑であり、その否定からこそ彼女の制作はスタートしているのだと言える。
豊嶋の作品における「私」=行為者は、一見すると代替可能なもののようにも思われる。豊嶋が考案したコンセプトこそが作品の主眼であり、行為者は誰でもいいという考え方だ。しかし自分はその見方を採らない。代替可能な存在でありつつも、それが唯一性を持った「私」であることが重要であると考えるからだ。豊嶋の作品における「私」の唯一性は戸籍に記載された「私」の唯一性に等しい。旧来の芸術表現であれば、そのことはネガティヴに捉えられるべきことだった。他者が強制的に規定した「私」以外に、もっと自分自身の生の感覚に近い「ほんとうの私」あるはずだという考えが、創造物の中に表現者の内面や「私」が表されているという思想へと繋がる。しかしその神秘性を忌避する豊嶋は、その代わりにこれまで否定的に扱われてきた社会的に規定される所与の「私」こそを肯定し、その唯一性を称揚しようとしているのではないだろうか。通知表で評価される「私」は一教師からの見方に過ぎず、「私」のことをもっとずっとよく知っている私自身の実感とは大きく異なる。しかしそれはこの世界における「私」を構成する一要素であり、そうやって構成される「私」(つまり発生した「私」)も、やはりこの世界においては代替不能で唯一の「私」なのである。それは創造物に表現者の内面が反映されるというような曖昧で神秘的な「私」よりも、ずっと客観的で確かな「私」なのだ。
それ故に、豊嶋の作品における行為者=作者は複雑な立場をとる。たとえば先に挙げた《サイコロ》を美術館でコレクションするとして、果たしてこの作品の作者の没後展示は可能だろうか? コンセプチュアル・アートによくあるように作者によるインストラクションだけを収蔵して、展示のたびに作者以外の誰かがサイコロを振ればいい…というものではないように思われる。この作品においてサイコロを振るのは、あくまで作者=豊嶋本人であることが重要なのではないか。だからこそ作品解説の中に「私が決めたさまざまな振り方で…」とわざわざ「私」という主語を登場させ、作者=行為者の「自由意志」を強調しているのだ。かと言って、作者が振った状態を固定してそのまま保存しておくというのも、それはそれでこの作品の主旨からは外れてしまうだろう。《サイコロ》は「創造」の神秘性を徹底的に無効化した作品だが、作者自身が振った状態を特別視し、保存し崇め奉るような在り方は、むしろ旧来の神秘化された創造における作者像に近くなってしまう。それは豊嶋の作品における作者=「私」の在り方の微妙さを損なうことになるだろう。
ちなみに自分は表現されたもののなかに表現した者の「私」が表れるという「旧い」創造観の持ち主なので、そんな豊嶋の作品においても、作者の厳しい抑制の間隙から垣間見える(と感じる)「私」の存在に敏感に反応してしまう。今回初めて見た作品のなかで自分が好きだったのは絵画作品の《色調補正2》(2005年)だ。この作品は色面で構成された抽象絵画を色ガラスの付いた額に入れ、それを別のキャンバスに色ガラス越しに混色して見えた状態のまま模写した作品である。同じように見える二枚の絵が、実は異なる仕組みで色が表れているというのが制作の主旨なのだが、なによりも自分はそこにそのシステムに則って「絵を描いている」豊嶋の存在を感じて嬉しくなってしまったのだ。視覚の曖昧さをテーマとする作品コンセプトから言えば展示されている絵を描くのは誰でも良さそうに思われるが、やはり自分は「自己表現」を抑えながら絵を描く作者の姿をそこに見てしまう。作者自身の芸術観とは相容れないかもしれないが、自己表出を抑制しつつも、結果的にそこに表れてしまう「私」に自分はなによりも惹かれてしまう。
本展を見て思ったのは豊嶋の作品の面白さは、作者のストイシズムにこそあるということだ。制作において創造の神秘性を忌避するストイシズムもそうだし、「作品」としてより他の意味を一切持たないナンセンスな行為を長期間にわたって孤独に継続するその意志の強さも豊嶋の作品の強度の源となっている。そのストイシズムが彼女の作品における「私」の唯一無二性を確かなものにしているのだと言っていい。
「違和感」の理由
しかし近年の作品では姿勢の変化も感じる。パネルの裏側に幾何学的な骨組みのパターンを作る《パネル》(2013年-)あたりからは、それまで厳しく制限してきた「造形」に対するコントロールの抑制が若干緩くなってきたように思えるのだ。複数の円形を組み合わせた造型作品である《地動説2020-2022》(2020-2022年)を初めて見たとき、自分はその変化を好ましいものとして評価した。しかし今回の展覧会を見て、やはりストイシズムこそが豊嶋の作品の要であると考えを改めた。展示のなかで見る限り、造形に対する抑制の緩い作品ほど、その見え方が弱くなっているように思われたからだ。
冒頭で今回の展示には違和感が残る部分もあったと書いたが、その原因の一つはこのことに関係するように思われる。本展が豊嶋の作品をフルに使った一大インスタレーションのような造りになっていることは最初に説明した通りである。そこに作者の意志が反映していることは間違いないだろう。つまりこの展覧会のインスタレーション自体が、作者による造形物として捉えることもできるのだ。それは頑なに作品から「造形」の要素を排除してきたこの作者の作家的な性質とは相反するものではないかと考えるのである。実際、そうして出来上がったインスタレーションは、見ようによっては結構おしゃれな空間になっていて、ともすればインテリアショップのデコレーションなどさえも連想させる。おそらくそれはこの作者の造形的な性向なのではないかと推察する。そのことを評価する向きもあるだろうが、自分はむしろこれはストイシズムによって押し隠すべきもののように思えたのだ。
「違和感」のもう一つの原因は(こちらの方が重要だが)、これだけ世の中のあらゆるシステムに対して「違った使い方」をして、そのことを通してシステムの本質を顕わにするということをやり続けてきた豊嶋が、なぜ「美術館における大規模個展」というシステムに対してはこんなにも「当たり前な使い方」をしているのか?という疑問である。《パネル》の作品に応じてか展示壁の裏側にも作品を展示するといったような工夫は見られたが、それは通常のインスタレーションの範疇に過ぎない。鉛筆は真ん中から削るようなひねくれたこの作者の展覧会に、なぜ「美術館展示」を相対化するような捻りが見られないのか。公立美術館での巨大個展開催という「成功」は享受されるだけで、それを成り立たせているシステムの相対化は行われないのか。その「成功」を相対化せずに自明視することで、豊嶋の作品における作者の立ち位置の微妙さが損なわれることはないのか。それらの意味において、本展は豊嶋康子の全貌を見るのには最適な展覧会であっても、展覧会自体は決して「豊嶋康子」的なものではなかったのではないかと考えるのである。
※展示情報
「豊嶋康子 発生法─天地左右の裏表」
会期:2023年12月9日(土)-2024年3月10日(日)
会場:東京都現代美術館 企画展示室 1F
料金:一般1,400円(1,120円) / 大学生・専門学校生・65 歳以上1000円(800円) / 中高生600円(480円) /小学生以下無料 ※( ) 内は20名以上の団体料金
URL:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/toyoshima_yasuko
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
