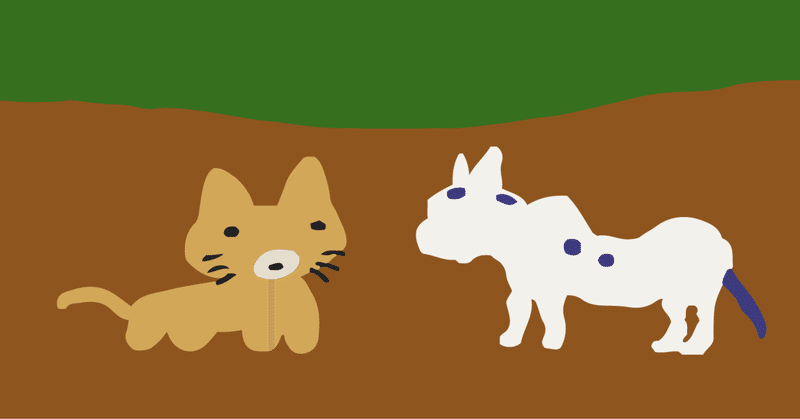
【再録】人はなぜ絵を描くのか?―熊谷守一の<写実>
再録シリーズ第2弾。もともとは雑誌『美術手帖』が公募した第14回芸術評論に応募して落選した原稿で、2009年9月より自分のサイトで公開していた(現在は削除)。芸術評論への応募はシャレのようなものだったのだが、書くための動機が欲しかったということもある。落選も当然の拙い出来だが、これを書いたことはその後の自分の制作活動やものの考え方に影響を与えていると思うので、書いたこと自体は良かったのだと思う。
前回の再録投稿はちょっとだけ手直ししたが、これは手を入れ始めたら切りがないのでそのまま投稿する。
以下、再録。
序 熊谷守一の絵の「生々しさ」
昨年、埼玉県立近代美術館で見た熊谷守一の大規模な回顧展『熊谷守一展-天与の色彩 究極のかたち-』(*1)は衝撃だった。なにかのきっかけでいままで目にしていたものが突然その様相を一変させ、目からウロコが剥がれたようにそれまで気付かずにいた未知の相貌がどんどん見えてくるようになる、そんな経験をしたことはないだろうか? この展覧会におけるわたしの「熊谷守一体験」がまさしくその典型であり、それも過去に経験したことのないほどの圧倒的な鮮烈さを伴っていたのだ。
このときのわたしの感覚をよく代弁してくれている文章があるので紹介しよう。
熊谷守一という名前はもちろん知っていて、その絵の塗り絵的なスタイルもなんとなく知ってはいたが、とくに気にとめることはなかったのだ。おそらくぼくはふつうの表面だけを見ていたんだと思う。それがしかし最近、私事であるが、世界のいろんな名画の中に描かれた猫を集めることになり、そこではじめて熊谷守一の小さな猫の絵を見た。見たとたんに「猫だ」と思った。生きている猫そのものの感触がある。こんなにも生々しい猫の絵があったのか。(*2)
わたしが驚愕したのもまさにこの「生々しさ」だった。そして、それは今まで他のどこでも見たことのないような種類の「生々しさ」だったのだ。
熊谷は大衆的な人気の大変高い画家だが、思うにこの「生々しさ」に気付くか否かで、その絵に対する評価は天と地ほども違ってくるように思える。というのも熊谷に対する人気は、その絵よりもむしろその人柄や言動(今風に言えば「キャラ」)の魅力によって流布されてきた観が否めず、ともすれば「絵より書、書より生き方が魅力」(*3)といった論調に代表されるように、作品の魅力をそのまま人間的な魅力へと還元させようとする傾向が強いからだ(*4)。
もちろん熊谷の絵は、そんな矮小なレベルへと落とし込めてしまえるものではない。それは彼の絵の、あの特異な「生々しさ」が証明している。
では、その「生々しさ」とはいったいなんなのか?
結論から先に言おう。それは写実である。もちろん単純に「フォトリアリスティックに描かれている」という意味の「写実」ではない。ほんとうの意味での<写実>だ。
本論では熊谷守一の<写実>について検証する(*5)。熊谷にとって絵を描くという行為はどのような意味を持っていたのか、そしてそこではなにが実現されていたのか、<写実>を軸にして考えてみたい。
1 「写実」とはなにか?
熊谷の絵における「写実」というと、通常は「レンブラント的」とも評される初期の作風のみがそれに当たるとされ、「守一様式」とも呼ばれる明快な色づかいと単純化されたかたちが特徴の後半生に到達した彼の代表的な作風では、表現の指向が変化し「写実」からは大きく遠ざかったとされている。しかし展覧会で時代を追ってその作品の全体像を見たときに強く感じたのは、熊谷が絵を描くことで「表現しようとしているもの」の揺るぎなき一貫性だった。表面上の作風が大きく変化しても、絵を描くことに対する姿勢と表現へのベクトルは、芸術学校時代から晩年に到るまで70年以上にわたるその画歴の中でまったくと言っていいほど変わっていない。
故にわたしは熊谷の「写実」がその初期の作品のみに留まるという通説に反して、熊谷の描く絵はその生涯にわたって一貫して<写実>であったと主張したい。そしてその<写実>こそが、熊谷の絵の「生々しさ」の源泉となっているのである。
ここで「写実」というものについてあらためて考えてみよう。
そもそも絵における「写実」とはなにか? それはどのような必要のもとに生まれ、どのような役割を果たしているのか?
ものごとを整理するために、まずは人間がどうして絵というものを描くようになったかを考えてみよう。
人類が絵を描くようになったその誕生については、二通りの考え方ができる。一つは原始の人間が根源的な表現衝動に駆られ今日で言うところの「絵」に当たるものを自然発生的に生み出したという仮説。もう一つは、なにかの必要に駆られて情報の視覚的伝達手段として「絵」が生まれたという仮説。可能性としてはその両方があり得るだろうが、それが多くの人々に共有され、文化として伝承・発展する可能性が高いのは後者のほうである(*6)。
例えば自分が遭遇した恐ろしい獣の姿について仲間に伝える場合、それを絵で描いて示すのが一番てっとりばやい。今日においても、例えば海外に旅行したときなどに言葉が通じない相手に対し簡単な絵を描いて自分の意思を伝えようとすることはあるだろう。そうした「説明のための図」が人類の、あるいは一人の人間の作画史の始原にあることは想像に難くない。
情報の視覚的伝達においては、最低限の記号的表現であってもそれが何を指しているのかが判別できれば事足りることがある。人類の作画史においては、そうした伝達記号としての絵が、やがて文字へと発展したのかもしれない。しかし場合によっては、絵に盛り込まれた情報が多ければ多いほど有用なこともある。例えば図鑑で目にする博物画などがこれに当たる。そこでは魚の鱗の一枚一枚や昆虫の触覚の細かい形状までが対象に忠実に描かれる。それは、そうしたディテールの情報までもがその絵の利用において必要とされるからこそ綿密に描き込まれるのであって、当然描かれる対象の姿に「似ている」こと、あるいは「描き込まれる情報量が多い」ことは、それらの絵において絵の有効性を高めることに繋がる。
そうした「対象に似ている」こと、あるいは「描き込まれた情報量の多さ」などを評して「写実」という形容が使われることがある。これがまず第一の種類の「写実」である。人類の作画史においてももっとも有効に活用されてきたと思われるこの種の「写実」は、しかし写真の誕生とともに今日ではその多くが役割を終えている。
もちろん人間は情報の視覚的伝達手段としてだけではなく、その他の理由でも絵を描くことがある。再び人類の作画史に思いを馳せると、例えば情報伝達のために描かれた獣の絵を、土器や住居の壁に装飾として描くものが出てくる。それは絵の視覚的伝達手段としての役割からの解放を意味する。あるいは宗教的な思想など具体的な描画対象を持たない情報を伝達するために絵が描かれる。その場合、絵は引きつづき視覚的伝達手段として用いられているが、伝達すべき情報はもはやビジュアルイメージとしての原型を持たない。さらには先行して世界に存在する絵に対する模倣や、あるいは「絵を描くこと」それ自体を目的として描かれる絵も生まれてくる。「芸術」として描かれる絵画や幼児のお絵かき、学校の授業で描く絵などは皆これに当たる。
これらの絵においては、対象の視覚情報を説明図として伝達すべき必要性はもはや存在しない。つまり「対象に似ている」「描き込まれた情報量が多い」といった博物画的な「写実」は、特別に評価されるべき重要事項ではなくなっている。しかし我々はこうした説明図として役割を解かれた絵に対しても、しばしば「写実」であることを理由に賞賛の声を上げる。例えば芸術を目的に描かれた絵画に対して「写実的だ!」と評するときに、それがマイナスの意味合いを帯びることはあまりない。ではその場合、我々はどういった理由でそれらの絵における「写実」を評価しているのだろうか?
第一に考えられるのが、作者の技量に対する賞賛である。スポーツ選手が人間の肉体能力の限界を超えてみせたときに賛嘆されるように、芸術においては人間業とは思えないほどの高度な手作業は、それ自体が賞賛の対象となる。「写真のように正確に細かく描く」「生きているように描く」「触れそうなくらいリアルに描く」などは、そのもっともワカリヤスイ技量の誇示の手立てとなる。
次に考えられるのが、表現上の効果としての有効性である。つまり「リアル」に描かれていたほうが、見てくれがよかったり、説得力が増したりする場合だ。襖に描かれた鶴の絵は「あたかも生きているかのように」描かれることによって、その部屋の空間的な緊張感を高めるのに役立つかもしれない。迫真的に描かれたキリストのほうが、平板に描かれたものよりも伝道すべき教義の信憑性が増すのかもしれない。その場合の「写実」は、視覚的伝達情報の正確さや豊富さといった直接的な成果ではなく、表現上の効果としての有効性が評価されているのである。しかしこうした種の「写実」は基本的には3D映画の「リアルさ」などとさして変わらぬ低位の概念である(*7)。
西洋の美術史において「写実」が単なる表現上の効果に収まらず一つの思想として目的化されるのは、19世紀におけるクールベらによる写実主義からである。そこで提唱される「写実」は、単純に表面的な視覚情報の伝達の正確さや神業的な技量を問うものではなく、画面上の効果としての有効性のことでもない。クールベは新古典主義やロマン主義の古典的な審美観に対するアンチテーゼとして、理想的な美やモチーフよりも現実世界に根ざしたありのままの美醜や同時代的なテーマを描くことを「写実(リアリズム)」として提唱した。つまり「目に見えるありのままの現実を描く」ことそれ自体が価値付けされたのだ。ここに到って「写実」の概念は、大きな飛躍を遂げる。単純に言ってしまえば19世紀以降の「写実」は、単なる情報の視覚的伝達手段や錯視的効果ではなく、時代や世界とそれに対峙する人間との相関関係によって生み出される高位の概念へと昇華したのだ。
その次に問題となるのは「目に見えるありのままの現実を描く」ことへのアプローチの方法と解釈の仕方であろう。クールベは旧来の古典的な美意識からかけ離れたより現実の生活世界に近接した画題や美的感覚を絵画に注入することによってそれを達成しようとし、つづく印象派の画家たちは「目に見えるもの=光」という観点から光の表現を重視した様式を開発し、ピカソやブラックは三次元的な知覚の二次元による再現の可能性を模索してキュビズムの方法を編み出した。「現実世界」を描くことそのものに価値を見出す発想は、その後の芸術にも引き継がれている。社会主義リアリズムもポップ・アートも「現代美術」も、同時代的な「ありのままの現実」を描いているとされるからこそ評価されるのである。そこには思想としての「写実(リアリズム)」が生き続けている。
では、熊谷の<写実>がこれらの「写実」のいったいどれに当たるかというと、そのいずれとも異なると言わざるを得ない。対象物を極度に単純化して描く「守一様式」が、細部の情報の緻密さや正確さによって評価される博物画的な「写実」とは180度異なることはあらためて説明するでもない。表現効果としての迫真的な「リアルさ」とも違う。熊谷の絵の「生々しさ」は、錯視的なものではない。クールベ以降の「写実」とも微妙に感触が異なる。「生々しさ」の質が違うのだ。おそらくそれは世界の把握の仕方、もしくは再現しようとしている世界そのものが異なっているのだろう。
では、熊谷の表現しようとしていた「世界」とは、どのようなものなのか?
2 「言葉では伝えられないからこそ描く」ということの意味
熊谷がどのような姿勢で制作にあたっていてたのか、絵画についてどのような考えを持っていたのか、熊谷自身の言葉をもとに検証してみよう。今日に残された熊谷の言葉の多く(もしくはすべて)は熊谷自身が起草したものではなく他人による聞き書きによるものだが、それにも関わらず彼の発言には、その画業同様驚くほどブレがない。それは熊谷が確固たる信念のもとに制作にあたっていたことを裏付ける。
例えば絵画について、熊谷は次のような言葉を残している。
景色がありましょう。景色の中に生きもの、例えば牛でも何でも描いてあるとするのです。それが絵では何時でもそこにいるでしょう。実際のものは、自然はそこにいないでしょう。その事の描けている絵と描けていない絵とあると思います。(*8)
ここで言われる「実際のものは、自然は(何時でも)そこにいない」ことを描けている絵が、博物画的な「写実」とはなんの関係もないことはすぐ解るだろう。博物画における牛の絵は、その色、かたち、細部のディテールなどの情報が伝わることが重要なのであって、「自然は(何時でも)そこにいない」ことまでもが表現される必要はないからだ。
それはまた表現上の効果としての「写実」、すなわち「迫真性」を演出しているのとも違う。多くの場合、表現効果としての「リアルさ」とは「今にも動き出しそうな」とか「手を伸ばせば触れそうな」とか「画面から飛び出してきそうな」といった形容で表されることからもわかるように騙し絵的な要素が強い。熊谷の言う「自然はそこにいない」こととは、騙し絵的な要素とはむしろ相反する。騙し絵的な「写実」はイリュージョンにより自然があたかもほんとうにそこにあるかのように表現するが、熊谷の言う「自然は(何時でも)そこにいない」ことまでも描けている絵は、あくまでそれ自体が「絵」であることは偽ろうとしていない。問題にしているのは絵において表現されている内容であって、そこが錯視によって自然を偽装する騙し絵的な「写実」とは根本的に異なる。
またそれはクールベ以降の「リアリズム」とも異なる。「リアリズム」の思想が重視するのは同時代性や物事の本質をあらわにすることであり、それに対して熊谷がここで言っているのはもっと存在論的な事柄だからだ。
それにしても「実際のものは、自然は(何時でも)そこにいない」ことまでも描けている絵とは、いったいどのような絵なのだろうか?
確かに我々は自然のなかにいる牛を見るとき、その牛が描かれた絵のように「何時でもそこにいる」とは思っていない。今この瞬間はここで草を食んでいるかもしれないが、別の瞬間にはその牛はここから立ち去り、どこかまた別の場所に存在するだろう。我々は自然を、「現実世界」を、そのように認識している。しかしそれらの認識を我々はほんとうに視覚情報から得ているのだろうか?
熊谷はまた次のようにも言っている。
あなたは此処にいるが、何時迄も此処にいない。それを描けるか。(*9)
来客がある。その人を目の前にして写真をパチリとやる。やがてその人は腰を上げここから立ち去り、またどこかここではない他の場所で生活を開始するだろう。我々は写した写真からそのことを知ることができるだろうか? なぜ我々は、あるものはいつまでもここにあり、あるものはそうではなく別の瞬間にはどこか別の場所にあることを認識できるのだろう? もちろん経験から得た知識として認識しているということは、当然考えられる。しかしここに牛を描いた二枚の絵があり、片方が永遠にそこで静止し続ける「絵的な絵」であり、もう片方が「実際のものは、自然は(何時でも)そこにいない」ことまで描けている絵だとすれば、我々はそうした存在論的な認識を純粋な二次元の視覚情報から得ることができるということにはならないだろうか?
この問題意識は旧来のどの「写実」も持ち得なかったものだ。それは「絵」というものの果たしてきた役割の、まったく新たな可能性を示している。情報の視覚的伝達手段でも、錯視的な効果でも、同時代性の共有でもない。熊谷は絵画を哲学的な探求の手段として用いている。そこで追求されているのは、自分が「どのように世界を認識しているのか」という認識論的な問いと世界の成り立ちそのものに対する探求である。
熊谷は生前、絵や方便はそっちのけで懐中時計の修理や音の振動数の計算などに没頭していた時期があったらしい。「私はいろいろなものの出来た過程を知っているということを欲しがるんです(*10)」と自らも証するように、「電車に乗れば電車の構造を」「魚を食ってもその魚がどこに泳いでいるか」を知りたがる熊谷は、事物の「根本」をいちいち知りたがらずにはいられない、そんな性分だったのだろう。
それは世の中で自明とされている事柄をすべてその根本より疑ってみないと気がすまない哲学者の態度と同じだ。そんな熊谷が、この世に生まれたすべての人間にとっての最大の謎である「この世界」の成り立ちについて知りたがらないはずはないだろう。熊谷にとって「絵を描くこと」とは、「この世界」の成り立ちを解き明かす、その最良の手段だったのだ。
哲学者は世界の成り立ちについて言葉で思考し、言葉で表現する。熊谷はそれを絵を描くことで成し遂げようとする。それはなぜだろうか? 言葉ではできない、絵を描くことでしか表現できないことはなにか?
画家が本当に絵を描くという事は言葉ではいえないから、絵にするのです。(*11)
熊谷はその生涯に、幾度にもわたって「言葉ではいえないから絵にする」ということを主張している。それは彼が絵を描くことの根本の理由としてあるのだろう。「言葉ではいえないから絵にする」とはよく画家が口にする言葉だが、熊谷にとってそれはどのような意味を持っていたのか? 熊谷は言う。
一般的に、ことばというのはものを正確に伝えることができません。絵なら、一本の線でも一つの色でも、描いてしまえばそれで決まってしまいます。青色はだれが見ても青色です。しかしことばの文章となると、「青」と書いても、どんな感じの青か正確にはわからない。いくらくわしく説明しても、だめです。私はほんとうは文章というものは信用していません。(*12)
人間は自分が見ているものの色を、正確にそのまま他人に伝えることはできない。自分の知覚をそのまま他人に伝達することができないからだ。自分が「見ているもの」と他人が「見ているもの」が果たして同じように「見えている」のか、我々は永遠に知ることができない。色の問題はその象徴的な事例である。
日常生活において我々は、それを言葉による共通認識を設けることによって解決している。リンゴや信号機の停まれのランプの色は「赤」と名付けられ、その認識が共有される。日常生活を送るにあたってはそれでなんの支障もないのだが、我々が「自分が見ているもの」を他者に伝達できないという問題自体は、実はなにも解決されていない。
自分の見ている「このリンゴ」の「この赤」を言葉によって他人に伝えようとするとき、我々は「赤」という言葉を「この赤」に近付けるため「赤」を細分化したり、文学的に表現したりする。「ちょっと紫がかった深い赤」「色見本の何番に近い赤」「朝焼けの空のような赤」「恋の炎を想わせる情熱的な赤」などなど。しかしそのことによって「この赤」にどんなに肉迫しようとも、その言葉が「この赤」そのものを表現することは不可能だ。わたしの見ている「この赤」とそれを表現する言葉が完全に重なり合う瞬間は永遠にやってこない。そこに言葉の限界がある。
絵ではどうだろうか? もちろん「このリンゴ」の「この赤」と同じ赤を絵の具で表現することは不可能だ。どんなに「このリンゴの赤」に近付いても、それは「絵の具の赤」であることには変わりがないからだ。言葉と同様、それは絵によっても伝達不能である。
しかし、すくなくとも「この絵の具によるこの赤」には、ズレがない。その赤が人によってどう見えるかは、異なるかもしれない。しかしその絵の具による「赤」は、それ自体が既に「この赤」なのである。言葉が「表象するもの」であることから逃れられないのに対して、絵の場合、一本の線でも一つの色でも描いてしまえばそれはもう「そのもの」なのだ。それが絵と言葉の最大の違いである。
もちろんそのようなことを意識することなく、我々は普段言葉によるコミュニケーションを行い、生活している。実際、日常生活においてはそれでなにも支障がないのだ。
しかし熊谷は「ほんとうは文章というものを信用していません」と断言して憚らない。そのことは彼がいかに「言葉と言葉が表象するものとのズレ」に対して敏感であったかを示している。熊谷の見ていたものは、そして彼が表現しようとしたものは、決して「言葉では伝えることができないもの」だったのだ。
言葉では決して伝えられないもの。それはなんだろうか?
3 <自然>を描くことの意味
熊谷は自然を主にそのモチーフにした画家として知られている。彼の描く「自然」はスケッチ旅行で見た旅先の風景から、樺太への調査隊や故郷で日傭をしていたときに目にした光景、そして自宅の庭に息づく昆虫や草花などの「小さな自然」にいたるまで多岐にわたる。しかし熊谷にとっての「自然」の定義は明快だ。それは「人の手によらないもの」である。樺太や故郷の山の中で見た大自然も自宅の庭先を這う蟻たちも、その意味において彼にとっては等しく<自然>なのだ。その態度は徹底していて、あるとき熊谷のもとを訪れた画学生が見てもらいたい絵があって他所に預けてあるので取りに戻りたいという。それらが「庭園」「寺の建物」「ありふれた風景」を描いた絵だと聞いた熊谷は「絵は持って来なくてもよい。庭や建物のほうは駄目だが、風景のほうは良さそうだ」と即座に断じたという(*13)。もちろん熊谷にも静物など「人の手によるもの」を描いた作品は存在するが(*14)、花屋にある花は死骸だと言って見向きもせず、それが枯れ始めるとようやく関心を示すといった具合に、彼にとって絵に描くべきものは、人の手によらない<自然>であった。
ではなぜ熊谷はかくも<自然>を描くことにこだわったのか? 彼にとって<自然>を描くことは、どのような意味を持っていたのだろうか?
熊谷が昼間太陽の下で見た<自然>は、夜電球の下で絵画化される。樺太で目にした光景をその五十年後に描いた傑作『土饅頭』(1954)のように、過去に見た光景が長い年月を経た後に描かれることもある。画商の向井加寿枝によると、驟雨を描いた絵を示して熊谷が「これは昔日傭をしていたときに降った雨だ」と説明したことがあるという(*15)。熊谷の描く光景は匿名の「雨」や「猫」ではなく、いつも特定された「それ」だったのだ。
熊谷の絵には同じモチーフを同じような構図で描いたものがしばしば見受けられる。なんでも熊谷はトレース紙を用いて同じ下絵から複数の絵を描いていたのだという(*16)。十数年の年月を隔てて同じ下絵がトレースされ、再び絵画化されることもある。しかし熊谷が絵を描くときは傍からは「いつでもはじめて絵というものを描くという様子で描きはじめる(*17)」ように見えたという。熊谷は言う。
自分が仕事をしている内に出て来るものがあるでしょう。それで仕事の仕甲斐がある。何故かと言えば仕事をしなければ無いのだから。仕事をするために出て来る。仕事をしていて、こんなのをどうして気が付かなかったかという事もあるのです。(*18)
熊谷にとって絵を描くことは「見えているものそのもの」を描くことではない。それは自分がどう世界を見ているのか、どう世界を知覚しているのか、その確認作業(もしくは発見作業)なのである(*19)。繰り返すがそれは自分が見ていた光景の「再現」ではない。自分が世界をどう知覚しているか、それを自分自身が知るためにこそ、描くのだ。
ではなぜ<自然>なのか?
花屋で買ってきた花は死骸だという熊谷に対して、夫人が水を吸うからまだ生きていると反論する。それに対して熊谷は言う。「水を吸うことは吸う。でも、初めの時とは違うわね(*20)」
野に咲く花と花屋で売られている花ではなにが違うのか? 花屋で売られている花は「人の手」を経ている。熊谷にとって<自然>とは「人の手によらないもの」のことだ。ではそこで「人の手」によって付与されたものとはなにか?
それは言葉である。人間は言葉によって自然を征服する。<自然>に付与された言葉と<人工物>に付与された言葉ではその意味合いがまったく異なる。<人工物>に付与された言葉は、そのものの本質である。金槌は釘を打つために作られ「金槌」と命名され、椅子は人が座るために作られ「椅子」と名付けられる。我々はそれらをその視覚情報とともに「金槌」「椅子」として認識する。つまり存在を、事物に付与された言葉によって認識する。
それに対して<自然>は人間による名付けに先行して世界に存在する。人間はその自らにとって未知の存在である<自然>に対して言葉を貼り付け、自らの体系へと組み入れる。我々は言葉による「意味」を付与してはじめて、未知の存在であった<自然>を識別可能な存在へと変換させるのだ。つまり木は「木」という言葉を与えられる以前は、我々にとって未知の「なにものか」としてしか現前し得ない。逆に言えば、木や川や蟻や猫は、「木」や「川」や「蟻」や「猫」である以前に、言葉では表現できない「なにものか」として世界に存在しているのだ(*21)。
つまり花屋で売られている花は「花」でしかない。それは人の手によって「花」とされてしまったものなのだ。熊谷から見れば、それは<自然>のなかに咲いていた名付けられる前の「それ」の死骸でしかない。
熊谷の絵の「生々しさ」は、彼にとってほんとうに「生きているもの」を描いているからこそ生まれるのだろう。そして熊谷にとって「生きている」とは、人の手を経ていない、言葉を付与される前の「なにものか」として存在する<自然>の状態にあることを意味する。そして(ここが肝心だが)我々は決して言葉によってはその地点には到達できないのだ。熊谷が<自然>を描く理由はそこにある。
熊谷が対象を見つめる眼は、人の手によって<自然>に付与されたあらゆる言葉をエポケーしている。
例えば熊谷の描く猫には髭がない。「髭がない」ということが一つのトピックになることからもわかるように、我々は猫の絵といえば髭を描くのが当たり前だと思っている。尖った耳にレモン型の眼、それに髭を何本か足せば猫の絵の出来上がりだ。それだけで誰もが「猫」だと判別できる。
しかしそうした猫の絵は、実は「猫」という文字と大した変わりはないのだ。つまりそれは我々が「猫」と名付けたその生き物を表すための記号に過ぎない。イラストやマンガのように単純化して描かれる絵だけではない。体の毛を一本一本細密に描いた「写実」の猫だって、自分の目でほんとうに見た「その猫」ではなく、単に画家の観念としての「猫」を描いただけの絵であるならば、それは<写実>の意味においては「猫」という文字と変わりがないのだ。
最近ある展覧会で、再び熊谷の猫の絵を見る機会があった(*22)。それは髭どころか眼も鼻もなにもない白一色の色面に青の斑が数個、たったそれだけで描かれた猫だった。しかしそれは紛れもなく猫だった。「猫そのもの」だった。なぜそんなことが可能なのか、その物理的な「からくり」は(もちろん)わからない。しかし絵の前に置かれた椅子に座り凝っとその絵を見つめていると、炬燵に当たりながら縁側越しに庭先を横切っていくその猫を見つめる熊谷の視覚がそのまま絵を見ている自分に乗り移ったかのようにさえ感じられてくる、そんなあり得ないような<リアルさ>だった。おそらくそれが、百万言を費やしても言葉による伝達では永遠に到達できない、絵を描くことでしか表現できない<写実>なのだ。
では<写実>の表現は我々になにをもたらすのだろうか。熊谷の絵の「生々しさ」に触れるとき、そこではなにが伝達され、そしてなにが生まれているのだろうか?
絵なんてものはいくら気をきかして描いたって、たいしたものではありません。その場所に自分がいて、はじめてわたしの絵ができるのです。(*23)
熊谷は繰り返し「画家は生まれ変わることができない限り他人にはなれないので、自分を生かすしかない」という意味の発言をしている。それはともすれば「下品な人は下品な絵を、ばかな人はばかな絵を、下手な人は下手な絵をかきなさい」という有名な言葉とともに、おのおのの人柄を生かした絵を描けといったレベルの話に落とし込められがちだ。しかし同時に「若し人柄が出過ぎたら人物景色静物など、皆同じ物で差別がつき兼ねます(*24)」という発言をしていることからもわかるように、熊谷が「自分を生かす自然な絵を描けばいい」とか「自分を出すより手はない」などと言うときの「自分」とは人柄のことではない。ましてや「キャラ」では絶対ない。
では「自分を出す」とはなにを意味するのか?
一つのものを作るのに綺麗だと思って描く場合もあり得るでしょう。綺麗だと思ったことも自分のところでは一遍ものを通したことになるのです。いくら気ばって描いたって、そこに本人がいなければ意味がない。絵なんていうものは、もっと違った次元でできるのです。(*25)
人間は「自分の見ている世界そのもの」を、他人に伝えることはできない。例えば目の前にある花が綺麗だと思い、それを「綺麗」という言葉で他人に伝えても、そこで伝達されるのは「綺麗」という言葉で共有されている概念のみである。「綺麗」は目の前にある花にあるのではなく、それを見た自分を一遍通って出てきたものである。その「一遍自分を通ったもの」と「綺麗」という言葉の間には、無尽の「切り捨てられたもの」が存在する。その「切り捨てられたもの」をすべて回収して、言葉によって他者に伝えることはまず不可能だろう。
言葉による世界認識の共有は単一化を指向する。そこでは認識のズレがないことこそが、生活の利便性やコミュニケーションの円滑化に繋がる。しかし本来人間の数だけあるはずの世界把握の多様性を押し殺すことで、我々の世界では「なにか」が失われている。本来芸術とは、その失われたものを補うためにこそ存在するのではないだろうか。
絵を描くことにおいて「自分を出す」とは、自分を「一遍通ったもの」を共通認識のための記号的表現に押し込まないことである。「綺麗」という言葉は、すくなくとも「綺麗」という言葉の持つ共通認識において「綺麗」であることは共有される。しかし自分の見ている、自分だけが見ている「この世界」を「自分を出して」表現したら、それは百人百様、共通する認識を探すことさえ困難になるに違いない。すくなくとも日常的なコミュニケーションにはまったく役に立たない。しかし白の絵の具の色面に過ぎない熊谷の猫に「生きている猫そのものの感触」を感じるように、記号的な伝達によらずおのおのの世界像の共有点に触れたとき、我々は世界の多様性とその無限の広がりに驚嘆することになるだろう。それこそが<写実>の持つ、ほんとうの意味なのだ。
4 単純化していく世界と<写実>
吉本隆明はその著書『日本語のゆくえ』(*26)の最終章において、現代の若い詩人たちの詩を読んだ感想として、その傾向を「まったく塗りつぶされたように“無”」であるとし、その原因として「天然自然の絶滅状態」により自然との関わりを失った若い詩人たちの自然に対する感受性の欠如を指摘している。
それ対して「若い詩人」の一人である安川奈緒はこう反論する。
はっきりさせておかねばならないことは、もはや、自然は治癒と保護と政治的陰謀の対象であるということである。自然そのものなどもはやありはしない。フレームに憑かれたわたしたちにとって、自然はもはや横長であり、わたしたちはそれにうまうまと包まれるわけにはいかない。居心地の悪さと人間であることの後ろめたさを覚えさせる対象として、自然は現前している。そのような苦い認識を踏まえたうえで、わたしたちは、雨や、雪や、花という語を恐る恐る、恥じらいを持って詩語とする。(*27)
吉本の言う「天然自然の絶滅状態」が、我々の身の周りから草木や手付かずの自然が失われたことを意味しているのに対し、安川が指摘しているのは<自然>の絶滅だ。それは熊谷の生きた時代にはまだ<人工物>の対義語であり得た<自然>が、現代においては変質してしまったことを意味している。安川は言う。
車窓、テレビ、パソコン、携帯といったフレームの攻撃さらされ、わたしたちの目に映るものはすべて既視の、あらかじめフレームに囲われたものかもしれないという恐怖(中略)。もはやわたしたちは自分が「像」として結べた映像はすべて破壊しなければならない。その像は愛おしくもなんともない、得体の知れないシステムによって眼前にぶらさげられた、強いられた願望の像であるかもしれないからだ。(*28)
詩作とは世界にラベリングされた分類記号としての言葉をひとつひとつ引き剥がし、解放していくような作業であろう。「雪」とひとこと詩語したとき、その「雪」という一語が、我々が「雪」として認識しているものをあらわす記号的な機能を超え、おのおのが「自分として」受け取った百人百様の「像」へと到達しない限り、その語は詩とはなるまい。ましてや「得体の知れないシステムによって眼前にぶらさげられた像」に根こそぎ集約されてしまうような世界において、言葉を表現の術とする詩人たちの困難は想像に余りある。
しかし事情は美術家たち、いやあらゆる現代の表現者たちにとっても変わらないはずだ。我々の視界に映るものは、いまやすべてがその表層を既存の「意味」によって覆い尽くされている。その触手に絡め取られることなく世界の本質を見つめることは至難の業だ。「自分には世界はこんなふうに見える」という表明も、すぐさま特定のレッテルへと回収され、単に自分が特定の主義や思想のもとにあることの表明へと変換されてしまう。世界に対する解釈は限定され、均質化される。「結局みんな同じ時代にいて、食べ物も似たようなもの、同じような気候のときにいて、同じようなものを見たり聞いたりしたら、同じ形のものが結局は出るんじゃないかと思うんです(*29)」という半世紀前になされた熊谷の予言は、現代において見事に的中している。
<自然>の消滅は、世界が単純化していくことを意味している。<写実>の有効性は、そこに生きる個々人の世界把握の多様性にこそあった。しかしすべてが言葉によってラベリングされた世界では、多様性は生まれない。木は「木」として、花は「花」として、記号的表象と人為的に付された「意味」によってのみ現前する。あらゆるものが「共有認識」によって構成され、世界はその深みと可能性を喪失する。
我々の生きる時代において、もはや熊谷のような<写実>の生まれる余地は、限りなくゼロに近いのかもしれない。しかしだからと言って熊谷を真似て敷地五十坪の自宅より一歩も外に出ず、ラジオ、テレビ、携帯、インターネットといった類の情報通信手段をすべて切断し、そこにある「小さな自然」を見つめて終生過ごせばそれで<写実>が実現できるかといえば、それもまた無理だろう。熊谷も言っているように(*30)、絵は時代から逃れることはできない。それは自分の生きている世界を描くことにはならない。
多様性の喪失は閉塞感を生む。のっぺりとした均質化に覆われた息苦しさの中で、我々は再び世界の本質に触れなければならない。この時代における真の<写実>を模索しなければならない。それこそが、この単純化していく世界に生きるすべての表現者が直面すべき課題なのである。
注
*1:2008年2月2日~3月23日。他に萬鉄五郎記念美術館、成羽町美術館、天童市美術館を巡回
*2:赤瀬川源平「見ることの距離を楽しむ」(熊谷守一『へたも絵のうち』(平凡社ライブラリー)解説)
*3:瀧悌三「熊谷守一について」(『美術の窓』1991年11月号)
*4:『天与の色彩 究極のかたち』展のカタログに所収されている池田良平の解説によると、熊谷の作品や資料が広く公開されるようになり熊谷研究が深化したのは、ここ10年くらいのことだという。
*5:ここで論考の対象とするのは熊谷の油彩画であり、日本画や書は含まない。既に多く指摘されているように日本画の制作が熊谷の油彩画の模索に活路を拓いたということは事実としてあるかもしれない。しかしそれはあくまで表現の手法面における影響に留まる。スケッチブックや制作時間を厳密に分け、日本画や書は気軽に人前で描いてみせたのに対し油彩画の制作現場には家人をも立ち入らせないなど、熊谷は油彩画に対する制作態度と日本画や書に対する制作態度を明確に違えていた。わたしは熊谷の日本画や書にも魅力を感じるが、それは彼の油彩画に対するものとは次元を異にする。むしろ日本画や書に関しては、その魅力を熊谷の人間的な魅力へと還元し得る性質のものであるように思う。
*6:もちろん前者の場合における「絵」という表現に仮託された衝動性は、視覚伝達手段としての「絵」のなかにも潜むことはある。プリミティブな表現衝動は「はけ口」さえ見付かればどのような表現形態へも変換可能であるが、それと同時に「絵を描く」という行為自体が表現衝動を生む誘因にもなり得る。そこが芸術の面白いところであり、また芸術表現のなされる初源的な理由を特定することの困難にも繋がっている。当然「写実」についても、それが描かれる理由とその筆触のひとつひとつに織り込まれる思想とは必ずしも一致するものではないが、ここでは敢えて乱暴にその用途と効果によって「写実」の存在理由を整理分類していく。
*7:錯視的な「写実」表現においても、三次元を二次元に転移することや世界を視覚的に複製することを指して、例えばそれを「神」と人間、あるいは自然と人間との関係で捉え、より高位の概念へと転じる端緒とすることは可能である。
*8:熊谷守一「私の生い立ちと絵の話」(『心』1955年6月号)
*9:同上
*10:熊谷守一「ピカソは一番分りいい」(『心』1952年12月号)
*11:「私の生い立ちと絵の話」
*12:『へたも絵のうち』
*13:木村定三「熊谷守一さんの芸術」(『三彩』1964年2月号)
*14:『熊谷守一全油彩画集』(求龍堂)の年譜によると、病気で臥せっていた長女が卵が黒い盆の上に乗っているのを見て涙を零したことをきっかけに、熊谷は静物でも人の心を動かすということに気付き、その関心を人の手による静物にも向けるようになったという。その「黒い盆の上に乗った卵」を描いた『仏前』(1948)と『たまご』(1959)の二点は、フォーヴィスムのように荒々しいタッチで激しい感情を表現したり、あるいは冷たい色彩で悲しみを表現するといった感情の記号的伝達のセオリーにまったく頼ることなく、その光景を目にしている画家の哀しさ(…と単純に言語化してしまえないようなその言葉にはできない感情)を見るものに伝えている。「絵といふものは作者が興奮しないときに、よく見るといふことが肝心である」として、自らの感情にさえも歪められることのなく正確に世界を把握しようと努めてきた熊谷が、更なる高次の<写実>へと到達した傑作である。
*15:向井加寿枝「熊谷守一をパリで自慢したかった」(『美術の窓』1991年11月号)
*16:廣江泰孝「モリカズ方程式」(『熊谷守一 守一ののこしたもの』展カタログ)からの指摘
*17:谷川徹三「熊谷守一の人と絵」(『へたも絵のうち』所収)
*18:「私の生い立ちと絵の話」
*19 「絵と言うものの私の考えはものの見方です。どう思えるかという事です。単純というのは、表現の方法です。どういう風に見たって絵にならなければ、形になって来ませんから……。」(同上)
*20:庄野潤三「熊谷守一の回顧展」(『芸術新潮』1962年6月号)
*21:言葉を覚える前の幼児の段階では<人工物>も<自然>と同じく言葉では表現できない「なにものか」としてしか現前しない。しかし言葉による世界把握を「知ってしまった」人間が再びアプリオリに世界を把握しようとするとき、言葉によってそのものの「本質」に既に辿り着いてしまっている<人工物>をその対象とすることは、<自然>を対象とすることに比べ困難となる。
*22 渋谷区立松濤美術館で開催された『素朴美の系譜 江戸から大正・昭和へ』(2008年12月9日~2009年1月25日)に出品された『猫』(1951)
*23:熊谷守一『蒼蠅』(求龍堂)
*24:「私の生い立ちと絵の話」
*25:同上
*26:吉本隆明『日本語のゆくえ』(光文社)
*27:安川奈緒「「私が見たものなど、何ほどのものでもない」という覚悟から描写を始めるために」(『現代詩手帖』2008年5月号)
*28:同上
*29:「ピカソは一番分りいい」
*30:「画家と時世に就いては――ずつと絵をやつてくると、住むところと時代や階級で、生れ変つて来なければどうにもならないものがある。もつとも私は自分の絵でも、自分が描いたと思つたら大間違ひだと考へてゐる。」(小熊秀雄「熊谷守一氏藝術談-青木繁との交遊など-」)「画家は環境を否定することはできない、自分だけといふわけにはいかない。」(同)「画の仕事は時代と住む所と時は変な風にからんでまして、まるでさずかりものです。」(「私の生い立ちと絵の話」)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
