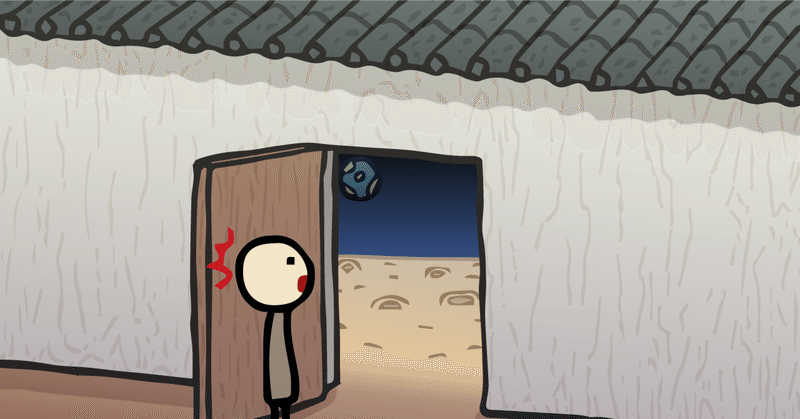
世界の片隅から月へと向かう―恵比寿映像祭2024「月へ行く30の方法/30 Ways to Go to the Moon」
2024年2月2日金曜日、東京都写真美術館へ恵比寿映像祭2024の展示を見に出かける。今年で16回目の開催となる恵比寿映像祭(通称エビゾウ)は、インフルエンザにかかって見られなかった初回を除き、その後の展示は欠かさず毎年見ている。ただ昔に比べるとエビゾウも随分変わったという印象だ。以前は展示を見るだけでも一日がかりの大イベントという感じだったのだが、近年は予算額の縮小を憶測させるような地味な内容の年も多く、今年の展示も午前中だけであっさりと見終わってしまった。「年々地味になってくるな~」と思いつつ帰ってきたのだが、しかし不思議と後に残った感覚は悪くない。目玉となるような作品があったわけでもないし、とりわけキュレーションの妙に唸らされる!という感じでもなかった。それでも自分のなかに残ったこの「良い感じ」は、過去に見たエビゾウの優れた回の展示で受けた印象にも似ている。考えるべき何かを確かに受け取ったという感覚がある。では今回の展示の何が自分に好印象をもたらしたのだろうか? そのことについて考えてみたい。
2階→3階→地下1階と辿る展示
今年の展示は2階からスタートする。写美の展示フロアーは3階、2階、地下1階で、全フロアーを使った展示ならば3階から始まって階段を使って順に下の階へと移動するのが合理的だ。過去の回のエビゾウでも3階スタートが通例だった。それを敢えて2階→3階→地下1階という無駄に上下階の移動の多い順路にしているのには、当然意味があるのだろう。
その2階の展示は、仕切り壁のない広い展示室に作品が点在するという造り。展示作品は現役作家の新作・近作に写美の収蔵作品を加え、新旧織り交じっている。混交しているのは制作年だけでなく、メディアも多種多彩だ。ビデオ映像や写真に加え、絵画、彫刻、サウンドインスタレーション、本、資料類の置かれた机、パフォーマンス(の告知)と、とても「映像祭」とは思えないような展示である。恵比寿映像祭の展示は伝統的に「映像」について考えるというテーマを持っていて、それ故に通常の映像作品とはかけ離れた形態の作品が展示されることもあったが、今回の展示の拡張ぶりはそれとはレベルが異なる。なにか理由があってこのような体裁の空間にしているのだろうと推察されるのだが、しかしその意味に思い至るのは後の展示を見てからのことで、この時点ではまだ「見たことある作品が多いな~」とか「仮設壁を作る予算を節約したのかなー」くらいの感想しか抱かなかった。
続く3階の展示は昨年から始まった「コミッション・プロジェクト」の展示。「コミッション・プロジェクト」とは審査員が選出した新進アーティストに制作委嘱をする事業で、昨年の恵比寿映像祭では選出された4名のアーティストが新作を展示していた。今年はそのとき特別賞を受賞した金仁淑と荒木悠の2名が、映像祭の総合テーマ「月へ行く30の方法」と連動させた展示をしている。昨年4名で展示していた空間を今年は2名で展示しているわけだが、フロアーの三分の一をアーカイブ用の部屋に当てているので、一人当たりのスペースは去年より若干広くなった程度。しかも新作を委嘱された昨年の展示に比べて、今年は二人とも旧作を使ったインスタレーションで、荒木に至ってはデビュー作に当る2014年制作の作品を出品している。こんなところでも「予算の縮小」を邪推してしまうのだが、しかし総合テーマとの絡みがなく本編の展示からは浮いた印象だった去年よりも、今年の展示のほうが自分にははるかに面白かった。
展示はまず金仁淑から始まるのだが、昨年も金が一番手だったので展示スペースはほぼ去年と同じ。多チャンネルの映像インスタレーションである点も一緒で、最初はデジャヴュ感もあった。しかし作品自体の印象はだいぶ違っていて、ポートレートとインタビューを組み合わせた長尺の映像群で構成された去年の展示に対し、今年の作品は各映像の尺が短めにまとめられている。モチーフとなるのはソウル市にある城北洞という街とそのコミュニティ。ジェントリフィケーションの進む街の旧い韓国家屋の並ぶ路地の風景や、そこに住む人々たちが集う様子をマルチチャンネルで同時上映することで、街の雰囲気や住人たちの気性が伝わってくるような好感の持てるインスタレーションになっていた。
続く荒木悠の展示は、荒木がレジデンス先のアイスランドで撮った「ロードムービー」をメインにしたインスタレーション。滞在した村で唯一外食できる店(ダイナー)のメニューにあったアメリカの国道66号線沿いの地名にちなんだファーストフードを順に食べていき「旅」をするという映像作品だ。この作品が制作された十年前に比べて現在の世界の食糧事情はさらに悪化している。日本も例外ではなく、物価高騰で一日一食に減らしても生活費が賄えないといったニュースが日常的に流れる。そんななかで戯れにファーストフードを暴食するこの動画は「不謹慎」であるとも言える。実際、自分もそこが少し不快だった。しかしそんなPCな価値観を乗り越えさせたのは、この映像作品に漂う「場末感」である。時折画面に移り込むダイナーの他の客や店員の様子。荒木と一緒に辟易しながら料理を食べ続ける地元の仲間たちの佇まい。そしてなによりも遠いアメリカの地の名を冠したとても健康に悪そうな料理の数々。ハリウッドを終着点とするアメリカの国道66号線という誰もが注目する世界の中心から遠く隔たった、誰も見向きもしない世界の片隅としてのアイスランドの田舎町。その対比の大きさ。しかしその誰も見向きもしない世界の片隅と、そこに生きる人々に向ける作者の眼差しには、その直前に見た金仁淑の城北洞とその住人たちに注ぐ眼差しと同じ温かみを感じる。そのことに気付いた瞬間、何かが繋がったような感覚があった。
展示は地下1階へと続く。総合テーマである「月へ行く30の方法」のもととなった土屋信子のインスタレーションを始め、ここには4組のアーティストの作品が展示されている。その中で自分が一番印象に残ったのはリッスン・トゥ・ザ・シティという韓国のコレクティブの展示の中にあった韓国における身体障がい者の外出問題を扱った15分ほどの動画だった。主な舞台となるのは移動手段としての地下鉄で、日本の地下鉄との類似点も多く、ハングルや英語に混じってひらがなの「のりば」の表記が映っているのを見ると親近感がわく。実際、映像のなかで扱われている、駅のエレベーターに健常者が押し寄せて本来それを一番必要としているはずの障がい者が乗れずに後回しになってしまう…などということはおそらく日本でも日常的に起こっていることなのだろう。それと同時に職員と抗議者がホームで対峙する「地下鉄デモ」の光景などは日本ではまず見かけない。これはデモが盛んだという韓国のまさに「お国柄」なのだろう。バリアフリーの問題は万国共通だが、その対応に違いもある他所の国の事情を見ることで、問題の本質がより明確になっているように思われた。
歴代の恵比寿映像祭のなかでは展示を通して世界のあちこちを旅しているような感覚があった回が強く印象を残っているのだが、今年の展示にもそのような傾向はあった。そこで訪れる場所は人々の耳目を集める名所や話題の中心地ではなく、金仁淑の城北洞の路地や荒木悠のアイスランドのダイナーのように、むしろ世界から忘れ去られたような「片隅」だ。リッスン・トゥ・ザ・シティの動画は同じ韓国ということで金の展示とシンクロするが、金が扱うのが郊外の閑静な街であったのに対し、この動画の舞台は都市の大動脈である地下鉄であり、「片隅」ではなくむしろ「中心」である。ここでの「片隅=世界から忘れられた存在」は場所ではなく、そこから排除されようとする障がい者たちなのだ。彼らが訴えるのは、「片隅」を切り捨てて「中心」に居られる強者だけで構成される社会に対する異議申し立てである。そしてその主張は、映像祭の総合テーマである「月へ行く30の方法」と組み合わされることで新たな相貌を帯びてくる。
「月へ行く」とはどういう意味か?
人類が最初に月へと到達できたその基礎に、東西冷戦による軍拡競争があったことは否定できないだろう。軍事技術への転用が可能なことや国威発揚に効果があるため東西の大国が競ってロケット技術を進化させた。その結果として人類は月面への着陸というとてつもない偉業を成し遂げることができたのだ。「月へ行く」が人類が未来へと進む進歩を意味するのだとすれば、ここでは大国同士のいがみ合いや軍拡競争こそが人類の進歩を導いたのだと言える。
しかしそれは月へ行くための「1つの方法」である。土屋信子の作品より採られた映像祭の総合テーマは「月へ行く30の方法」であることこそが重要なのだ。世界各所で愚かな破壊と殺戮が進行している現在の状況を見れば(いや、見ずとも)、軍拡競争による「進歩」がいかに危険に満ち、誤った道であるかは自明である。我々はもうそのやり方をやめて、人類の進歩のための「別の方法」を探らなければならない。「月へ行く30の方法」が意味するのは、まさにそのことなのである。
映像をめぐる現在も無関係ではない。自宅から会場へと移動する途中で渋谷駅を経由したのだが、駅の構内は某動画投稿サービスの動画広告で埋め尽くされていた。そこでは「開始一か月でフォロワーが何百万人!」などの宣伝文句が躍っていたのだが、動画投稿サイトやSNSに代表されるアッテンションエコノミーが現在の社会の大きな推進力となっていることは間違いない。富と影響力を一点に集め、誰もがその立場になれるのだと煽って人を呼び込み、そのエネルギーで経済を先に進めていく。しかしそのやり方の弊害は誰の目にも明らかで、もはや限界に来ているように思われる。リッスン・トゥ・ザ・シティの動画のなかで障害を持つ出演者が韓国の地下鉄の駅構内に張り巡らされた広告を前に、弱者を切り捨て強者のみで前に進もうとする今の社会の歪さを訴えていたが、映像の中の風景と現実の光景で隣の国とこの国が繋がり、世界を覆う問題の根深さが露わになったような気がした。
動画のなかで障がい者の移動の自由を訴える出演者が「これは障がい者だけの問題じゃないんだ!」と強調していたのがもっとも印象に残った。それは健常者も事故などで障がい者になるかもしれないから…というだけの意味ではないだろう。彼女が言いたかったのは、障がい者が健常者と同じように移動ができ、生活できる社会を作ることこそが「月へ行く方法」のひとつであるということなのだ。旧来の軍拡競争やアッテンションエコノミーのような巨大な力が牽引していく「進歩」ではなく、「別のやり方」による人類が未来へと進むための道こそがここでは示されているのである。
そして本展における「月へ行く」、すなわち人類の進歩のための「別の方法」の提案は、一点集中型のパワータイプではなく、世界の片隅で起こるささやかな、日常的なものから生まれる力をこそ指向する姿勢において一貫している。「予算の縮小」は自分の憶測でしかないが、しかしその姿勢は現在の恵比寿映像祭の佇まいとも良く一致する。世界の最先端の芸術や最先端の映像テクノロジーを見られる場ではないかもしれないが、ここにはこの場所ならではの、人類の未来を切り開く「先端」があるということなのだろう。新たな進歩は「片隅」や小さなコミュニティからこそ生まれ得るのである。2階の展示が「映像祭」の看板にもかかわらず、個々の作品に鑑賞者が個別に集中する映像作品中心の展示ではなく、作品同士が入り混じる広場のような造りにしたのもそうした意図からなのではないか。そこに集う人たちによる小さなコミュニティのようなもの(あるいはその感覚)の形成こそが企図されているのかもしれない。
同じことはオフサイト展示の「Poems in Code—ジェネラティブ・アートの現在/プログラミングで生成される映像」にも言える。恵比寿ガーデンプレイスのセンター広場に設置された巨大なLEDスクリーンに映し出されるのは、この手の映像祭にありがちな「世界最先端のCG映像!」などではない。むしろどこか時代錯誤でノスタルジックな感覚すらも漂う(敢えて言えば)プリミティブなCGである。実際、参加作家にはこの分野におけるトップランナーに加え、ワークショップに参加した一般のクリエーターも混じっている。つまりここで流されているのは、巨大資本による人と金を集中して作った「最新映像」ではなく、その対極にある個人による制作物なのだ。その個人のクリエーターたちがゆるやかに繋がって、ともに進歩するコミュニティのかたちこそがここでは示されているのだと言ってよい。つまりこれも大資本による旧来の映像進化の方法とは異なる、新しい映像表現の進化の在り方、つまり新しい「月へ行く方法」の一つなのである。
歴代の恵比寿映像祭はどの年もテーマが秀逸で、そのテーマと展示の内容がうまくかみ合っている年ほど鮮明に印象が残っている。その意味では今回の展示も、今後長く記憶に留まるものになるような予感がする。
※展示情報
恵比寿映像祭2024「月へ行く30の方法/30 Ways to Go to the Moon」
会期:2024年2月2日(金)~2月18日(日)[15日間]
月曜休館〈ただし12日(月・振休)は開館し、13日(火)休館〉
※コミッション・プロジェクト(3F展示室)のみ3月24日(日)まで
時間:10:00–20:00(18日は18:00まで)
※2月20日(火)~3月24日(日)のコミッション・プロジェクトは月曜休館 10:00–18:00(木・金は20:00まで)
※入館は閉館の30分前まで
会場:東京都写真美術館、恵比寿ガーデンプレイス センター広場、地域連携各所ほか
料金:入場無料 ※一部のプログラム(上映など)は有料
URL:https://www.yebizo.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
