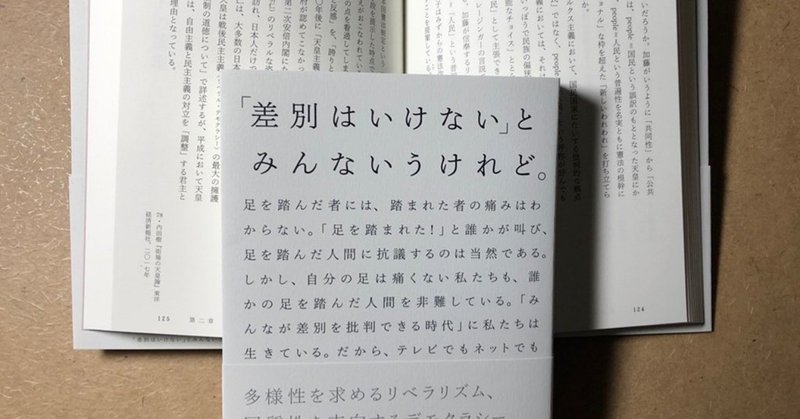
みんなが差別を批判できる時代ーーアイデンティティからシティズンシップへ
『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社、2200円)が7/18発売されて以来、さまざまな反響をいただいています。読者にも恵まれ、発売後即重版が決定、電子書籍版も発売されました!(8/30追記、3刷になりました!10/03追記、4刷になりました!) 今回、本書全体の見取り図となる「シティズンシップ」と「アイデンティティ」の論理を説明した「まえがき みんなが差別を批判できる時代ーーアイデンティティからシティズンシップへ」を公開します。
『「差別はいけない」とみんないうけれど。』の目次その他詳細は平凡社HPからご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まえがき みんなが差別を批判できる時代
(アイデンティティからシティズンシップへ)
本書は『「差別はいけない」とみんないうけれど。』と題されている。誤解されても困るので、まず最初に本書の立場を示しておこう。「差別はいけない」というのが大前提である。オフィスやキャンパスでセクハラをしてはならないし、朝鮮人にたいするヘイトスピーチ(差別表現)をネットに書き込んではならない。そして、このような考えはほぼ常識化しており、みんなが「差別はいけない」という時代になりつつあるといっていい。
しかし、世の中には「差別はいけない」ということに反発・反感を覚えるひとも一定数存在する。本書はそのような反発・反感には、それなりの、当然の理由があると考える。セクハラやヘイトスピーチが跡を絶たないのは、「差別はいけない」と叫ぶだけでは解決できない問題がその背景にあるからである。本書は、彼/彼女らの反発を手がかりにして、差別が生じる政治的・経済的・社会的な背景に迫っていきたい。本書のタイトル『「差別はいけない」とみんないうけれど。』にはそんな意味が込められている。
「ポリティカル・コレクトネス」という言葉が本書のキーワードとなる。「差別はいけない」という考えに強く反発するひとびとは、しばしばこの「ポリティカル・コレクトネス」(もしくは略して「ポリコレ」、「PC」)を憎々しげに使うからだ。ドナルド・トランプ大統領が誕生したアメリカ大統領選(二〇一六年一一月)で初めて耳にしたひとも多いだろう。「ポリティカル・コレクトネス」に反発したひとびとが、トランプの勝利を後押しした、とたびたびニュースで解説された。「ポリティカル・コレクトネス」については第一章で詳しく説明するが、ここでは「みんなが「差別はいけない」と考え、あらゆる差別を批判する状況」のことだとしておこう。
ハリウッド映画プロデューサーのハービー・ワインスタインの性暴力・セクハラにたいする告発から始まった#MeToo運動、日本の女性新聞記者への財務省事務次官によるセクハラ発言、杉田水脈(みお)衆議院議員によるLGBT生産性発言と掲載誌『新潮45』の休刊、ジャーナリスト広河隆一による性暴力にたいする告発と『DAYS JAPAN』の休刊……。ここ数年で起こった差別にかんする騒動の一部だ。「セクハラ」や「ヘイトスピーチ」問題がテレビで大々的に取り上げられ、インターネットで炎上するのは、いまや見慣れた光景となっている。まさにみんなが差別を批判できる、「ポリティカル・コレクトネス」の時代が到来している。本書は、みんなが差別を批判できる時代を基本的には望ましいとしながらも、いっぽうでいくつかの問題点があると考えている。これが、本書のタイトル『「差別はいけない」とみんないうけれど。』に込められたもうひとつの意味である。
実は、みんなが差別を批判できるようになったのは、つい最近のことなのだ。かつては差別を受けた当事者(被差別者)だけが差別を批判できる、という考えが支配的であった。この変化は、単に「差別はいけない」という考えがひろく世間に浸透したからではない。差別を批判する言説に大きな転換があったためである。その転換は「アイデンティティ」から「シティズンシップ」へ、とまとめることができる。この「まえがき」では、「差別はいけない」という反差別言説には、「アイデンティティ」と「シティズンシップ」というふたつの論理があることを示しつつ、本書全体の構成を説明したいと思う。
「足を踏んだ者には、踏まれた者の痛みがわからない」という有名な言葉がある。差別は差別された者にしかわからない、という意味だ。いくら想像力を働かせたとしても、踏まれた他者の痛みは直接体験できない。だから、当事者(被差別者)以外の人間が批判の声をあげたとしても、当事者にたいして引け目を感じざるをえないはずだ。痛みを直接体験できない人間は正しく差別=足の痛みを理解しているのか、みずからに問いかけ続けるしかないからである。しかし、ここ数年の炎上騒動において状況はあきらかに異なっている。ひとびとは、自分は本当に差別をしていないか、と省みることなく、差別者を批判している。ここに、差別を批判するロジックが「アイデンティティ」から「シティズンシップ」にかわったことが見てとれる。
差別は特定の人種、民族、ジェンダー、性的指向や障害などを持つ人間を不当に扱う行為である。また、差別は個人が所属する社会的カテゴリーにたいする偏見から生じる。これら不当に扱われるアイデンティティ(帰属性)を持つ集団が、社会的地位の向上や偏見の解消を目指す政治運動をアイデンティティ・ポリティクスと呼ぶ。たとえば、フェミニズムは家庭に閉じ込められていた女性の社会進出をうながし、「女性は感情的だ」とか「母性本能」といった男の偏見にたいして闘ってきた。
「足を踏んだ者には、踏まれた者の痛みがわからない」とは、マイノリティがマジョリティにたいして、しばしば非難の意味を込めて向ける抗議であり、論理である。たとえば、筆者はヘテロ日本人男性だが、「在日朝鮮人やゲイの苦しみがわかるか」と問われれば、やはり「わからない」と答えるしかない。アイデンティティをそう簡単に取りかえることはできないからだ。杉田水脈の「LGBTは生産性がない」発言を取りあげると、杉田を本来批判できるのは、性的マイノリティの当事者だけということになる。それ以外の人間は直接的・間接的に差別に加担しているかもしれないからである。しかし、この事例では、周囲の人間たちは実に雄弁で、当事者以上に前面に出て杉田の発言を批判していたように思われる。
アイデンティティの論理ではなく、シティズンシップの論理が差別やセクハラの炎上騒動の背景となっている。それは、当事者/非当事者を問わず、ひとりの「市民」として差別を批判する立場である。ヘイトスピーチを例に出して見てみよう。
二〇〇九年ごろから、「朝鮮人を殺せ!」といった差別表現を叫びながら、コリアンタウンである東京・新大久保や大阪・鶴橋をデモする団体が登場し、社会問題化した。最も知られるのが在特会(在日特権を許さない市民の会)で、二〇一〇年には京都の朝鮮学校のまえで街宣をおこない、メンバー四人が逮捕されている。このようなヘイトスピーチにたいして、マイノリティである在日朝鮮人・韓国人など当事者にくわえ、マジョリティである日本人側からも、在特会のデモ行動や排斥的・差別的言動を阻止しようとカウンター活動が活発化した。人種や民族や国籍にかんする差別的言動を禁じるヘイトスピーチの規制を求める声があがり、二〇一六年にヘイトスピーチ解消法(「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)が成立・施行された。
アイデンティティ・ポリティクスを規準にすれば、在特会を批判できるのは、そのヘイトスピーチの対象となっている在日朝鮮人らだけである。では、どのようなロジックで日本人は、日本人による在日朝鮮人らにたいするヘイトスピーチを批判したのか。対レイシスト行動集団C.R.A.C.(前身団体「レイシストをしばき隊」)を結成した野間易通(やすみち)は、アメリカの政治哲学者ジョン・ロールズの「秩序ある社会」、そして「公正としての正義」を目指したと述べている*1。
ここでは、同じくロールズに依拠しながら、ヘイトスピーチ規制法の必要性を訴えているアメリカの法学者ジェレミー・ウォルドロンを見てみよう。ウォルドロンはヘイトスピーチ規制法が保護するものについて次のように述べている。
ヘイトスピーチを規制する立法が擁護するのは、(あらゆる集団のあらゆる成員のための)平等なシティズンシップの尊厳である。そしてそれは、(特定の集団の成員についての)集団に対する名誉毀損が市民から成る何らかの集団全体の地位を傷つける危険があるときには、集団に対する名誉毀損を阻止するためにできることをするのである*2。
ここで重要なのは、法が守るのは「平等なシティズンシップの尊厳」であるということだ。この文の前の箇所では、尊厳とは「集団の個々の成員」の「尊厳」なのであって、「集団そのものの尊厳や、集団をまとめる文化的または社会的構造の尊厳」*3ではないと注意をうながしている。つまり、尊厳とは「市民」の尊厳であって、民族や人種といったアイデンティティの尊厳ではないのである。
野間とウォルドロンの両者がロールズに依拠するのは、ロールズがあらゆる社会的アイデンティティにかかわらない正義を考えたからだ。『正義論』においてロールズは、ひとびとが正義の原理を選択する際に、「誰も社会における自分の境遇、階級上の地位や社会的身分」や「もって生まれた資産や能力、知性、体力」*4などがまったくわからない状態=「無知のヴェール」に覆われた状態を想定した。ここで注意すべきは、あらゆるアイデンティティが「無知のヴェール」に覆い隠されることだ。
「市民」であれば、だれもが差別を批判できる。これがシティズンシップの論理である。差別やパワハラの炎上騒動で当事者以外の人間がとても雄弁だったのは、この正義を前提にしているからだ。
シティズンシップの論理であれば、アイデンティティ・ポリティクスが持つ問題点も避けることができる。「足を踏んだ者には、踏まれた者の痛みがわからない」という言葉をもう一度考えてみよう。重要なポイントは「足を踏む」という比喩である。「殴る」や「蹴る」は意図的な行為だが、「足を踏む」は意図的とはかぎらない。だれしも電車のなかで無意識に他人の足を踏んでしまった経験があるだろう。自分が踏んでいたことに気づかなかったこともあったかもしれない。そのような行為が差別の比喩として用いられている。差別かどうかを決めるのは特定のアイデンティティを持つ当事者だ。たとえ、反差別運動に積極的にコミットしているひとであっても、いくらそのひとが意図したわけではなかったとしても、差別とみなされる可能性がある。
差別者と被差別者のあいだには差別をめぐっていちじるしい認識のギャップがある。反差別運動は、たとえ差別する意図がなかったとしても、差別者には責任があるという考えを前提としてきた(「第六章差別は意図的なものか」)。差別を理解できない人間にとって、自身の差別を批判されることは、いわれのない言いがかりを受けているようにしか思えない。自分は差別していると思っていないのに、おまえは差別していると批判されるからだ。それが昂じると、自分がマジョリティであるというだけで差別だと非難されるのか、と間違った被害者意識を持つ者が出てくる。アイデンティティ・ポリティクスはマイノリティによる反差別運動だった。しかし、いま反ポリコレを訴えるマジョリティによるアイデンティティ・ポリティクスが登場しつつある理由はここにある(「第一章ポリティカル・コレクトネスの由来」)。
アイデンティティの論理を前提とすると、いくら反差別運動に献身的にコミットしたとしても、差別に問われる可能性がある。先ほど説明した野間のカウンター団体も、日本人男性が中心のメンバーだったため、「日本人ばかりではないか、朝鮮人差別だ」「女性が少ないではないか、男性中心主義だ」と批判が集まったという。しかし、野間は、そのような批判は運動を停滞させるだけだとして、アイデンティティ・ポリティクスを運動の原理に据えなかったことに積極的な価値を感じているようだ。たしかに野間が指摘するとおり、アイデンティティの論理はしばしば運動内部に亀裂や対立をもたらしてしまう。当事者・非当事者にかかわらず、広範なかたちで反差別運動をつくるためには、やはりシティズンシップに基づいた考え方が必要となる。
シティズンシップの論理は、非当事者をふくめたみんなが差別を批判できる状況をつくった。しかし、いっぽうで差別批判を「炎上」という娯楽にしてしまったといえる。インターネットだけでなく、週刊誌・ワイドショーで消費される格好のネタになった。ここ数年の炎上騒動は、差別者を一方的に悪者に仕立て上げる傾向がある。それが可能なのは、みんなが自身が持つ差別性を問われることなく、安心して差別者を糾弾できるからだ。そのため、差別の原因や背景などが考察されないまま、どのような社会的制裁を受けるか・与えるかばかりに注目が集まり、そして新たな差別者の告発に躍起になる。しかし、本当に差別者だけが悪なのか。私たちだけが善なのか。シティズンシップの論理は、もしかしたら差別をしているかもしれない、とみずからに問いなおすこと、差別とは何か、と考えるきっかけを失わせている。
スケープゴートとは、みずからの罪を償うために、一匹の山羊に罪をかぶせて荒野に放つ宗教的儀式のことだが、いま目のまえで繰り広げられているスケープゴートでは、私たちが犯しているかもしれない罪=責任を、差別者たちに背負わせて追放しているかのようだ。差別者を糾弾し断罪するだけでは差別はなくならないし、みんなで差別者を排除することで、抽象的な理念にとどまりがちな「市民」に、「私たちは差別者ではない、同じ市民である」という「同質性」をなんとかして確保し、「市民」としての結束を高めようとする儀式に成り果てている(「第五章合理的な差別と統治功利主義」、「第六章差別は意図的なものか」)。繰り返すが、本書は、みんなが差別を批判できる時代は望ましいという立場をとるが、スケープゴートというかたちで、差別批判が「炎上」として消費されることには抵抗したい、本書はその抵抗のための手がかりになりたい、と考えている。
アイデンティティとシティズンシップ。このふたつの論理ははっきりと区別されるわけではない。反差別運動においてときには協働し、ときには対立してきた。本書では、みんなが差別を批判できる時代の問題点をさらに考えていくために、アイデンティティとシティズンシップというふたつの反差別のロジックをもう少し細かく検討したい。その特徴を簡単にまとめると次の図のようになる。

この整理は、ドイツの法学者カール・シュミット(一八八八–一九八五)の理論によっている*5。いま私たちは選挙で政治家を選び、政治家たちが国会で議論し法律を制定し、議会で首相が選ばれる政治制度のもとで暮らしている。私たちはこの政治制度をリベラル・デモクラシーと漠然と呼んでいる。しかし、シュミットは、ここには「自由主義」と「民主主義」というふたつの政治システムが組み合わさっていると指摘する。詳しくは第一章で述べるが、シュミットによる「自由主義」と「民主主義」のちがいについて触れておこう。
シュミットによれば、「自由主義」とは「討論による統治」*6を信念としているという。シュミットは、自由主義の特徴として次の三つをあげている。
一、「諸権力」が討論し、そのことを通じて共通に真理を求めるよう、つねにしむけられていること、
二、すべての国家生活の公開性が、「諸権力」を市民の統制のもとにおいていること、
三、出版の自由が、市民をして、自らの真理を求め、それを「権力」に向かって発言するように促していること*7
討論をおこなうためには、「公開性」がなければならない*8。議会でどのようなことが議論されているか、市民は知らなければならないし、市民がどんな考えを持っているか、を公表できなければならない。そのためには「言論の自由、出版の自由、集会の自由、討論の自由」*9も必要となってくる。また、議会だけでなく、複数の権力機関が「討論」しなければならないという考えから、立法権、行政権、司法権がそれぞれ抑制し合うという三権分立の考えが生まれてくる。「多様」な意見を持った「個人」が「市民」として討議するのが自由主義である。いっぽうで、シュミットは、民主主義の特徴として「同一性」をあげている。
治者と被治者との、支配者と被支配者との同一性、国家の権威の主体と客体との同一性、国民と議会における国民代表との同一性、[国家とその時々に投票する国民との同一性]、国家と法律との同一性、最後に、量的なるもの(数量的な多数、または全員一致)と質的なるもの(法律の正しさ)との同一性、である*10。
また、シュミットによれば、「同一性」を担保とする民主主義は、同じ民族である、同じ言語を使うといった「同質性」が必要となる。そして、その「同質性」を保つためには、「必要があれば、異質なるものの排除あるいは殲滅が必要である」とさえいわれている*11。
また、この自由主義と民主主義は平等をめぐっても異なる考え方を示す。シュミットによれば、あらゆる人間は平等であるという人権思想は自由主義的である。しかし、絶対的な人間の平等は、「概念上も実際上も、空虚などうでもよい平等」*12であるために、経済という「政治上の外見的平等のかたわらで、実質的な不平等が貫徹しているような別の領域」*13を生んでしまう。たいして、民主主義は「国民としての同質性」*14があるために、一国内にかぎられるとはいえ、「国籍を有するものの範囲内では相対的にみて広汎な人間の平等」*15を実現する。
さて、シュミットの「自由主義」と「民主主義」の区別を踏まえると、アイデンティティとシティズンシップという反差別言説のふたつのロジックは次のように整理できる。アイデンティティ・ポリティクスとは、社会的不利益を被っているアイデンティティを持つ集団が結束して社会的地位の向上を目指す政治運動だった。たとえば、黒人という人種、女性という性別、朝鮮人という民族といったさまざまなアイデンティティに基づいた政治運動が存在するが、しかし、それらはすべてアイデンティティの「同質性」をもとにしているために、シュミットの区分にしたがえば、民主主義に属するものといえる。
いっぽうでシティズンシップの論理は、あるアイデンティティを持った「集団そのものの尊厳」ではなく、「平等なシティズンシップの尊厳」を守るものであった。つまり、シティズンシップの論理では、「市民」という「個人」の権利が重視されている。そして、シュミットの区分にしたがえば、個人の権利、人権もまた自由主義的な考えであった。しかし、ここで注意すべきなのは、シュミットは「自由主義的な個人意識と民主主義的な同質性」は「克服できない対立」*16であると述べていることだ。これから現在の政治状況を見ていくが、シュミットの指摘は正しいように思われる。アイデンティティとシティズンシップの論理もまた「克服できない対立」なのである(「第二章日本のポリコレ批判」参照)。
このように整理すると、反差別言説がアクチュアルな政治問題と深くかかわっていることがわかる。現在、先進諸国では移民排斥を訴える極右勢力の台頭がいちじるしい。これらの運動は単なる「ポリティカル・コレクトネス」への反発なのではない。KKK(クー・クラックス・クラン。アメリカの人種差別主義的秘密組織)や在特会といった排外主義は、実はアイデンティティ・ポリティクスをおこなっているのだ。白人や日本人の誇りを取り戻そうとする運動だからだ。彼らは「逆差別」という言葉を用いて、マジョリティである私たちが逆にマイノリティによって虐げられている、と主張する。もちろん、両者でその主張内容は大きく異なるが、在特会といった日本人による排外主義は、形式面においては在日朝鮮人のアイデンティティ・ポリティクスとまったく同じことをしているのである。
たとえば、EU諸国ではEUが加盟国にたいして社会保障費や公共事業費の削減などを求める緊縮財政政策への反発が起こっている。社会福祉の充実などを掲げて、EUに奪われている国家の主権を取り戻し、あらためて自国に民主主義を取り戻そうとする反緊縮運動が起こっているのである。ギリシャ債務危機後に政権を獲得した「シリザ」や、左派ポピュリズムの成功例としてしばしば言及されるスペインの「ポデモス」、二〇一八年に政権を獲得したイタリアの「五つ星運動」などが反緊縮政策を掲げる政党として知られている。ここで、シュミットの自由主義と民主主義の観点に立てば、このような反緊縮運動と排外主義的なアイデンティティ・ポリティクスとのかかわりが見えてくる。
まずEUが進める経済の自由化は自由主義的な政策である。EUにたいする反緊縮運動は民主主義的な傾向を持つ。シュミットによれば、経済とは自由主義の最たるものであり、「政治上の外見的平等のかたわらで、実質的な不平等が貫徹しているような別の領域」であった。これにたいして民主主義は「国籍を有するものの範囲内では相対的にみて広汎な人間の平等」を実現する。つまり、経済格差の是正を求める運動は民主主義的なのである。
しかし、いっぽうで、民主主義は「同質性」を必要とする。同じ文化や言語を共有する民族が、民主主義の「同質性」の担保となる場合が多い。たとえばEUによるシリア内戦の難民受け入れ政策は、あらゆる人間に人権があるという発想のもと、市民の多様性を重視する政策である点で自由主義である。しかし、このような難民の受け入れは、民主主義の「同質性」を危うくするものである。シュミットの定義によれば、民主主義はその「同質性」を保つために「異質なるものの排除あるいは殲滅が必要であ」ったことを思い出そう。そのため、EUの政策に反対する運動からは、民族の「同質性」を保つために「移民」を排除する傾向がどうしても生まれてくる。先に指摘した、マジョリティによるアイデンティティ・ポリティクスが台頭するのである。移民排斥と格差是正を求めることはともに民主主義の帰結なのである。
まとめると、自由主義的(反民主主義的)で多様性を標榜するEUと、移民排斥を訴え、民族の同質性を志向する、民主主義(反自由主義的なもの)との対立ということになる。このような観点からすれば、反緊縮運動の困難さを指摘することができる。反緊縮運動ではEU各国の運動が国境を越えて連帯することの必要性が説かれるが、経済格差の是正(同質性)を求める運動が民主主義的であるかぎりにおいて、移民排斥をとなえる排外主義も台頭するのである。EUの緊縮政策や移民政策に反発し、国民投票でEUからの離脱を決定したイギリスや、反緊縮政策を掲げる「五つ星運動」が反移民を掲げる極右政党の「北部同盟」と連立政権を組んだイタリアなどの事例が、反緊縮運動の困難さを象徴している。
そして、問題はそのような排外主義的な運動が、「ポリティカル・コレクトネス」への反発というかたちをとることである。いま現在「ポリティカル・コレクトネス」と呼ばれるシティズンシップの論理は、上流階級の道徳、つまり「ブルジョワ道徳」とみなされる傾向があるからだ。これには性表現や差別表現の規制にかんして「ハラスメント」という考えが重要な役割を果たしてきたことが関連している。
第三章で説明するが、アメリカでは性表現や差別表現にたいして法的規制はされてこなかった。アメリカ合衆国憲法修正第一条で、「表現の自由」を妨げる法律を制定することを禁止しているからだ。しかし、いっぽうで、企業や大学においては性表現や差別表現は「レイシャル・ハラスメント」(人種的ハラスメント)や「セクシャル・ハラスメント」として禁止されてきた。先に紹介したウォルドロンは、ヘイトスピーチを禁止する法律を、キャンパスやオフィスで実施されている「ハラスメント」の禁止規定を社会全体に広げたものだととらえている。
「ハラスメント」規制がすでに実施されている大学や企業に勤める人間からすれば、ヘイトスピーチを禁止する法整備は当然のこと、あたりまえのことのように思われる。しかし、大学や企業と無縁な貧しいひとびとからすれば、このような「ポリティカル・コレクトネス」の普及はどう見えるだろうか。上流階級の道徳にしか見えないのではないか。経済格差の是正を求める民主主義的な運動において、排外主義的な傾向だけでなく、「ポリティカル・コレクトネス」に反発する傾向があるのはこのような理由による。
さて、アイデンティティ(民主主義)とシティズンシップ(自由主義)の対立、という本書のおおまかな見取り図は示すことができたと思う。最後に本書の構成について、簡単に触れておこう。すでにいくつか言及したが、みんなが差別を批判できる時代の問題点を考えるために、以下の問題を論じたい。
❖第一章 ポリティカル・コレクトネスの由来
「ポリコレ」と呼ばれているものの歴史的由来は、意外に知られていない。この言葉は、一九九〇年代以前は、アメリカのフェミニズムや黒人運動の内部で、階級闘争を目指し共産党=前衛党を支持する古い左翼を皮肉った表現として用いられていたが、九〇年代初頭、保守派によるリベラルな価値観や教育を攻撃する言葉として転用されるようになる。「ポリコレ」という言葉が登場した背景には、冷戦終結後の民族主義の台頭に直面した多民族国家アメリカの危機感があったことを、哲学者のアラン・ブルームやリチャード・ローティ、歴史学者のアーサー・シュレージンガーらの言説から指摘したい。
❖第二章 日本のポリコレ批判
アメリカの「ポリコレ」をめぐるブルームやローティらの議論は、日本の言論においてだれの主張に相当するだろうか。本書では評論家の内田樹(たつる)『ためらいの倫理学』が、「ポリコレ」批判の典型的な言説だと考えている。くわえて文芸批評家の加藤典洋『敗戦後論』をめぐる哲学者の高橋哲哉らとの論争(歴史主体論争)、朴裕河(パクユハ)『帝国の慰安婦』をめぐる論争を、アイデンティティとシティズンシップの観点から再解釈し、このふたつの論理が「克服できない対立」にあることを示す。
❖第三章 ハラスメントの論理
いま私たちが「ポリティカル・コレクトネス」と呼ぶ言説は、ブルームや内田樹が批判した言説とはあきらかに異なっている。現在の反差別言説であるシティズンシップの論理において、「セクシャル・ハラスメント」「レイシャル・ハラスメント」といった「ハラスメント」という考えが重要な役割を果たしている。
なぜ「ハラスメント」が性表現や差別表現を規制する根拠になったのか。弁護士のキャサリン・マッキノンによるポルノグラフィ規制論にまでさかのぼって考えたい。
❖第四章 道徳としての差別
近年、発展の目覚ましい認知心理学や行動経済学において、人間の生物学的・進化的特性があきらかになってきている。人間本性にかんする新しい知見は、「差別はいけない」という考えが一般的になった現在においても、差別が一向になくならない理由を教えてくれる。人間は論理的な思考があまり得意ではなく、偏見やステレオタイプを免れない傾向があることがわかっている。しかし、そのいっぽうで、人種間や男女間の生得的なちがいを示す科学的な知見が、マジョリティによるアイデンティティ・ポリティクスによって、市民という理念(シティズンシップの論理)の空虚さを暴露することに悪用されている現状を指摘する。
❖第五章 合理的な差別と統治功利主義
近年、ファクトやエビデンスに基づかないフェイクニュースが社会問題化した。そのような差別的言説の多くが、読者に真実と思い込ませるために黙説法(もくせつほう)や言い落としといったレトリックを多用する傾向がある。しかし、将来より問題になると予想されるのは、ファクトやエビデンスに基づいた差別的言説であることを指摘する。ここで重要なのは、差別的であることと合理的であることはまったく別だという認識を持つことである。また、認知心理学などの人間本性の新しい知見は、近代リベラリズムが理想とした「自律」的な「個人」という人間像を覆しつつある。個人の「自律」に期待しても叶わないので、周囲の環境を介して、パターナリスティックに個人の行動に(知らぬ間に)介入し、よりましな行動を導こうとする「ナッジ」という手法を使った「アーキテクチュア」による「統治」が近年存在感を増しつつある。人種間や男女間のちがいを示す科学的な知見は、市民という理念の空虚さを暴露するだけでなく、このような「アーキテクチュア」による「統治」を導く危険性があることを示す。
❖第六章 差別は意図的なものか
「足を踏んだ者には、踏まれた者の痛みがわからない」という表現が示唆するのは、足を踏んだ側(差別者)と踏まれた側(被差別者)の認識にギャップがある、ということだ。しかし、人間は、みずからの意志によらない行為の責任をとれるだろうか。近代法の理念では、人間(成人)は原則的に自由意志の主体であり、主体は行為を選択できるので、その選択の結果生じる事態に責任を持つとされる。しかし、差別においてこのような想定は成り立たないのではないか。差別においては、行為者の意図とかかわりなく、行為の結果によって責任があるかどうか判定されるからだ。このような責任理論は、「内なる差別」という言葉に象徴される、あたかも宗教的な罪があるかのような、差別にたいする責任の過度な内面化を生む。そして、このような責任理論もまた、マジョリティによるアイデンティティ・ポリティクスに悪用されており、差別主義者も反差別主義者も互いの「責任」を追及し合うという現状に陥っている。「ポリティカル・コレクトネス」が持つ息苦しさやうっとうしさはこの責任の問題に起因する。
❖第七章 天皇制の道徳について
二〇一九年五月に新天皇が即位したが、平成における象徴天皇制にたいしては、しばしばその「リベラル」な価値観を支持する言説が多かった。しかし、日本だけでなく、立憲君主制を採用する世界各国の君主が「ポリティカル・コレクトネス」の道徳を体現するかのように振る舞っている。このような君主のリベラル化は、君主制と民主主義を両立させようとするパラドックス(矛盾)から生じる。つまり、世襲による身分制度である君主制と、生まれによる特権や差別を許さない平等主義的な民主主義を両立させることから生じる。そして、近年、自由主義と民主主義の対立があらわになるなかで、君主制がその対立を融和し、調整するような存在として支持されている現状を指摘する。
以上が、本書『「差別はいけない」とみんないうけれど。』の内容である。
1◆野間易通『実録・レイシストをしばき隊』河出書房新社、二〇一八年、三三〇頁
2◆ジェレミー・ウォルドロン『ヘイト・スピーチという危害』谷澤正嗣+川岸令和訳、みすず書房、二〇一五年、七二頁
3◆ウォルドロン『ヘイト・スピーチという危害』七一頁
4◆ジョン・ロールズ『正義論』川本隆史ほか訳、紀伊國屋書店、二〇一〇年、一八頁
5◆カール・シュミット『現代議会主義の精神史的状況』樋口陽一訳、岩波文庫、二〇一五年。また、「自由主義」と「民主主義」の観点から差別を読み解いた先駆的な著作として、絓秀実『「超」言葉狩り宣言』太田出版、一九九四年
6◆シュミット「議会主義と現代の大衆民主主義との対立」『現代議会主義の精神史的状況』樋口陽一訳、岩波文庫、一三九頁
7◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』三六頁
8◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』三八頁
9◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』三八頁
10◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』二三頁
11◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』一三九頁
12◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』一四四–一四五頁
13◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』一四六頁
14◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』一四五頁
15◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』一四五頁
16◆シュミット『現代議会主義の精神史的状況』一五四頁
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
