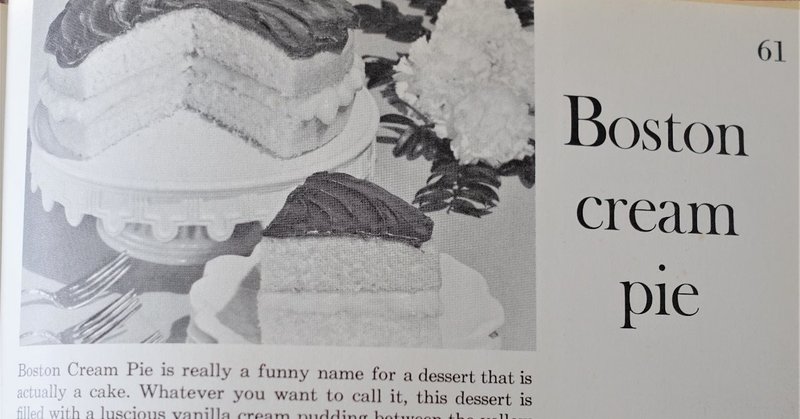
思い出のアメリカン・フード (3:ボストンクリームパイ)
第3章 ボストンクリームパイというケーキ
パイというものには二種類ある。一つはフランス式の折りパイで、もう一つはアメリカ式の、パイ生地をパイ皿に敷き込んでフィリング(詰め物)を入れて焼いたものである――という説明を、どこかのお菓子の本で読んだことがある。
しかし、今回の話題のボストンクリームパイはどちらにも当たらない。黄色味の強い丸形スポンジケーキの厚みを二つに切り、流れずに形を保つくらいの固さのカスタードクリームを間に挟んで、上にダークチョコレートのグレーズをかけたお菓子を指す。ケーキなのにパイという名前なのは、昔はケーキもパイも同じ型で作っていたので、両方の言葉が意味の区別なく使われていたことに由来するという。歴史的背景のある名前なのだ。
この原稿を書くにあたり、ネットで画像検索をしてみたところ、今は黄色くない普通のスポンジケーキを使うのが主流になっているようだ。しかし、記憶にあるものは間違いなく黄色かった。
初めてボストンクリームパイを食べる機会があったのは、アメリカに家族で住んでいた小学生の頃だった。冷たいたっぷりのカスタードクリームとスポンジ、濃いチョコレートとの組み合わせがとても印象的で、これを何とかもう一度食べたいものだと日本に帰国してからもときどき思い出していた。
上の参考写真は、第2章で紹介した古い子ども向け料理本の、ボストンクリームパイの作り方のページから引用している。じゃあそれを見て作ればいいじゃないかと思われるかもしれないが、困ったことに材料が手に入らない。スポンジ台は市販のイエローケーキのミックスで、クリームはインスタントのヴァニラプディングのミックスで作るという指示で、これらはアメリカのスーパーマーケットなら一般的に売っているだろうけれど、1980年代の北海道在住の中学生には手に入れようがない。そして本の指示通りにしたところで、記憶の味を再現できる保証はなかった。
十数年後。大学院生として再びアメリカに暮らすようになったが、ボストンクリームパイのことはほぼ忘れていた。それが再び意識に上ったのは、留学先のシカゴから夏休みの旅行先としてボストンを訪れた際だった。ボストンと名前にあるのだから、ここでなら食べられるのではないだろうか?
ボストン滞在中、定評あるシーフードレストランのメニューにボストンクリームパイを発見し、どきどきしながら注文してみた。ホールケーキからカットされたあの三角のピースと再会できるのを期待して待っていたところ、若いウエイターがしずしずと運んできたのは、記憶とは似ても似つかないお洒落なデザートだった。大きな皿の真ん中に、ガナッシュをかけた一人前サイズの円筒形ケーキがちょこんと鎮座しており、そこにチョコレートや生クリームを使ったデコレーションが施してある。思わず、「これはわたしの思っていたのと違う」と口走ると、ウエイター氏はちょっと肩をすくめ、「それなら、召し上がらなくても結構ですが……」と言った。いやまあ、見た目は違うけれども食べますと言って食べ始めたが、味もやっぱり憶えていたようなものではないのだった。せめて、ボストンクリームパイの概念が変わるほど素晴らしいデザートだとか何かあればよかったのだが、残念ながらそういうこともなかった。
留学を終えて日本に戻り、アメリカ人の級友から贈られた料理百科を見ていると、その中にボストンクリームパイの作り方があった。インスタントではなく、英語で言えば from scratch――いちから、つまり小麦粉や卵などの材料から作る方法である。パイではなく、ケーキの章に入れられている。「二層のゴールドレイヤーケーキの間にカスタードクリームを挟み、ケーキの側面は何も塗らず、上面にチョコレートアイシングを塗る」と指示があり、ケーキ台、クリーム、アイシングそれぞれの作り方のページが示されていた。お菓子を作る人なら経験があるように、ケーキには大きく分けて、主として泡立てた卵の力でふくらますもの(=スポンジケーキ。バターを入れる場合、後から液状に溶かして加える)と、砂糖とバターをクリーム状に泡立ててふくらますもの(=バターケーキ。後から卵を加える)との二種類があるが、ゴールドレイヤーケーキとは後者の方だった。日本で普通に見るレシピと異なるのは、全卵ではなく卵黄だけを加える点だ。なるほど、スポンジ部分が黄色いのはこのためだったのか。本当にこれでできるかどうか、やってみようか……。
この本に従って作ってみた結果を言えば、外見はそれらしくなったが、自分が昔食べたものの再現とはならなかった。スポンジ部分の食感が違うのだ。この料理百科は本格的なもので、アメリカではよく知られ権威もある書物なので、おそらくこれがオーソドックスな形だったのだろう。小学生の自分が食べたものは、ある意味で現代化された、要するに大量生産的に作られたものだったのではないか、と思い至った。
さらに十数年が経った一昨年、第1章でも触れた家族での北米旅行で、カナダの友人宅に滞在した。友人と一緒にスーパーマーケットに出かけ、商品棚を見ていると、ケーキミックスが目に留まった。イエローケーキのミックスもある。英語・フランス語併記のパッケージで、メーカー名も知らないものだったが、もしかしてこれでボストンクリームパイを作れるかもしれない、と直感が働いた。
そのミックスを買って帰り、自宅で作ってみると、果せるかな。「そうそう、こんなんだった!」と言いたくなる、三十年あまり前の記憶の通りのものができたのである。小学生の自分が忘れられなくなったケーキの味とは、北米のケーキミックスの味だったのだ……。
そして今年の秋。小学二年生で初めて北米を訪れ、あちらのものをいろいろ食べる経験をした娘が、アメリカのぶどうを札幌で食べている。北米ではぶどうの粒や一口大に切ったパイナップル、いちごなどを透明プラスチックのカップに詰めたものをよく売っているが、娘はその中に入っていた、皮ごと食べられる薄緑色の種なしぶどうを気に入って、また食べたいと言い出したのだ。
小学校の給食では巨峰が出るというし、近所のスーパーには、果物の産地として有名な余市町から届いたばかりのキャンベルやナポレオンが、通り過ぎる者の足を止めるほどの素晴らしい芳香を放って並んでいる。なのに、娘は美しくみずみずしい日本のぶどうには見向きもせず、長旅でくたびれた顔をしたアメリカのぶどうを選ぶのだった。「種がなくて、皮ごと食べられるのがいいの?」と訊いてみると、「味もこれが好き!」とご満悦である。そして、絞っても果汁が出ないのではないかと思われるほど水気が少なく実の締まったぶどうを、一口菓子をつまむように枝からちぎっては口に入れる。
子ども時代に何かを特に美味しいと感じた経験があると、その後の人生でもっと美味しいものに出会っても最初に気に入ったものを容易に忘れはしないし、他のものの方が美味しいからもうこれは食べなくていい、ともならないようだ。そうした味の記憶がわたしたちの気持ちや行動におよぼす力については、また稿を改めて書きたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
