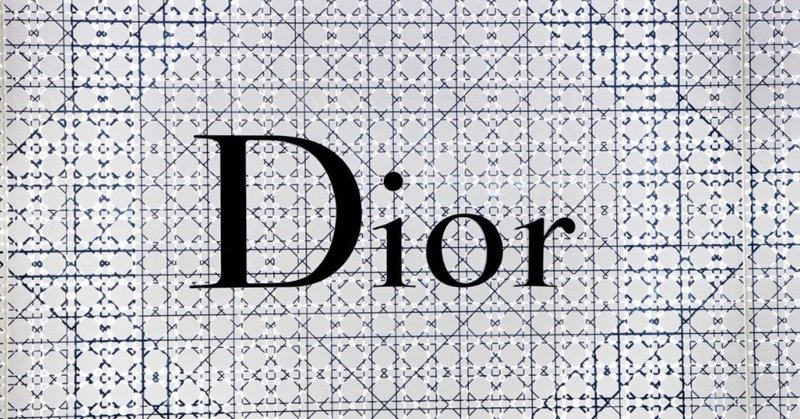
BTSに衣装提供… 老舗メゾン「Dior」を自由研究してみた(第1回)
5月2日(木)、BTSのスタジアムツアー「LOVE YOUR SELF:SPEAK YOURSELF」の衣装を、Diorが手掛けることが発表された。
衣装はツアーのキックオフだったLA公演で披露された。その後、5月25日(土)サンパウロ公演、6月1日(土)ロンドン公演、6月7日(金)パリ公演でも着用されるとアナウンスされた。
これまでBTSは、Billboard Music Awardsなどの授賞式、自国の音楽番組、サイン会、空港など、さまざまなところでラグジュアリーブランドを身にまとってきた。そのたびにSaint Laurentだ、GUCCIだ、BALENCIAGAだと騒がれ、それを「すごいなぁ」と眺める一方で、そのブランドにどんな歴史があり、特徴があり、何がすごいのかが一切わからない、教養のなさが浮き彫りになる気がした。
そんななかで発表されたのがDiorの衣装提供だった。これを良い機会だととらえ、今回はDiorの系譜やイズムを掘り下げてみることにした。
大半は創設者クリスチャン・ディオールのエピソードになるが、最後にBTSの衣装を担当したメンズ部門クリエイティブ・ディレクター、キム・ジョーンズについても少しふれたいと思う。
Diorの規範は「エレガンス」
Diorと聞いてどのようなイメージが思い浮かぶだろうか。おそらく、多くの人が「フェミニン」「エレガント」というような言葉で形容するのではないだろうか。
ドレスはもちろん、コレクションのオープニングの定番、ブラックルックでさえもシルエットはとても女性的だ。胸のふくらみに対するウエストのくびれなど、美しいラインが目にとまる。
Diorはなぜここまで女性的なエレガンスを守り続けるのか──その“規範”を紐解くには、ディオールが幼少期に培った"美しさ"の価値観、そして彼が生き抜いた時代の背景を知る必要がある。
というわけで、ディオールの生い立ちを見ていこう。
ピンク、花模様、ハイヒールをはいた脚
1905年、フランスのグランヴィルで生まれたクリスチャン・ディオール。5歳でパリに引っ越すまで暮らした生家がこれだ。
現在は政府が買い取り、美術館「Musée Christian Dior」として公開されている。
この生家は、ディオール自身が「私の生活も趣味も、すべてこの家の影響を受けている」と断言するほど、彼の価値観と美意識の形成に大きくかかわっている。
まずは色。ディオールの好きな色はピンクとグレー。フェミニンかつ洗練されたその色合いは、まさに生家の壁の色の影響だった。
そして審美眼。いたるところに芸術品が飾られていた生家。玄関には五重の塔、階段の壁には北斎の版画があったという。そのような日本芸術の影響から、花や鳥をシルクに刺繍したものをコレクションに用いたこともあった。
また、デザインに多用される花・植物好きの一面もこの時代に形成されている。母親の花好きを譲るように、ディオールも花を愛した。フランスの老舗種子会社「ヴィルモラン」が出版した植物図鑑がお気に入りで、それを見ながら植物を覚えていたそうだ。
これらの様子から察しがつくと思うが、ディオール一家は裕福なブルジョワだった。召使いもいたほどだ。それもまた、Diorのベースにある重要なファクターだと私は考える。
追って紹介するが、青年~壮年期のディオールには数々の困難が訪れる。そのなかには戦争という不可抗力によるものもある。
しかし、心が折れ、愛したパリに戻れなくなったときも、ディオールは"美しさ"が持つ力をずっと信じていた。そして、一生を通じて、暗い時代を憎んだり、他人を嫉んだり、金や名声へ執着したりといった"心の貧しさ"は、自伝からは一切感じられなかった。
グランヴィルでの裕福な日々は、何の心配もなく、美しいものを素直に心の栄養にし、生涯にわたって素養としたという意味で、ディオール史では欠かせない要素なのだ。
そんな幼少期を経て、5歳のときにパリへ引っ越す。新しい家はルイ16世様式。装飾レースのカーテンなど、軽やかで美しい内装だった。これはのちにDiorの内装に影響することになる。内装はドキュメンタリー映画「ディオールと私」で観ることができる。
花模様、華やかなもの、美しいもの、軽やかなものは「何時間見ていても飽きなかった」というディオール。ファッションにはあまり興味がなかったそうだが、9歳のときにはある“クセ”があったそうだ。それは、教科書に、ハイヒールをはいた女性の脚を落書きすること。
ディオールの趣味嗜好やこのエピソードから勘付く方もいると思うのだが、ディオールはゲイだった。
また、明記されている資料は見つけられなかったのだが、おそらく、トランスジェンダーだったのではないかと思われる。いわゆるMTF(Male To Female)=体は男性、心は女性の状態だ。そのなかでも、性転換や容姿(女装など)までは望まずとも、女性に近づきたいという願望があったタイプなのではないだろうか。
Diorのデザインは、フェミニンで、ロマンチックで、エレガントだ。しかし見様によっては、それらは過度にフェミニンで、過度にロマンチックで、過度にエレガントなものでもある。
ディオールが体と心が同じ性で生まれていたら、それが男性でなく女性であったとしても、あのデザインは生まれなかったのではないか。体が男性だったがゆえに、手の届かない女性性への思いは日に日に研ぎ澄まされていった──だからこそ、あの圧倒的なフェミニンとエレガンスが生まれたのではないか。
それこそが最初のコレクションでバッシングを受ける一因にもなるのだが、それはまたのちほど記述する。
建築家になりたかったディオール
第一次世界大戦が始まった1914年。14歳のディオール少年は、バザーで出会った占い師にこんなことを言われたそうだ。
「あなたは、婦人によって利益を得る」
まさにディオールの未来を言い当てているのだが、当時はもちろんピンとこなかった。しかし、このときからかはわからないが、ディオールは生涯を通して占いに信頼を置いている。メゾン設立時も後押しされたほどだ。
戦後は大学入学試験の準備をしながら、アーティストの友達をたくさん作った。そのなかには画家のサルバドール・ダリ、詩人のマックス・ジャコブなどがいる。決して楽観視できない時代だったが、アバンギャルドなアート友達と、好きなもの、美しいものの話に花を咲かせ、青春時代を過ごした。
進学先は建築を学ぶため美術学校を希望。グランヴィルの生家やパリの実家のエピソードからもわかるように、ディオールは建築への興味を自覚していた。
しかし、両親が反対したため法律学校へ進学。それでも、この報われなかった建築への思いは、長い目で見たときに功を奏することになった。ディオールは自分のデザインについてこんなふうに語っている。
「私の作る衣装は女性の体のプロポーションを美しく見せる、瞬間的な建築」
つまり、ファッションにおける間接的な表現技法として建築を使っているのである。実際に、ディオールがデザインしたオートクチュールは、一番シンプルなものであっても「メイドを雇わないと着られない」ほど複雑で、骨組みなどを含め、実に建築的だったそうだ。
美術大学への進学は叶わなかったものの、生活は「すべてが新しくて楽しい」ものだった。大好きなアート友達と語らい、好きな映画を片っ端から観る、刺激的な生活。
しかし、そんな生活にもいったん区切りをつけなければならなかった。兵役である。
フランスは1990年半ばまで徴兵制があった国だ。ディオールも例にもれず軍務に服す義務があった。できるだけ入隊を先延ばしにしていたそうだが、1927年、22歳のときには入隊しなければいけなかった。
ただ、それも長い目で見ると功を奏したようだ。刺激的な生活から距離を置き、自身のキャリアについて落ち着いて考える時間ができたという。その結果、兵役後にギャラリーの支配人になることを決意。
軍隊生活を終えるやいなや、友人ジャック・ボンシャンと共同で小さいギャラリーをオープン。展示したのはアート友達の作品だ。翌年の1928年には軌道に乗り、運営は成功。このまま、またあの楽しい生活が続く──かと思われた。
ここからディオールの暗黒時代が始まる。
実家が破産… 極貧パリ生活
1929年、世界恐慌が起きる。
翌年、兄弟が精神病にかかり、そのショックで母親が亡くなる。花好きの一面など、ディオールに大きな影響を与えた母親の死には深く悲しんだはずだが、彼はこれを「かえってよかった」と振り返っている。この不幸はまだ序章にすぎなかったからだ。
悪化の一途をたどる経済状況に、父親が破産。ディオール、そして母親も愛した芸術作品だけでなく、家までも売らなければならなくなった。家族はノルマンディーに引っ越し、ディオールだけがパリに残ることに。
ディオールが共同運営していたギャラリーも窮地に陥っていた。というのも、ギャラリーの出資者には父親が含まれていたのだ(ただし、世間体によるものか、実名は明かさずこっそり出資していたという)。
友達の家を転々としながらギャラリーの絵画を次々と手放す日々。日銭を稼ごうにも就職先がなく、身の回りのものを差し押さえられながら、なんとか展示会を続けていた。
先行き不安な日々が続き、食事もまともに食べられなかったディオールは、ついに体調を崩す。容体は深刻で長期にわたる静養が必要だった。
もはや一文無しのディオールだったが、友人がお金を出し合ってくれたおかげで療養生活に突入。一時的にパリを離れ、地方で静養を始める。
精神的にも経済的にも、将来への不安も抱えていたに違いないが、この期間はメゾン「Dior」の誕生には欠かせない時間だった。というのも、ディオールは当時をこう振り返っている。
「パリから離れて暮らしてみると、パリでは他人の芸術活動で満足できていたが、ここでは自分で何か新しいものを作りたいという強い願いを心のなかに発見した」
このクリエイティブへの欲求の自覚こそが、Dior設立に向けて大きなターニングポイントになったのだ。
将来を決めた"120フラン"
体調も回復し、パリに戻ったディオールは、働き口を探して駆けずり回った。そこで1920~1940年代に活躍したデザイナー、ルシアン・ルロンのもとも訪れている。
ルロンは、ディオールのデザイナー人生におけるキーパーソンだ。なぜなら、ディオールは彼のもとでファッションを学ぶことになるのである。
このときルロンのもとには働き口がなかったものの、この出会いはディオールが衣装作りを意識するきっかけとなった。ディオールは、デザイン画を描き始めたのだ。
当時ディオールは、友人でデザイナーのジャン・オゼンヌと暮らしていた。心優しきジャンは、自分のデザイン画を買う客に、ディオールのデザイン画も見せてくれるようになった。それがきっかけで初めてデザイン画を売ることに成功する。
120フラン。それが最初のデザイン画につけられた値段だ。のちのDiorの成功に比べれば雀の涙ほどもないだろう。しかし、その喜びをディオールは自伝にしっかり書き記している。
「長い夜が明けて、輝き出た太陽の光のようであった。この120フランが私の将来を決定し、今なお輝き続けているのである」
しかし、ディオールにはまだ過酷な運命が待ち受けていた。
陥落した花の都
1939年、第二次世界大戦が始まる。翌年6月にはドイツ軍がパリに到達。フランスを降伏させた。
ドイツに占領されたパリでは、CHANELを含むいくつかのメゾンが閉鎖。ニューヨークへ避難したメゾンもあった。
軍隊に駆り出されたディオールは、除隊後、田舎で暮らすことを決意。デザイン画を描きたいという強い思いはあったが「占領されている都を見たくない」と、パリには戻らなかった。
生活は貧しかった。畑で野菜を育てて食べる、自給自足のような生活。そのうち「百姓になった自分がパリへ行けるものか」という気持ちも募るように。
しかし、そんなディオールを探し当てた人物がいた。日刊紙「フィガロ」のポール・カルベスである。
ポールはディオールにデザイン画を送るよう依頼。ディオールは収入面だけでなく「(デザインの)腕を落とさないためにも嬉しかった」と語っており、この依頼を受けることに。
そして、戦争によって傷つき、愛するパリも失ったと意気消沈していたディオールは、ポールとのつながりのなかで気づくのだった。
「パリが生き延びようとしている」
そうしてディオールはパリに戻ることを決意する。

次は、ディオールのデザイナー人生を紐解いていく。第2回はこちら。
