
About Roy Ayers : ロイ・エアーズ - レアグルーヴ~ヒップホップ~ネオソウルなどが再評価したレジェンドのこと
キング・オブ・ヴァイブス、キング・オブ・ネオソウルなどとも呼ばれるレジェンドのロイ・エアーズに取材する機会を得た。
以前から僕はロイ・エアーズのその音楽性のことをよく考えていた。ジャズでもソウルでもファンクでもないその不思議な音楽性は他に類を見ない。90年代以降の再評価は来るべくして来たものだったと僕は思う。僕はその再評価される理由をきちんと考えてみたいと思った。それやったのがRolling Stone Japanでのインタビューだ。
そして、そのインタビュー記事と併せてより深くロイ・エアーズを知ってもらうための論考をここに書いた。
最初の《Intro》はロイ・エアーズ入門編、その後に書いてある部分が更に先に進みたい人のための論考だ。
ちょっと長いが、本記事とRolling Stone Japaの記事はヒップホップやネオソウル、クラブシーンから再評価された理由について、つまり《90年代以降のロイ・エアーズとは何だったのか?》を考えてみたものだ。
ぜひ読んでみてもらいたい。
※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。
あなたのドネーションがこのnoteの次の記事を作る予算になります。
■intro.1 ロイ・エアーズ入門編:キャリア
◆Roy Ayers:ジャズ~ソウルジャズ
ジャズのヴィブラフォン奏者としてデビューしているので、最初期は割とオーセンティックなジャズサウンド。デビュー作の『West Coast Vibes』(1963)はそんな感じです。
そこからアトランティックへ移籍してからは『Virgo Vibes』(1967)、『Stoned Soul Picnic』(1968)、『Daddy Bug』(1969)といわゆるソウルジャズと言われるスタイルで、ソウルやR&B、ポップスのヒット曲などをカヴァーしたりしています。このあたりからジャンルの融合に積極的だったことがわかる。ジャズフルート奏者ハービー・マンのソウルジャズの名盤『Mamphis Underground』とかに参加しているのも納得。
・『Virgo Vibes』(1967)
・『Stoned Soul Picnic』(1968)
・『Daddy Bug』(1969)

◆Ubiquity:ジャズファンク~ニューソウル
ポリドールに移籍して最初の『Ubiquity』(1971)がサイケデリックなジャケットなのからもわかるようにかなり大胆にジャンルの融合を進めていく。アルバムのタイトルをグループ名にしてRoy Ayers Ubiquityを結成。そこから70年代は怒涛の傑作群をリリースします。
1968年にジミ・ヘンドリックスが『Electric Ladyland』を、1969年にスライ&ザ・ファミリー・ストーンが『Stand!』を、70年にマイルス・デイヴィスが『Bitches Brew』を、マーヴィン・ゲイが71年に『What's Goin On』を、72年にスティービー・ワンダーの3部作を、1973年にハービー・ハンコックが『Head Hunters』を、といった時代。ジョージ・クリントンがファンカデリックとパーラメントのファーストをリリースしたのが1970年。
そんなトレンドに呼応したジャズとファンクとソウルとロックが融合したサウンドを生み出す。大胆にヴォーカリストを起用しつつ、ジャズの即興も同居したサウンドも特徴。
・『Ubiquity』(1971)
・『He's Coming』(1972)
・『Coffy』(1973)
・『Virgo Red』(1973)
・『Red Black & Green』(1973)
・『Change Up The Groove』(1974)
・『A Tear To A Smile』(1975)
・『Mystic Voyage』(1975)

◆Ubiquity:ディスコ~アーバンファンク~フュージョン
76年にマーヴィン・ゲイが『I Want You』をジョージ・ベンソンが『Breezin』を、77年にはアース・ウィンド&ファイアが『All’n All』を、サルソウル・オーケストラが『Magic Journey』をリリースしたころ。ワイルド・チェリー「Play That Funky Music」やKC & サンシャイン・バンド「That's the Way (I Like It)」がヒットしていた時期。
それに合わせ、少しづつだが路線を変えている。具体的にはアーシーなサウンドが消えて、シンセを多用したアーバンなサウンドとディスコ由来のダンスビートが前景しつつ、これまでのジャズ的な要素も絶妙に残したこの時期はDJからの支持が最も高い時期とも言える。鍵盤奏者フィリップ・ウー(Philip Woo)を加入させたことでトレンドを掴んだメロウかつスペイシーなサウンドを鳴らせるようになったのも大きい。
・『Everybody Loves The Sunshine』(1976)
・『Vibrations』(1976)
・『Lifeline』(1977)
・『Starbooty』(1978)

◆Roy Ayers:ディスコ~アーバンファンク~フュージョン
1978年にプリンスが『For you』でデビュー、ジョー・サンプルが『Rainbow Seeker』を、79年にマイケル・ジャクソンが『Off The Wall』を、シックが『Risque』を、クルセイダーズが『Street Life』を、80年にはシュガーヒル・ギャングが1stを、81年にはルーサー・ヴァンドロスが『Never Too Much』という時期。
ここからユビキティという名義を使わなくなり、個人名へ。それと同時にバンド感は若干後退。80年代へ向かっていくこの時期になると、ジャズの要素はかなり後退して、フュージョン色が色濃くなり、ブラック・コンテンポラリーっぽい感じになっていく。ただ、ロイ自身はわりと厳しい時代で、ポリドールから、エレクトラを挟み、自身が運営するUno melodicに移り、そこからコロンビアと契約したりと、レーベルも転々。
とはいえ、フェラ・クティ(Fela Kuti)とのコラボや、自身のレーベルに移ってからの『Silver Vibrations』『Lots Of Love』でのディスコ/ブギー路線はハウス/ガラージ系のDJから人気が高かったり要所要所で輝きを見せている。80年代にはドン・ブラックマン(Don Blackman)やトム・ブラウン(Tom Browne)を起用していたり、とにかく「今イケてるやつ」を探し続けトレンドを追っていて意識の高さも健在。
82年には前年に『Street Song』をリリースしていた絶頂期のリック・ジェイムスの『Throwin' Down』に起用されている。インタビューで影響を受けた音楽家の一人にリック・ジェイムスの名前をあげていたり、思い入れは強い。こういう経験が以後のブリブリのサウンドのきっかけになったのかもという感じもある。
・『You Send Me』(1978)
・『Let's Do It』(1978)
・Roy Ayers & Wayne Henderson『Step In To Our Life』(1978)
・『No Stranger To Love』(1979)
・Fela Anikulapo Kuti And Roy Ayers『Music Of Many Colours』1980
・『Africa, Center Of The World』(1981)
・『Feeling Good』(1982)
・『Silver Vibrations』(1983)
・『Lots Of Love』(1983)
・『In The Dark』(1984)
・『You Might Be Surprised』(1985)
・『I'm The One (For Your Love Tonight)』(1987)
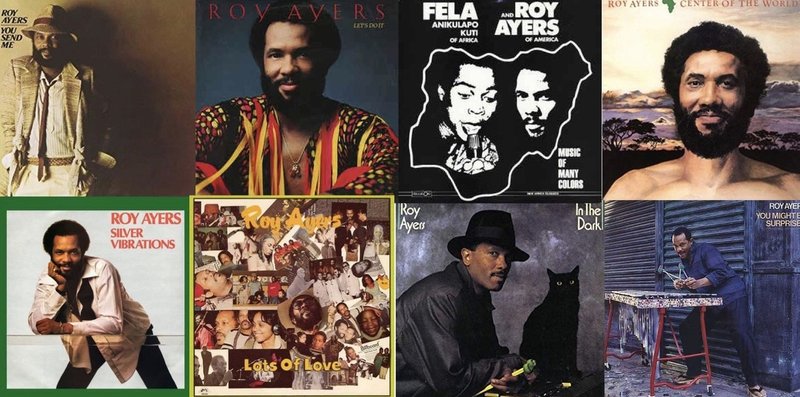
◆のちに再発見されたプロデュース・ワーク
実はロイ・エアーズ本人の名盤と肩を並べるくらいに高い評価を得ているのがこのあたりのプロデュースワーク。この3作に関してはカルト的な人気がある。
ランプ(RAMP)はユビキティ―からジャズ成分=即興性を下げて音響やテクスチャーへのこだわりを上げた感じで、ロイらしさとロイにはないセンスが同居している。「Everybody Loves The Sunshine」ひとつとっても、ユビキティーのバージョンと全く違う。スペースをたっぷり空けた空間に、ドラムのバスドラとリムショットが立体的かつシャープでドライに浮かび上がっていて、それがきっちりループされるので、そのままでヒップホップに聴こえる。「Daylight」も同じで、このアルバムがなぜそこまでサンプリングされるかは聴けば一発でわかる。同時にUbiquityとRAMPの違いからは、ロイが自身の名を冠した音楽にジャズの要素を求めていたことも見えてくる。
エイティーズ・レディース(Eighties Ladies)とシルヴィア・ストリプリン(Sylvia Striplin)は共に女性ヴォーカルをフロントに据えたポップな歌もので、シルヴィアはエイティーズ・レイディースのメンバー。エイティーズ・レイディースとシルヴィアに関しては音響的にもかなり面白いのもあるし、リズムセクションに関してもランプと同じでサンプリングしたくなる鳴りをしている。
80年代には自身の作品ではなかなか思うような結果が出なかった時期もあるが新たな才能や新たな声と出会い、ジャズ的な手法や作法から離れて、バンドやグループのためにきっちり曲を書いて作り込んだことで、大きな成果を得た。これらはロイのプロデューサーとしての才能がこの時期も輝いていたことを証明する作品群とも言える。
・Ramp『Come Into Knowledge』(1977)
・Eighties Ladies『Ladies Of The Eighties』(1980)
・Sylvia Striplin『Give Me Your Love』(1980)

◆ヒップホップ以降の再評価
UKのアシッドジャズからの熱烈なリスペクトや、エリカ・バドゥやザ・ルーツの曲への客演などの90年代以降のヒップホップ~ネオソウルからの再評価を受け、彼をリスペクトしているエリカ・バドゥを起用して、「Everybody Loves The Sunshine」「Searching」「Pretty Brown Skin」といったヒップホップの文脈も抑えた選曲で過去の名曲を再演した2003年の『Mahogany Vibe』がヒットし、話題に。
それに合わせて、未発表曲集をリリースし、更には立て続けにリミックス盤がリリースされ、当時のトップDJたちがロイ・エアーズをリミックス。クラブシーンではかなり話題になった。このあたりはクラブシーンではお馴染みのUKのBBEレーベルの仕事。クラブでDJが使えるオフィシャル音源をどんどん投下したことで、DJからの知名度も支持も盤石に。クラブジャズ/クロスオーヴー/NuJazzのシーン的にはこのあたりがかなり重要なトピックかと。
・『Mahogany Vibe』(2003)
・『Virgin Ubiquity (Unreleased Recordings 1976-1981)』(2003)
・『Virgin Ubiquity II (Unreleased Recordings 1976-1981)』(2005)
・『Virgin Ubiquity Remixed』(2006)
・『Virgin Ubiquity Remixed EP2』~『同EP5』(2006)
・『Holiday Virgin Ubiquity Remixes』(2005)
・『Sugar (Joey Negro Remix)』(2004)
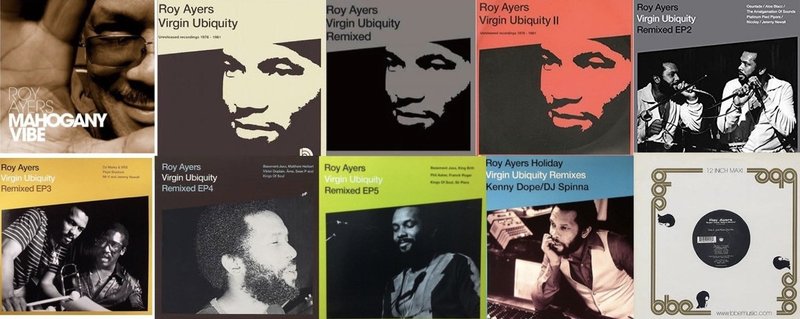
■intro.2 ロイ・エアーズ入門編:ヒップホップとサンプリングソース
とりあえず90年代以降、「ロイ・エアーズといえば、ヒップホップによって再評価された人だ」というイメージが強かった。名曲にサンプリングされまくりなので掻い摘んで見ていこう。
最も有名なのは「Everybody Loves the Sunshine」だろうか。
メアリー・J・ブライジ「My Life」やDr.ドレ「My Life」でサンプリングされている。
あと「Running Away」。
これはトライブ・コールド・クエスト「Description of a Fool」やコモン「Nag Champa (Afrodisiac for the World)」でサンプリングされている。
「Searching」はピート・ロック&C.L.スムース「Searching」
プロデュースものだと最も有名なのがRAMPの「Daylight」。
これはトライブ・コールド・クエスト「Bonita Applebum」にサンプリングされている。
ジャズやレアグルーヴ系のDJ的には「Red, Black & Green」「2000Black」「We Live in Brooklyn, Baby」あたりが重要だろうか。「2000Black」は4HEROのディーゴが自身のレーベル名に引用しているほど。
そういった幾多のサンプリングやクラブでの再評価を経て、実際にコラボレーションをするようになったりして、その評価が固まっていったのが90年代のロイ・エアーズの歴史。
ヒップホップだとGURU『Jazzmatazz』、ハウス(やアシッドジャズ)でもマスターズ・アット・ワークのプロジェクトのニューヨリカン・ソウルをはじめとして、山のようにコラボレーションしている。2010年代に入っても、タイラー・ザ・クリエイター「Find Your Wings」とかで相変わらず使われてるのがすごい。
この辺のヒップホップやハウスやアシッドジャズとの接点に関しては、ロイ・エアーズに関するあらゆる記事にたいてい書いてある。
また、なぜここまでサンプリングされたかに関しても、自身のレーベルUno Merodicを運営し、楽曲の権利を自身で管理していたことと、自身で権利を持っていたからこそサンプルングを積極的に認めて、サンプリング経由の収入を見込んでいたことも含めて、経営者的な視点を持っていたミュージシャンでもあったから、というのもある。
そういった話は検索したら出てくると思うので、各自探して読んでみてください。
そこにもう一つ加えるとすれば、ジャズミュージシャンには珍しくエレクトリック・レディ・スタジオやシグマ・スタジオといった名スタジオで録音していて、音質が良かったことや、音の分離が良かったこともあるだろうと僕は考えている。
で、ここまでは入門用のイントロダクション。
この記事の本題はここから先になります。
■アフロビートとネオソウル:フェラ・クティとのコラボレーション
ロイ・エアーズの活動の中で、音楽としてだけでなく、歴史的に高く評価されているのが、アフロビートの創始者フェラ・クティとのコラボレーションだ。
僕はRolling Stone Japanに
「彼はニューソウルやファンクのみならず、アフロビートにまで関心を示し、過去にはフェラ・クティとも共演している。その姿勢は同時代のヒップホップやR&Bを消化して新たな音楽を生み出し、フェラ・クティの子供たちともコラボレーションしたロイ・ハーグローヴやロバート・グラスパーを筆頭とした、先進的なアフロアメリカン・ジャズ・ミュージシャンの理想的なモデルになっていたようにすら思う。」
という推薦文を書いたが、
2010年代になって、アフロビートが再注目されていて、クリス・デイヴやネイト・スミスがアフロビートをプレイしたり、ロバート・グラスパーがフェラの息子のシェウン・クティをプロデュースしたりしている状況があり、
それをさかのぼると、2000年ごろにはディアンジェロ周辺のソウルクエリアンズやロイ・ハーグローヴがフェラ・クティを再評価し、その流れもあり、フェラの息子のフェミ・クティが彼らと共演したりしていた。
という流れを考えてみると、ロイ・エアーズとフェラ・クティがコラボレーションした1980年の『Fela Anikulapo Kuti & Roy Ayers - Music Of Many Colours』は21世紀に起こったそういった出来事を結ぶストーリーの出発点であり、ロイはパイオニアだったとも言えるだろう。
ちなみにフェラ・クティと共演することも唐突ではなく、タイトルを汎アフリカ主義の旗の色でもある3色からとったと思われるアルバム『Red Black &Green』を作ったり、『A Tears to a Smile』では「2000Black」「Ebony Blaze」という曲をやっていたり、アフロアメリカンへのメッセージを常に発信してきた人だからこそのフェラ・クティとの共演だったのは言うまでもない。ファンクのグルーヴとパーカッションを入れたポリリズムを組み合わせた音楽を得意としていたことも共演をスムースにした理由かもしれない。
ちなみに1981年にはフェラ・クティの曲をタイトルに持ってきたアルバム『Africa, Center Of The World』を作ったり、1983年の『Lots of Love』で思いっきりアフロビートな「Black Family」って曲をやってたり、本人もかなり影響されたのは間違いないみたい。
■エドウィン・バードソング:サイケデリック・ロックとディスコの影響
ロイ・エアーズとネオソウルというところで言うと、ロイの音楽にサイケデリックな要素があるのはかなり大きいと思う。
Rolling Stone japanの原稿でもふれたが、エレクトリック・レディ・スタジオ(Electric Lady Studio)でレコーディングしていたことも含めて、70年代前半のロイ・エアーズは明らかにジミ・ヘンドリックスをはじめとしたサイケデリックなロックを意識していたのがわかる。『Ubiquity』のジャケットのアートワークから既にサイケデリックだし、「The Fuzz」なんて曲もある。当時のジャズ系のミュージシャンでここまでゴリゴリな人はほとんどいない。
とはいえ、60年代のロイ・エアーズにはそんな要素はほとんどない。トレンドを意識し、ソウルやR&B、ボサノヴァまで幅広くプレイしてはいたが、サイケデリックなロックを、というのは70年代に入ってから突然入ってくる。
そういう経緯を考えてみても、これに関しては、エドウィン・バードソング(Edwin Birdsong)の影響だと考えたほうがいいのかもしれない。
ロイの右腕として彼のバンドのユビキティで演奏しつつ、自身もデビューしていた彼はゴスペルを出発点にマンハッタン音大とジュリアード音大で学んだエリートでもあり、鍵盤も作曲も出来て、そしてシンガーとしても一流。ロイ曰く天才でもある。そんな彼の音楽はゴスペル色は強く、ファンク色も濃厚で、そこにジャズの要素が入ってくると言った感じだろうか。ロイ・エアーズの楽曲にコール&レスポンス的なゴスペルの要素や、ゴスペル経由のオルガンのサウンドが加わったことにもエドウィン・バードソングの影響はかなりありそうだ。
エドウィン・バードソングのデビュー作ではロイ・エアーズ『Ubiquity』に収録されている「Pretty Brown Skin」のプロトタイプのような曲が聴けたりもして、洗練されてポップなロイのバージョンに比べると粗削りでパワフル、もっとアンダーグラウンドな雰囲気があるのがわかったりして面白い。
そんなエドウィン・バードソングにはロックからの影響をかなり受けていて、1973年リリースの『Super Natural』を今聴くとかなりサイケデリックでファンキーなブルースロックという感じもありつつ、キャッチ―な要素も併せ持っていてかなりかっこいい。おそらくジミヘンとPファンクが入り混じったような新しいブラックミュージックを狙ったもので、さっきも紹介した「The Fuzz」みたいな曲と同じ文脈でクオリティは高いのだが、どうやらセールスは振るわなかったようだ。
自身の活動はなかなか軌道に乗らなかったエドウィンだが、ロイ・エアーズのバンドでは着実に貢献しつつ、紆余曲折を経てディスコに接近。70年代後半にはフィラデルフィア・インターナショナルと契約し、「Phiss-Phizz」などのシングルを何枚かリリースしている。この当時の曲はいわゆるポップな売れ線というよりは、フロアでの機能性に特化した曲で、その中にはサイケデリックな要素もあって、彼らしさが見える。
その後は、サルソウル(Salsoul)と契約し、名盤『FUNTAZTIK』をリリースし、ダフトパンクにサンプリングされた「Cola Bottle Baby」や、アンダーグラウンド・ディスコとしてカルト的な人気を得ている「Rapper Dapper Snapper」を生み出したりしてる。ラリー・レヴァンのお気に入りだったので、過激なハウスなどを掘っていたレフトフィールドなDJにとっては、ロイ・エアーズの右腕ではなく、この時期の彼のほうがはるかに有名だろう。
ソウルやファンクにも理解のあるジャズミュージシャンであったロイ・エアーズ70年代を通して時代に寄り添うことができたこと、つまりサイケデリックなロックが強かった時期やニューソウルが強かった時期だけでなく、徐々にディスコが強くなってきた時代に移り変わっていっても「Running Away」「Can't You See Me?」といった楽曲を生み出し、そこに対応できたことはエドウィン・バードソングのような存在が近くにいたことが大きかったことは容易に想像できる。
更に、1970年代後半にはそこにフュージョンやディスコの要素に適応させるためにシンセサイザーに強い鍵盤奏者フィリップ・ウーを加えたり。ロイ・エアーズのサウンドというのはプロデューサー的に有能な個性を適切に活用することで生まれているのだ。
エドウィン・バードソングに関しては以下のWAX POETICのインタビュー(英語)は必読。彼のキャリアがよくわかる。
■ハリー・ウィテカー:スピリチュアルジャズの影響
また、ロイ・エアーズにはもう一人右腕がいた。
エドウィン・バードソングと同じようにユビキティ―を始めた頃に起用し始めたのが鍵盤奏者で作曲家のハリー・ウィテカー(Harry Whitaker)。
元々はジャズピアニストだったようだが、ロイ・エアーズ作品での演奏で知られているので、90年代以降はレアグルーヴ系のカルトヒーローのような存在になっているが、ロバータ・フラックの作品では音楽監督も担当していたりとメジャーな仕事も少なくなくその実力は折り紙付きだ。
ウェザーリポートのメンバーのミロスラフ・ヴィトウスとアルフォンゾ・ムザーンまでもが参加しているユージーン・マグダニエルのアルバムに象徴的だが、このあたりのアルバムはソウルとジャズが融合したタイプのもので、まだそのジャンルの混ざり具合をあれこれ模索していたチャレンジングな時期でもあった。ロバータ・フラックももともとはジャズヴォーカリストとソウルシンガーの間のような売られ方をしていた人で、かなり特異な存在だった。ハリー・ウィテカーはそんな時代に求められたミュージシャンだったのだろう。
ロイ・エアーズのバンドだと、「We Live in Brooklyn, Baby」が作曲者としての代表曲なのと、ブラックムービー・サントラの傑作『Coffy』での仕事が重要で、多彩な作風、演奏で貢献している。。
一方で、彼は自分のことをジャズミュージシャンだと自負していたように思われる。これは彼が自分の名義で残した数少ない作品がすべてオーセンティックなジャズ・アルバムだからだ。
晩年に2001年にリリースしたピアノトリオでの『The Sound of Harry Whitaker』を聴くとかなりビバップ系なのに加え、ストライドピアノやゴスペルを消化したデューク・エリントンやセロニアス・モンクにも通じるオールドスクールなスタイルも聴こえる。その中でもコルトレーンの「Equinox」をやってるあたりにポスト・コルトレーンな彼の志向の一面が見えてくる気もする。
そんなハリー・ウィテカーの代表作は日本のベイステイト・レーベルに残した『Black Reneissance』というアルバム。ジャズ史にはまず出てこないであろうマイナー盤だ。
これはいわゆるスピリチュアルジャズと呼ばれるタイプのジャズで、アフロアメリカンのミュージシャン達がジョン・コルトレーンが無くなった後に彼の音楽をベースに作り上げたサウンドの系譜にある。人種差別問題へのメッセージが込められていて、アフロセントリックな表現が多用されたりするのも特徴的だ。
このアルバムはジャズシーンでは無名に近いピアニストをリーダーに据えてあるうえに、日本のレーベルからリリースされていることもあり、超マイナー盤。にもかかわらず、クレジットを見るとウディ―・ショーやビリー・ハート、エイゾー・ローレンス、エムトゥーメイなど名手がずらり。つまり「なんだ、これは!?」的にあとあと再発見されたもので、オリジナル盤のレコードは超レアでプレミアもの。そんなスピリチュアルジャズの中でもカルト的に知られているマニアにはお馴染みの人気盤だ。
例えば、マッドリブがThe Last Electro-Acoustic Space Jazz & Percussion Ensemble名義でリリースした『Miles Away』でハリー・ウィテカーとブラック・ルネッサンスに捧げた曲を作っていたりするあたりからもその辺の感覚は伝わるかなと。
この『Black Renaissance』というアルバムがただのスピリチュアルジャズと違うのは、音響効果が巧みに使われていて、特に薄っすら聴こえている女性コーラスやヴォイスに効果的に使われるディレイやリヴァーヴなどがサイケデリックで、昂揚感が尋常じゃないことだ。そして、25分を超える楽曲の中でひたすら繰り返されるベースとピアノによるリフが生むヒプノティックな陶酔感もまたどこまでも効果的だ。
ただ、それらの要素はロイ・エアーズの作品にも共通して存在する要素とも言える気がするのだ。ハリー・ウィテカーはモーダルなジャズやフリージャズへも接近した70年代のジャズの流れをおさえつつも、ロイ・エアーズの作品で得たサイケデリックロックやニューソウルやファンクなどの要素を自身の作品に投入していたのだろう。だからこそ『Black Renaissance』はスピリチュアルジャズの中でも特別な一枚としてDJを中心に再評価されるようにもなった。
一方で、ロイ・エアーズはハリー・ウィテカーが考えていた様々なコンセプトやアイデアを柔軟に採用していたからこそ、70年代初頭のロイ・エアーズの作品にはスピリチュアルジャズとも通じる要素があったとも言える。
僕のイメージでは、ロイ・エアーズという人は、ジャズで言うとウェルドン・アーヴィンやドナルド・バードと同じ枠で、マーヴィン・ゲイやスティービー・ワンダー、ダニー・ハサウェイなどのニューソウルのアーティストたちの動きに対するジャズからの回答のような存在だと思っている。ただ、そういったニューソウルが持っていた時代性と同時に、コルトレーン以降のスピリチュアルジャズのサウンドが持っていた時代性をも纏わせることができたことで、ロイ・エアーズの音楽は唯一無二の音楽になりえたし、フェラ・クティとの共演のような歴史的事件も起きたのだろう。
そして、そんなジャズとニューソウルを両立させることができた絶妙なバランスを生み出すことができたのはなぜか、と考えると、ハリー・ウィテカーのような存在へとたどり着く。
そう考えると、70年代のロイ・エアーズというのは本人の音楽性だけでなく、サイケデリックなサウンドとファンクを得意としていたエドウィン・バードソング、ジャズをベースにしていたハリー・ウィテカーという二人の作編曲家のキャラクターが相当強く音楽に出ていたのではないか。
即興性が高く変化を求めるジャズの要素と、スタジオできっちり「曲」を作り込むソウルやロック、ひたすら反復されて行くことでグルーヴしていくファンク、そういった要素の綱引きのようなロイ・エアーズのサウンドは、このロイ・エアーズ、エドウィン・バードソング、ハリー・ウィテカーの3人を含めたユビキティというユニットだからこそ生み出すことができたものなのかもしれない。ある意味で、実に民主的で、個を重視しているという意味では、ロイ・エアーズの音楽観は想像以上にジャズミュージシャン的だったように思う。
そういえば『Wax Poetics』(日本版1号/US版7号)に掲載されていたロイ・エアーズのインタビューにGURUのJAZZMATAZZに参加したころの話がある。
「GURUの音楽はインプロヴィゼーションが少なかった。自分としてはヒップホップとジャズのインプロヴィゼーションのバランスをもっととった音楽をやってもらいたかった(要約)」
というようなことを中心にロイ・エアーズはジャズのあり方と精神性について語っている。実際にロイ・エアーズのキャリアの最初期は普通にジャズだし、70年代前期~中期の作品もジャズであることを強く意識していて即興演奏とバンドの相互作用を重視した音楽であることは間違いない。ロイ・エアーズの音楽はどんな要素が混ざろうとも基本的には「ジャズ」でもあろうとしていた、のだろう。
そのロイのスピリッツを受け継いだネオソウルを1曲紹介したい。「We Live in Brookyn, Baby」をサンプリングしてループしたトラックの上でジル・スコットがフィラデルフィアについて即興を交えてポエトリーをする名曲「We Live in Philly」。即興との相性の良さはこういうところからも聴かれる気がする。
ハリー・ウィテカーに関してもWAX POETICSの以下の記事がおススメ。
■ラテンジャズ:西海岸のラテンカルチャー
ロイ・エアーズは『Africa Center of The World』というアルバムを出していたり、アフリカっぽい民族衣装を着ていたりすることもあり、アフリカのイメージが強いし、公民権運動に呼応した音楽家だったことも含めて、同時代のスティービー・ワンダー、ハービー・ハンコックやEW&Fやラムゼイ・ルイスあたりとも通じるアフロフューチャリズム/アフロセントリックなイメージも強い。
彼の音楽を聴いていると、上記のジャズやソウルのアーティストと同じように基本的にはソウルやファンクとジャズを合わせたような音楽がベースにあり、リズムに関してもジャズファンクがベースになっている。
ただ、ロイ・エアーズの音楽はそのリズム部分のヴァリエーションが多彩で、16のファンクビートを基に作っていても、そこには様々なリズムパターンを用いているし、同じようなビートでもドラムの音色を変えたり、ベースや(時には2人の)キーボードとのコンビネーションを工夫しているので、リズムだけをとってもアレンジの巧みさに驚いてしまう。
それゆえにドラマーは最初期はアルフォンゾ・ムザーン、70年代以降の『A Tears to a Smile』『Vibrations』『Let's Do It』ではバーナード・パーディー、それ以外の多くの作品ではデヴィッド・ボウイ諸作で知られるデニス・デイヴィスを起用するなど、キーボード奏者と同じように強いこだわりを感じられる。デニス・デイヴィスに関しては、ロイ・エアーズ『Virgo Red』での起用あたりからキャリアが始まっていて、ロイがその才能を世に紹介したと言ってもいいだろう。
そんなロイ・エアーズの音楽の中で重要な役割を果たしているのパーカッションだと僕は考えている。
1970年の『Ubiquity』では後にマイルス・デイヴィス『Bitches Brew』にも起用されるパーカッション奏者のジュマ・サントスが起用されていて、彼とアルフォンゾ・ムザーンとの強力なコンビネーションがこのアルバムの魅力にもなっている。
僕はパーカッションを含めたリズムをパズルのように組み合わせたり、そのパーカッションの音色を楽曲の雰囲気に合うウワモノ的な意味も考慮したりしながらリズムを作るロイの作編曲の巧みさはラテン音楽からの影響があるのではないかと想像している。
例えば、ロイのバンドにはプエルトリコ出身のパーカッション奏者のチャノ・オファレルが在籍していたり、プーチョ&ラテン・ソウル・ブラザーズやモンゴ・サンタマリアのバンドにメンバーだったベーシストで作曲家のウィリアム・アレンといったミュージシャンも名を連ねていたりもする。
ロイ・エアーズはLA出身。西海岸にはラティーノやチカーノのカルチャーがあり、ラテンの音楽との接点も豊富で、そこで影響を受けた可能性は十分に考えられる。
例えば、ロイ・エアーズが在籍していたオーケストラの作曲家ジェラルド・ウィルソンはラテン系の曲をいくつも書いていることで知られている。例えば、ディジー・ガレスピーとのコラボレーションを重ねて、彼のためにいくつも曲を書いていて、その中にはラテンジャズの佳曲「Guarachi Guaro」もある。
またジェラルド・ウィルソンとラテンといえば「Viva Tirado」。自身のバンドでも演奏している彼の名曲のひとつだが、この曲はラテン・ソウル・バンドのエル・チカーノのカヴァーで知られているし、キューバの名バンドのファニア・オール・スターズもカヴァーしている。実はジェラルド・ウィルソンは西海岸のラテンカルチャーとも接点があったのではないか、と推測してしまう。
西海岸のミュージシャンにはそんな例は多い。それはロイ・エアーズもバンドに在籍していたドラマーのチコ・ハミルトンのバンドにも言える。「チコ」という名前からラテンっぽいこの人はラテンのパーカッション奏者ウィリー・ボボを起用した『El Chico』だったり、ラテンとソウルとロックを足したような『The Master』あたりがわかりやすいし、他にも「El Toro」という曲を書いたり、かなりラテンジャズをやっている。
ロイ・エアーズもそんな西海岸のラテンカルチャーからの影響を受けていたのではないだろうかと僕は想像している。そして、主にリズム面での工夫があったからこそ、のちに彼の音楽がクロスオーヴァーなサウンドとして再評価されたのではないかとも僕は考えている。
例えば、DJからの人気が高い『Vibration』『Everybody Loves the Sunshine』『Lifeline』からはラテンの影響やパーカッションの重要性がかなり聴こえてくる。ディスコを意識し始めてからパーカッションの役割が更に増していることと、エドウィン・バードソングも契約していたサルソウルとの関係はどうなんだろうとか余計な想像が膨らむ感じも楽しい。
そういえば、思いっきりラテンジャズをやるわけではないが、ジャズの中にソウルやファンク(やヒップホップ)などの要素を混ぜ、更にラテンもうまく取り入れているカマシ・ワシントンもまたジェラルド・ウィルソンの門下生なのは偶然ではない気もする。(カマシもまたLAのラテンコミュニティーとの交流からの影響も語っている。)
とはいえ、ロイにあなたのバンドにはラテン系のミュージシャンがいますねと言ったら「いいミュージシャンを使ってるだけだよ」と返されてしまったけども。また話を聞ける機会があったら、別の角度から聞いてみたい。
※追記
と思っていたら、廣瀬大輔くんにVi Redd『Birdcall』のライナーノーツに
「ロイ・エアーズはカーティス・エイミーのバンドや、彼自身のアフロキューバン・グループを率いてLA周辺で活動している」
と書いてあることを教えてもらった。
ロイ・エアーズにはアフロキューバンをやっていた時期があったということでこの件はまるっと納得である。
■ロイ・エアーズとは何だったのか
先にも書いたが、ロイ・エアーズの音楽は、ニューソウルへのジャズからの回答であり、そこにはジャズファンクやフュージョンだけでなくスピリチュアルジャズも入っていれば、ニューソウル以降のディスコにも対応して名曲を残した。更にそこにはサイケデリックロックからの影響があったり、アフリカやラテンとのつながりもある。時期によって取り入れた要素が異なるので、表面的なサウンドもかなり異なっていて、「ロイ・エアーズとはこんなサウンド」と簡単に評しづらい音楽性の人でもある。とにかく時代にやトレンド、そして自分の興味にしたがって、変化し続けてきた人でもあった。
90年代以降にクラブシーンで再評価された多くのブラックミュージックのレコードは様々なジャンルを取り入れながら新たなサウンドを模索していて越境性や実験性を持っていたものが多かった。ロイ・エアーズはそういった時代の音楽家の最良の成果だったと言えるのかもしれない。どのジャンルにも限定できない音楽性だからこそ、さまざまな側面で再評価され、リスペクトされ続けているのだろうと思う。
ネオソウル=エリカ・バドゥへの影響に関してはRolling Stone Japanにも書いたが、ここでも少しだけ。バンドで同じフレーズの繰り返しを効果的に使うだけでなく、ボーカリストの声さえも歌というよりはリフのように使い、同じとセンテンスを繰り返すことで昂揚感を作る手法、パーカッションを入れたポリリズム、隙間をたっぷり作りその空間を活かしたスペイシーなサウンド、即興性の高さ、スピリチュアルジャズ的なアフロセントリックな雰囲気などロイ・エアーズとの共通点は多い。サンプリングも多いが「Searching」をカヴァーしている1997年の『Live』での(シンセでヴィブラフォン的な音色を演奏させたりもしている)ジャジーなサウンドを聴くと、もっと音楽的にロイ・エアーズを消化しようとしていたように思える。自作のコーラスの入れ方だけでなく、客演のうまさに関してもシルヴィア・ストリプリンやチカスなどのロイのバンドのヴォーカリストたちの手法を研究した結果なのではないかと思ったりもする。そういう部分はハイエイタス・カイヨーテのネイ・パームやムーンチャイルドのアンバー・ナヴランなど、コーラスや多重録音をよりプログレッシブに使っているエリカのフォロワーたちにも受け継がれているはずだ。
ディアンジェロがニューソウルやファンクを強く感じさせるとすれば、エリカ・バドゥはニューソウルとジャズを感じさせ、それは正にロイ・エアーズを参照していたからではないかと思う。例えば、以下のライブ映像はロイ・エアーズ的なジャズ要素を感じさせる気がする。
また、2000年以降、ネオソウルからの影響を昇華して、ヒップホップとジャズの間に新たな関係性を生み出しているロバート・グラスパー周辺のミュージシャンも以下の動画のようにロイ・エアーズをトリビュートしていたりする。彼らはディアンジェロやエリカ・バドゥの世代の子供たちで、ロイ・エアーズの世代の孫たちとも言えるだろうし、だからこそグラスパーらはフェラ・クティ系譜のアフロビートともナチュラルに交流していく。それは明らかにロイ・エアーズが切り開いてきたものの先にある景色だ。
ちなみにこの世代で最もロイ・エアーズ的なものが聴こえるのはサンダーキャットなのかもしれないと思う。声の使い方や空間性、サイケデリックな音像、そこに組み込む即興性や、スペイシーなシンセの使い方、などに共通点を感じる。彼はエリカ・バドゥの元から育って行った一人で、ロイと同じLA出身なんだよなと思ったら、ロイのトリビュートライブにサンダーキャットも出ていたり。ここういう連続性が見えるのがUSの強みか…
ロイ・エアーズの音楽はきっと今、こういう場所で受け継がれていて、これから先もブラックミュージックが新たなチャレンジをする場所で参照され続けることだろう。
※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。
あなたのドネーションがこのnoteの次の記事を作る予算になります。
続きをみるには
¥ 250
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
