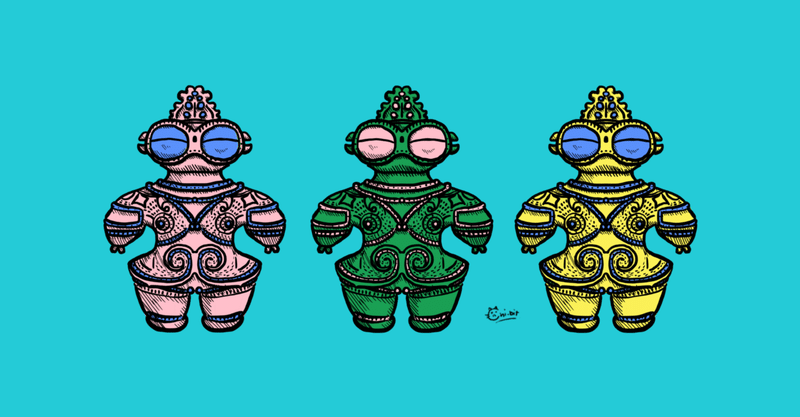
【温故知新】1万年間続いた縄文時代から、新しい生き方のコツを学ぶ
先日、飛騨金山で「筋骨めぐり」をしたのですが、この時、案内してくださったガイドさんが、筋骨の他に「金山巨石群」のガイドもしていらっしゃる方で、出発前に「巨石群と縄文時代」について詳しくお話してくださいました。
この時、ガイドさんから伺ったお話が非常に興味深く、私の心に深く残ったので、ここに備忘録として書き留めておこうと思います。
縄文時代は平和で平等な時代だった
縄文時代は、今からおよそ13000年前から2300年前まで、約1万年間続いた時代です。
そして、この縄文時代の遺跡を調べると、武器や武具は見つからず、戦で人が亡くなったと思われる跡もないのだとか。そこから推測するに、縄文時代はとても平和で穏やかな時代だったようです。
一万年も続いた縄文時代。どうして平和だったのでしょう?
そこで、ガイドさんが教えてくださった答えが、
①蓄(たくわ)えを持たなかった
②決まった職業がなかった
でした。この二つの答えについて解説していきますね。
①「蓄え」を持たなかった
縄文社会には、富を独り占めして「貯めておく」「蓄えておく」という価値観がなかったそうです。食料も物資も「必要な分」だけを手に入れて、手に入れた分はすぐに使い切っていたようです。
そのため「蓄え」がない分、「持っている者」と「持たない者」との格差が起きず、貧富の差も生じず、奪い合うための「争い」も起きなかった…とのこと。
もしも万が一、生活で何か困ったことがあれば、皆で助け合い、支え合ってピンチをしのいでいたそうです。
「貯めない」「蓄えない」からこそ、うまく回っていく。
なるほどなぁ…。シンプルだけど理にかなっていると思いました。
今、世界規模で起きている貧富の差や格差問題。これらは、長い歴史を有する根深い問題であり、簡単に解決できるものではない…と思います。
でも、今のこの現状(巨万の富を得て、それを個人でキープしている人がいる反面、どんなに働いても貧しく苦しい暮らしを強いられている人もいる)は、縄文時代にはなかった構図なんですよね。
縄文時代が終わって弥生時代に入り、稲作が定着していく過程で「たくさんコメが生産できる」「作ったコメを備蓄する」ことが可能になったところから、貧富の差が生まれてきたようです。力がある者が富を独り占めしたり、蓄えてさらに力を増強していくことで、「持っている者」が「持たない者」を支配する構図が生まれ、身分の差も出来上がっていったんだそうです。
そう考えると、私たちの「富を蓄えるために必死に働く」という価値観は、逆に社会に格差を生み出すことになるのではないか…と、そんな気がしてきます。
つまり、働いて得たものを、ただ貯め込んでしまうのではなく、必要な時にはちゃんと使って社会に循環させることが必要なんじゃないか…と。富を自分の手元に固く留めておかないで、どんどん使って社会に還元させていくことが、本来のあるべき姿なんじゃないかな?…と、そんなことをふと思いました。
とはいえ、小市民な私は、得たものを貯めないでパッと使ってしまうことに不安と恐怖を感じてしまうんですよね…😅。これって、弥生時代以降の厳しい格差社会を果敢に生き抜いた私たち人類の、魂に深く刻まれた「トラウマ」みたいなもんでしょうか(汗)。
江戸っ子の「宵越しの銭は持たねぇ」スピリットは、縄文の価値観そのままかもしれません。しかし、こんな風に気っ風良く言い切れるとカッコいいんですけどね…。あは。
②決まった職業がなかった
これも「なるほど~!」と思ったお話です。
縄文時代にも、例えば天文学に詳しくて暦を見る人や、病気やケガの手当てをする人、祈りをささげる人…等、個々に得意な分野があり、それぞれの能力を発揮して活動はしていました。
でも、食料を得たり、狩りをしたり等、「生きてために必要なこと」は、みんな平等に同じようにやっていたそうです。
つまり、狩りをする人、暦を作る人…というように「専門の仕事」を作ることはしなかったんだとか。みんな同じように狩りに行ったり、食べ物を探したり、役割に対して特別扱いはなく、上も下もなく、みんな平等だったそうです。
そのため、偏見や差別が生まれにくく、職業や立場の違いによって生じる格差や身分もなかったそうです。
専門職がないから、人々の意識もフラット。平等な世界
この差別も偏見もない平等な社会…。これってまさに、今を生きる私たちが目指している「理想の世界」ではないか!と思いました。
今は「どの仕事に就くと、安定した収入が得られるか?」でみんな必死だし、職種や社会的立場で「あの人は偉い」と人を崇め奉ったり、また逆に「この人は格下」と見下したり…等、そういう観点で人を見ようとする癖が抜けきらない人、今も世の中にはたくさんいるのではないでしょうか。
職種や肩書き、社会的立場やキャリア、年収…等で「人の価値」を見定め、人をジャッジしてしまう傾向があるけど、これも縄文時代にはなかった価値観なんですよね。弥生時代以降、暮らしが安定して豊かになっていくにしたがって、自然発生的に生まれて根付いた価値観なのでしょう。
そう考えると、今の子ども達や若者たちには、権力と富の争奪戦でドロドロした弥生時代以降の価値観じゃなくて、平和と平等の感覚がすーと通っていた縄文時代の感覚で生きてほしいなぁ…と切に思います。
「そんなの今さら無理だよ」と言われるかもしれないけど、これからの新時代は、縄文的価値観で生きていく方が、自分らしく幸せに、そして心豊かに生きられるんじゃないか…そんな気がするのです。
最後に
縄文時代は、人間も自然の一部分となって自然と共に生きていた時代なので、今の現代社会と比べても、うんと生死がはっきりしていて過酷だっただろうし、厳しい一面もあったと思います。
でも、人を貶めることはなく、また、人から奪い取ることもなかった平等な時代。皆が穏やかに心豊かに生きてきた平和な時代。
それが縄文時代です。
そんな時代が、私たちがいるこの場所で、一万年もの間、脈々と続いていたんですよね…。
これって本当にすごいことです。
あの時代にそっくり戻ることはできなくても、でも、あの時代の人々の価値観や生き方で見習うべき点はたくさんあると思うのです。
…と、ガイドさんから縄文時代について貴重なお話を聞かせていただき、以上のようなことを深く考えたのでした。
よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは旅の資金にさせていただきます✨
